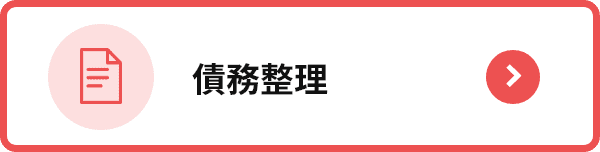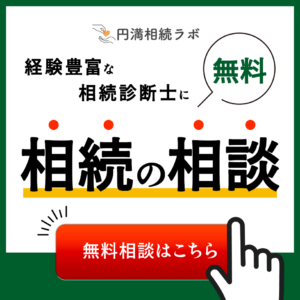土地の贈与税の計算方法とは?節税のコツ、贈与手続きの流れや書類について解説

Contents
土地の贈与とは?贈与税の基本を理解しよう
ここでは、贈与税の基本について解説します。贈与税の意義や、贈与税がかかるケースなど、わかりやすく説明します。
贈与税とは?
贈与税とは、個人から財産を取得した際に課される税金です。相続した財産の価額から基礎控除といわれる一定の額を控除して計算します。
贈与税がかかるケース
土地の名義を変更した場合や、共有持ち分を変更した場合など、財産を取得したとみなされる場合には、基本的に贈与税がかかります。
土地の名義変更をした場合
土地の名義を無償で他の人に変えたとき、その土地は贈与とみなされます。たとえば、誰かが所有する土地を別の人の名義にする場合、財産が無償で移転したと判断されるため、贈与税がかかります。
共有持分を変更した場合
複数人で共有している土地の持分を無償で変更した場合、その変更によって増えた持分は贈与とみなされます。たとえば、土地を半分ずつ共有していた状況で、持分の割合を変更して片方の持分が増えた場合、その増加分に贈与税がかかります。
土地を著しく低い価額で譲渡された場合
土地を時価よりも大幅に安い価格で親族から譲り受けた場合、その差額が贈与とみなされます。目安として、時価の80%以上で譲り受けた場合は問題になりにくいですが、それを下回る場合には贈与税が課される可能性があります。
共有名義の土地を分筆した場合
共有名義の土地を分筆(いくつかの土地に分けて登記)したとき、分筆後の土地の価値が持分の割合と異なる場合、差額が贈与とみなされます。この場合も贈与税の対象となります。
負担付贈与を行った場合
土地を譲る際に、借金の返済を引き受けてもらう条件を付けた場合、それは負担付贈与となります。この場合、土地の時価から引き受けた借金の残高を差し引いた金額が贈与税の対象となります。たとえば、土地の価値が1,000万円で、300万円の借金を引き受けてもらう場合、残りの700万円分が贈与税の計算対象です。
土地の贈与税がかからないケースと贈与税を抑える方法
ここでは、土地の贈与税がかからないケースと、贈与税がかかったとしても最小限に抑える方法を紹介します。
贈与税がかからないケース
土地の一部を無償で借りるなど、「使用貸借」に該当する場合には、基本的には贈与税はかかりません。
親の土地の一部を無償で借りた場合
土地の使用貸借とは、無償で土地を借受けることを指し、基本的に親子間で行われます。
親子間であれば無償の貸借であったとしてもみなし贈与と認定されないため、結果的に贈与税が課されません。
土地の贈与税を抑える方法
ここでは、住宅資金の特例や、配偶者控除、相続時精算課税の非課税枠を利用するなど、土地の贈与税を抑える方法を紹介します。
住宅取得資金等の特例を活用する
住宅取得資金等の特例は、親や祖父母から家の購入や新築、増改築のための資金を贈与された場合に、一定の金額まで贈与税がかからなくなる制度です。
通常、年間で110万円を超える贈与には贈与税が課税されますが、この特例を利用すれば、それ以上の金額を非課税で贈与してもらうことができます。
非課税の上限は、購入する住宅の種類によって異なり、省エネ性能や耐震性などの基準を満たした住宅では最大1,000万円、一般的な住宅では最大500万円となります。
この特例の適用期限は、2024年の税制改正によって2026年12月31日まで延長されています。また、暦年贈与や相続時精算課税制度と併用することも可能です。それぞれの制度をうまく活用することで、節税をしていきいましょう。
配偶者控除(おしどり贈与)を利用する
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。
なお、贈与を受けた年の翌年3月15日までに当該不動産に贈与を受けた者が住んでおり、その後も引き続き住む見込みがあることが条件です。
また、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
相続時精算課税の非課税枠を利用する
相続時精算課税制度を使えば、累計で2,500万円まで贈与税がかからずに贈与できます。たとえ年間110万円を超える贈与をしても、この控除額の範囲内なら贈与税はかかりません。しかし、贈与した財産は贈与者が亡くなったときに相続財産として計算に含まれ、相続税を支払う必要があります。
一方で、贈与額が累計2,500万円を超える場合は、超過分に対して毎年20%の贈与税がかかります。この特例を活用することで、将来の相続税の負担を考えながら計画的に贈与を進めることが可能です。
相続時精算課税制度では、贈与を受けた人(受贈者)ごとに年間110万円の基礎控除が設けられています。この基礎控除内の金額には贈与税がかかりません。また、この制度では、相続開始前7年間の贈与額が110万円以下であれば、それを相続財産に加算する必要がありません。
これは暦年課税制度と異なる重要なポイントです。暦年課税では、相続開始前7年間に行われた贈与額は110万円以下であっても相続財産に含める必要があります。そのため、相続時精算課税制度を選ぶことで、贈与と相続の税負担を調整しやすくなる場合があります。
暦年課税の基礎控除を利用する
暦年課税とは原則的な課税方法であり、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除の110万円を差し引いた残額に対して課税されます。
つまり、贈与を受けた財産の合計額が110万円以下である場合には贈与税はかかりません。
なお、受贈者・贈与者の年齢は問いません。
貸家建付地にして評価額を下げる
贈与税の計算の基となる土地の価額を下げることで、相続税を安く抑えるという方法もあります。
土地の評価額はその土地の用途によって決定されるため、自分で自由に使用している土地(自用地)よりも第三者に貸し付けている土地(貸宅地)の方が安く評価されます。
このように課税制度の選択以外にも贈与税を節税できる方法がありますので、各々に合った最善の方法を検討することが重要です。
土地の贈与税の計算方法

ここでは、土地の贈与税の計算方法を紹介します。
贈与税の計算手順
土地の贈与税は、まず土地の評価額を出し、課税価格を算出した上で計算します。流れに沿って解説します。
土地の評価額の計算
まずは土地の評価額を計算します。計算方法は、「路線価方式」と「倍率方式」のふたつがあります。どちらの方式に該当するかは、国税庁のウェブサイトで確認できます。
路線価方式
路線価は、「路線価×補正率×地積」で計算します。
路線価は、先ほど紹介した国税庁のウェブサイトに記載してあります。
倍率方式
倍率方式では、「固定資産税評価額×倍率」で計算します。
固定資産税評価額は、固定資産税納税通知書などで確認できます。
課税価格の算出
課税価格は、土地の評価額-(基礎控除+非課税枠)で計算できます。
基礎控除額と非課税額については、複雑な判断が必要なので、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
税額の計算
課税価格が算出できたら、贈与税を計算します。
詳しくは、暦年課税制度での贈与税の計算方法、相続時精算課税制度での贈与税の計算方法を参照してください。
暦年課税制度の計算方法と注意点
ここでは、「暦年課税制度」の概要や、計算方法などについて解説します。注意点も併せて説明するので、参考にしてみてください。
暦年課税制度とは?
暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産に対して贈与税がかかる仕組みです。この1年とは、毎年1月1日から12月31日までの期間を指します。贈与を受けた金額の合計から、基礎控除として110万円を引いた残りの金額が課税対象となります。
たとえば、1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。また、この制度では贈与する人とされる人の年齢に制限はありません。誰でも同じルールが適用されます。
暦年課税制度での贈与税の計算方法
前述のとおり、暦年課税では1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除である110万円を差し引いた残額に一定の税率を乗じて税額を計算します。
なお、贈与税の税率は「特例贈与財産」と「一般贈与財産」によって区分されています。
特例贈与財産
この贈与税率速算表は、18歳以上の者が親などの直系尊属から贈与を受けた場合に使用します。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などが特例贈与財産に該当します。(夫の父からの贈与等は該当しません。)
| 基礎控除後の財産の価額 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | – | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
例えば、父から18歳以上の子が1,000万円の土地の贈与を受けた場合
→ 基礎控除後の課税価格 1,000万円 – 110万円(基礎控除)= 890万円
贈与税額の計算 890万円 × 30%(税率)- 90万円(控除額)= 177万円(税額)
一般贈与財産
この贈与税率速算表は「特例贈与財産」に該当しない場合に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年(18歳未満)の場合などが一般贈与財産に該当します。
| 基礎控除後の財産の価額 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | – | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
例えば、夫から1,000万円の土地の贈与を受けた場合
→基礎控除後の課税価格 1,000万円 – 110万円(基礎控除)= 890万円
贈与税額の計算 890万円 × 40%(税率)- 125万円(控除額)= 231万円(税額)
暦年課税制度の注意点
暦年課税では、年間の贈与額が110万円を超える場合、贈与税の対象となります。特に、一度に大きな金額を贈与する場合、多額の税負担が発生する可能性がありますので注意が必要です。
さらに、毎年110万円以下の金額を分けて贈与する場合は、贈与ごとにしっかりと贈与契約書を作成することが求められます。これを怠ると、計画的な贈与とみなされ、全額をまとめて課税される「定期贈与」として扱われるリスクがあります。適切な手続きを行い、トラブルを回避することが重要です。
相続時精算課税制度の計算方法と注意点
ここでは、「相続時精算課税制度」の概要や、計算方法などについて解説します。注意点も併せて説明するので、参考にしてみてください。
相続時精算課税制度とは?
前述のとおり、相続時精算課税は60歳以上の父母や祖父母が18歳以上の子や孫に対して、財産を贈与した場合に選択することができます。
ただし、相続時精算課税制度を利用できるのは、贈与者と受贈者に以下のような特定の条件がある場合のみです。
- 贈与者:60歳以上の父母または祖父母
- 受贈者:18歳以上の子どもや孫(養子を含む)
また、2022年3月31日以前の贈与では、受贈者の年齢要件が20歳以上となる点にも注意が必要です。
相続時精算課税制度での贈与税の計算方法
相続時精算課税制度の特別控除は、贈与財産の合計額から特別控除額2,500万円を控除した残額に一律20%の税率を乗じて税額を計算します。
例えば、2021年と2022年にそれぞれ、60歳以上の父から18歳以上の子が2,000万円の土地の贈与を受けた場合で、特別控除を利用する場合の計算は、以下の通りです。
→ 2,000万円 – 2,000万円(特別控除額)= 0円(税額)2021年分
特別控除額=2,500万円 – 2,000万円 =500万円
2,000万円 – 500万円(特別控除額)= 1,500万円
1,500万円 × 20% = 300万円(税額)2022年分
相続時精算課税制度の注意点
相続時精算課税を選択した際に注意すべきポイントがいくつかあります。
- 相続時精算課税を選択すると、その選択に係る贈与者からの贈与については以後すべて相続時精算課税が適用される(途中で暦年課税に変更できない)
- 贈与時に相続時精算課税制度を使うと、贈与した土地に「小規模宅地等の特例」を相続の際に適用できなくなる
- 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に「相続時精算課税選択届出書」及び贈与税の申告書を提出する必要がある
上記のポイントに注意して、上手に相続時精算課税制度を利用しましょう。
土地の贈与手続きと必要な書類
ここでは具体的な土地の贈与手続きについて説明します。必要書類も紹介しているので、実際に贈与を行う際に参考にしてみてください。
贈与手続きの流れ
最初に、贈与手続きの流れについて解説します。実際の手続きの流れに沿って説明していきます。
贈与契約書の作成
贈与契約書は、財産を誰に贈与するのかを証明するための書類です。贈与者と受贈者が合意した内容を記録し、贈与の証拠として利用されます。この書類は、土地の名義変更やトラブル防止にも役立ちます。
贈与契約書は2通作成し、贈与する人と受け取る人がそれぞれ1通ずつ保管します。書式に決まった形はありませんが、必要な情報を正確に記載することが重要です。具体的には以下の内容が必須です。
- 贈与する人(贈与者)の氏名と住所
- 贈与を受ける人(受贈者)の氏名と住所
- 贈与を行う日付
- 贈与する財産の詳細(例:土地や現金の情報)
- 贈与の方法(どのように財産を渡すか)
これらを明確に記載することで、贈与に関する後々のトラブルを防ぐことができます。内容に悩む場合には、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
名義変更登記
贈与契約書を作成したら、不動産の名義を贈与を受けた人に変更する手続きが必要です。この手続きは「所有権移転登記」と呼ばれ、土地の新しい所有者を正式に登録するものです。
手続きは、贈与された土地を管轄する法務局で行います。申請にはいくつかの書類が必要です。主な書類は以下の通りです。
- 登記申請書
- 贈与契約書
- 土地の権利書(登記識別情報または登記済証)
- 土地の固定資産評価証明書
- 贈与者の印鑑証明書
- 受贈者の住所を証明する書類
- 委任状(代理人が申請する場合)
これらの書類をそろえて申請します。ただし、登記手続きには専門的な知識が必要です。そのため、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士に依頼する場合、費用がかかるため、事前に金額を確認してから依頼するかどうかを決めましょう。
贈与税の申告
土地を生前贈与する場合、その価格が1年間で110万円を超えると贈与税が発生します。贈与税は自分で計算し、税務署に申告して納める必要があります。この手続きは、贈与があった翌年に行います。
具体的には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告を済ませなければなりません。この期限を過ぎると、延滞税やペナルティが発生する可能性があるため注意が必要です。
贈与税の申告は手続きが複雑になることもあります。不安な場合は、税理士に相談してサポートを受けることをおすすめします。
贈与税申告に必要な書類
贈与税申告に必要な書類は、以下の通りです。
贈与税の申告書
贈与税を申告するには、「申告書第1表」と「本人確認書類」を用意する必要があります。この2つは、課税方法や非課税の特例を利用する場合でも必ず提出しなければなりません。
申告書第1表は、贈与税の計算結果を記載するための書類です。これに加えて、本人確認書類の提出が求められます。本人確認書類としては、マイナンバーカードが最も便利ですが、まだ取得していない場合も対応可能です。その場合は、次の2つを組み合わせて準備します。
- マイナンバーが記載された住民票
- 運転免許証や健康保険証などの身分証明書(2点)
暦年課税制度を利用する場合の書類
暦年課税制度を利用する際には、選択した課税方法や贈与内容によって提出する書類が異なります。まず全員に共通して必要なのが、「申告書第1表」と「本人確認書類」です。
さらに、課税価格が300万円を超え、特例税率が適用される場合は、「資産を受け取った人の戸籍謄本」も必要です。また、贈与された財産が土地であり、その評価が必要な場合は、「土地の評価証明書」を添付しなければなりません。
相続時精算課税制度を利用する場合の書類
相続時精算課税制度を利用する場合、財産をあげる人ともらう人の両方が書類を準備する必要があります。この制度では、「申告書第1表」と「本人確認書類」のほか、いくつかの添付書類をそろえる必要があるため、事前に確認しておくことが大切です。
具体的に準備する書類は次の通りです。
- 資産をもらう人の戸籍謄本
- 資産をもらう人の戸籍の附票のコピー
- 相続時精算課税選択届出書
- 資産をあげる人の戸籍の附票のコピー
- 資産をあげる人の住民票のコピー(60歳以降に取得したもの)
- 申告書第2表
これらの書類は、贈与する側ともらう側がそれぞれ準備しなければなりません。特に戸籍謄本や附票、住民票などの公的書類が必要となるため、役所での取得が必要になる場合があります。
土地の贈与に関する注意点
ここでは、土地の贈与に関する注意点を紹介します。贈与税以外にかかる税金や、専門家への相談が必要な場合など、詳しく説明しているので、参考にしてみてください。
非課税でも不動産取得税や登録免許税がかかる
不動産取得税は、土地の固定資産税評価額に基づいて計算され、「評価額の半分 × 3%」が課税されます。この税率は2026年3月31日まで適用されますが、条件によって評価額の半分が適用されない場合もあります。
一方、登録免許税は、土地の名義を変更するときに課税されます。その計算方法は「固定資産税評価額 × 2%」です。この税率により、土地の贈与には一定の税負担が生じます。
相続の場合はこれらの税金が軽減されます。具体的には、不動産取得税は非課税となり、登録免許税の税率は「固定資産税評価額 × 0.4%」に引き下げられます。そのため、贈与よりも相続のほうが税負担が軽くなることが多いです。
土地の贈与を検討する際は、不動産取得税や登録免許税も含めて費用を計算し、負担がどれくらいになるか確認することが大切です。
贈与後3年から7年以内の死亡時には相続税がかかる
暦年課税を利用して財産を贈与した場合でも、贈与から3~7年以内に贈与者が亡くなると、その贈与分が相続財産に加算され、相続税の対象となります。このため、亡くなる直前に土地などの財産を贈与しても、相続税の計算には影響を与えません。
ただし、相続時に亡くなった人から財産を受け取らなかった人は、亡くなる前3年以内に贈与を受けていても、その分は相続財産に加算されません。
この期間については、2023年までは「3年以内」が対象でしたが、2024年以降の生前贈与では段階的に「7年以内」へと延長されることになっています。贈与と相続の関係は複雑なため、計画を立てる際には注意が必要です。
共有財産の贈与時には持分に注意が必要
不動産の共有持分を贈与すると、受け取った人が贈与税を支払わなければなりません。また、共有持分を放棄した場合でも、それは他の共有者全員に贈与したとみなされます。その結果、共有者全員が贈与税の対象となります。
さらに、共有持分の贈与を受けた不動産を将来売却する場合、贈与時の時価で課税され、その後の売却時にも再び時価に基づく課税が行われます。このように、取得費を引き継ぐ部分を超えた金額については二重課税となることがあります。
一方、共有持分を放棄した場合は、取得費の引き継ぎがなく、贈与課税時の時価が取得費とされます。このため、放棄の場合には二重課税が生じない仕組みになっています。
税理士への相談も検討する
土地を贈与や売買で移転すると、評価額や取引額が高いため、税金の負担が大きくなることがよくあります。しかし、条件によっては優遇措置を利用して税金を減らせる可能性があります。これを最大限に活用するためには、専門知識が必要です。
土地の移転を計画している場合は、不動産に詳しい税理士に早めに相談することをおすすめします。税理士に相談することで、あなたの状況に合った最適な手続きや優遇措置の活用方法を見つけることができます。税負担を軽減し、スムーズに進めるためにも、専門家の力を借りることを検討してみてください。
また、「円満相続ラボ」では、相続や生前贈与に関する基本知識やトラブル回避の方法をわかりやすくお伝えし、専門家によるサポートを提供しています。
生前贈与に関する疑問がある方には、相続診断士による無料相談窓口もご利用いただけます。どうぞお気軽にご相談ください。
土地の贈与に関するよくある質問
最後に、土地の贈与に関して多くの方から寄せられる質問に詳しくお答えします。土地を贈与するのと相続するのはどちらが得なのか、暦年課税と相続時精算課税どちらを選択するのが合理的なのかなど、土地の贈与を検討する際に役立つ情報を紹介します。
土地の贈与と相続、どちらが得?
土地の贈与と相続は、それぞれにメリットとデメリットがあります。贈与の場合、早めに財産を移転することで節税効果を得られる可能性があり、家族間での財産の使い方を計画的に進めやすいという利点があります。また、非課税枠や特例を使えば、贈与税を抑えることも可能です。
財産の引き継ぎを計画する際は、まず相続税や贈与税の対象となる財産を把握することが重要です。そのうえで、生前贈与と相続のどちらが自分にとって有利かを比較し、慎重に検討しましょう。
確実に税金の負担を減らすためには、相続の専門知識を持つ税理士に相談するのが安心です。専門家のアドバイスを受けることで、最適な方法を選ぶことができます。
暦年課税と相続時精算課税はどちらを選択するのが良い?
暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶべきかは、贈与の期間や金額によって変わります。それぞれの仕組みを理解して、自分の状況に合った制度を選ぶことが大切です。
短い期間で少額の贈与を行う場合は、相続時精算課税制度を選んだほうが税負担が軽くなることが多いです。この制度では、最大2,500万円までの贈与が非課税となり、相続時にまとめて精算されます。
一方で、長い期間にわたって多額の贈与を行う場合は、暦年課税を選んだほうが有利になるケースが多く見られます。暦年課税では、年間110万円の非課税枠を活用することで、長期的に贈与税を抑えることが可能です。
どちらを選ぶか迷ったときは、自分の贈与計画を整理し、将来的な相続税の負担も含めて比較検討しましょう。また、専門家に相談することで、最適な選択をするための具体的なアドバイスを受けることができます。
暦年贈与や相続時精算課税制度を利用する際の注意すべきことは?
暦年課税と相続時精算課税制度を選ぶときは、慎重な判断が必要です。特に相続時精算課税制度を一度選ぶと、暦年課税制度には戻れないという重要なポイントがあります。この選択は取り消しができないため、軽率な判断は避けなければなりません。
また、相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、相続時に使える「小規模宅地等の特例」が適用できなくなることがあります。これにより、相続税の負担が増えるリスクがあるため注意が必要です。
制度の選択に迷ったり、不安がある場合は、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、将来の税負担を最小限に抑える方法を見つけることができます。
贈与税の申告期限が過ぎた場合どうすればいい?
贈与税の申告期限を過ぎてしまった場合は、できるだけ早く申告書と必要書類を用意し、管轄の税務署に提出しましょう。期限を過ぎるとペナルティが課されますが、早めに対応することで負担を最小限に抑えられます。
申告が間に合わなかった理由としては、書類作成が遅れた場合や申告期限を間違えた場合が考えられます。どのような理由であれ、すぐに対応することが重要です。
期限を過ぎた場合に課せられる主なペナルティには次のものがあります。
- 無申告加算税:期限内に申告しなかった場合に課されます。
- 過少申告加算税:申告した金額が少なかった場合に課されます。
- 重加算税:故意に申告内容を隠したり偽装した場合に課されます。
- 延滞税:税金の支払いが遅れた場合に日数分加算されます。
申告を忘れた場合や知らなかった場合には、無申告加算税と延滞税が課されます。申告後に金額の不足が判明した場合は過少申告加算税が、意図的に偽装した場合は重加算税が適用されます。延滞税は遅れた日数に応じて増えるため、早めに申告すれば負担を抑えられます。
税務署から指摘される前に、自分で申告書を提出することが大切です。期限を過ぎてしまったと気づいたら、すぐに書類をそろえて対応しましょう。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を書いたのは…

弁護士・ライター
中澤 泉(なかざわ いずみ)
弁護士事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続といった幅広い分野の案件を担当した後、メーカーの法務部で企業法務の経験を積んでまいりました。
事務所勤務時にはウェブサイトの立ち上げにも従事し、現在は法律分野を中心にフリーランスのライター・編集者として活動しています。
法律をはじめ、記事執筆やコンテンツ制作のご依頼がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。