代償分割の仕組みとは?メリットや注意点、手続きの流れから税金の扱いまで解説

Contents
代償分割とは何か―他の遺産分割方法との違い
代償分割は、相続における代表的な分割方法のひとつです。他にも「現物分割」「換価分割」「共有分割」などがありますが、それぞれに特徴と向き不向きがあります。ここでは基本的な方法について整理し、代償分割がどのような場面で活用されるのかを解説します。
代表的な遺産分割の4つの方法
主な分割方法には、「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」の4種類があります。これらは民法で明確に分類されているわけではありませんが、実務上よく使われる区分として認識されています。
以下で、それぞれの特徴と違いを具体的に解説します。
現物分割:現物のまま分け合う
「現物分割」とは、遺産をそのままの形で相続人に分ける方法です。たとえば、被相続人が所有していた不動産を長男が相続し、預貯金を次男が受け取るなど、異なる種類の財産をそれぞれの相続分に応じて取得するケースがこれにあたります。
ただし、財産の性質によっては分けにくい場合もあり、必ずしも全員が満足する結果になるとは限りません。
換価分割:売却して現金で分配
「換価分割」は、相続財産を売却して現金化し、その現金を相続人の間で分ける方法です。相続人全員が土地や建物の相続を希望しない場合、売却してから分配すれば公平性を保ちやすくなります。
ただし、売却には時間や手数料がかかり、市況によっては思った価格で売れないリスクもあります。
代償分割:代償金を支払って相続
「代償分割」は、特定の相続人が相続財産を取得し、その代わりに他の相続人へ金銭などの代償財産を支払う方法です。たとえば、実家を長男が相続し、次男に代償金を支払うといったケースです。
不動産や事業用資産など、分けにくい財産がある場合に有効な方法で、相続財産を残したまま公平な分配を図ることができます。
共有分割:財産を共有名義で相続
「共有分割」は、相続人全員で1つの財産を共有名義で所有する方法です。特に土地や建物のような資産でよく見られます。
一見公平なように見えますが、将来的にその財産を売却する、管理するなどの意思決定を行う際に意見の対立が生じやすく、トラブルの原因となる可能性もあります。
代償分割が選ばれる代表的なケース
代償分割は、以下のような場面でよく活用されます。
- 相続財産のほとんどが不動産で、現金など他に分けられる資産が少ない場合
- 相続人のひとりがその不動産に住み続けたい、または事業を継続したいと希望している場合
- 共有状態を避けたいが、不動産の売却も望まない場合
たとえば、親と同居していた長男が自宅を引き継ぎ、他の兄弟には代償金を支払う形で相続する、というケースが典型です。
このように代償分割は、相続人間の公平性を保ちながら、不動産の維持や事業の承継を可能にする柔軟な分割方法といえます。
代償分割を選択すべき・避けるべきケース
代償分割は便利な制度ですが、すべての相続ケースに適しているわけではありません。財産の内容や相続人の事情によっては、他の分割方法の方がスムーズに進むこともあります。
ここでは、代償分割が向いている代表的なケースと、避けたほうが良いケースについて具体的に見ていきましょう。
代償分割の活用が有効なケース
代償分割が特に有効となるのは、遺産の大部分が不動産など「分割が難しい資産」で構成されており、かつ、特定の相続人がその不動産を使用し続けたい、または管理を引き継ぎたいと考えているケースです。
このような場合、遺産を特定の相続人が取得し、他の相続人には代償金を支払うことで公平な相続が可能になります。
主な財産が不動産の場合
不動産は現物分割が困難であり、共有にすると管理や処分でトラブルが起こりやすくなります。売却も選択肢の一つですが、思った価格で売れない可能性もあります。
このような場面では、不動産を1人の相続人が相続し、他の相続人に代償金を支払う形にすることで、トラブルを回避しつつ円滑な分割が可能です。
居住継続や事業承継を希望する相続人がいる場合
たとえば、被相続人と同居していた配偶者や子が、これまで通り住み続けたい場合、家を共有や売却するのは現実的ではありません。また、農業や事業用の不動産を使っている相続人が、そのまま事業を引き継ぐことを望むケースも多くあります。
このような場面で代償分割を使えば、住居や事業を守りながら、他の相続人との公平な関係も保つことができます。
代償金を用意できる相続人が存在する
代償金を支払うには、それに見合った現金や資産を持っている必要があります。たとえば、資金に余裕がある長男が家を相続し、他の兄弟に代償金を支払うことで、スムーズに分割がまとまるケースもあります。
相続税の納税資金としても、現金を保有していることは有利に働くことが多いです。
不動産市況が低迷している
不動産の市場価格が低迷している時期に売却するのは、望ましい金額での換価が難しく、不利な選択になる可能性があります。このような場合に代償分割を選択することで、不動産を売却せずに済み、後の市場回復を待ちながら資産を維持できます。
代償分割が不向きなケース
一方で、代償分割が適さない、または実行が難しい場面もあります。
代償金の用意ができない場合
代償分割の最大の前提は、代償金を支払えることです。取得者が必要な資金を用意できない場合は制度自体が成立せず、むしろ争いの原因になることがあります。
特に高額な不動産を取得しようとする場合、現金の準備ができなければ他の相続人からの同意が得られず、分割協議が頓挫する可能性があります。
評価方法や金額に争いが起こる恐れがある場合
不動産の価値は評価方法によって差が出ることが多く、「時価」「相続税評価額」「固定資産税評価額」など、どれを基準とするかで意見が分かれやすいです。
この評価のズレにより、代償金額への不満が生じたり、合意に至らなかったりすることもあります。
相続人間の関係が悪化している場合
代償分割には、相続人全員の協議と合意が必要です。そのため、すでに相続人間の信頼関係が失われているようなケースでは、協議が成立せずトラブルに発展するリスクが高まります。
このような場合には、専門家を交えて話し合うか、他の分割方法を検討するのが望ましいでしょう。
代償分割の利点と注意点
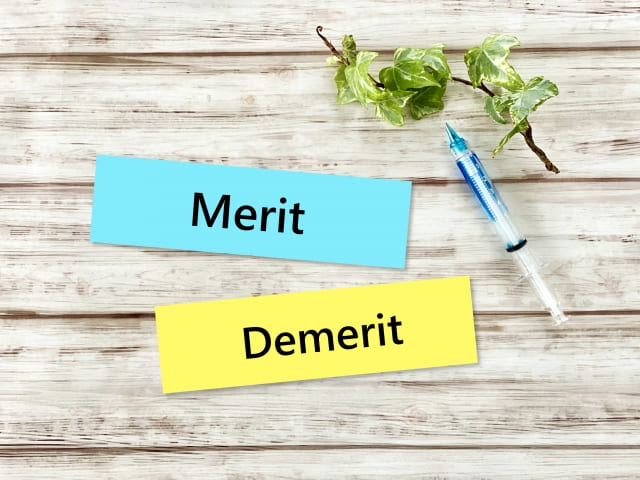
代償分割は、遺産の分け方として非常に柔軟性が高く、さまざまな状況に対応できる方法です。ただし、実際に行う際には一定のリスクやデメリットも存在します。
ここでは、代償分割のメリットとデメリットの両面を整理し、制度を活用する際の注意点を解説します。
代償分割の主なメリット
代償分割には、相続人間の公平性を保ちつつ、財産の性質を尊重した分割が可能という強みがあります。以下はその主な利点です。
公平な分割が可能になる
分割しにくい不動産などを特定の相続人が取得し、他の相続人に代償金を支払うことで、全体としてバランスのとれた相続が実現できます。
たとえば、長男が家を取得して住み続け、他の兄弟には現金を渡すことで「誰も損をしない形」での分割が可能になります。
不動産の売却や共有を避けられる
不動産を複数人で共有すると、後に売却やリフォームの判断をする際にトラブルになりがちです。また、すぐに売却するのが難しい市況の場合は換価分割も不向きです。
代償分割なら、不動産をそのまま引き継ぎながら、他の相続人には代償金を支払うことで、売却や共有の必要がなくなります。
相続税の軽減につながる可能性がある
一定の条件を満たすことで「小規模宅地等の特例」が適用され、相続税評価額を最大80%まで減額できるケースがあります(国税庁「No.4124 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」参照)。
たとえば、同居していた家族が自宅を相続するケースでは、330㎡までの宅地が80%減額対象となることがあり、大幅な節税につながります。
遺産分割で不満が起きるリスクを軽減
代償分割をうまく活用することで、相続人全員が納得できる分割結果となりやすく、相続トラブルを未然に防げる可能性があります。
被相続人の事業承継や居住の継続など、特定の目的を尊重しつつ他の相続人の権利も守るという点で、合理的な選択といえるでしょう。
代償分割のデメリットと注意点
一方で、代償分割には実務上の注意点やリスクもあります。制度を選択する際には、以下のような点に十分配慮が必要です。
代償金を用意できないと制度が使えない
代償金の支払いができなければ、代償分割そのものが成り立ちません。特に高額な不動産を取得しようとする場合には、相当な資金を用意する必要があります。
支払能力のない相続人が取得希望を出しても、他の相続人が納得せず、協議が行き詰まる恐れがあります。
不動産評価の方法で争いが起こる可能性
代償金の金額は、原則として不動産などの価値をもとに決定します。しかしその評価方法(時価・相続税評価額・固定資産税評価額など)に関して、相続人間で意見が分かれることが多いです。
特に市場価値が変動しやすい都市部の土地などは、評価額の差異が大きく、争いの火種になりやすい点に注意が必要です。
相続税以外の税負担が生じる場合がある
代償財産を現金ではなく不動産などの物件で支払う場合には、「譲渡所得税」が課税される可能性があります。また、手続きが不備な場合は贈与税がかかるリスクもあります。
このような税務上のトラブルを防ぐためには、協議書の書き方や評価額の妥当性を税理士など専門家にチェックしてもらうことが推奨されます。
代償財産の内容によって揉める可能性がある
代償として渡す資産が現金ではなく、株式や自分の所有する不動産であった場合、その価値や管理に関する意見の対立が起こることもあります。
特に、不動産や非上場株式のように流動性が低く、すぐに換金できない財産を代償と
代償金の決定方法と評価基準
代償分割における重要なポイントのひとつが、「代償金をいくらに設定するか」です。
代償金の金額は、相続人間の公平性を保つうえで非常に重要であり、適切な評価基準に基づいて決定しなければトラブルの原因になりかねません。
ここでは、不動産をはじめとする相続財産の評価方法や、代償金額を決める際の考え方について解説します。
不動産の評価基準
代償金額を決めるうえでまず重要なのが、不動産の「評価額」をどう見るかです。不動産の評価にはいくつかの方法があり、状況に応じて使い分けが必要です。
時価を基準とするケース
「時価」は、市場で実際に売買されるとしたらどの程度の金額になるかを推定した価格です。地価公示価格や不動産業者による査定を参考にするケースが多く、相続人全員が納得すれば、時価ベースでの評価も有効です。
ただし、時価には客観的な基準が明確に定まっていないため、相続人間で評価が割れることがよくあります。
相続税評価額・固定資産税評価額の活用
より客観的かつ一般的に利用されるのが、「相続税評価額」や「固定資産税評価額」です。特に相続税申告においては、国税庁が定める評価基準に基づく「相続税評価額」が基準となります。
たとえば土地の評価には、「路線価方式」または「倍率方式」が使われます。国税庁のホームページには毎年最新の評価方法が公開されています。
参考:国税庁|財産評価基準書 路線価図・評価倍率表
この評価方法により、公平な基準で評価額を算出することが可能です。家庭裁判所が関与する遺産分割調停などでも、相続税評価額が参考にされることが多いです。
代償金額を決める際の留意点
評価方法を決めた後は、それをもとに代償金の具体的な金額を算出します。ここでは実務上、特に重要な2つの視点をご紹介します。
法定相続分に沿ってバランスを取る
代償金額の決定においては、法定相続分に基づく分割が基本となります。たとえば、長男が相続する不動産が全体の資産の大半を占めるような場合、その価値のうち長男の法定相続分を超えた金額について、代償金を支払う必要があると考えられます。
これは裁判所でも一般的に採用される考え方であり、相続人間で争いが生じた場合にも説得力を持ちます。
合意があれば柔軟な評価も可能
代償金の額や不動産の評価方法については、相続人全員が合意すれば、柔軟に取り決めることが可能です。たとえば、地元不動産業者の査定をもとに時価で合意する、税理士のアドバイスを受けて相続税評価額を基準にするなど、ケースに応じた対応が可能です。
ただし、合意が不完全だったり、後から不満が出たりする場合もあるため、協議の過程や合意内容は遺産分割協議書に明記し、できれば専門家に確認してもらうことが望ましいです。
代償分割に関わる税金の基礎知識
代償分割を行う際には、相続税だけでなく、贈与税や譲渡所得税などの他の税金が関わってくる可能性があります。手続きや記載方法に誤りがあると、予定外の課税リスクが発生することもあるため、注意が必要です。
この章では、代償分割に関連する代表的な税金について、その計算方法や課税の有無、回避のためのポイントを解説します。
相続税の扱いと課税価格の算定
代償分割を行う場合でも、相続税は必ず関係してきます。相続税の課税価格は、代償金を含めた取得財産の価値に基づいて計算されますが、評価基準によって算出結果が変わるため注意が必要です。
相続税評価額に基づく例
一般的には、「相続税評価額」(国税庁が定める評価方法)をもとに、各相続人の課税価格を計算します。
たとえば、Aさんが評価額3,000万円の土地を相続し、Bさんに1,500万円の代償金を支払った場合:
- Aさんの課税価格は、3,000万円(取得財産)-1,500万円(代償金)=1,500万円
- Bさんは1,500万円の代償金を取得するため、1,500万円が課税対象
となります。
時価を用いた課税例
代償分割において、代償金の金額を不動産の「時価(市場価格)」を基準に決めることがあります。これは実際にその不動産を売却したときに得られると想定される金額に基づいて評価する方法です。
ただし、相続税の計算では通常「相続税評価額(路線価や倍率方式で算出された価格)」が使われます。時価と相続税評価額の間に差がある場合、その差によって、各相続人の「課税される相続税の金額」が変わってくる可能性があるのです。
【例:時価を基準に代償金を決定した場合】
- 相続税評価額:3,000万円(※申告の基準となる評価額)
- 時価(実勢価格):4,500万円(※不動産会社の査定などに基づく)
- 代償金の額:1,500万円(※相続人Bが受け取る)
この場合、不動産を取得する相続人Aと、代償金を受け取る相続人Bとの間で、相続税の課税価格をどのように割り振るかが問題となります。
相続税評価額と時価の間に1.5倍(4,500万円 ÷ 3,000万円)の差があるため、実際に取得する経済的利益の大きさに合わせて課税価格が調整されることがあります。
この調整は、次のような比率を使って計算されます。
相続人A(不動産取得者)の課税価格:
3,000万円-〔1,500万円×(3,000万円÷4,500万円)〕
= 3,000万円-1,000万円
= 2,000万円
相続人B(代償金取得者)の課税価格:
1,500万円×(3,000万円÷4,500万円)
= 1,000万円
このように、代償金を受け取る相続人が受け取った金額そのものが課税対象になるわけではなく、「不動産の評価方法」との関係性を踏まえて、調整後の金額が課税ベースとなる場合があるのです。
このような特殊な計算が必要となるため、時価ベースで代償金を設定する場合には、税務署や税理士への事前確認をおすすめします。
代償分割における贈与税の扱い
代償分割で最も誤解されやすいのが「贈与税」の課税対象になるかどうかです。相続に基づく代償金の支払いであっても、手続きが不備だと税務署に「贈与」とみなされるおそれがあります。
遺産分割協議書の記載が重要
代償分割を行う場合は、必ず遺産分割協議書に代償金の内容を明記する必要があります。これがないと、受け取った相続人が「他の相続人から財産をもらった」と見なされ、贈与税が課される可能性があります。
代償金が財産超過の場合の課税リスク
相続人が本来の法定相続分を超える財産(代償金など)を取得した場合、その超過部分について贈与税が課される場合があります。これは、相続税の対象外とされる部分が「無償の財産移転」と判断されるためです。
実務では、相続税申告時に「各人の取得財産が法定相続分に基づくか」を必ず確認し、必要に応じて税理士の指導を仰ぐのが望ましいです。
所得税(譲渡所得税)の発生条件
代償分割では、通常「現金」で代償金を支払うのが一般的ですが、相続人が手元に十分な現金を持っていない場合、不動産や株式などの資産そのものを代償財産として渡すケースもあります。
しかし、このような「物による代償」は、税法上は“譲渡”とみなされる可能性があり、「譲渡所得税(所得税・住民税)」の課税対象になることがあります。
譲渡所得の計算と取得費の注意点
たとえば、Aさんが自分名義の土地を、相続人Bに対する代償財産として譲渡するケースを考えます。
- 土地の取得価格(※購入したときの価格):1,000万円
- 現在の時価(※譲渡時点の市場価値):2,000万円
- 代償としてこの土地をBさんに引き渡した場合
この場合、税務上は「Aさんが不動産をBさんに売却した」とみなされ、2,000万円(時価)-1,000万円(取得費)=1,000万円 が「譲渡所得」として課税対象になります。
この譲渡所得に対しては、所得税(および住民税)が課税されることになります。
譲渡所得の計算では、「取得費」が重要な役割を果たします。取得費には、土地の購入代金だけでなく、登記費用・仲介手数料などの付随費用も含まれます。
しかし、古い不動産や親族から贈与されたものなどでは、「取得費の記録が残っていない」こともあります。この場合、取得費を「譲渡価額の5%」とみなして計算する(概算取得費)方法もありますが、これは課税額が大きくなる可能性があるため注意が必要です。
代償分割において不動産などを代償財産として渡す場合、評価額の算出、譲渡所得税の計算、取得費の確認など、高度な税務知識が必要になります。
不適切な手続きによって譲渡所得税が課税されるリスクを避けるためにも、税理士や弁護士に必ず相談することを強くおすすめします。
その他の税金
代償分割では、相続税・贈与税・所得税以外にも、以下のような税金が関係する場合があります。
不動産取得税の要否
相続により不動産を取得する場合、不動産取得税は原則として非課税です。ただし、代償分割の形式が複雑で「売買」に近いと判断される場合は、課税対象になることもあるため、個別に確認が必要です。
登録免許税の発生タイミング
不動産の相続登記には、「登録免許税」が発生します。代償分割の場合でも、不動産を取得する相続人は、相続登記を行う際に相応の税負担(0.4%相当)を負うことになります。
たとえば、評価額3,000万円の土地を相続する場合、登録免許税は12万円程度となります。
代償分割を進める際の流れと手続き
代償分割を実際に行うには、相続人全員の合意を得たうえで、評価・支払い・登記など、複数のステップを正確に踏んでいく必要があります。ここでは、代償分割を進める際の標準的なフローと、各段階で注意すべきポイントについてわかりやすく整理します。
手続きの全体フロー
代償分割は、以下のような手順で進められるのが一般的です。
①相続人全員による協議と合意
②代償金の金額や支払い方法の決定
③遺産分割協議書の作成
④実際の代償金の支払い
この順序を守らずに進めると、税務処理のミスや贈与とみなされるリスクが生じるため、正しいフローに沿って丁寧に進めることが重要です。
代償分割の合意と方針決定
まず行うべきは、相続人全員による遺産分割協議です。代償分割は法定の義務ではなく相続人同士の任意の合意に基づく制度のため、一人でも反対する相続人がいれば実行できません。
代償分割を提案する相続人は、不動産の取得理由や代償金の支払い能力について丁寧に説明し、他の相続人の理解を得ることが大切です。
話し合いの場には、できる限り中立的な専門家(司法書士、弁護士、税理士など)を同席させることで、協議がスムーズに進むこともあります。
代償金の金額設定
次に、代償金の金額を決定します。評価基準としては「相続税評価額」がよく使われますが、相続人間の合意があれば「時価」や「不動産業者による査定額」を参考にしても問題ありません。
ただし、前述の通り、金額の設定には税務上の注意点が伴うため、評価方法・金額・支払方法は明確に協議書に記載する必要があります。
また、分割払いとする場合でも、その旨を明記し、支払い条件(回数・期日・利息など)を明確にしておくことで、後のトラブル防止につながります。
遺産分割協議書の作成と記載方法
代償分割の合意内容を正式な書面としてまとめるのが「遺産分割協議書」です。この書類は、不動産の相続登記や金融資産の名義変更、相続税の申告などにおいて、法的な証拠として必須となります。
特に代償分割の場合は、以下の記載が必要です。
- 相続財産の詳細と取得する相続人の名前
- 代償金を支払う相続人と受け取る相続人の情報
- 代償金の額と支払い方法
- 相続人全員の署名・実印の押印
- 印鑑証明書の添付(登記等で使用)
正確に記載されていない場合、贈与税の課税対象になるリスクがあるため、専門家によるチェックを受けることを推奨します。
代償金の支払い実行
協議書の作成が終わったら、代償金の支払いを実行します。支払いは一括が原則ですが、相続人同士の合意があれば、分割払いも可能です。
ただし、支払いが長期間にわたる場合や滞納が発生すると、他の相続人との間にトラブルが生じやすくなります。できる限り早期の支払いを行い、領収書などで証拠を残しておくことも大切です。
また、相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)までに支払いを終えていない場合、一部の特例(例:小規模宅地等の特例)を適用できなくなるおそれもあります。
遺産分割協議書における記載内容と例
遺産分割協議書は、相続人全員が相続内容について合意したことを証明する法的に非常に重要な書類です。特に代償分割を行う場合には、「誰が何を取得し」「誰にいくら代償金を支払うのか」といった情報を明確かつ正確に記載する必要があります。
この章では、代償分割における記載のポイントと、参考となる記載例について解説します。
代償分割を正確に記載するポイント
遺産分割協議書の作成は、複数の相続人がいる場合、基本的に被相続人の口座の解約(故人の死亡が確認されると金融機関から口座を凍結されるため)、被相続人の不動産資産の所有権移転登記等を行う際に必須です。
また、代償金を支払う旨が未記載だと、代償金を受け取る人に税務署から贈与税が課せられるおそれもあります。
そのため代償分割を伴う遺産分割協議書には、次の内容を必ず明記しましょう。
- 被相続人の最後の住所や氏名・死亡日
- 相続人全員が合意した内容
- 引き継ぐ相続財産の詳細
- 代償金を支払う旨
- 相続人全員の氏名と住所、実印の押印
代償金を支払う旨の記載は、例えば「代償金として相続人〇〇に、金〇〇〇〇円を支払う」という内容となります。
記載例・テンプレートの参考
遺産分割協議書
被相続人〇〇〇〇(最終住所:東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番地、生年月日:昭和○年○月○日、死亡日:令和○年○月○日)について、下記のとおり遺産分割の協議が成立した。
1.不動産(東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番地の宅地及び建物)は、相続人〇〇〇〇が取得する。
2.相続人〇〇〇〇は、上記不動産の取得に代償するため、相続人△△△△に対し、金1,500万円を支払う。
3.上記以外の遺産(預貯金等)は、別紙財産目録に基づき、各相続人の法定相続分に従って分割する。
本協議書の内容に相違ないことを確認の上、相続人全員が記名押印する。
令和○年○月○日
(相続人署名・住所・実印)
〇〇〇〇(印)
△△△△(印)
□□□□(印)
このように、簡潔かつ具体的に「誰が何を取得し、誰が誰にいくら支払うか」を明記することが重要です。
また、不動産の記載に関しては、登記事項証明書と一致させる必要があるため、法務局の登記情報を参考にしながら記載してください。
参考:法務省「不動産登記の申請書様式について」
よくある疑問とその対応
代償分割を検討する中で、多くの方が直面するのが「このやり方で本当に問題ないのか?」「税金はどうなる?」「トラブルが起きたらどうすれば?」といった実務上の不安です。
この章では、特に相談の多い代表的な疑問について、具体的な回答と共に整理します。
代償分割と換価分割の違いは?
代償分割は、相続人の1人が遺産を取得し、その代わりに他の相続人へ「代償金」を支払ってバランスを取る方法です。一方、換価分割は、相続財産をいったん売却し、現金化した上で分け合う方法です。
| 比較項目 | 代償分割 | 換価分割 |
| 遺産の形 | 形のまま残す(不動産など) | 売却して現金化 |
| メリット | 居住継続・事業承継がしやすい | 公平な分配がしやすい |
| デメリット | 代償金の支払いが必要 | 市況によって価格が変動 |
両者は目的が大きく異なるため、「不動産を保持したいか、それとも現金で分けたいか」によって適切な方法を選びましょう。
代償金の支払期限はいつまで?
法律上、代償金の支払期限について明確な期限規定はありません。しかし、遺産分割協議の中で定めた支払条件に従って実行されるのが通常です。
実務上は、相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)までに支払いを終えておくことが望ましく、そうすることで小規模宅地等の特例など、税務上のメリットを享受できる場合もあります。
遅延や分割払いとする場合は、協議書に期日や分割回数、支払方法を明記しておくことでトラブルを予防できます。
ローンで代償金を支払ってもよい?
はい、代償金の支払いにローン(たとえば金融機関からの借入)を利用することも可能です。特に不動産を取得する相続人が現金を持っていない場合、ローンによる代償金支払いはよくある方法です。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 返済負担による家計圧迫のリスク
- 分割払いが他の相続人の同意を得られるかどうか
- 金融機関の融資審査に通るかどうか
また、支払能力に不安がある場合は、代償分割ではなく換価分割や共有分割を検討する方が無難なケースもあります。
代償分割の拒否・トラブル時の対応策
代償分割は相続人全員の合意が必要な任意の方法です。そのため、1人でも拒否する相続人がいれば成立しません。
トラブルが起きた場合の主な対応策は次のとおりです。
①第三者を交えた協議
弁護士や司法書士、税理士など専門家に入ってもらい、中立的な調整を図ります。
②家庭裁判所への遺産分割調停の申立て
合意が得られない場合、家庭裁判所に申立てを行い、調停手続きを通じて解決を目指します。
③調停が不成立の場合、審判へ移行
裁判官が法定相続分や資産の実態に基づいて、分割方法を最終的に決定します。
早期に専門家へ相談することで、争いを未然に防ぎ、円満な相続の実現につなげることができます。
専門家への相談を検討する方へ
代償分割は、一見シンプルな制度に見えるかもしれませんが、実際には「相続人間の合意形成」「財産評価の妥当性」「税務処理の適正性」といった複雑な要素が絡んできます。特に不動産が絡む相続では、税金・登記・評価額のずれが大きなトラブルの火種となることも少なくありません。
そのため、相続の話し合いがまとまらない、代償金の金額に迷う、協議書の書き方が分からないといった悩みを抱えている方は、できるだけ早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すべきケース
以下のような場合は、弁護士など法的専門職のサポートを受けるのが安心です。
- 相続人同士の意見が対立しており、話し合いが進まない
- 代償金の支払い方法や金額をめぐって不満が出ている
- 相続財産に非上場株式や事業用資産など、評価が難しいものが含まれている
- すでに相続トラブルに発展し、法的手続きが視野に入っている
弁護士は、相続人の間の利害調整だけでなく、税務署や家庭裁判所との対応にも精通しており、最適な分割方法の設計から実行までを一貫して支援してくれます。
また、「円満相続ラボ」では、相続に関する基本知識やトラブル回避の方法をわかりやすくお伝えし、専門家によるサポートを提供しています。相続の状況は家庭によって千差万別。だからこそ、円満な相続を実現するための最適なご提案をいたします。
また、相続に関する疑問がある方には、相続診断士による無料相談窓口もご利用いただけます。ご家族での相談、手続きの進め方に迷ったときなど、どうぞお気軽にご相談ください。
相談前に準備しておくとよい情報
相談をスムーズに進めるためには、以下のような情報をあらかじめ整理しておくと効果的です。
- 被相続人の財産一覧(不動産、預貯金、株式など)
- 各財産の概算評価額
- 相続人の人数と関係性
- すでに行われた話し合いの内容や合意事項
- 支払い能力や希望する相続の方向性
これらの情報が揃っていれば、専門家も状況を正確に把握でき、より的確なアドバイスが可能になります。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を監修したのは…

東京丸の内法律事務所 パートナー弁護士
清水 豊(しみず ゆたか)
行政書士、司法書士、税理士、FPと連携して相続相談会を20か所以上で開催し多くのご相談をお受けして参りました。
その経験から相続のトラブルを回避するには遺言の準備が大切であり、遺言を正しく作成するには専門家のアドバイスが不可欠だと感じています。遺言の書き方セミナーも開催しておりますのでお問い合わせください。
経営者の相続については、株式の扱い、相続後のガバナンス体制の構築が重要です。こうした経営者の相続についてもご相談をお受けしております。








