相続税の非課税枠はいくら?計算方法と節税対策を税理士が徹底解説

相続税の非課税枠について詳しく知りたい方向けに、基礎控除額の計算方法から配偶者の税額軽減制度、生命保険金や退職手当金の非課税枠まで、税理士が分かりやすく解説します。この記事を読むことで、あなたの相続財産に対する相続税額を正確に把握し、効果的な節税対策を立てることができるようになります。
Contents
1. 相続税の非課税枠とは
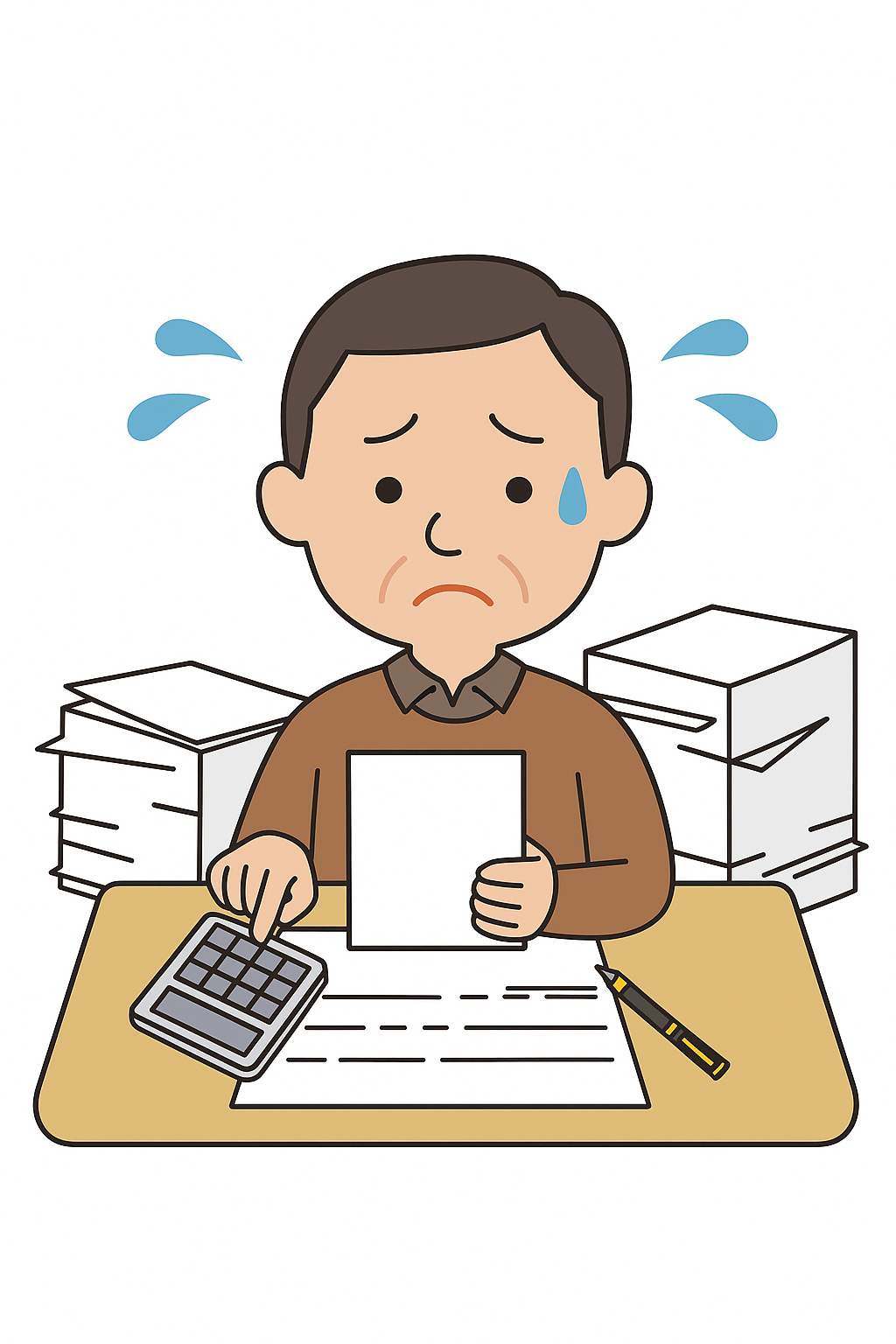
1.1 相続税の基本的な仕組み
相続税は、被相続人(亡くなった方)から相続人が財産を取得した際に課される国税です。日本では相続開始時点で被相続人の住所が日本国内にある場合、または相続人の住所が日本国内にある場合に相続税の課税対象となります。
相続税の課税対象となる財産には、現金・預貯金・株式・不動産・貴金属などの積極財産だけでなく、借入金や未払金などの消極財産も含まれます。相続税は正味の遺産額(積極財産から消極財産を差し引いた金額)に対して課税されるのが基本的な仕組みです。
ただし、すべての相続で相続税が課されるわけではありません。相続税には様々な控除制度や特例措置が設けられており、これらを適用することで税負担を軽減したり、場合によっては相続税を非課税とすることが可能です。
1.2 非課税枠の種類と概要
相続税における非課税枠は、相続財産から一定金額を控除することで税負担を軽減する制度の総称です。これらの制度を適切に活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる場合があります。
主要な非課税枠は以下の通りです:
| 非課税枠の種類 | 適用対象 | 控除額・特例内容 |
| 基礎控除 | すべての相続 | 3,000万円+600万円×法定相続人数 |
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が取得する財産 | 1億6,000万円または法定相続分まで |
| 生命保険金の非課税枠 | 死亡保険金 | 500万円×法定相続人数 |
| 退職手当金の非課税枠 | 死亡退職金等 | 500万円×法定相続人数 |
| 小規模宅地等の特例 | 居住用・事業用宅地 | 評価額の50%~80%減額 |
基礎控除は相続税における最も基本的な非課税枠で、すべての相続において適用されます。平成27年1月1日以降の相続では、「3,000万円+600万円×法定相続人数」で計算され、正味の遺産額がこの金額以下の場合は相続税がかかりません。
配偶者の税額軽減制度は、配偶者が相続する財産について非常に大きな優遇措置を提供しています。配偶者が取得した財産については、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかからないという制度です。
生命保険金や退職手当金についても、それぞれ「500万円×法定相続人数」の非課税枠が設けられています。これらの非課税枠は基礎控除とは別枠で適用されるため、相続税対策として生命保険を活用する方法が広く用いられています。
小規模宅地等の特例は、居住用や事業用の宅地について評価額を大幅に減額する制度です。適用要件を満たせば、居住用宅地で最大80%、事業用宅地で最大80%の評価減を受けることができ、実質的な非課税効果をもたらします。
これらの非課税枠を理解し適切に活用することで、相続税の負担を合法的に軽減することが可能です。ただし、それぞれに詳細な適用要件や手続きが定められているため、専門家のアドバイスを受けながら対策を検討することが重要です。
2. 相続税の基礎控除額
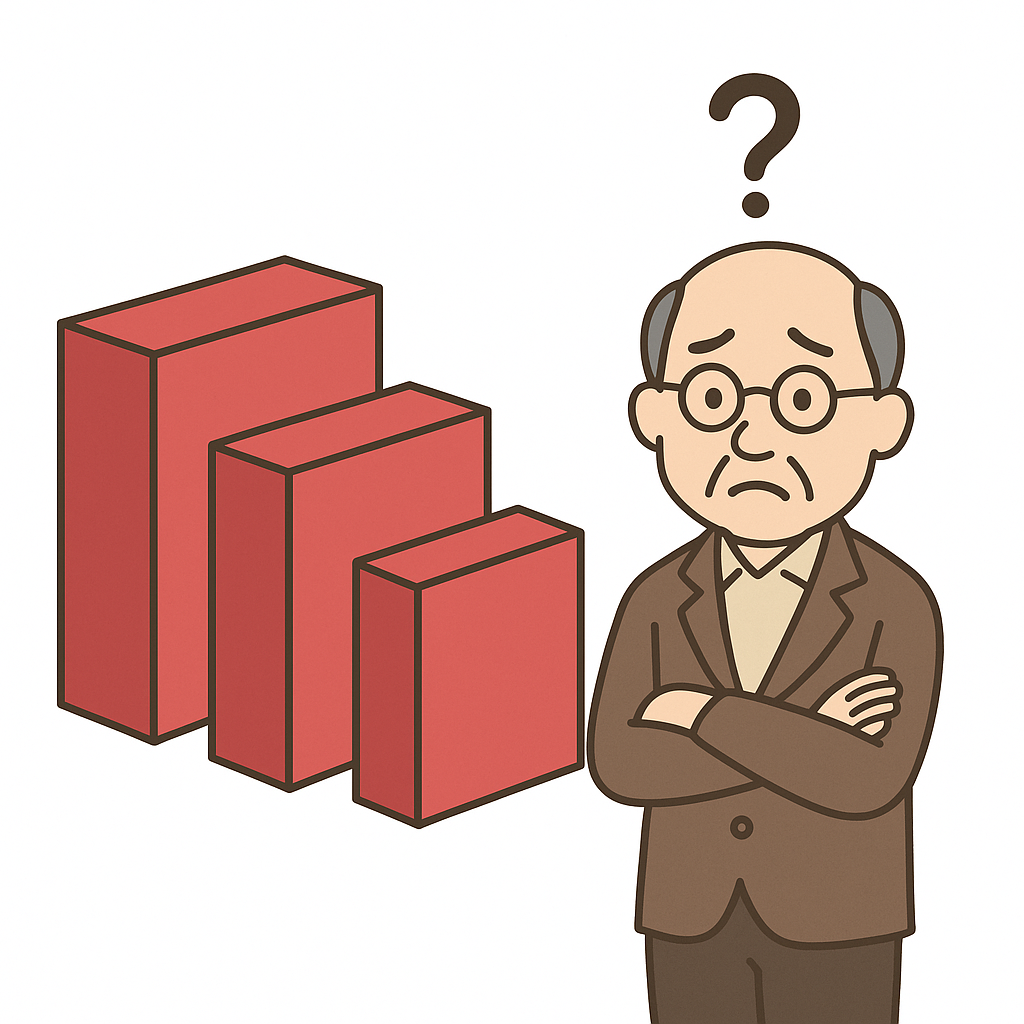
2.1 基礎控除額の計算式
相続税の基礎控除額は、3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数で計算されます。この基礎控除額以下の相続財産については、相続税は一切かかりません。
基礎控除額の計算における重要なポイントは以下の通りです。
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 定額控除 | 3,000万円 | 法定相続人の数に関係なく一律 |
| 比例控除 | 600万円 × 法定相続人の数 | 法定相続人1人につき600万円 |
この基礎控除額は平成27年1月1日以降に開始した相続から適用されており、それ以前は定額控除が5,000万円、比例控除が1,000万円でした。税制改正により、基礎控除額が大幅に引き下げられたため、相続税の対象となる相続が大幅に増加しました。
2.2 法定相続人の数え方
基礎控除額の計算で最も重要となるのが、法定相続人の数の正確な算定です。法定相続人の数え方には、以下のルールがあります。
相続放棄をした人も法定相続人の数に含めることが重要なポイントです。相続放棄があっても基礎控除額の計算上は、放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。
| 相続順位 | 法定相続人 | 相続分 |
| 配偶者 | 常に相続人 | 第1順位:1/2、第2順位:2/3、第3順位:3/4 |
| 第1順位 | 子・孫(直系卑属) | 配偶者がいる場合:1/2、いない場合:全部 |
| 第2順位 | 父母・祖父母(直系尊属) | 配偶者がいる場合:1/3、いない場合:全部 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹・甥姪 | 配偶者がいる場合:1/4、いない場合:全部 |
養子がいる場合の法定相続人の数の計算には特別なルールがあります。
- 実子がいる場合:養子は1人まで法定相続人の数に加算
- 実子がいない場合:養子は2人まで法定相続人の数に加算
ただし、以下の場合は養子の数の制限を受けません。
- 被相続人との特別養子縁組により養子となった人
- 被相続人の配偶者の実の子で被相続人の養子となった人
- 被相続人の実の子や養子、直系卑属が既に死亡しているか相続権を失ったため、その子が代襲相続人となった場合
2.3 基礎控除額の具体例
基礎控除額の計算について、具体的なケースを見てみましょう。
2.3.1 ケース1:配偶者と子2人の場合
被相続人に配偶者と子2人がいる場合の基礎控除額は以下のようになります。
| 項目 | 計算 | 金額 |
| 法定相続人の数 | 配偶者1人 + 子2人 | 3人 |
| 定額控除 | – | 3,000万円 |
| 比例控除 | 600万円 × 3人 | 1,800万円 |
| 基礎控除額合計 | 3,000万円 + 1,800万円 | 4,800万円 |
2.3.2 ケース2:配偶者のみの場合
被相続人に配偶者のみがいる場合の基礎控除額は以下のようになります。
| 項目 | 計算 | 金額 |
| 法定相続人の数 | 配偶者1人 | 1人 |
| 定額控除 | – | 3,000万円 |
| 比例控除 | 600万円 × 1人 | 600万円 |
| 基礎控除額合計 | 3,000万円 + 600万円 | 3,600万円 |
2.3.3 ケース3:相続放棄がある場合
被相続人に配偶者と子3人がおり、そのうち1人の子が相続放棄をした場合でも、基礎控除額の計算では放棄がなかったものとして計算します。
| 項目 | 計算 | 金額 |
| 法定相続人の数 | 配偶者1人 + 子3人(相続放棄1人含む) | 4人 |
| 定額控除 | – | 3,000万円 |
| 比例控除 | 600万円 × 4人 | 2,400万円 |
| 基礎控除額合計 | 3,000万円 + 2,400万円 | 5,400万円 |
このように、相続放棄があっても基礎控除額の計算には影響しないことを理解しておくことが重要です。これは相続税の負担軽減を目的とした制度であり、相続放棄による基礎控除額の減少を防ぐ仕組みとなっています。
基礎控除額を正確に把握することで、相続税の申告が必要かどうかの判断ができるようになります。相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要となるため、早めの準備が重要です。
3. 配偶者の税額軽減制度

配偶者の税額軽減制度は、相続税における最も重要な非課税制度の一つです。この制度により、配偶者が相続する財産については大幅な税額軽減が受けられ、多くのケースで相続税負担を大きく軽減できます。
3.1 配偶者控除の適用条件
配偶者の税額軽減制度を利用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
| 適用条件 | 詳細 |
| 法律上の配偶者 | 被相続人と法律上の婚姻関係にある配偶者であること |
| 相続税の申告 | 相続税の申告書を提出すること |
| 申告期限の遵守 | 相続開始から10ヶ月以内に申告書を提出すること |
| 遺産分割の確定 | 相続税の申告期限までに遺産分割が確定していること |
内縁関係や事実婚の場合は、法律上の配偶者ではないため、この制度の適用を受けることができません。また、相続税がゼロになる場合でも、配偶者の税額軽減制度を利用する際は必ず相続税の申告が必要となります。
遺産分割が申告期限までに確定しない場合は、いったん法定相続分で申告を行い、分割確定後に更正の請求を行うことで制度の適用が可能です。
3.2 1億6000万円または法定相続分までの非課税
配偶者の税額軽減制度では、配偶者が相続する財産について以下のいずれか多い方の金額まで相続税が非課税となります。
| 軽減額の基準 | 金額・割合 | 備考 |
| 定額控除 | 1億6000万円 | ・相続財産の総額に関係なく適用 ・配偶者が実際に取得をした財産の価額が1億6,000万円まで |
| 法定相続分 | 配偶者の法定相続分相当額 | 相続財産が多い場合に有利 |
例えば、相続財産が5億円の場合、配偶者の法定相続分が2分の1であれば、2億5000万円まで非課税となります。この場合、1億6000万円より法定相続分の2億5000万円の方が多いため、2億5000万円まで相続税が課税されません。
法定相続分は相続人の構成によって以下のように決まります。
| 相続人の構成 | 配偶者の法定相続分 |
| 配偶者と子 | 2分の1 |
| 配偶者と直系尊属(父母等) | 3分の2 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 |
| 配偶者のみ | すべて |
3.3 配偶者控除を利用する際の注意点
配偶者の税額軽減制度は非常に有利な制度ですが、利用する際には以下の点に注意が必要です。
二次相続への影響を考慮する必要があります。配偶者が多くの財産を相続すると、配偶者が亡くなった際の二次相続で子どもたちの相続税負担が大きくなる可能性があります。一次相続と二次相続の合計税額を試算し、最適な遺産分割を検討することが重要です。
小規模宅地等の特例との併用については、配偶者が居住用宅地を相続する場合、小規模宅地等の特例を適用するよりも、子どもが相続して特例を適用した方が税務上有利になるケースがあります。
申告手続きについては、配偶者の税額軽減制度を適用する場合、以下の書類の提出が必要です。
| 必要書類 | 取得先 |
| 戸籍謄本 | 市区町村役場 |
| 遺産分割協議書の写し | 相続人間で作成 |
| 相続税の申告書 | 税務署 |
また、配偶者が日本国籍を有しない場合や日本に住所を有しない場合には、特別な手続きや制限があるため、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
将来の税制改正リスクも考慮すべき点です。配偶者の税額軽減制度は現行制度に基づくものであり、将来の税制改正により制度内容が変更される可能性があります。長期的な相続対策を検討する際は、このようなリスクも含めて検討することが大切です。
4. その他の相続税非課税枠

基礎控除額や配偶者の税額軽減制度以外にも、相続税には様々な非課税枠や特例措置が設けられています。これらの制度を適切に活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる場合があります。
4.1 生命保険金の非課税枠
被相続人が被保険者となっている生命保険金については、法定相続人1人当たり500万円までが非課税となります。この非課税枠は相続税の基礎控除とは別枠で適用されるため、相続税対策として非常に有効です。
| 法定相続人の数 | 生命保険金の非課税限度額 | 計算式 |
| 1人 | 500万円 | 500万円×1人 |
| 2人 | 1,000万円 | 500万円×2人 |
| 3人 | 1,500万円 | 500万円×3人 |
| 4人 | 2,000万円 | 500万円×4人 |
ただし、この非課税枠が適用されるのは、相続人が取得した生命保険金のみです。相続を放棄した人や相続権を失った人が取得した保険金は対象外となります。また、保険金の受取人が相続人以外の場合は遺贈の対象となるため注意が必要です。
4.2 退職手当金の非課税枠
被相続人の死亡により支給される退職手当金、功労金、その他これらに準ずる給与についても、生命保険金と同様の非課税枠が設けられています。法定相続人1人当たり500万円までが非課税となります。
退職手当金の非課税枠の対象となる主な給付は以下の通りです:
- 退職手当金
- 功労金
- 慰労金
- 企業年金
- 小規模企業共済の共済金
なお、生命保険金と退職手当金の非課税枠はそれぞれ独立して適用されるため、両方の制度を活用することで最大限の節税効果を得ることができます。
4.3 小規模宅地等の特例
相続税における小規模宅地等の特例は、被相続人や同族会社が事業や居住用として使用していた宅地について、一定の要件を満たした場合に評価額を大幅に減額できる制度です。この特例により、実質的に相続税の負担を軽減することが可能です。
| 宅地の種類 | 限度面積 | 減額割合 | 主な適用要件 |
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80%減額 | 被相続人の居住用、配偶者または同居親族が取得 |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80%減額 | 被相続人の事業用、事業を継承する親族が取得 |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80%減額 | 同族会社の事業用、会社の株式等を相続する親族が取得 |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50%減額 | 被相続人の貸付事業用、事業を継承する親族が取得 |
この特例を適用するには、相続税の申告期限まで宅地等を所有し続け、居住または事業を継続する必要があります。また、複数の宅地がある場合は、調整計算により適用面積の上限が設けられています。
4.4 贈与税の基礎控除額との関係
相続税の非課税枠を考える際には、贈与税との関係も重要です。贈与税には年間110万円の基礎控除があり、これを活用した生前贈与により相続財産を減らすことで、相続税の負担を軽減できます。
相続開始前3年以内(令和6年1月1日以降は7年以内に段階的に延長)に行われた贈与については、相続財産に加算されるため注意が必要です。ただし、以下の贈与については加算対象外となります:
- 配偶者控除(居住用不動産等の贈与)
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置
- 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置
- 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置
これらの特例制度を組み合わせることで、効果的な相続税対策を実現することが可能です。ただし、それぞれの制度には詳細な適用要件があるため、専門家に相談することをお勧めします。
5. 相続税非課税枠の計算方法

5.1 相続税額の算出手順
相続税の計算は複数のステップを踏んで行われます。正確な計算手順を理解することで、適切な相続税額を算出できます。
相続税額の算出は以下の6つのステップで進めていきます。
| ステップ | 計算内容 | 詳細 |
| 1 | 遺産総額の算出 | 相続財産から債務・葬式費用を差し引く |
| 2 | 課税遺産総額の計算 | 遺産総額から基礎控除額を差し引く |
| 3 | 相続税の総額の計算 | 法定相続分で按分し税率を適用 |
| 4 | 各人の算出税額の計算 | 実際の相続割合で按分 |
| 5 | 税額控除の適用 | 配偶者控除等を適用 |
| 6 | 納付税額の確定 | 最終的な納税額を算出 |
基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となります。この金額を超える遺産がある場合のみ、相続税の申告と納税が必要となります。
相続税の税率は累進課税制度を採用しており、課税遺産総額が大きいほど税率も高くなります。税率は10%から最高55%まで8段階に分かれています。
5.2 実際の計算例
具体的な計算例を用いて、相続税額の算出過程を詳しく解説します。
【計算例】被相続人:父、相続人:母・長男・次男の3人
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 相続財産 | 1億2,000万円 | 現金・不動産・有価証券等 |
| 債務・葬式費用 | 200万円 | 借入金・葬式費用等 |
| 遺産総額 | 1億1,800万円 | 相続財産-債務・葬式費用 |
| 基礎控除額 | 4,800万円 | 3,000万円+600万円×3人 |
| 課税遺産総額 | 7,000万円 | 遺産総額-基礎控除額 |
法定相続分による相続税の総額計算:
| 相続人 | 法定相続分 | 取得金額 | 税率 | 控除額 | 税額 |
| 配偶者(母) | 1/2 | 3,500万円 | 20% | 200万円 | 500万円 |
| 長男 | 1/4 | 1,750万円 | 15% | 50万円 | 212.5万円 |
| 次男 | 1/4 | 1,750万円 | 15% | 50万円 | 212.5万円 |
| 相続税の総額 | 925万円 | ||||
実際の相続割合で按分した場合(母が6,000万円、長男・次男がそれぞれ2,900万円を相続):
配偶者は配偶者の税額軽減により税額が0円となり、長男・次男はそれぞれ約236万円の相続税を納付することになります。
5.3 よくある計算間違いと対策
相続税の計算において、多くの方が間違いやすいポイントがあります。正確な申告のためにも、これらの注意点を押さえておくことが重要です。
1. 法定相続人の数え方の間違い
養子がいる場合、実子がいるときは養子1人まで、実子がいないときは養子2人までしか法定相続人として算入できません。また、相続放棄をした人も法定相続人として数えます。
2. 財産評価の間違い
不動産の評価において、路線価や固定資産税評価額を正しく適用していないケースがあります。土地については路線価方式または倍率方式で評価し、建物については固定資産税評価額で評価します。
3. 債務控除の適用漏れ
被相続人の借入金や未払金、葬式費用などの債務控除を適用し忘れることがあります。これらは遺産総額から差し引くことができます。
4. 配偶者の税額軽減の適用間違い
配偶者の税額軽減は、相続税の申告期限までに遺産分割が確定している必要があります。未分割の状態では適用できないため、期限までに分割協議を完了させることが必要です。
5. 小規模宅地等の特例の適用要件の確認不足
居住用宅地や事業用宅地について適用できる小規模宅地等の特例は、適用要件が複雑です。配偶者や同居親族、家業継承者など、適用対象者の要件を正確に確認する必要があります。
| 間違いやすいポイント | 正しい対応 | 影響 |
| 生命保険金を遺産に含める | 非課税枠(500万円×法定相続人数)を適用 | 税額が過大になる |
| 退職手当金を遺産に含める | 非課税枠(500万円×法定相続人数)を適用 | 税額が過大になる |
| 相続放棄者を法定相続人から除外 | 基礎控除額の計算には含める | 基礎控除額が過少になる |
| 配偶者控除を自動適用 | 申告書への記載と添付書類が必要 | 控除が適用されない |
これらの間違いを防ぐためには、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に相続財産が複雑な場合や、特例の適用を検討する場合には、専門知識が不可欠です。
6. 相続税の節税対策

相続税の節税対策は、事前の準備と計画的な実行が重要です。法律に基づいた適切な方法を選択することで、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。ここでは、実効性の高い主要な節税対策について詳しく解説します。
6.1 生前贈与を活用した節税方法
生前贈与は相続税対策として最も基本的かつ効果的な手法の一つです。贈与税の基礎控除額110万円を毎年活用することで、相続財産を段階的に減少させることができます。
6.1.1 暦年贈与の活用
暦年贈与では、1年間に110万円以下の贈与であれば贈与税がかかりません。複数の相続人に対して継続的に贈与を行うことで、相続財産の圧縮効果を高めることができます。
| 贈与先 | 年間贈与額 | 10年間の総贈与額 | 贈与税 |
| 配偶者 | 110万円 | 1,100万円 | 0円 |
| 長男 | 110万円 | 1,100万円 | 0円 |
| 長女 | 110万円 | 1,100万円 | 0円 |
| 合計 | 330万円 | 3,300万円 | 0円 |
6.1.2 相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫への贈与について、2,500万円まで贈与税を課税せずに贈与できる制度です。将来値上がりが期待される資産の贈与に特に有効です。
6.1.3 住宅取得等資金の贈与の非課税制度
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となります。省エネ等住宅の場合は1,000万円、その他の住宅の場合は500万円まで非課税となります。
6.2 養子縁組による基礎控除額の増加
養子縁組は相続税の基礎控除額を増加させる効果的な手法です。法定相続人の数が増えることで基礎控除額が600万円ずつ増加し、相続税の負担軽減につながります。
6.2.1 養子縁組による控除額の増加効果
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。養子縁組により法定相続人が1人増えると、基礎控除額が600万円増加します。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 控除額の増加 |
| 2人(配偶者、子1人) | 4,200万円 | – |
| 3人(配偶者、子1人、養子1人) | 4,800万円 | 600万円増 |
| 4人(配偶者、子1人、養子2人) | 5,400万円 | 1,200万円増 |
6.2.2 養子縁組の注意点
養子縁組による相続税対策には制限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に含めることができます。また、相続税回避のみを目的とした養子縁組は税務署から否認される可能性があるため、適切な手続きと合理的な理由が必要です。
6.3 不動産を活用した相続税対策
不動産は相続税評価額が時価よりも低くなるため、現金を不動産に変えることで相続財産の評価額を圧縮できます。特に賃貸不動産は評価減の効果が大きく、効果的な節税対策となります。
6.3.1 小規模宅地等の特例
被相続人の居住用宅地や事業用宅地について、一定の要件を満たす場合に相続税評価額を50%から80%減額できる特例です。
| 宅地の種類 | 限度面積 | 減額割合 | 適用要件 |
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80%減 | 配偶者または同居親族が取得 |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80%減 | 事業を継続する親族が取得 |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50%減 | 貸付事業を継続する親族が取得 |
6.3.2 賃貸不動産による評価減効果
賃貸マンションやアパートなどの賃貸用不動産は、自用地や自用建物と比較して相続税評価額が低くなります。土地は貸家建付地として約20%、建物は貸家として約30%の評価減が適用されます。
6.3.3 タワーマンション節税
高層階のタワーマンションは、相続税評価額と実際の取引価格に大きな差が生じることがあります。ただし、過度な節税目的での購入は税務署から否認される可能性があるため、注意が必要です。
6.4 生命保険を活用した節税対策
生命保険は相続税対策として非常に有効なツールです。死亡保険金には非課税枠があり、相続税の軽減効果と納税資金の準備を同時に実現できます。
6.4.1 生命保険金の非課税枠
相続人が受け取る死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」まで相続税が非課税となります。この非課税枠を最大限活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できます。
| 法定相続人の数 | 生命保険金の非課税枠 | 課税対象となる保険金 |
| 2人 | 1,000万円 | 1,000万円超の部分 |
| 3人 | 1,500万円 | 1,500万円超の部分 |
| 4人 | 2,000万円 | 2,000万円超の部分 |
6.4.2 生命保険の契約形態による税務上の違い
生命保険の契約形態により、課税される税金の種類が変わります。相続税対策として最も効果的なのは、被相続人が契約者・被保険者となり、相続人が受益者となる契約形態です。
6.4.3 一時払い終身保険の活用
高齢者でも加入しやすい一時払い終身保険は、現金を保険に変えることで相続税の非課税枠を活用できます。また、保険金は受取人固有の財産として遺産分割協議の対象外となるため、相続手続きの円滑化にも寄与します。
6.4.4 暦年贈与と組み合わせた保険料支払い
毎年の基礎控除額110万円を活用して、相続人が保険料を支払う方法もあります。この場合、保険金は相続人固有の財産となり、相続税の課税対象外となります。ただし、暦年贈与による保険料の支払いは「生前贈与加算(相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算される)」の対象となる場合があるため、注意が必要です。長期間にわたって実施することで、より大きな節税効果を得ることができます。
7. 相続税申告の手続きと注意点

7.1 申告が必要となる場合
相続税の申告が必要となるのは、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、例えば法定相続人が2人の場合は4,200万円、3人の場合は4,800万円となります。
ただし、以下のような特例を利用する場合は、相続財産が基礎控除額以下であっても申告が必要となります:
| 特例名 | 申告の必要性 | 主な条件 |
| 配偶者の税額軽減 | 必要 | 配偶者が相続する場合 |
| 小規模宅地等の特例 | 必要 | 居住用・事業用宅地を相続する場合 |
| 農地等の納税猶予の特例 | 必要 | 農業を継続する相続人が農地を相続する場合 |
これらの特例を適用することで相続税額がゼロになる場合でも、申告書の提出は義務となっています。申告を怠ると特例の適用が受けられなくなる可能性があるため注意が必要です。
7.2 申告期限と必要書類
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。例えば、2024年1月15日に死亡した場合、申告期限は2024年11月15日となります。期限が土日祝日の場合は、翌営業日が期限となります。
申告に必要な主な書類は以下のとおりです:
7.2.1 基本的な申告書類
- 相続税の申告書(第1表から第15表)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
- 遺言書の写し(遺言書がある場合)
7.2.2 財産評価に関する書類
- 固定資産評価証明書
- 土地の登記事項証明書
- 建物の登記事項証明書
- 預貯金の残高証明書
- 有価証券の評価証明書
- 生命保険金支払通知書
- 退職手当金等の支払調書
申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署となります。郵送での提出も可能ですが、配達記録が残る方法での送付が推奨されます。
7.3 税務調査の対象となりやすいケース
国税庁の統計によると、相続税の税務調査は申告件数の約10〜15%程度で実施されています。税務調査の対象となりやすいケースには以下のような特徴があります:
7.3.1 財産規模が大きい場合
相続財産の総額が3億円を超えるような大規模な相続では、調査対象となる可能性が高くなります。特に不動産の評価額が高い場合や、複数の事業を営んでいた場合は注意が必要です。
7.3.2 申告内容に疑義がある場合
以下のような申告内容は調査対象となりやすいとされています:
| 疑義のポイント | 具体例 | 対策 |
| 預貯金の申告漏れ | 名義預金、海外資産の未申告 | 全ての金融機関を調査し、正確に申告 |
| 不動産の評価額 | 路線価との大幅な乖離 | 不動産鑑定士による適正な評価 |
| 生前贈与の取扱い | 贈与契約書の不備、名義預金 | 適切な贈与手続きの実施 |
7.3.3 生前の資金移動が多い場合
被相続人が亡くなる前の3年間に多額の資金移動がある場合、生前贈与として適切に処理されているかが調査されることがあります。特に、贈与契約書が作成されていない資金移動や、贈与税の申告が行われていない場合は注意が必要です。
また、実務上は多額の資金移動について、その使用目的や支出内容が正当であるかを確認できる書類(領収書・振込記録など)を保管しておくことが重要です。
税務調査への対応準備として、申告書の控えと関連書類は7年間保存し、調査時には税理士への依頼を検討することが重要です。また、申告前から税理士に相談し、適切な申告書の作成と証拠書類の整備を行うことで、調査リスクを軽減できます。
8. 税制改正による非課税枠の変更点

8.1 過去の税制改正の推移
相続税の非課税枠は、社会情勢や税収確保の観点から定期的に見直しが行われてきました。特に平成27年(2015年)1月1日からの大幅な改正は、相続税の課税対象者を大幅に拡大する重要な変更となりました。
8.1.1 平成27年改正の主要な変更点
平成27年の税制改正では、相続税の基礎控除額が大幅に縮小されました。この改正により、相続税の課税対象となる世帯数は約2倍に増加しています。
| 項目 | 改正前(平成26年12月31日まで) | 改正後(平成27年1月1日以降) |
| 基礎控除額 | 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
| 税率構造 | 最高税率50%(6段階) | 最高税率55%(8段階) |
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の場合、改正前は8,000万円だった基礎控除額が、改正後は4,800万円に減額されました。これにより、従来は相続税の対象外だった多くの一般家庭が課税対象となっています。
8.1.2 過去の主要な税制改正
平成27年改正以前にも、相続税制度は段階的に変更されてきました。
| 改正年 | 主な変更内容 | 背景・目的 |
| 平成15年 | 配偶者の税額軽減制度の拡充 | 高齢化社会への対応 |
| 平成21年 | 小規模宅地等の特例の拡充 | 居住用・事業用財産の保護 |
| 平成25年 | 教育資金一括贈与の特例創設 | 世代間資産移転の促進 |
8.1.3 特例制度の変遷
相続税の特例制度についても、時代とともに見直しが行われています。特に小規模宅地等の特例は適用面積や減額割合が段階的に拡充されており、居住用宅地については330平方メートルまで80%の評価減が適用されています。
生命保険金の非課税枠についても、平成27年改正において基本的な枠組みは維持されたものの、基礎控除額の縮小により相対的な節税効果が高まっています。
8.2 今後の税制改正の動向
相続税制度は、社会保障制度の持続可能性や所得格差の是正といった社会的課題を背景に、今後も見直しが検討される可能性があります。
8.2.1 検討が想定される主要論点
基礎控除額のさらなる見直しについては、税収確保の観点から議論される可能性があります。特に都市部での不動産価格上昇により、一般的な住宅であっても課税対象となるケースが増加していることから、制度の在り方が注目されています。
配偶者の税額軽減制度についても、高齢化の進展や家族形態の多様化を踏まえた制度設計の見直しが議論される可能性があります。現行制度は法定相続分または1億6,000万円までの非課税を認めていますが、この水準の適切性について検証が行われる可能性があります。
8.2.2 国際的な動向との整合性
日本の相続税制度は、国際的に見ても比較的重い税負担となっています。グローバル化の進展により、国際的な税制調和や二重課税の回避といった観点からの制度見直しも重要な論点となっています。
特に、海外資産を保有する富裕層の増加や、国際的な資産移転への対応として、情報交換制度の拡充や申告制度の強化が進められています。
8.2.3 デジタル化への対応
相続手続きのデジタル化推進により、申告制度や課税実務の効率化が図られています。これに伴い、適正な課税の実現と納税者の利便性向上の両立を目指した制度改正が継続的に検討されています。
また、暗号資産(仮想通貨)やデジタル資産の相続に関する取扱いについても、技術の進歩に応じた制度整備が必要となっており、今後の重要な検討課題となっています。
9. まとめ
相続税の非課税枠には基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を始め、配偶者の税額軽減制度、生命保険金や退職手当金の非課税枠など複数の制度があります。これらを適切に活用することで相続税負担を大幅に軽減できる可能性があります。ただし、各制度には適用条件や注意点があるため、相続が発生する前から計画的な対策を行うことが重要です。相続税の申告が必要な場合は期限内に適切な手続きを行い、不明な点は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を監修したのは…

一般社団法人日本相続研究所理事兼税理士
扇山 博司(おおぎやま ひろし)
「揉めない」相続のためにそばに寄り添える専門家です。実は「遺産相続争いは、親の人生を冒涜する最も悲しい社会問題」です。相続なんて関係ないと思っている人も今現在相続について悩んでいる人も「争続」ではなく将来の「笑顔相続」のために一緒に考えていきましょう。








