誰が相続人?「相続人調査」で確実に判明させる方法と費用

相続手続きの最初の壁「相続人調査」。誰が法定相続人になるのか、その調査方法や費用に不安はありませんか?この記事では、相続人調査の重要性から、戸籍を辿って確実に相続人を判明させる具体的な手順、必要書類の取得方法、自分で進める際の費用、さらには複雑なケースで専門家に依頼するメリットと費用相場まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたは相続人調査の全貌を理解し、トラブルなく相続手続きを進めるための確かな知識と解決策を得られるでしょう。
Contents
1. 相続人調査とは?なぜ必要なのか

相続が発生した際、故人(被相続人)の財産を誰が、どのように引き継ぐのかを確定するためには、まず「誰が法的に相続人であるか」を正確に把握することが不可欠です。この、相続人を特定し、その範囲と順位を明らかにする一連の作業を「相続人調査」と呼びます。
相続人調査は、単に家族構成を確認するだけではありません。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を遡って辿り、隠れた相続人や、代襲相続、数次相続によって発生する複雑な相続関係を解明する、非常に専門的かつ重要な手続きです。
1.1 相続人調査の目的と重要性
相続人調査は、その後のすべての相続手続きの土台となる、最も初期かつ重要なステップです。主な目的と重要性は以下の通りです。
- 遺産分割協議の適正な実施: 故人の遺産をどのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」は、相続人全員の合意がなければ成立しません。相続人調査により、遺産分割協議に参加すべき全員を正確に特定し、後々のトラブルを防ぎます。
- 相続手続きの確実な進行: 不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約・名義変更、株式の移管など、あらゆる相続手続きにおいて、金融機関や法務局から相続人全員を証明する書類の提出が求められます。相続人調査で作成する「相続関係説明図」や取得した戸籍謄本類は、これらの手続きに不可欠な書類となります。
- 相続税申告の正確性確保: 相続税の申告には、相続人全員の氏名や続柄、取得財産などを正確に記載する必要があります。相続人が漏れていたり、誤った情報で申告すると、税務署からの指摘や追徴課税の対象となる可能性があります。
- 相続放棄の検討: 故人に多額の借金があった場合など、相続人が「相続放棄」を検討することがあります。相続放棄の手続きを行う際にも、自分が法的に相続人であることを証明するための戸籍謄本類が必要となります。
- 法的な義務と責任の明確化: 民法では、誰が法定相続人となるか、その順位が明確に定められています。相続人調査は、これらの民法の規定に基づき、法的に誰が相続の権利と義務を負うのかを確定させるために不可欠です。
1.2 相続人調査を怠ると起こるリスク
相続人調査を適切に行わない、あるいは軽視すると、後々深刻な問題やトラブルに発展する可能性があります。主なリスクは以下の通りです。
| リスクの種類 | 具体的な内容 |
| 遺産分割協議の無効化・やり直し | 相続人調査を怠った結果、後から新たな相続人が見つかった場合、既に行った遺産分割協議は無効となり、その相続人を含めて最初からやり直す必要が生じます。これにより、時間と労力が無駄になるだけでなく、関係者間の信頼関係が損なわれる原因にもなります。 |
| 相続手続きの停滞・不承認 | 金融機関や法務局での相続手続きは、相続人全員が確定していなければ進めることができません。不備がある場合、手続きが中断したり、申請が却下されたりするため、相続財産の凍結が長期化し、必要な資金が引き出せないなどの不都合が生じます。 |
| 親族間のトラブル・紛争 | 相続人が正確に把握されていない状態で遺産分割を進めると、「なぜあの人が相続人に入っていないのか」「私はなぜ呼ばれなかったのか」といった不信感が生じ、親族間で深刻な争いに発展するリスクが高まります。最悪の場合、裁判にまで発展するケースも少なくありません。 |
| 予期せぬ債務の相続 | 故人に借金があった場合、相続人はその債務も引き継ぐことになります。相続人調査を怠り、相続放棄の検討期間(原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内)を過ぎてから債務の存在を知った場合、放棄が困難になる可能性があります。 |
| 相続税の追徴課税・過料 | 相続人が漏れていたために、相続税の申告額が過少になった場合、税務署から追徴課税を受けたり、加算税や延滞税が課されたりすることがあります。また、申告期限に間に合わないことで無申告加算税や延滞税が発生する可能性もあります。 |
| 相続登記の義務化と罰則 | 2024年4月1日からは相続登記が義務化され、正当な理由なく申請を怠ると過料の対象となります。相続人調査の遅れは、この義務化された相続登記の申請遅延につながり、罰則を受けるリスクを高めます。 |
これらのリスクを回避し、円滑かつ確実に相続手続きを進めるためには、相続人調査を徹底し、法的に正しい相続関係を確定することが極めて重要です。
2. 相続人調査で判明する「法定相続人」の順位

相続人調査を行う最大の目的は、民法で定められた「法定相続人」を漏れなく、かつ正確に特定することです。法定相続人とは、法律によって相続する権利が認められた人のことであり、この確定がなければ遺産分割協議を進めることも、相続税の申告を行うこともできません。相続人には順位があり、特定の順位の人がいない場合に次の順位の人が相続人となります。
2.1 法定相続人の基本原則
民法では、被相続人(亡くなった人)の財産を誰が相続するかについて、明確なルールを定めています。このルールに基づいて相続人となるのが法定相続人です。
法定相続人は、常に相続人となる配偶者を除き、以下の順位で定められています。
- 第1順位:子(直系卑属)
- 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹
これらの順位は厳格に適用され、上位の順位の相続人が一人でもいる場合、下位の順位の人は相続人にはなりません。また、同じ順位の相続人が複数いる場合は、原則として均等に遺産を相続する権利(法定相続分)を持ちます。
2.2 常に相続人となる配偶者
被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に法定相続人となります。これは、他のどのような順位の相続人がいても変わらない原則です。ただし、ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にあった人を指します。
- 内縁関係のパートナーや、すでに離婚した元配偶者は、相続人にはなりません。
- 配偶者の法定相続分は、他に相続人がいるかどうか、またその相続人がどの順位であるかによって変動します。
例えば、子が相続人となる場合は配偶者と子が共同で相続し、子がいない場合は配偶者と直系尊属が共同で相続するといった形になります。
2.3 第1順位の相続人
法定相続人の第1順位は、被相続人の「子」です。子には、実子(嫡出子)、養子、非嫡出子(認知された子)のすべてが含まれます。もし被相続人の子がすでに亡くなっている場合でも、その子にさらに子(被相続人から見て孫)がいれば、その孫が「代襲相続人」として相続する権利を持ちます。
第1順位の相続人がいる場合の法定相続分は以下の通りです。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | 子の相続分 |
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2(子が複数いる場合は均等に分割) |
| 子のみ | なし | すべて(子が複数いる場合は均等に分割) |
2.4 第2順位の相続人
被相続人に第1順位の相続人(子やその代襲相続人)が一人もいない場合、第2順位の相続人として「直系尊属」が相続人となります。直系尊属とは、父母、祖父母、曽祖父母など、被相続人より前の世代の直系の血族を指します。
- 父母が健在であれば父母が相続人となり、父母がすでに亡くなっている場合は祖父母が相続人となります。
- より被相続人に近い世代の直系尊属が優先されます。例えば、父母が健在であれば祖父母は相続人になりません。
- 直系尊属には代襲相続はありません。
第2順位の相続人がいる場合の法定相続分は以下の通りです。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | 直系尊属の相続分 |
| 配偶者と直系尊属 | 2/3 | 1/3(複数いる場合は均等に分割) |
| 直系尊属のみ | なし | すべて(複数いる場合は均等に分割) |
2.5 第3順位の相続人
被相続人に第1順位の相続人(子やその代襲相続人)も、第2順位の相続人(直系尊属)も一人もいない場合、第3順位の相続人として「兄弟姉妹」が相続人となります。兄弟姉妹には、父母が同じ「全血兄弟姉妹」と、父母のどちらか一方のみが同じ「半血兄弟姉妹」がいます。
- 半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の半分と定められています。
- 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合でも、その兄弟姉妹に子(被相続人から見て甥・姪)がいれば、その甥・姪が「代襲相続人」として相続する権利を持ちます。
第3順位の相続人がいる場合の法定相続分は以下の通りです。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | 兄弟姉妹の相続分 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(複数いる場合は均等に分割、半血は全血の半分) |
| 兄弟姉妹のみ | なし | すべて(複数いる場合は均等に分割、半血は全血の半分) |
2.6 代襲相続と数次相続
相続人調査を進める中で、法定相続人の順位だけでなく、「代襲相続」や「数次相続」といった状況も考慮に入れる必要があります。これらは、相続関係を複雑にする要因となるため、正確な把握が不可欠です。
2.6.1 代襲相続とは?
代襲相続とは、相続人となるべき人が、相続開始以前に死亡していたり、相続欠格(相続人としての資格を失うこと)や廃除(被相続人によって相続権を剥奪されること)によって相続権を失っていたりした場合に、その人の子が代わりに相続人となる制度です。
代襲相続が認められるのは、以下のケースです。
- 第1順位の相続人(子)が代襲される場合:
- 被相続人の子が死亡・相続欠格・廃除となった場合、その子の子(被相続人から見て孫)が代襲相続人となります。
- さらに、その孫も死亡・相続欠格・廃除となった場合は、ひ孫が代襲相続人となる「再代襲」も発生します。
- 第3順位の相続人(兄弟姉妹)が代襲される場合:
- 被相続人の兄弟姉妹が死亡・相続欠格・廃除となった場合、その兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥・姪)が代襲相続人となります。
- 兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までで、それより下の世代への再代襲は認められません。
第2順位の相続人である直系尊属(父母、祖父母など)には、代襲相続は発生しません。例えば、被相続人の親がすでに亡くなっている場合、その親の親(被相続人の祖父母)が存命であれば、祖父母が相続人となりますが、これは代襲相続ではなく、単に世代が上の直系尊属が相続人となるためです。
2.6.2 数次相続とは?
数次相続とは、最初の相続(一次相続)の手続きが完了する前に、その相続人(二次相続の被相続人)が亡くなり、次の相続(二次相続)が連続して発生することを指します。
例えば、父が亡くなり、その相続手続き中に母も亡くなった場合、父の遺産はまず母に相続され、次に母の遺産として子が相続することになります。この場合、父の遺産について、父から母へ、そして母から子へと、二段階の相続が発生するため、非常に複雑な手続きが必要となります。
数次相続が発生すると、相続人の確定や遺産分割協議、相続税の申告などがさらに複雑になります。それぞれの相続で相続人を確定し、それぞれの相続について遺産分割協議を行う必要が生じます。戸籍調査もより広範囲にわたるため、専門家のサポートが不可欠となるケースが多いです。
法定相続人の順位に関する詳細な情報は、法務省のウェブサイトなどでも確認できます。 法務省
3. 自分でできる!相続人調査の具体的な手順と必要書類

相続人調査は、専門家に依頼せずとも、ご自身で行うことが可能です。時間と手間はかかりますが、費用を抑えたい場合や、ご自身のペースで進めたい場合には有効な手段となります。ここでは、具体的な手順と必要となる書類、そしてその取得方法について詳しく解説します。
3.1 自分で相続人調査を行う流れ
相続人調査を自分で行う場合、大きく分けて3つのステップで進めます。正確な情報を得るためには、それぞれのステップを慎重に進めることが重要です。
3.1.1 ステップ1 被相続人の出生から死亡までの戸籍を辿る
まず最初に行うべきは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍を漏れなく収集することです。これにより、被相続人の正確な身分事項(婚姻、離婚、養子縁組、認知など)が明らかになり、すべての法定相続人を網羅的に把握できます。
戸籍は、本籍地を移す「転籍」や、法改正による「改製」が行われるたびに新しい戸籍が作られます。そのため、被相続人の最後の本籍地で現在の戸籍(戸籍謄本または戸籍全部事項証明書)を取得し、その戸籍に記載されている「前の本籍地」や「改製前の戸籍」の情報をもとに、順に古い戸籍を遡って取得していく必要があります。
特に注意すべきは、被相続人に「認知した子」や「養子」がいる場合です。これらの情報は現在の戸籍には記載されていないことが多く、過去の戸籍を丹念に辿ることで初めて判明することがあります。たとえ疎遠であったとしても、法定相続人であることに変わりはなく、相続手続きには全員の同意や関与が必要となるため、非常に重要な作業です。
3.1.2 ステップ2 相続人全員の現在の戸籍を確認する
被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集めると、その戸籍に記載されている情報から、法定相続人となる可能性のある人物が判明します。次に、これらの判明した相続人全員について、現在の戸籍(戸籍謄本または戸籍全部事項証明書)を取得し、生存していることや現在の氏名、本籍地などを確認します。
相続人がすでに亡くなっている場合は、その相続人の戸籍も出生から死亡まで遡って取得し、代襲相続人がいるかどうかを確認する必要があります。代襲相続については、記事の他の章で詳しく解説されていますが、ここでその有無を判断するための情報収集を行います。
また、相続人の現在の戸籍を確認することで、現在の氏名や本籍地、生年月日などの情報を把握し、後の相続手続き(相続登記や預貯金の解約など)で必要となる情報を揃えることができます。
3.1.3 ステップ3 相続関係説明図を作成する
すべての戸籍謄本類が揃い、相続人全員の情報を確認できたら、それらの情報を基に「相続関係説明図」を作成します。相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係性を視覚的に分かりやすくまとめた家系図のようなものです。
相続関係説明図には、通常、以下の情報を記載します。
- 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の本籍地、最後の住所
- 相続人全員の氏名、生年月日、被相続人との続柄、現在の本籍地、現在の住所
- 代襲相続がある場合は、その旨と代襲相続人の情報
この相続関係説明図は、法務局での相続登記や、金融機関での預貯金解約など、さまざまな相続手続きにおいて、戸籍謄本の束に代わる添付書類として利用できるため、非常に重要な書類となります。正確に作成することで、手続きがスムーズに進みます。
3.2 相続人調査で取得する戸籍謄本の種類
相続人調査では、複数の種類の戸籍謄本等を取得することになります。それぞれの戸籍がどのような情報を含んでいるのかを理解しておくことは、調査を効率的に進める上で役立ちます。
3.2.1 戸籍謄本
現在の戸籍の正式名称は「戸籍全部事項証明書」といい、戸籍に記録されている全員について記載されたものです。一般的に「戸籍謄本」と呼ばれます。
現在の戸籍に記載されている情報は、本籍、筆頭者、そしてその戸籍に入っている全員の氏名、生年月日、父母との続柄、婚姻や離婚、養子縁組、認知といった身分事項などです。被相続人が死亡した際に、最後に属していた戸籍がこれに該当します。
3.2.2 除籍謄本
除籍謄本とは、戸籍に記載されていた全員が、婚姻や死亡、転籍などによってその戸籍から除かれた(いなくなった)状態になった戸籍のことです。戸籍に誰もいなくなった状態を「除籍」と呼びます。
被相続人が転籍を繰り返していた場合や、兄弟姉妹が結婚などで独立して被相続人だけが残った後に転籍した場合などに、過去の除籍謄本を取得する必要があります。除籍謄本には、除籍される前の身分事項が記載されており、過去の婚姻や子の情報などが確認できます。
3.2.3 改製原戸籍
改製原戸籍とは、戸籍の様式が法改正によって変更された際に、それまでの古い様式で作成されていた戸籍を指します。代表的なものに、昭和23年の戸籍法改正による「昭和改製原戸籍」や、平成6年の戸籍コンピュータ化による「平成改製原戸籍」などがあります。
これらの改製原戸籍には、改製される前の身分事項がそのまま記載されています。特に古い戸籍を辿る際には、この改製原戸籍が頻繁に登場し、被相続人の出生時の情報や、幼少期の家族構成、過去の婚姻・離婚歴などが確認できる重要な書類となります。
3.3 戸籍謄本などの取得方法と費用
戸籍謄本類は、原則として本籍地の市区町村役場で取得します。遠方の場合でも、郵送での取得が可能です。また、2024年3月1日からは、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本などを取得できる「戸籍証明書等の広域交付制度」が開始され、利便性が向上しました。
3.3.1 取得できる場所
- 本籍地の市区町村役場: 最も基本的な取得場所です。窓口で直接請求します。
- 郵送での請求: 本籍地が遠方の場合でも、郵送で請求することが可能です。
- 本籍地以外の市区町村役場(広域交付): 2024年3月1日以降、本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村役場の窓口で、本人や直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)の戸籍証明書を取得できるようになりました。ただし、郵送請求や代理人による請求は対象外です。
3.3.2 取得に必要な書類
戸籍謄本などを請求する際には、以下の書類が必要となります。
- 交付請求書: 各市区町村役場の窓口に備え付けられているほか、多くの場合、役所のウェブサイトからダウンロードできます。必要な戸籍の種類や請求理由、使用目的などを記入します。
- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、住民基本台帳カードなど、顔写真付きの公的な身分証明書が必要です。郵送の場合はコピーを同封します。
- 請求する戸籍と請求者との関係を示す資料: 請求者が戸籍に記載されている者(本人)やその直系尊属・卑属でない場合(例:兄弟姉妹の戸籍を請求する場合など)は、その関係性を証明する戸籍謄本などが必要となることがあります。
- 委任状: 代理人が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
3.3.3 郵送での取得方法
本籍地が遠方で直接窓口に行けない場合は、郵送で戸籍謄本などを取得することができます。以下のものを同封して、本籍地の市区町村役場宛に送付します。
- 交付請求書: 必要事項を記入したもの。
- 本人確認書類のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなどのコピー。
- 返信用封筒: 請求者の住所・氏名を記載し、切手を貼付したもの。速達を希望する場合は、速達料金分の切手を追加します。
- 手数料分の定額小為替: 郵便局で購入できます。おつりが出ないように、必要な金額分の定額小為替を用意します。
郵送での請求は、往復の郵送期間と役所での処理期間がかかるため、申請から取得まで1週間から2週間程度かかることを想定しておきましょう。
3.3.4 戸籍謄本などの発行手数料
戸籍謄本などの発行手数料は、全国一律で定められています。定額小為替で支払う場合は、手数料の合計額に合うように用意しましょう。
| 書類の種類 | 手数料(1通あたり) |
| 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 450円 |
| 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) | 450円 |
| 除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 750円 |
| 改製原戸籍謄本(改製原戸籍全部事項証明書) | 750円 |
| 住民票の写し | 200円~300円程度(市区町村により異なる) |
※上記は一般的な手数料であり、市区町村によっては異なる場合があります。事前に各役所のウェブサイトなどで確認することをおすすめします。
4. 相続人調査を専門家に依頼するメリットと費用

相続人調査は、自分で戸籍を辿ることも可能ですが、時間と手間がかかる上に、複雑な戸籍の読み解きには専門知識が必要です。このような場合、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に依頼することで、確実かつ効率的に調査を進めることができます。
4.1 専門家に依頼する主なメリット
専門家に相続人調査を依頼することには、以下のような多くのメリットがあります。
4.1.1 複雑な戸籍の読み解き
被相続人の出生から死亡までの戸籍を辿る作業は、時に非常に複雑になります。特に、転籍や婚姻、養子縁組、認知などにより戸籍が何度も変わっている場合や、手書きの古い戸籍、戦前の戸籍など、現代の戸籍とは異なる形式のものが含まれることも少なくありません。これらの戸籍には、専門的な知識がなければ読み解くことが難しい記載も多く、誤った解釈をしてしまうと相続人漏れにつながる恐れがあります。
専門家は、これらの複雑な戸籍の読み解きに慣れており、正確に法定相続人を特定するノウハウを持っています。これにより、相続人調査の精度が格段に向上し、その後の相続手続きにおけるトラブルのリスクを低減できます。
4.1.2 調査時間の短縮
自分で戸籍を収集する場合、本籍地の役所が遠方であれば郵送でのやり取りが必要となり、複数の役所から取り寄せが必要な場合は、何度も書類のやり取りを繰り返すことになります。また、戸籍の請求書作成や必要書類の準備にも時間がかかります。
専門家は、戸籍収集の経験が豊富であり、効率的な請求方法や役所との連携に慣れています。必要な戸籍を漏れなく、かつ迅速に取得できるため、相続人調査にかかる時間を大幅に短縮できます。これにより、相続手続き全体の早期完了に繋がり、相続人の精神的・時間的負担を軽減することが可能です。
4.1.3 手続きの確実性
相続人調査は、遺産分割協議や相続登記、預貯金の解約など、その後のすべての相続手続きの基礎となる重要な作業です。もし相続人に漏れがあった場合、その後の遺産分割協議が無効となったり、再度やり直しが必要になったりするなどの重大なトラブルに発展する可能性があります。
専門家に依頼することで、法的な観点から正確な相続人調査が行われ、相続人漏れのリスクを最小限に抑えることができます。これにより、その後の遺産分割協議が円滑に進み、不動産の相続登記や金融機関での手続きも確実に完了させることが可能となり、将来的な紛争を未然に防ぐことにも繋がります。
4.2 相続人調査を依頼できる専門家と費用相場
相続人調査を依頼できる専門家は、主に弁護士、司法書士、行政書士の3種類です。それぞれの専門家には得意分野があり、費用相場も異なります。
| 専門家 | 主な対応業務 | 相続人調査の費用相場(目安) |
| 弁護士 | 相続問題全般(遺産分割協議、調停・審判、遺言執行、相続放棄、相続税申告サポートなど)。紛争性のある案件に対応可能。 | 10万円~30万円程度(事案の複雑さや、その後の手続きまで依頼するかで変動) |
| 司法書士 | 不動産登記、預貯金解約・名義変更、遺産承継業務、遺言書作成、相続放棄申述書作成など。 | 5万円~15万円程度(取得する戸籍の通数や難易度で変動) |
| 行政書士 | 戸籍収集、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成、遺言書作成など。書類作成業務が中心。 | 3万円~10万円程度(取得する戸籍の通数や難易度で変動) |
上記はあくまで一般的な費用相場であり、事案の複雑さ、戸籍の通数、専門家の事務所の方針によって変動します。また、相続人調査のみを依頼する場合と、その後の遺産分割協議や相続登記、預貯金解約まで一貫して依頼する場合とでは、費用体系が異なることがほとんどです。事前に見積もりを依頼し、費用の内訳を明確に確認することが重要です。
4.2.1 弁護士に依頼する場合
弁護士は、相続に関するあらゆる問題に対応できる法律の専門家です。相続人調査だけでなく、遺産分割協議がまとまらない場合の調停や審判、他の相続人との交渉、遺留分侵害額請求など、紛争性のある案件にも対応できます。もし相続人間で争いが生じる可能性がある場合や、複雑な法的判断が必要な場合は、弁護士に依頼するのが最も適しています。相続人調査からその後の遺産分割まで、一貫してサポートを依頼できる点が大きなメリットです。
4.2.2 司法書士に依頼する場合
司法書士は、不動産登記の専門家であり、相続登記を主な業務としています。相続人調査は、相続登記を行う上で必須となるため、相続登記と合わせて依頼することが一般的です。また、預貯金の解約や名義変更手続き、遺産承継業務(相続手続き全般の代行)も行えます。紛争性のない相続手続きをスムーズに進めたい場合や、不動産を相続する予定がある場合に適しています。弁護士に比べて費用が抑えられる傾向にあります。
4.2.3 行政書士に依頼する場合
行政書士は、権利義務に関する書類作成の専門家です。相続人調査のための戸籍収集や、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成などが主な業務となります。紛争性のない、純粋な相続人調査や書類作成に特化しており、他の専門家と比較して比較的安価に依頼できる傾向があります。相続人間で争いがなく、必要な書類作成のみを依頼したい場合に有効な選択肢となります。
4.3 専門家選びのポイント
相続人調査を依頼する専門家を選ぶ際には、以下の点を考慮すると良いでしょう。
- 実績と経験: 相続案件、特に相続人調査の実績が豊富であるかを確認しましょう。複雑な戸籍の読み解き経験が豊富な専門家を選ぶことが重要です。
- 専門分野: 自身の相続の状況(紛争の有無、資産内容など)に合った専門家を選びましょう。紛争の可能性があるなら弁護士、不動産が主な財産なら司法書士、書類作成のみなら行政書士など、適切な選択が重要です。
- 費用体系の明確さ: 依頼前に、見積もりを提示してもらい、費用の内訳や追加料金の有無を明確に確認しましょう。納得できる料金体系であるかを確認することが大切です。
- コミュニケーション: 専門家との相性や、こちらの疑問に対して丁寧に説明してくれるかどうかも重要なポイントです。安心して相談できる専門家を選びましょう。
- 初回相談の有無: 多くの専門家事務所では、初回無料相談を実施しています。複数の専門家に相談し、比較検討することで、ご自身に最適な専門家を見つけることができるでしょう。
5. 相続人調査に関するよくある質問

5.1 相続人調査にはどれくらいの期間がかかる?
相続人調査にかかる期間は、ケースによって大きく異なります。被相続人の本籍地が頻繁に移動していたり、取得すべき戸籍の数が多かったり、相続人が海外に居住していたりする場合には、より多くの時間が必要となります。
一般的に、ご自身で戸籍謄本などを取得し、調査を進める場合は、数週間から数ヶ月かかることが一般的です。特に、郵送でのやり取りが多くなると、往復の時間も考慮に入れる必要があります。専門家に依頼した場合は、専門家の知識と経験により、よりスムーズに手続きが進むため、1ヶ月〜2ヶ月程度で完了するケースが多いです。
ただし、戦災などで戸籍が焼失している場合や、非常に古い戸籍を辿る必要がある場合は、さらに時間がかかることもあります。
5.2 疎遠な相続人がいる場合の調査方法は?
疎遠な相続人がいる場合でも、戸籍を辿ることでその存在自体は判明します。しかし、現在の住所や連絡先が不明なケースが少なくありません。
このような場合、以下の方法が考えられます。
- 住民票・戸籍の附票の取得:相続人であることが確認できれば、市町村役場で相続人の住民票や戸籍の附票を取得できる場合があります。これにより、現在の住所を特定できる可能性があります。ただし、正当な理由(相続手続きのためなど)が必要です。
- 専門家への依頼:弁護士や司法書士などの専門家は、職務上請求として住民票や戸籍の附票を取得できる場合があります。また、弁護士であれば、弁護士会照会制度(弁護士法23条照会)を利用して、金融機関や携帯電話会社などに情報の照会を行うことも可能です。
- 戸籍の情報を元にした聞き込み:戸籍に記載された情報(本籍地、筆頭者など)から、親族や知人を通じて情報を得る方法もありますが、プライバシーに配慮し慎重に行う必要があります。
ご自身での調査が困難な場合は、専門家への依頼が最も確実で効率的な方法と言えるでしょう。
5.3 相続人がいない場合はどうなる?
法定相続人が一人も存在しない場合や、全ての相続人が相続放棄をした結果、相続人がいなくなった場合は、その財産は最終的に国庫に帰属することになります。
しかし、すぐに国庫に帰属するわけではなく、以下のような法的な手続きが踏まれます。
- 相続財産清算人の選任申立て:利害関係人(債権者など)や検察官が家庭裁判所に申し立て、相続財産を管理・清算する「相続財産清算人」が選任されます。
- 債権者・受遺者への公告:相続財産清算人は、被相続人の債権者や遺言による受遺者に対し、一定期間内に請求を申し出るよう公告します。
- 相続人捜索の公告:さらに、家庭裁判所は、相続人がいるかどうかの捜索のため、一定期間(通常6ヶ月以上)の公告を行います。この期間内に相続人が現れなければ、相続人はいないものと確定します。
- 特別縁故者への財産分与:相続人が確定しない場合でも、被相続人と生計を共にしていた者や療養看護に努めた者など、特別の縁故があったと認められる者(特別縁故者)がいれば、その者からの申立てにより、家庭裁判所の審判で財産の一部または全部が分与されることがあります。
- 国庫への帰属:上記の手続きを経てもなお残った財産は、最終的に国庫に帰属します。
相続人がいない場合でも、相続財産の整理や債務の清算は必要となるため、相続人調査は非常に重要な意味を持ちます。
5.4 相続放棄をする場合も相続人調査は必要?
はい、相続放棄をする場合でも、相続人調査は必要不可欠です。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。この「知った時」を確定するためには、まず自分が相続人であることを把握し、かつ被相続人が亡くなったこと(相続の開始)を知る必要があります。相続人調査によって、自分が法定相続人であることが確認できるため、この期間の起算点を知る上で重要となります。
また、相続放棄は、その順位の相続人全員が放棄することで、次の順位の相続人に相続権が移転します。例えば、被相続人に子がなく、兄弟姉妹が相続人となる場合、全ての兄弟姉妹が相続放棄をすれば、その次の順位の相続人はいません。しかし、もし子がいて、その子が相続放棄をした場合、次の順位である直系尊属(父母など)に相続権が移ります。さらに、直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹に相続権が移ります。このように、誰が次の相続人になるのかを正確に把握するためにも、相続人調査は必要です。
相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出する際にも、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本や、相続放棄をしようとする人が相続人であることを証明する戸籍謄本など、相続人調査で取得する書類が必要となります。
6. まとめ
相続人調査は、相続手続きの第一歩であり、円滑な遺産分割や将来的なトラブルを避けるために不可欠です。法定相続人の順位を正確に理解し、戸籍謄本などを辿ることでご自身でも調査は可能ですが、複雑な戸籍の読み解きや時間的な制約がある場合は、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家への依頼も有効な選択肢となります。確実な相続人調査を行うことで、安心して相続手続きを進めることができるでしょう。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を監修したのは…
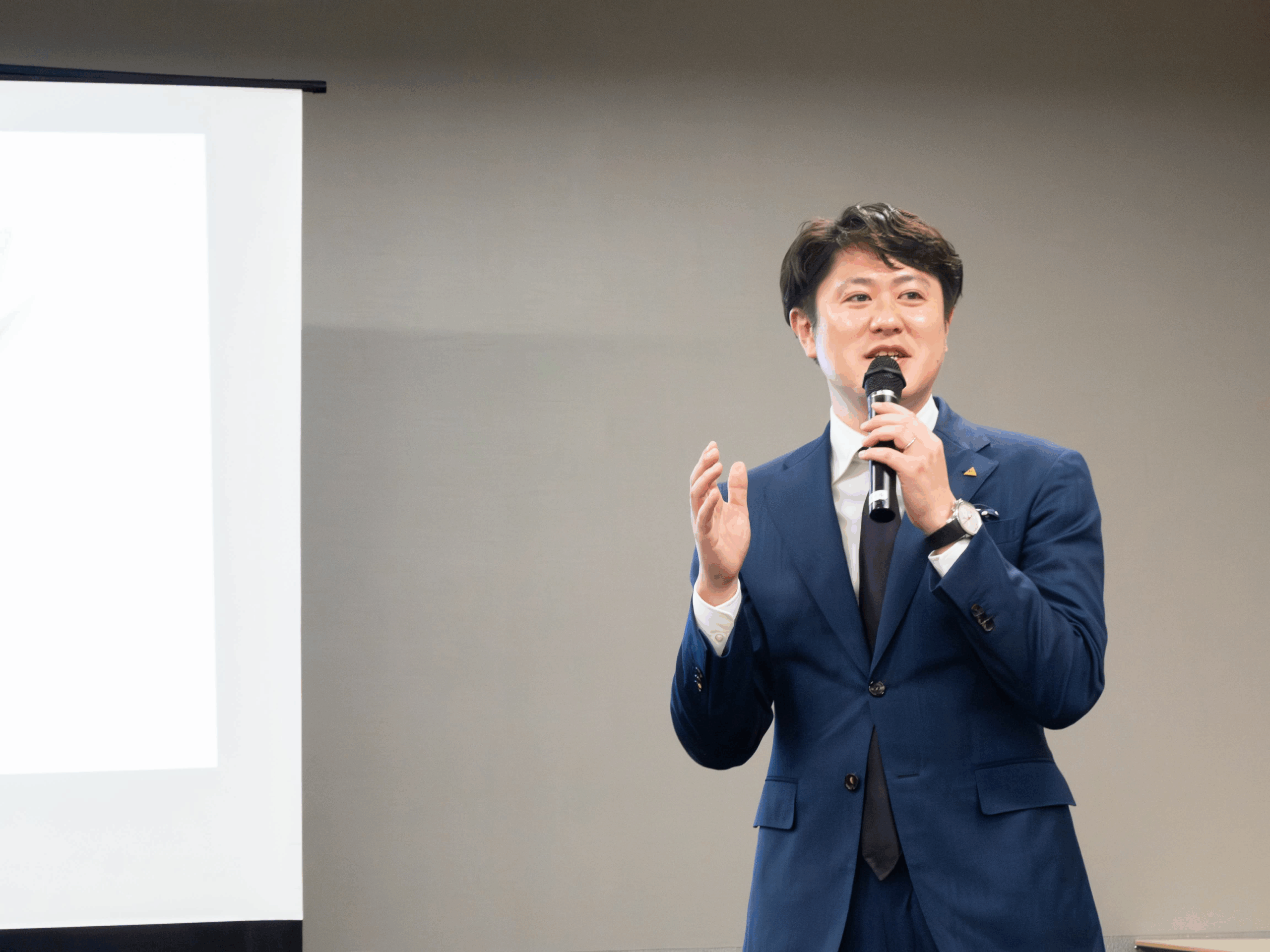
司法書士法人・行政書士あかりテラス代表、株式会社あかりテラス代表、 一般社団法人債務整理相談センター
宮村 和哉(みやむら かずや)
司法書士・行政書士宮村和哉は、相続手続きに精通した司法書士として、地域密着型のサービスを展開。相続トラブルにしないためには「事前準備」が大切であるとの想いで、情報発信を積極的に行っている。年間相談件数700件、終活セミナー年間80会場。熊本を拠点に、福岡などにも支店を構え、多くの相続相談に対応してきた実績を持つ。親しみやすい人柄と的確なアドバイスで信頼を集めている。
サイトURL:https://office-akariterrace.com/ https://www.instagram.com/akariterrace.hohoemi/








