死亡届はいつまでに出す?期限切れのペナルティと正しい提出方法
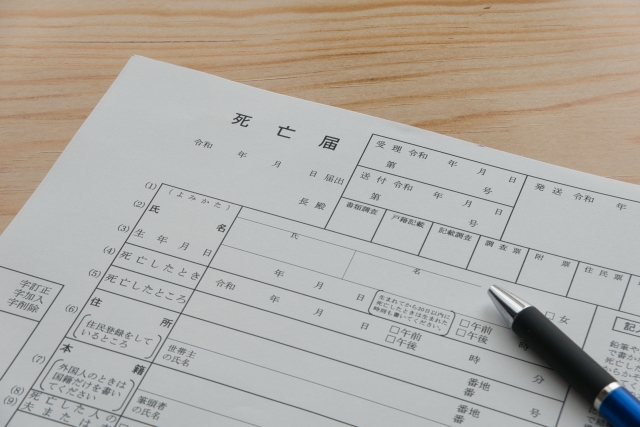
大切な方が亡くなられた際、まず必要となるのが「死亡届」の提出です。「死亡届はいつまでに出せばいいの?」「期限を過ぎたらどうなる?」といった疑問や不安をお持ちの方も多いでしょう。この記事では、死亡届の提出期限が原則「7日以内」であること、期限を過ぎた場合のペナルティや対処法、さらには正しい提出方法や必要書類、関連手続きまでを網羅的に解説します。この記事を読めば、死亡届に関するあらゆる疑問が解消され、安心して手続きを進めることができるでしょう。
Contents
1. 死亡届の提出期限はいつまで?基本的なルール
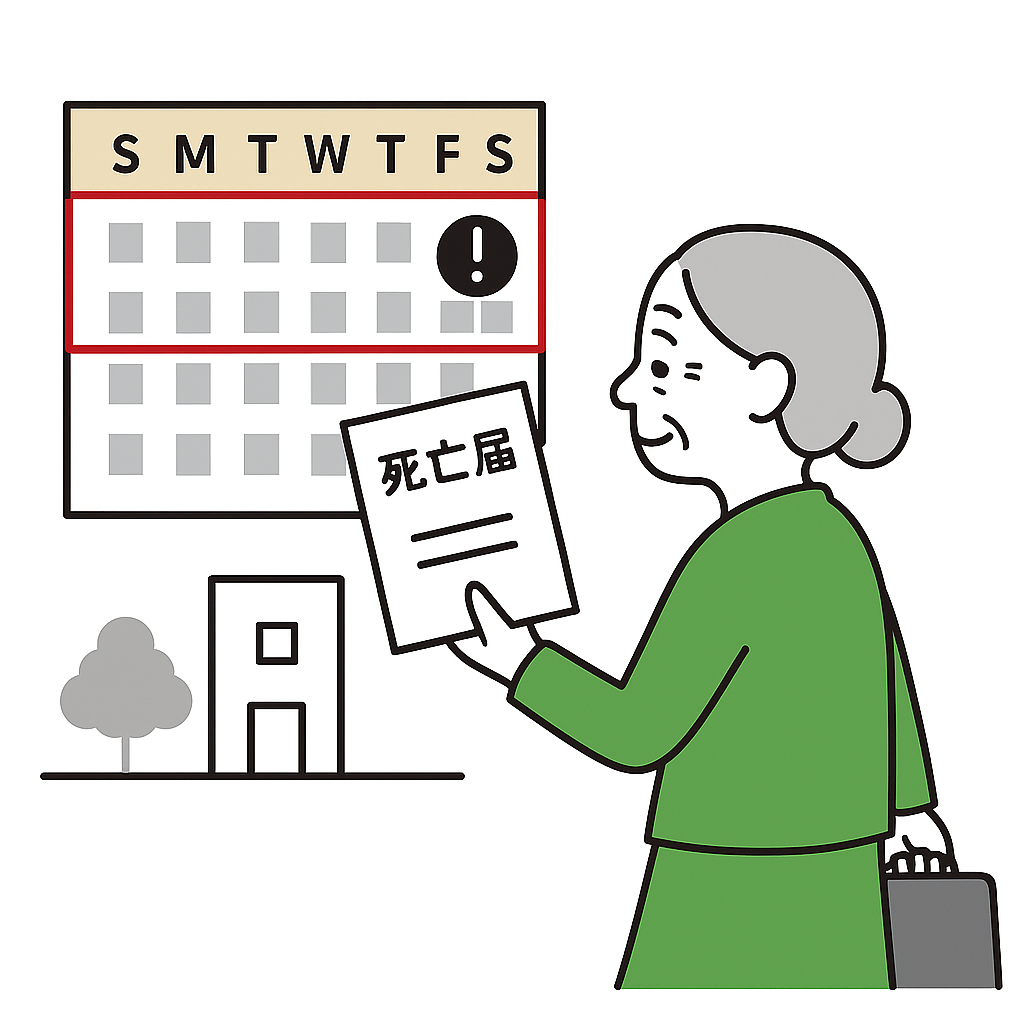
故人が亡くなった際に、まず行わなければならない手続きの一つが死亡届の提出です。この死亡届には法律で定められた提出期限があり、これを守ることが非常に重要です。ここでは、死亡届の提出に関する基本的なルールについて詳しく解説します。
1.1 死亡届の提出期限は「7日以内」が原則
死亡届の提出期限は、戸籍法第86条によって厳格に定められています。原則として、「死亡の事実を知った日から7日以内」に提出しなければなりません。
この「7日以内」という期間は、死亡届を提出する上で最も重要なルールの一つです。例えば、病院で亡くなった場合は、通常、医師が死亡を確認し、死亡診断書が発行された日が「死亡の事実を知った日」となります。自宅で亡くなり、後日発見されたようなケースでは、発見者が死亡の事実を知った日が起算日となります。
もし故人が日本国外で亡くなった場合は、この期限が異なります。国外で亡くなった場合は、「死亡の事実を知った日から3ヶ月以内」に、その国の日本大使館や領事館、または本籍地の市区町村役場に提出することになります。
参照:戸籍法(法務省)
1.2 提出期限の起算日はいつから?
死亡届の提出期限である「7日以内」を数え始める日、つまり起算日は「死亡の事実を知った日」です。これは「死亡した日」と混同されがちですが、厳密には異なります。
具体的には、以下のようなケースで起算日が決定されます。
- 病院で亡くなった場合: 医師が死亡を確認し、死亡診断書を発行した日が「死亡の事実を知った日」となることが一般的です。
- 自宅などで亡くなり、後日発見された場合: 遺体を発見し、死亡の事実を認識した日が「死亡の事実を知った日」となります。この場合、警察による検視が行われ、死体検案書が作成されます。
このように、「いつ、誰が、死亡の事実を明確に認識したか」が起算日を特定する上でのポイントとなります。
1.3 提出期限が土日祝日や年末年始の場合
死亡届の提出期限である7日目が、土曜日、日曜日、国民の祝日、または年末年始(12月29日から1月3日)などの役所の閉庁日に当たる場合には、期限が延長されます。
民法第142条の規定により、期間の末日が休日に当たる場合は、その翌日をもって期間の末日とすると定められています。このため、死亡届の提出期限も同様に、直後の役所の開庁日まで延長されます。
例えば、死亡の事実を知った日が1月1日で、そこから7日後の1月8日が日曜日だった場合、提出期限は翌開庁日である1月9日(月曜日)になります。年末年始も同様に、閉庁期間を考慮して直後の開庁日が期限となります。
具体的な例を以下の表に示します。
| 死亡の事実を知った日 | 7日後の日付 | 提出期限日 | 備考 |
| 1月1日(月) | 1月8日(月) | 1月8日(月) | 平日なのでそのまま |
| 1月2日(火) | 1月9日(火) | 1月9日(火) | 平日なのでそのまま |
| 1月3日(水) | 1月10日(水) | 1月10日(水) | 平日なのでそのまま |
| 1月4日(木) | 1月11日(木) | 1月11日(木) | 平日なのでそのまま |
| 1月5日(金) | 1月12日(金) | 1月12日(金) | 平日なのでそのまま |
| 1月6日(土) | 1月13日(土) | 1月15日(月) | 13日(土)、14日(日)が休日のため、翌開庁日まで延長 |
| 12月25日(月) | 1月1日(月) | 1月4日(木) | 1月1日~3日が年末年始のため、翌開庁日まで延長 |
このように、休日の有無によって提出期限が変わるため、計算する際には注意が必要です。
2. 死亡届の提出期限を過ぎたらどうなる?ペナルティと対処法

死亡届は故人の戸籍を抹消し、公的に死亡を証明するための重要な手続きです。提出期限が法律で定められているため、もし期限を過ぎてしまうと、過料(かりょう)の対象となる可能性があります。ここでは、期限を過ぎた場合の具体的なペナルティと、その対処法について詳しく解説します。
2.1 死亡届の提出が遅れると過料の対象になる可能性
死亡届の提出は、戸籍法第44条によって義務付けられています。同法第86条には「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内にする」と明記されており、これに違反した場合、同法第137条により過料に処される可能性があります。
過料とは、行政上の義務違反に対する金銭的な制裁であり、刑罰とは異なります。一般的には5万円以下の過料が定められていますが、具体的な金額は裁判所が個別の事情を考慮して決定します。過料が科されるかどうか、またその金額は、遅延の期間や理由、悪質性などによって判断されるため、一律ではありません。
過料の対象となるのは、死亡届の提出義務を負う届出人です。届出人が複数いる場合でも、いずれか一人が提出すれば義務は果たされますが、誰も提出しない場合は、その全員が過料の対象となり得ます。
参照元:e-Gov法令検索「戸籍法」
2.2 「正当な理由」があれば過料は免除される?
戸籍法第137条では、「正当な理由がある場合」には過料が免除される可能性があるとされています。しかし、この「正当な理由」の解釈は非常に厳格であり、一般的に以下のようなケースが該当すると考えられます。
- 大規模な自然災害により、交通機関が麻痺し、役所への到達が困難であった場合
- 届出義務者自身が重篤な病気や事故により、長期入院を余儀なくされ、手続きが物理的に不可能であった場合
- 海外に滞在しており、帰国が困難で、代理人による手続きも不可能であった場合
一方で、以下のような理由では「正当な理由」とは認められにくい傾向があります。
- 単なる手続きの失念や多忙
- 必要書類の準備に手間取った
- 死亡のショックによる精神的な動揺
「正当な理由」と認められるかどうかは、最終的には裁判所の判断に委ねられます。もし遅延の理由が上記のようなやむを得ない事情に該当する場合は、遅延理由書や診断書など、状況を証明できる書類を添えて提出することで、考慮される可能性があります。しかし、基本的には期限内の提出が最も重要です。
2.3 提出期限が過ぎてしまった場合の対処法
もし死亡届の提出期限を過ぎてしまった場合でも、速やかに役所の戸籍窓口へ相談し、提出することが最も重要です。放置することは絶対に避けるべきです。
具体的な対処法は以下の通りです。
| ステップ | 内容 | ポイント |
| 1. 役所への連絡・相談 | まずは、死亡届を提出する予定の市区町村役場の戸籍担当窓口に電話で連絡し、提出が遅れた旨を伝えて指示を仰ぎましょう。 | 遅延の理由を正直に説明し、今後の手続きについて確認します。 |
| 2. 必要書類の準備 | 死亡届の用紙、死亡診断書(または死体検案書)、届出人の印鑑、本人確認書類など、通常の提出に必要な書類を揃えます。 | 遅延理由書や、遅延の事情を証明できる書類(診断書など)が必要となる場合がありますので、事前に確認しましょう。 |
| 3. 速やかな提出 | 必要書類が揃い次第、できるだけ早く役所の窓口へ死亡届を提出します。 | 窓口では、遅延の理由について改めて聞かれることがありますので、簡潔かつ明確に説明できるように準備しておきましょう。 |
提出が遅れたからといって、死亡届が受理されないということはありません。しかし、遅延が発覚した場合、裁判所から過料に関する通知が届く可能性があります。その際は、通知の内容に従い、適切な対応を取る必要があります。誠実に対応することで、過料の金額が軽減されたり、免除されたりする可能性もゼロではありません。
何よりも、遅れても必ず提出するという意識を持つことが重要です。提出しないままでいると、故人の戸籍が抹消されず、その後の相続手続きや年金、健康保険などの各種手続きが一切進まなくなり、非常に大きな問題に発展します。
3. 死亡届の正しい提出方法と必要書類
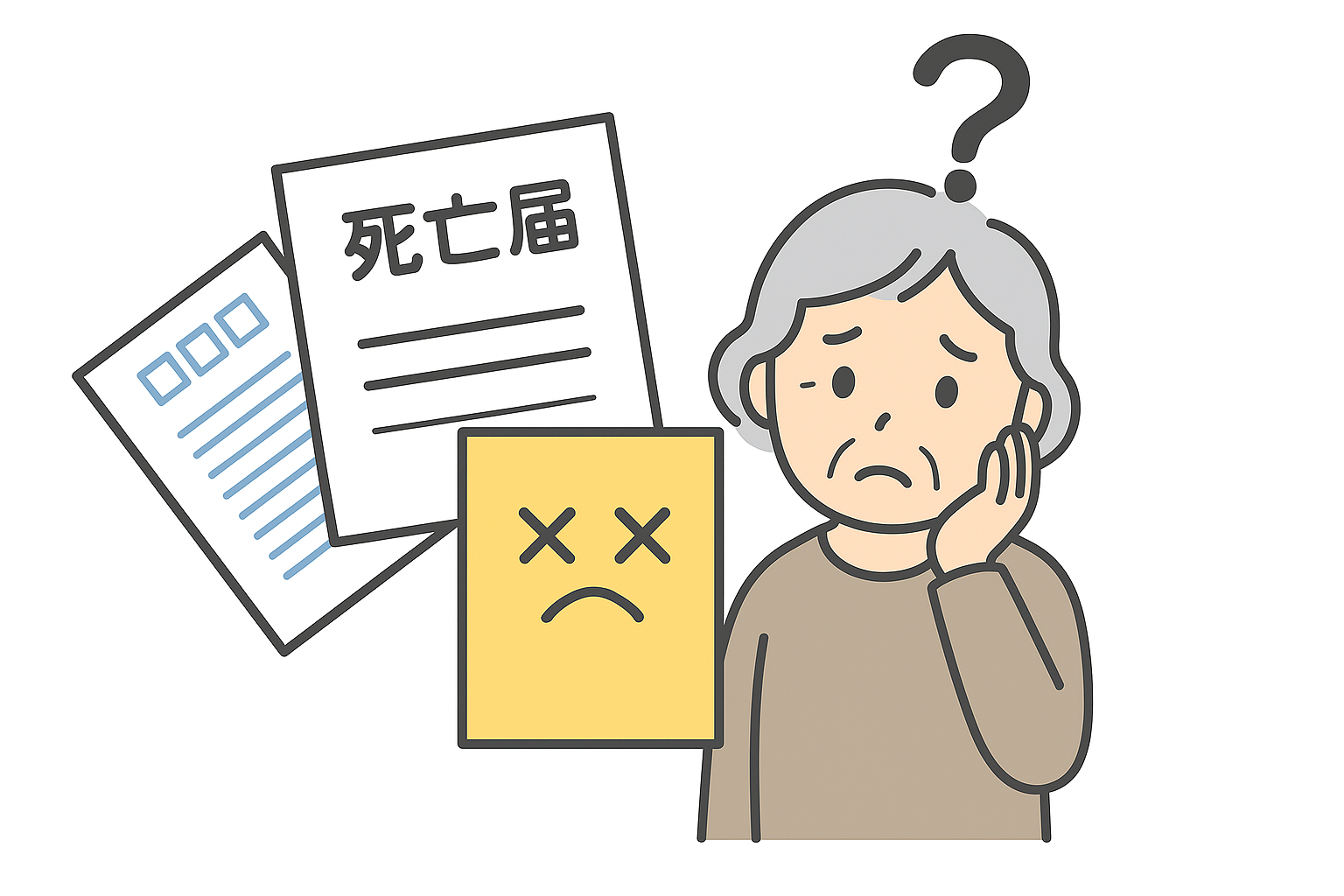
死亡届は、故人の情報を公的に記録し、その後の様々な手続きの基盤となる重要な書類です。ここでは、死亡届の提出場所、届出人になれる人、必要な書類、そして記入方法や提出後の流れについて詳しく解説します。
3.1 死亡届を提出できる場所
死亡届は、以下のいずれかの市区町村役場に提出することができます。
- 故人の本籍地
- 届出人の所在地(住所地)
- 死亡地(故人が亡くなった場所)
通常、死亡届は故人が亡くなった場所の病院や施設から葬儀社を通じて提出されることが多いですが、ご自身で提出することも可能です。提出は、各市区町村役場の戸籍住民課などの窓口で行います。夜間や休日、年末年始など閉庁時間帯でも、宿日直窓口で受け付けてもらえますが、その場で内容の確認や書類の不備に関する指摘はされない場合があるため、後日改めて担当部署から連絡が入ることがあります。
3.2 死亡届の届出人になれる人
死亡届の届出人になれる人は、戸籍法によって定められています。届出義務者と呼ばれる優先順位があり、通常は以下のいずれかの人が届出人となります。
| 区分 | 具体的な例 | 備考 |
| 同居の親族 | 配偶者、子、父母、兄弟姉妹など | 故人と同居していた親族 |
| その他の親族 | 配偶者、子、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母、叔父叔母など | 故人と同居していなくても可能 |
| 同居者 | 内縁の妻・夫、友人など | 故人と生計を共にしていた場合など |
| 家主、地主または家屋若しくは土地の管理人 | 賃貸物件のオーナー、管理会社など | 故人が住んでいた建物の所有者や管理者 |
| 公設所の長 | 病院長、施設長など | 故人が病院や施設で亡くなった場合 |
| 後見人、保佐人、補助人、任意後見人 | 法定後見人、任意後見契約の受任者など | 故人の生前の財産管理や身上監護を行っていた者 |
届出人となる人が複数いる場合は、そのうちの誰か一人が届け出れば問題ありません。また、届出人自身が役所へ行けない場合でも、代理人が提出することは可能です。ただし、死亡届の「届出人」欄には、実際に届け出る代理人ではなく、上記の資格を持つ人が署名・押印する必要があります。
3.3 死亡届の提出に必要な書類
死亡届の提出には、主に以下の書類が必要となります。
3.3.1 死亡診断書または死体検案書
死亡届用紙の右半分は、医師が記入する死亡診断書または死体検案書となっています。病院で亡くなった場合は主治医が死亡診断書を、自宅などで亡くなり警察の検視が入った場合は監察医などが死体検案書を作成します。この書類は、故人の死亡を確認し、死因などを医学的に証明する非常に重要なものです。
死亡届を提出する際は、必ずこの死亡診断書または死体検案書が記載された原本が必要となります。コピーでは受け付けてもらえません。葬儀社に手続きを依頼する場合は、葬儀社が原本を預かり、手続きを進めてくれます。
3.3.2 届出人の印鑑と本人確認書類
死亡届には、届出人の署名と押印が必要です。印鑑は認印で差し支えありませんが、シャチハタなどのゴム印は避けてください。訂正が必要になった場合に備え、届出時に持参すると良いでしょう。
また、窓口での手続きの際には、届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など)の提示を求められることがあります。代理人が提出する場合も、代理人の本人確認書類が必要となります。
3.4 死亡届の記入方法と注意点
死亡届は、役所の窓口や病院、葬儀社などで入手できます。複写式の用紙になっており、左側が「死亡届」、右側が「死亡診断書」または「死体検案書」となっています。届出人が記入するのは主に左側の「死亡届」部分です。
主な記入項目は以下の通りです。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
| 死亡者 | 氏名、生年月日、死亡日時、死亡場所、本籍、世帯主の氏名、故人との続柄など | 住民票や戸籍謄本の内容と一致させる。死亡時刻は医師の記載と一致させる。 |
| 届出人 | 氏名、住所、本籍、生年月日、署名、押印など | 戸籍法で定められた届出人資格を持つ人が記入。 |
| その他 | 世帯主の変更の有無、火葬場の希望など | 必要に応じて記入。火葬場の希望は火葬許可証の発行に影響。 |
記入の際は、死亡診断書(死体検案書)に記載されている内容と整合性を取るように注意しましょう。特に、死亡日時や死亡場所は医師の記載と一字一句同じになるように記入してください。もし書き損じてしまった場合は、二重線で訂正し、届出人の印鑑を押してください。修正液や修正テープは使用できません。
3.5 死亡届の提出後の流れ
死亡届が受理されると、いくつかの重要な手続きが自動的に、または続けて行われます。
3.5.1 火葬許可証・埋葬許可証の発行
死亡届が受理されると、原則として火葬許可証または埋葬許可証が発行されます。これは、火葬や埋葬を行う上で必須となる重要な書類であり、火葬場や斎場に提出しなければ火葬・埋葬を行うことができません。通常、死亡届の提出と同時に申請し、その場で発行されます。再発行は困難なため、紛失しないよう厳重に保管してください。火葬後に火葬許可証は「埋葬許可証」として返却され、納骨の際に必要となります。
3.5.2 住民票の抹消
死亡届が受理されると、故人の住民票は自動的に抹消され、「住民票除票」となります。これによって、故人が住民として登録されていた記録が公的に終了します。この手続きは役所側で行われるため、別途申請する必要はありません。
4. 死亡届の提出と同時に検討したい関連手続き

死亡届の提出は、故人の公的な記録を更新する上で最も重要な手続きの一つですが、それと同時に、故人の社会的なつながりや財産に関わる様々な手続きを速やかに進める必要があります。これらの手続きは、故人の生活状況や遺族の状況によって異なりますが、多くの場合、期限が設けられているため、死亡届の提出と並行して確認し、準備を進めることが重要です。
4.1 年金受給停止の手続き
故人が年金を受給していた場合、死亡届を提出しただけでは年金の支給は自動的に止まりません。年金受給停止の手続きを別途行う必要があります。この手続きを怠ると、年金を不正に受給したとみなされ、後日返還を求められる可能性があります。
また、故人が加入していた年金制度によっては、遺族が受け取れる年金(遺族年金)や、まだ受け取っていなかった年金(未支給年金)がある場合があります。これらの手続きも同時に検討し、申請漏れがないようにしましょう。
4.1.1 年金受給停止の期限と提出先
年金の種類によって手続きの期限や提出先が異なります。
- 国民年金・厚生年金: 死亡後14日以内に、故人の住民票があった市区町村役場の国民年金担当窓口、または管轄の年金事務所・年金相談センターへ提出します。
- 共済年金: 死亡後14日以内に、各共済組合へ提出します。
提出が遅れると、過払い分の返還を求められるため、速やかに手続きを行いましょう。
4.1.2 年金受給停止手続きに必要な書類
年金受給停止の手続きには、主に以下の書類が必要となります。
| 書類名 | 備考 |
| 年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書または年金受給権者死亡届(報告書) | 日本年金機構のサイトで書類テンプレートをDLすることができます。 |
| 故人の年金手帳または年金証書 | 年金に関する基礎情報が記載されています。 |
| 死亡診断書(写し)または戸籍謄本 | 故人の死亡の事実を証明します。 |
| 手続きを行う方の本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど。 |
| 手続きを行う方の印鑑 | 認印で構いません。 |
| 故人との関係がわかる書類(戸籍謄本など) | 遺族年金や未支給年金の手続きで必要になる場合があります。 |
| 年金を受け取る方の預貯金通帳 | 未支給年金や遺族年金が振り込まれる口座情報です。 |
これらの書類はあくまで一般的なものであり、故人の加入していた年金制度や個別の状況によって追加の書類が必要となる場合があります。手続き前に、必ず提出先の窓口に確認することをおすすめします。日本年金機構のウェブサイトでも詳細を確認できます。
4.2 健康保険証の返還と資格喪失手続き
故人が加入していた健康保険の資格喪失手続きも、死亡届の提出と同時に進めるべき重要な手続きです。健康保険証は、故人が亡くなった時点で無効となります。速やかに返還し、資格喪失の手続きを行いましょう。
また、故人が国民健康保険に加入していた場合、葬儀を行った方(喪主)は「葬祭費」の支給を、社会保険(健康保険組合や協会けんぽ)に加入していた場合は、一定の条件を満たせば「埋葬料(埋葬費)」の支給を受けることができます。これらの申請も忘れずに行いましょう。
4.2.1 健康保険証の返還・資格喪失の期限と提出先
故人が加入していた健康保険の種類によって、手続きの期限や提出先が異なります。
- 国民健康保険: 死亡後14日以内に、故人の住民票があった市区町村役場の国民健康保険担当窓口へ健康保険証を返還し、資格喪失届を提出します。
- 社会保険(健康保険組合・協会けんぽ): 故人の勤務先を通じて、速やかに健康保険組合または協会けんぽへ連絡し、健康保険証を返還します。勤務先が手続きを代行してくれることがほとんどです。
手続きが遅れると、無効な保険証で医療サービスを受けてしまい、後日医療費の全額を請求されるなどのトラブルにつながる可能性があります。
4.2.2 健康保険証返還・資格喪失手続きに必要な書類
健康保険の種類によって必要な書類は異なりますが、一般的には以下の書類が必要となります。
| 書類名 | 備考 |
| 国民健康保険資格喪失届 | 各市区町村の役場で手に入ります。 |
| 故人の健康保険証 | 原本を返還します。 |
| 死亡診断書(写し)または戸籍謄本 | 故人の死亡の事実を証明します。 |
| 手続きを行う方の本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど。 |
| 手続きを行う方の印鑑 | 認印で構いません。 |
| 葬祭費・埋葬料の申請に必要な書類 | 葬儀の領収書、喪主の氏名が確認できる書類など。 |
詳細については、加入していた健康保険の窓口や勤務先に確認してください。厚生労働省のウェブサイトでも関連情報を確認できます。
4.3 世帯主変更届の提出
故人が世帯主であった場合、世帯主変更届を提出しなければならない場合があります。死亡届提出と同時に処理される自治体が多いのですが、別途「世帯主変更届」を書くよう指示されることがあるためです。これは、故人が亡くなった後、残された家族の中から新しい世帯主を定めるための手続きです。世帯主が不在のままでは、行政からの重要なお知らせが届かなくなったり、国民健康保険料の通知などが滞ったりする可能性があります。
4.3.1 世帯主変更届の提出が必要な場合の期限と提出先
世帯主変更届は、故人が亡くなった日を含めて14日以内に、故人の住民票があった市区町村役場の住民課窓口へ提出します。
新しい世帯主となる方が手続きを行うのが一般的です。
4.3.2 世帯主変更届に必要な書類
世帯主変更届の提出には、主に以下の書類が必要となります。
- 世帯主変更届
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 届出人の印鑑(認印で構いません)
世帯構成や状況によっては、追加の書類が必要となる場合があるため、事前に市区町村役場に確認することをおすすめします。
4.4 相続手続きの準備
故人が財産を残していた場合、相続手続きを進める必要があります。相続は、故人の財産(遺産)を法定相続人が引き継ぐための法的な手続きであり、非常に複雑で時間のかかる場合があります。死亡届の提出後、できるだけ早く準備に着手することが重要です。
4.4.1 相続手続きの主な流れと期限
相続手続きは、一般的に以下の流れで進められます。
- 遺言書の有無の確認: 故人が遺言書を残していたかを確認します。遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産が分割されます。
- 相続人の確定: 故人の戸籍謄本などを取り寄せ、誰が法定相続人であるかを確定します。
- 相続財産の調査: 故人の預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も全て調査します。
- 遺産分割協議: 相続人全員で、故人の遺産をどのように分けるか話し合います。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
- 相続放棄・限定承認の検討: 故人の借金が多いなど、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、相続放棄や限定承認を検討します。相続放棄の申述期限は、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内です。
- 相続税の申告と納税: 相続財産の総額が一定額を超える場合、相続税が発生します。相続税の申告と納税は、故人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
- 準確定申告: 故人に所得があった場合、死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が確定申告を行う必要があります。これを準確定申告といい、故人の死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。
相続手続きは、専門的な知識を要するため、弁護士、税理士、司法書士などの専門家に相談することも検討しましょう。国税庁のウェブサイトでは相続税に関する情報が提供されています。
5. 死亡届に関するよくある疑問
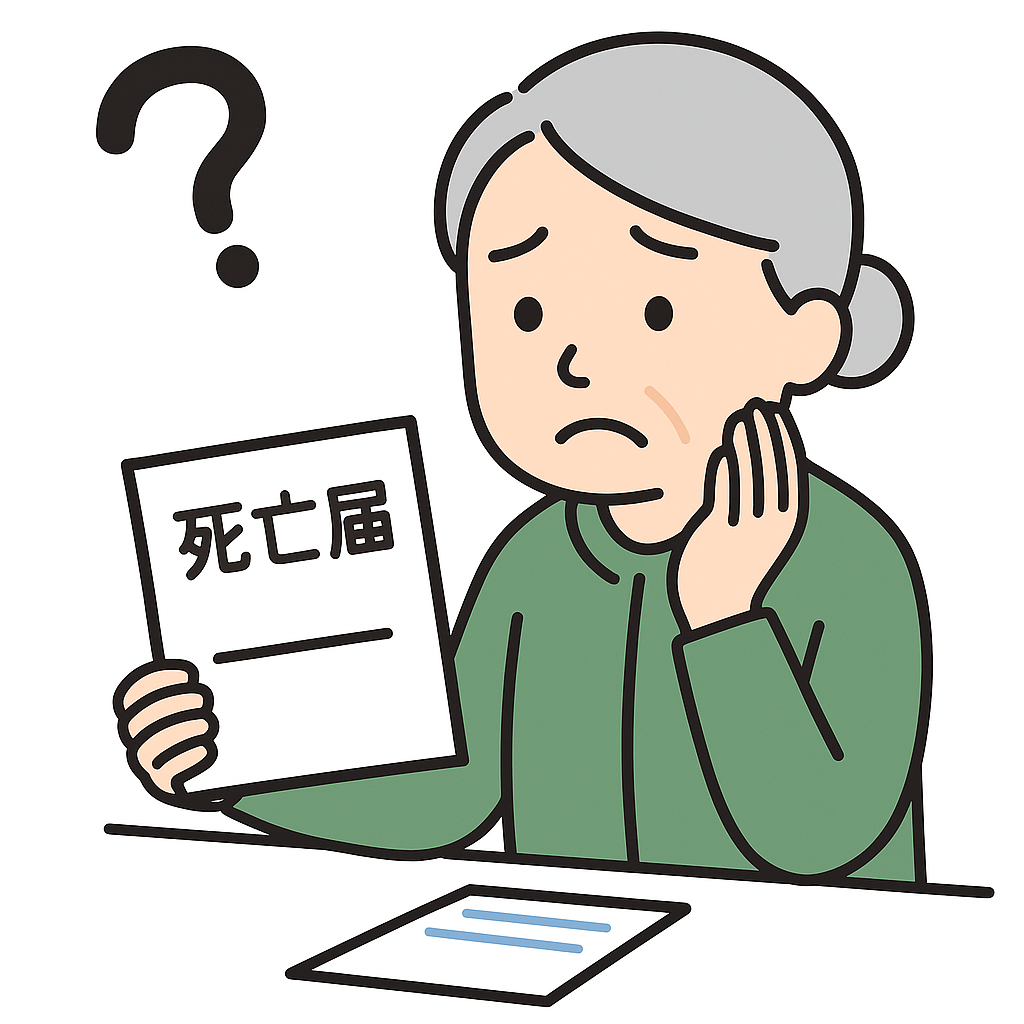
5.1 死亡届は郵送でも提出できる?
原則として、死亡届は市区町村役場の窓口に提出することが推奨されています。これは、届出内容に不備があった場合や、不明な点があった際にその場で確認・訂正ができるためです。
しかし、多くの市区町村では郵送による提出も受け付けています。ただし、郵送で提出する際にはいくつかの注意点があります。
- 郵送方法: 書留郵便など、追跡可能な方法で送ることを強く推奨します。普通郵便では紛失のリスクがあり、万が一の場合に届出が遅れる原因となります。
- 必要書類の確認: 提出前に、死亡届の記入漏れがないか、死亡診断書(または死体検案書)の添付があるかなど、必要書類がすべて揃っているかを十分に確認してください。不備があった場合、役場から連絡が入り、手続きが遅れる可能性があります。
- 連絡先の明記: 死亡届の余白や送付状に、届出人の氏名と日中連絡が取れる電話番号を記載しておくと、不備があった際にスムーズに連絡が取れます。
- 火葬許可証・埋葬許可証の受け取り: 郵送で提出した場合、火葬許可証や埋葬許可証の受け取り方法を事前に確認しておく必要があります。返信用封筒(切手貼付済み)を同封することで、郵送での返送を依頼できる場合が多いですが、自治体によっては窓口での受け取りを求められることもあります。
5.2 死亡届を提出しないとどうなる?
死亡届は、故人の死亡の事実を公的に登録し、その後の行政手続きを進める上で不可欠な書類です。提出期限内に死亡届を提出しない場合、法的なペナルティや様々な不利益が生じる可能性があります。
主な影響は以下の通りです。
| 影響の種類 | 具体的な内容 |
| 法的なペナルティ | 戸籍法第138条により、正当な理由なく届出を怠った場合、5万円以下の過料に処される可能性があります。 |
| 火葬・埋葬の遅延 | 死亡届が受理され、火葬許可証または埋葬許可証が発行されなければ、遺体の火葬や埋葬を行うことができません。これにより、葬儀の実施が大幅に遅れることになります。 |
| 行政手続きの停滞 | 故人の住民票の抹消、年金受給停止、健康保険資格喪失、介護保険資格喪失などの手続きが滞り、不正受給とみなされるリスクが生じたり、故人宛ての郵便物が届き続けたりするなどの問題が発生します。 |
| 相続手続きへの影響 | 故人の死亡が公的に確認されないため、銀行口座の凍結解除、不動産の名義変更、遺産分割協議など、相続に関するあらゆる手続きを進めることが困難になります。 |
これらの問題を避けるためにも、死亡届は定められた期限内に必ず提出するようにしましょう。参考:法務省「戸籍法」
5.3 外国で亡くなった場合の死亡届の提出は?
日本人が外国で亡くなった場合も、日本の戸籍に死亡の事実を登録するため、死亡届の提出が必要です。手続きは国内で亡くなった場合とは異なります。
5.3.1 提出期限と提出先
原則として、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に、以下のいずれかの場所に提出します。
- 在外公館(日本大使館・領事館): 故人の本籍地または届出人の所在地を管轄する在外公館に提出します。
- 本籍地の市区町村役場: 日本国内にある故人の本籍地の市区町村役場に直接郵送または代理人を通じて提出することも可能です。
5.3.2 必要書類
外国で亡くなった場合の死亡届の提出には、以下の書類が必要となります。
- 死亡届書: 所定の様式に記入します。
- 死亡証明書(現地の公的機関発行): 故人が亡くなった国の公的機関が発行した死亡証明書が必要です。
- 死亡証明書の和訳文: 死亡証明書が外国語で記載されている場合、翻訳者(翻訳した人の氏名と住所を記載)による日本語訳文を添付する必要があります。翻訳者は届出人自身でも構いません。
- 届出人の本人確認書類: 届出人のパスポートなど。
- その他: 必要に応じて、身分関係を証明する書類(戸籍謄本など)を求められる場合があります。
現地の法律や慣習により、死亡証明書の形式や手続きが異なる場合があるため、事前に管轄の在外公館や本籍地の市区町村役場に確認することをおすすめします。また、遺体を日本へ搬送する場合や現地で火葬・埋葬する場合など、状況によって必要な手続きが多岐にわたるため、早期に相談することが重要です。参考:外務省「海外で事故・事件に巻き込まれたら」
6. まとめ
死亡届は、故人の尊厳を守り、その後の社会的な手続きを円滑に進めるために不可欠な書類です。原則として「7日以内」という提出期限が定められており、この期限を過ぎると過料の対象となる可能性があります。提出場所や必要書類を事前に確認し、正確に記入することが重要です。また、死亡届の提出後には、年金や健康保険の手続き、世帯主変更、相続の準備など、多くの関連手続きが控えています。不明な点があれば、速やかに自治体の窓口や専門家へ相談し、滞りなく手続きを進めるようにしましょう。適切な手続きが、故人への最後の務めとなります。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を監修したのは…

湯口行政書士事務所
湯口 智子(ゆぐち ともこ)
認知症対策・親なき後問題に力を入れている行政書士です。
母が障害児の塾を開いていたことから、そこを手伝う話もありましたが、法律面でのサポートを希望。
相続の視点のみならず、福祉・教育・心理の視点を交えてサポートいたします。
2022年、地元の士業と共に、「(一社)きたかなRe-Lifeサポーターズ」を立ち上げ、代表として活動中。
資格:行政書士、小学校教諭免許、介護初任者研修、終活カウンセラー、家族信託専門士
サイトURL:https://yuguchi-gyohuku.jp/








