二次相続とは?一次相続との違い、相続税のシミュレーションや節税対策について

Contents
二次相続とは?一次相続との違い
「一次相続」と「二次相続」では、相続の仕組みや税負担が異なります。二次相続の対策をしないと、思わぬ税負担が発生することもあります。ここでは、二次相続の定義や一次相続との違いについてわかりやすく解説します。
二次相続の定義と基本的な仕組み
二次相続とは、最初の相続(一次相続)で財産を受け継いだ親が亡くなったときに発生する相続のことです。たとえば、父が亡くなり、母と子どもが遺産を相続したとします。その後、母も亡くなれば、今度は子どもが母の財産を相続します。これが二次相続です。
二次相続では、配偶者がすでにいないため、相続のルールや税金の負担が一次相続とは異なります。特に相続税の負担が大きくなる傾向があるため、早めの対策が重要です。
一次相続との違いとは?
一次相続と二次相続では、相続人の構成や税負担に大きな違いがあります。
- 一次相続:亡くなったのが父の場合、母と子どもが法定相続人となる。
- 二次相続:母も亡くなった場合、相続人は子どものみになる。
一次相続では、配偶者が相続する分には「配偶者控除」が適用され、相続税の負担が軽くなるのが特徴です。しかし、二次相続ではこの控除が使えないため、相続税が高くなりやすい傾向にあります。
また、一次相続では母が財産を管理するため、遺産分割でもめることは少ないですが、二次相続では兄弟姉妹だけで遺産を分けるため、相続トラブルが起こりやすいのも特徴です。
二次相続の発生タイミングと流れ
二次相続は、一次相続で財産を受け取った配偶者が亡くなったときに発生します。その流れを簡単に説明します。
- 親の死亡(一次相続)
まず、父が亡くなり、母と子どもが財産を相続。母が財産を多く引き継ぐことが一般的です。 - 母の死亡(二次相続)
その後、母が亡くなると、子どもたちが母の財産を相続します。 - 相続手続きの開始
遺言書があれば、それに沿って遺産を分けます。遺言書がない場合は、法定相続のルールに従って遺産を分けることになります。 - 相続税の申告と納税
相続税が発生する場合、10か月以内に税務署へ申告し、納税します。
二次相続では、配偶者がすでにいないため、相続税の基礎控除額が減り、税負担が増えるのがポイントです。また、兄弟姉妹間で財産の分け方について意見が食い違い、トラブルが起こることもあります。
このような問題を防ぐためには、一次相続の段階から二次相続を見据えた対策を立てることが大切です。
二次相続の相続税が高くなる理由
二次相続では相続税負担が大きくなる可能性もあり、事前に相続税の軽減措置を取る必要があります。相続税負担が大きくなる理由は次の通りです。
相続人の減少に伴う基礎控除額の減少
相続税には基礎控除という税負担の軽減措置があります。こちらの基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」なので、両親とも亡くなり子どもだけが法定相続人になると、その分控除額は小さくなります。
例えば、一次相続の時点で母親と子ども(1人)が法定相続人の場合、
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
相続税の基礎控除額は4,200万円です。
しかし、二次相続の時点で子ども(1人)が法定相続人の場合、
3,000万円+600万円×1人=3,600万円
相続税の基礎控除額は3,600万円となり、600万円もの差が出てしまいます。
配偶者の税額軽減が適用されない
また、一次相続の際は「配偶者控除」という極めて大きな相続税の軽減措置も利用できます。
配偶者控除とは被相続人の配偶者が引き継いだ遺産のうち、課税対象となる額が
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
のいずれか多い金額までなら、相続税が非課税となる措置です。
ただし、この控除制度は配偶者に限定されているため、子どもは利用できません。
死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が縮小される
死亡保険金や死亡退職金には、相続税の非課税枠があります。これは、法定相続人1人あたり500万円まで税金がかからないという制度です。
たとえば、父が亡くなり、母と子2人が相続人だった場合、非課税枠の合計は1,500万円(500万円×3人)になります。しかし、母が亡くなったあとの二次相続では、法定相続人は子ども2人だけ。非課税枠は1,000万円(500万円×2人)に減ります。
このように、一次相続では非課税枠が広く使えますが、二次相続では相続人が減るため、非課税枠も小さくなります。その結果、課税対象となる金額が増え、相続税の負担が重くなるのです。
この影響を少なくするためには、一次相続の段階から、死亡保険金や退職金の受取人を工夫することが重要です。たとえば、子どもだけでなく、孫を受取人にするなど、早めの対策を考えましょう。
小規模宅地等の特例の適用が難しくなる可能性
相続税を大きく減らせる「小規模宅地等の特例」。これは、亡くなった人(被相続人)が住んでいた土地を相続するときに、評価額を最大80%減らせる制度です。しかし、この特例を使うためには条件があります。
一次相続(たとえば父が亡くなったとき)では、母が土地を相続すれば必ず特例が適用されます。しかし、母が亡くなった後の二次相続では、子どもが相続する場合、条件が厳しくなります。
- 配偶者(例:母)が相続する場合→必ず80%評価減が適用
- 同居していた子どもが相続する場合→相続前から申告期限まで住み続ける必要がある
具体的には、以下の場合に特例が使えなくなります。
① 子どもが実家を相続するが、すでに持ち家がある
② 親と同居していたが、相続後すぐに引っ越した
③ もともと別の場所に住んでいた子が実家を相続
このように、二次相続では特例が使えないケースが増えるため、事前にしっかり準備することが大切です。
「どの土地を誰が相続するのが最も有利か?」を考え、早めに専門家に相談するのがおすすめです。
相続財産の増加による相続税率の上昇
一次相続では子どもの他に親も法定相続人となっており、その親が配偶者控除を活用し、被相続人の遺産の多くを非課税で引き継いだケースもあるでしょう。
一次相続以後の、次のようなケースでは注意が必要です。
例えば一次相続の法定相続人であった母親が働いていた場合、その収入を預金する等して、母親も資産を形成していた可能性があります。
二次相続では、母親が一次相続で引き継いだ遺産に加え、母親が蓄えてきた資産も合算されるため、相続財産が多くなるケースも想定されます。
相続財産が増えれば、その分、相続税の負担も大きくなるおそれがあります。
二次相続で起こりうる遺産分割争いとは?
二次相続では子どもだけが法定相続人となりますが、次のようなトラブルが懸念されます。
遺産分割協議でなかなか話が進まない
子どもが1人ではなく複数いる場合、兄弟姉妹で仲が悪く、遺産分割の際に誰が遺産を引き継ぐかで揉める可能性もあります。
また、親である被相続人が特定の子どもに一定金額の遺産を引き継がせたくとも、兄弟間の遺産分割の話し合いによっては、親の希望通りにいかない場合もあるでしょう。
そんな時は、遺言書で各相続人の遺産分与について指定しておくか、別の方法で対応する必要があります。
相続財産によっては誰も引き継がない状況もある
一次相続では被相続人の残した土地・建物を配偶者が引き継ぎ、預金・現金は子ども達が引き継ぐ形で遺産分割を取り決めたケースもあるでしょう。
しかし、土地・建物を引き継いだ配偶者が亡くなり、二次相続が発生した場合、相続財産である土地・建物をどうするかで揉めてしまうおそれがあります。
子ども達が既に独立し、それぞれがマイホームを持っているなら、親の残した土地・建物を誰も引き継がない可能性はあります。
そのため、親が生前に土地・建物を売却後、シニア向けの賃貸マンションに住み、売却代金を遺産分割しやすい金融資産として残す等、工夫が必要です。
二次相続の税負担シミュレーション
一次相続のときに「どう遺産を分けるか」で、二次相続の相続税が大きく変わります。
今回は、4つのケースをシミュレーションし、どの分割方法が最も税負担を抑えられるのかを比較します。
父が6000万円の財産を遺して亡くなり、母と子ども2人が相続人、その後母が亡くなって2人の子供が相続する場合を考えてみましょう。
配偶者が財産の大部分を相続した場合
一次相続で配偶者(母)がほとんどの遺産を引き継ぐと、「配偶者の税額軽減」が適用され、相続税はかかりません。しかし、この方法には大きな落とし穴があります。母が亡くなった際の二次相続での税負担が大きくなるのです。
【シミュレーション】
- 一次相続(父の財産):6,000万円
- 母の財産:一次相続で全額相続 → 6,000万円
- 一次相続の相続税:0円(配偶者の税額軽減適用)
- 二次相続の相続税:620万円
- 続税の総額:620万円
一次相続で配偶者に全財産を相続させると、一時的に相続税がかからないため「節税できた」と思いがちです。しかし、二次相続のときにまとめて相続税を支払うことになり、負担が一気に増える点に注意が必要です。
法定相続分どおりに分割した場合
法定相続分どおりに遺産を分けると、一次相続の時点で子どもにも遺産が分配されるため、母の相続財産が減り、二次相続の税負担も軽減されます。
【シミュレーション】
- 一次相続の分割:母が1/2(3,000万円)、子が1/4ずつ(1,500万円×2)
- 一次相続の相続税:60万円
- 二次相続の相続税:180万円
- 相続税の総額:240万円
母の相続分を抑えることで、二次相続の税額が少なくなります。
均等に分割した場合
母と子どもが同じ割合で遺産を受け取ると、母の財産がさらに減り、二次相続の税負担がさらに軽くなります。
【シミュレーション】
- 一次相続の分割:母が1/3(2,000万円)、子が1/3ずつ(2,000万円×2)
- 一次相続の相続税:80万円
- 二次相続の相続税:80万円
- 相続税の総額:160万円
母の相続額をさらに減らすことで、最終的な相続税負担を最小限にできます。
資産性の高い財産を子に相続させた場合
現金よりも不動産や株式などの資産性が高い財産を子に相続させると、特例を活用して税負担を抑えることができます。
【シミュレーション例】
- 父の4,000万円の不動産を子どもが相続
- 母は現金のみ相続(2,000万円)
- 小規模宅地等の特例を適用して相続税の軽減が可能
資産の種類に応じた節税対策を組み合わせることで、二次相続の税負担を減らせます。
二次相続を見据えた相続税対策
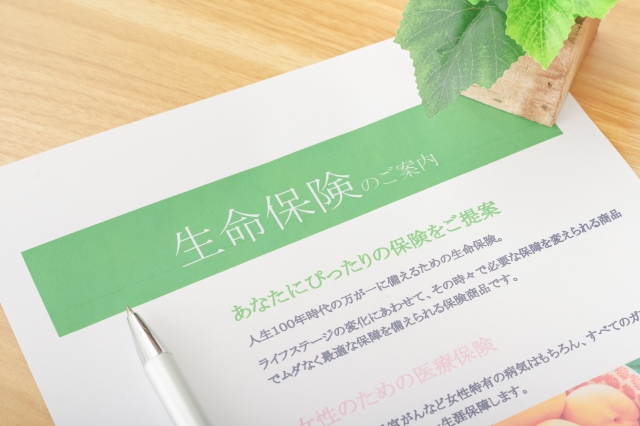
相続時には、一次相続の税額だけを見るのではなく、二次相続まで考えた遺産分割を検討することが重要です。
生前贈与を計画的に進める
相続税を減らす方法のひとつに「生前贈与」があります。これは、生きているうちに家族へ財産を分け与えることで、相続時の課税対象となる財産を減らす対策です。特に、年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかからない仕組みになっています。この制度を活用すれば、将来の相続税の負担を軽くすることが可能です。
たとえば、一次相続の際に配偶者が1,000万円の遺産を受け取ったとします。その後、毎年100万円ずつ子どもへ生前贈与を行えば、10年後には合計1,000万円を非課税で子どもに渡せます。この方法を使えば、二次相続のときにはすでに財産が移っているため、相続税の対象になりません。
ただし、贈与のタイミングには注意が必要です。生前贈与でも「相続開始前7年以内」に行われたものは、相続税の計算に含まれてしまいます。そのため、相続が近いと予想される場合は、生前贈与の効果が薄れることを理解しておく必要があります。
生命保険を活用して納税資金を確保する
二次相続が発生し、子どもたちに重い相続税を負担させたくない、遺産分割協議で揉めるような事態を避けたい、子どもたちが分割し易いように資産を残したい、という場合は「生命保険」の活用を検討してみましょう。
生命保険とは生命保険会社が販売している任意保険です。二次相続の対策として加入する生命保険の場合、死亡保険金が下りる保険商品を選びます。
該当する保険商品は死亡保険(終身保険・定期保険)、養老保険、個人年金保険等があります。
二次相続対策のために生命保険を活用するメリット
こちらでは、二次相続の対策として生命保険に加入するメリットを説明しましょう。
- 死亡保険金には非課税枠がある
生命保険から下りる死亡保険金には「非課税枠」が設定されています。非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」なので、法定相続人2人ならば1,000万円もの非課税枠が利用可能です。
非課税枠は保険金受取人が相続人の場合に適用されるので、子どもを受取人にすれば相続税の軽減措置が受けられます。
- 平等に相続財産を分けやすい
遺産分割協議で誰が遺産をどのくらい取得するのか、兄弟間で揉めそうなときも、生命保険の活用は有効な方法です。
死亡保険金は受取人固有の財産なので、遺産分割協議の対象外となる財産であり、自分が渡したい人へ確実に財産を残せる方法です。
また、複数の保険金受取人を設定できるので、保険金額を平等に分割し、子どもたちに取得させることもできます。
生命保険を二次相続の対策に活用する方法
まず被相続人が生命保険会社と保険契約を締結します。
その際に、保険契約書や契約画面(インターネット申込の場合)で、死亡保険金の受取人を指定します。子どもを受取人に指定していないと、二次相続対策にはならないので注意しましょう。
受取人の指定の際は、1名だけを指定しても、複数人を指定しても構いません。また、保険加入後に保険金受取人の変更も可能です。
受取人に指定するとき当人の同意は不要です。ただし、事前に「自分の保険金の受取人を○○にしている。」と受取人に伝えておいた方が、相続開始の際はスムーズに保険金請求手続きが行えます。
保険金請求後は、生命保険会社から早ければ即日、遅くても10日程度で受取人に保険金が支払われます。
死亡保険金は受取人の固有の財産なので、相続発生の際、金融機関から被相続人の預金口座を凍結されるような状況にもなりません。
生命保険を二次相続対策として活用した事例
母親の二次相続時には、多額の相続税負担となる可能性があったので、生前贈与および生命保険を利用した事例を紹介します。
【生命保険活用の背景】
母親は子ども3人の同意のもとで、配偶者控除を利用し、亡父の相続財産をすべて引き継ぎました(一次相続)。
配偶者控除で相続税の負担は0円に抑えられましたが、二次相続の際は子ども3人へ多額の相続税負担となる事実が判明します。
【生命保険等の活用】
母親と子ども3人は次のような対応を考え、実行に移します。
- 母親は生命保険に加入し、保険金受取人を子ども3人にして、保険金額を平等に分けられるよう設定
- 遺産分割が難しい土地・建物を売却し、売却代金を生命保険料にあてる他、子ども3人に生前贈与し、徐々に相続財産を減らしていく
【二次相続対策の効果】
生命保険を二次相続対策に活用したので、遺産分割協議の対象となる相続財産を可能な限り減らすことができ、将来の相続トラブル回避につながります。
また、相続税の基礎控除に加え死亡保険金の非課税枠(1,500万円)も適用され、大幅に税負担を下げる効果も期待できます。
生命保険を用いた二次相続対策のポイント
こちらでは、二次相続対策として生命保険へ加入する前に確認すべきポイントや、どこで保険に関する相談すれば良いかを取り上げましょう。
- 相続対策では終身保険が最適
死亡保険金が下りる生命保険は、各生命保険会社から数多く販売されています。
その中でも、「終身保険」が二次相続対策に最適です。
終身保険とは一生涯にわたり死亡保障が受けられる生命保険です。つまり、何歳で被保険者が亡くなっても確実に保険金は受取人へ支払われます。
一方、生命保険には「定期保険」という、一定期間にわたり保障される保険もあります。しかし、この保険には契約更新の上限年齢が設定されているので注意しましょう。
例えば「被保険者が90歳になれば保険契約終了」と取り決められ、所定の上限年齢を超えた場合、契約は失効し、保険が継続できないばかりか、これまで払い続けた保険料も戻ってきません。
- 契約条件をしっかり確認する
生命保険を契約する際は、複数の保険商品の保障内容(例えば保険金設定は何千万円まで可能か等)を比較し、最も自分にあった保険を選びましょう。
なお、加入できる年齢を超えていないか、健康告知項目(例:持病の有無や、手術歴等)に該当していないかを良く確認の上で、申込をしましょう。
- 相談は無料の保険相談窓口へ
生命保険で二次相続対策をしたいが、どんな保険に入れば良いかわからない等の悩みがあれば「保険相談窓口」に相談してみましょう。
最近では、ショッピングモールや駅前等に多くの無料保険相談窓口が店舗を構えています。窓口スタッフの中には相続対策に詳しい人もいるので、相談者のニーズに合わせた生命保険を提案してくれるはずです。
まずはお近くの保険相談窓口を予約し、アドバイスを受けてみましょう。
一次相続時に自宅を子供に相続させる
相続税を抑える方法のひとつとして、一次相続で自宅を子供に相続させることが考えられます。自宅の土地や建物は、遺産の中でも大きな割合を占めるため、配偶者がすべてを相続すると二次相続時の税負担が大きくなる可能性があります。そのため、最初の相続で同居している子供に自宅を譲ることで、配偶者の相続財産を減らし、二次相続時の相続税を抑えることができます。
小規模宅地等の特例の適用条件に注意
自宅を子供に相続させる際は、「小規模宅地等の特例」を活用できるかを確認することが重要です。この特例を使えば、一定の条件を満たす場合に、自宅の土地の評価額を最大80%減額することができます。
特例を受けるためには、以下の条件のいずれかを満たしている必要があります。
- 配偶者が自宅を相続する場合(必ず適用される)
- 同居している子供が相続する場合(相続後も住み続けることが条件)
- 同居していない子供が相続する場合は適用されないことが多い
このため、実家を相続する子供がすでに別の場所に住んでいる場合、特例が使えなくなる可能性があります。また、同居していても、相続後にすぐに家を売却したり転居したりすると、特例の適用外になってしまうので注意が必要です。
配偶者居住権を設定する選択肢
自宅を子供に相続させた場合でも、残された配偶者が安心して住み続けられるようにする方法があります。そのひとつが「配偶者居住権」の活用です。
配偶者居住権とは、配偶者が亡くなるまで自宅に住み続けられる権利です。これを利用することによって、家の所有権は子供に移りますが、配偶者の住む権利は確保されます。
さらに、配偶者が相続する財産を減らせるため、二次相続の税負担を軽減する効果も期待できます。
相続する財産の種類を調整する
相続する財産の種類を調整して、二次相続で相続税を節約することもできます。いくつか例をあげましょう。
値上がりが予想される資産は子に相続させる
相続対策の一つとして、将来的に価値が上がる可能性が高い資産は、一次相続の時点で子供に相続させる方法があります。
例えば、以下のような資産は、今後価値が上がる可能性があります。
- 再開発が予定されている土地(都市部や商業エリアなど)
- 業績が好調な企業の株式(株価が上昇する見込みがある)
- 人気が高まっているエリアの不動産(住宅需要が増えている地域)
これらの資産は時間が経つほど価値が上がるため、二次相続のタイミングでは評価額が大幅に増えてしまい、相続税も高額になる可能性があります。こうした状況を防ぐため、最初の相続の段階で、値上がりが見込まれる資産は子供に相続させる方が有利になる場合があります。
現金化しておくことで相続税対策をする
相続税は基本的に現金で納める必要があります。そのため、相続財産のほとんどが不動産だと、納税資金が足りなくなる可能性があります。相続した不動産を売却して現金化することもできますが、すぐに買い手が見つかるとは限りません。希望の価格で売却できなかったり、売却に時間がかかることもあります。
また、納税資金が用意できない場合、分割払い(延納)を選択することも可能ですが、その場合は利子が発生します。さらに、例外的に不動産などの現物で納める「物納」という方法もありますが、条件が厳しく、すべてのケースで認められるわけではありません。
こうしたリスクを避けるために、生前のうちに一部の不動産を売却し、現金を確保しておくことが有効です。例えば、親が住まなくなった家や、あまり活用していない土地を事前に売却し、そのお金を預金として残しておくと、相続後の納税がスムーズになります。
相次相続控除を活用する
相続が短期間に続くと、同じ財産に二度相続税がかかることになります。これにより、相続人の負担が大きくなります。そこで活用できるのが「相次相続控除」です。この制度を利用すると、短期間で発生した二次相続の相続税を軽減できます。
相次相続控除の適用条件と控除額
相次相続控除を適用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。以下に、その主な条件をわかりやすく説明します。
① 被相続人の相続人であること
この控除を受けるには、二次相続で財産を引き継ぐ人が、亡くなった人の法定相続人である必要があります。たとえば、一次相続(父が死亡)で財産を受け継いだ母が、その後亡くなり、子が二次相続を行う場合が該当します。ただし、遺言による遺贈を受けた人は適用対象外となります。
② 一次相続から10年以内に二次相続が発生していること
相次相続控除は、一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合に適用できます。たとえば、父が亡くなった後、8年以内に母が亡くなった場合、控除の対象となります。相続税の申告期限ではなく、相続が発生した日から数える点に注意が必要です。
③ 二次相続の被相続人が一次相続で財産を相続していること
一次相続の際に財産を受け取っていなかった場合、相次相続控除は適用できません。例えば、母が父の財産をすべて放棄し、子がすべて相続した場合、母が亡くなっても控除は使えません。母が一次相続で財産を相続し、それを子に引き継ぐ場合に適用されます。
④ 一次相続で相続税を納めていること
一次相続で財産を受け取った人(母)が、相続税を納めていることが条件になります。例えば、配偶者の税額軽減を利用して相続税がゼロになった場合、二次相続で子が控除を受けることはできません。申告だけではなく、実際に納税していることがポイントです。
相次相続控除の金額は、一次相続で納めた相続税を基に計算されます。具体的には、以下の計算式で算出されます。
- 一次相続の相続税額(A)
亡くなった配偶者が一次相続で支払った相続税の額です。 - 一次相続の純資産価額(B)
一次相続で取得した財産の価額から、借金や未払い費用を引いた金額です。 - 二次相続の純資産総額(C)
二次相続時点で被相続人(母)が所有していた財産の総額です。 - 二次相続の純資産価額(D)
子が二次相続で取得する財産の評価額です。 - 一次相続から二次相続までの年数(E)
一次相続の発生日から二次相続の発生日までの期間(年単位)です。1年未満の期間は切り捨てられます。
控除額の計算式は、以下のとおりです。
相次相続控除額=(A×D/B)×(10-E)÷10
この計算により、相続税額の一部が控除されます。例えば、一次相続から5年後に二次相続が発生した場合、一次相続の相続税額の50%が控除されます。期間が短いほど控除額は大きくなるため、短期間に連続した相続が発生した際には、この制度を活用することで相続税の負担を減らすことができます。
税負担だけでなく遺産分割にも配慮を
相続の計画を立てる際には、相続税の負担を減らすことだけに目を向けるのではなく、遺産をどのように分けるか、残された家族の生活をどう支えるかも重要なポイントです。
特に、一次相続で配偶者の財産を極端に減らしすぎると、二次相続の税負担は軽くなりますが、その間の生活に困る可能性があります。遺産分割の方法をしっかり考え、家族全員が納得できる相続対策を進めましょう。
遺産争いを防ぐための事前準備
相続をめぐるトラブルは珍しくありません。特に、親が亡くなった後に兄弟姉妹の間で争いが起こるケースもあります。そのため、遺産の分け方を明確にしておくことが大切です。遺言書を作成したり、事前に家族と話し合ったりすることで、相続を円滑に進められます。
また、不動産など分割が難しい資産がある場合は、売却して現金化するか、相続人が納得できる形での共有を検討することが必要です。公平な分割を行うためにも、専門家のアドバイスを受けながら準備を進めると安心です。
配偶者の生活費と住居の確保
配偶者が長く安心して暮らせるよう、住居と生活費の確保も考えておく必要があります。たとえば、自宅を配偶者が引き継ぐ形にすることで、住まいを失う心配をなくすことができます。しかし、自宅を相続しただけでは、生活費が不足することもあります。そうならないよう、現金や預貯金もある程度配偶者に残しておくことが重要です。
また、「配偶者居住権」という制度を活用すれば、住む場所を確保しつつ、財産の分け方を工夫することができます。この制度を利用すると、配偶者は自宅に住み続けることができ、その分ほかの財産を子どもに分配しやすくなります。こうした選択肢を知り、配偶者が安心して暮らせる方法を検討しましょう。
相続は税金対策だけでなく、家族の将来の生活も考えながら進めることが大切です。配偶者の生活費や住まいを確保しつつ、遺産争いを避けるために事前の準備をしておきましょう。相続の手続きや計画に不安がある場合は、専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。
「円満相続ラボ」では、相続に関する基本知識やトラブル回避の方法をわかりやすくお伝えし、専門家によるサポートを提供しています。円満な相続を実現するための最適なご提案をいたします。
相続に関する疑問がある方には、相続診断士による無料相談窓口もご利用いただけます。どうぞお気軽にご相談ください。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を書いたのは…

弁護士・ライター
中澤 泉(なかざわ いずみ)
弁護士事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続といった幅広い分野の案件を担当した後、メーカーの法務部で企業法務の経験を積んでまいりました。
事務所勤務時にはウェブサイトの立ち上げにも従事し、現在は法律分野を中心にフリーランスのライター・編集者として活動しています。
法律をはじめ、記事執筆やコンテンツ制作のご依頼がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。








