弁護士が解説:「親の借金」問題、あなたの負担を減らす解決策
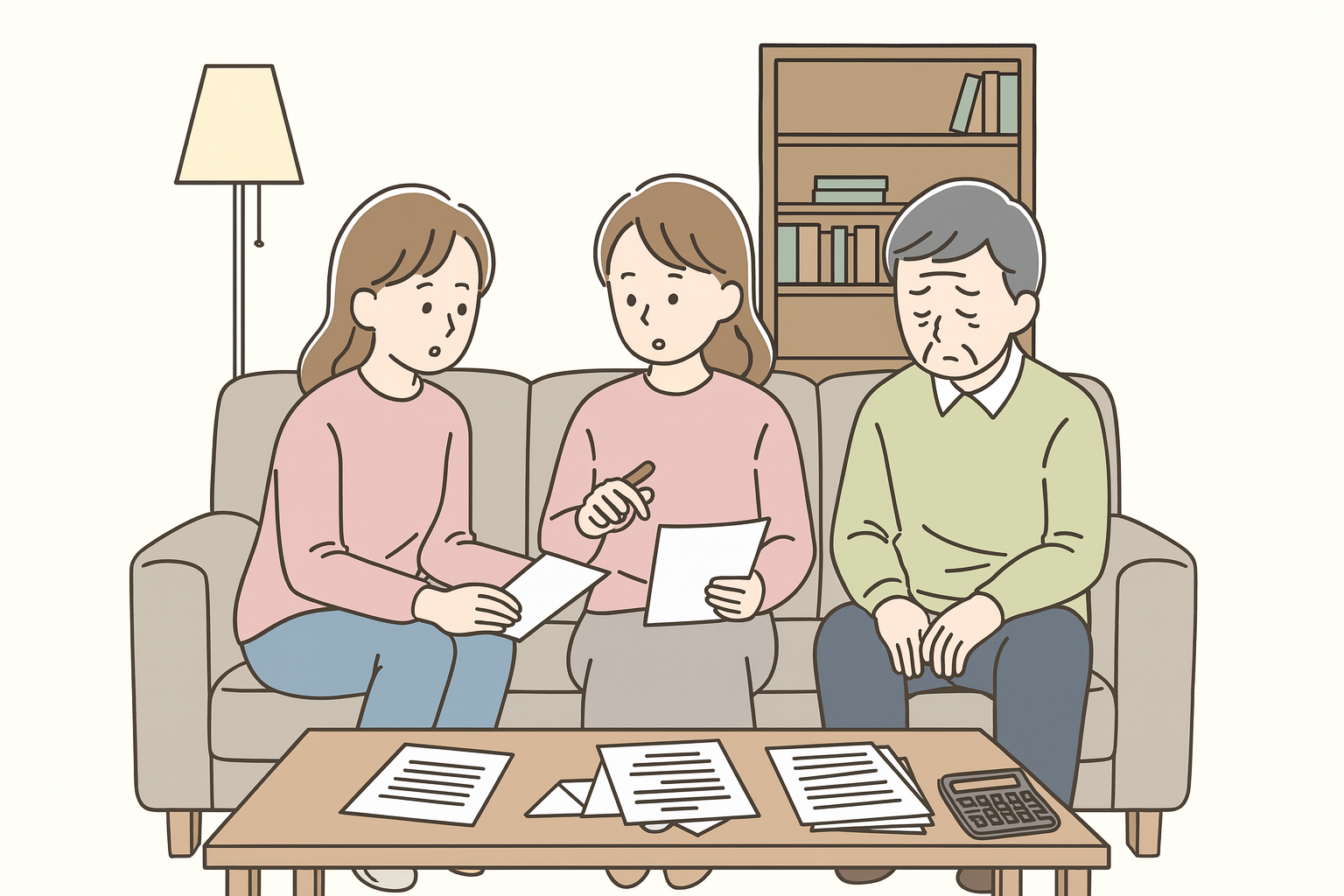
「親の借金」が発覚し、途方に暮れていませんか?原則として、親の借金は子に支払い義務はありません。連帯保証人でない限り、あなたがその負担を背負う必要はないのです。この記事では、相続放棄や限定承認、債務整理、時効援用といった具体的な法的解決策から、親が生きている場合・亡くなった場合の対処法、弁護士への相談方法まで、あなたの状況に応じた最適な解決策を提示します。一人で抱え込まず、この情報を活用して、親の借金問題から解放されるための具体的な一歩を踏み出しましょう。
Contents
記事内容を動画で解説
1. 親の借金が発覚したら、まず知るべきこと
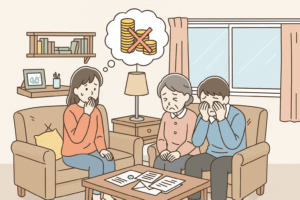
親の借金が突然発覚したとき、大きな衝撃と同時に「自分が返済しなければならないのか」という不安に襲われる方は少なくありません。しかし、親の借金は、原則として子が引き継ぐ義務はありません。まずは冷静になり、法的な知識に基づいて状況を正しく理解することが重要です。
1.1 親の借金は子に支払い義務があるのか
日本の民法において、親が負った借金は、原則としてその子どもが直接的に返済する義務を負うことはありません。これは、借金が「個人」に帰属するものであり、家族という単位で自動的に引き継がれるものではないという考え方に基づいています。
しかし、この原則にはいくつかの例外や注意点が存在します。最も重要なのは、親が亡くなり、その借金を含む「相続」が発生した場合です。この場合、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。もし親の借金を引き継ぎたくない場合は、後述する「相続放棄」や「限定承認」といった法的な手続きを検討する必要があります。
また、親の借金について、あなたが「保証人」や「連帯保証人」になっている場合は、その限りではありません。この点については、次の項目で詳しく解説します。
1.2 連帯保証人になっている場合の責任
親の借金に関して、あなたが「連帯保証人」になっている場合、親が返済できなくなったときに、あなた自身が親の借金を返済する義務を負います。連帯保証人は、主債務者(この場合、親)と全く同じ返済義務を負うため、その責任は非常に重いです。
通常の「保証人」には、債権者(お金を貸した側)から請求があった際に「まずは主債務者に請求してください」と主張できる「催告の抗弁権」や、「主債務者に財産があるなら、そちらから取り立ててください」と主張できる「検索の抗弁権」があります。しかし、連帯保証人には、これらの抗弁権が一切ありません。
そのため、連帯保証人になっている場合、債権者は親に請求することなく、直接あなたに借金の全額を請求することが可能です。もし請求に応じなければ、財産を差し押さえられたり、給与が差し押さえられたりする可能性もあります。自分が連帯保証人になっているかどうかは、契約書を確認するか、金融機関に問い合わせることで確認できます。
1.3 借金の種類と対処法の違い
親の借金の種類によって、その性質や対処法が大きく異なります。借金がどこからのものか、どのような契約になっているのかを正確に把握することが、適切な解決策を見つけるための第一歩となります。
| 借金の種類 | 主な特徴 | 対処法のポイント |
|---|---|---|
| 消費者金融・銀行カードローン・クレジットカードのキャッシング |
|
|
| 住宅ローン・自動車ローンなど(担保付ローン) |
|
|
| 奨学金 |
|
|
| 闇金(違法な高金利業者) |
|
|
| 個人間の借金 |
|
|
借金の種類によっては、時効が成立しているケースや、過払い金が発生しているケースもあります。まずは、借金の全体像を把握し、どの種類の借金がどれくらいの額あるのかを正確に把握することが、解決への第一歩となります。
2. 親の借金問題を解決するための法的手段

親の借金問題に直面した際、感情的になるだけでなく、法的な視点から冷静に対処することが重要です。ここでは、借金の負担を軽減または回避するための具体的な法的手段について解説します。
2.1 相続放棄で親の借金を背負わない方法
親が亡くなった後で借金が発覚した場合、最も根本的な解決策の一つが相続放棄です。相続放棄とは、被相続人(亡くなった親)の財産や負債を一切引き継がないという意思表示をすることです。これにより、親の借金を子が背負う義務はなくなります。
2.1.1 相続放棄の期間と手続き
相続放棄を行うには、自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行う必要があります。この3ヶ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続財産(プラスの財産とマイナスの財産)を調査し、相続するか放棄するかを判断するための期間です。
もし、この3ヶ月の期間内に調査が終わらない場合や、借金の存在を知らなかったなどの正当な理由がある場合は、家庭裁判所に申し立てることで期間の延長が認められることもあります。
手続きとしては、以下の書類を揃え、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要な場合もあります)
- その他、相続関係を示す戸籍謄本など
これらの書類準備には時間と手間がかかるため、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
2.1.2 相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄は強力な手段ですが、そのメリットとデメリットを十分に理解しておくことが重要です。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 借金(負債) | 親の借金を一切引き継ぐ必要がなくなる | なし |
| 財産(資産) | なし | 預貯金、不動産、有価証券などプラスの財産も一切引き継げなくなる |
| 撤回 | なし | 一度、家庭裁判所で受理されると原則として撤回できない |
| 次の相続人 | なし | 相続放棄をすると、相続権が次の順位の相続人(例:子が放棄すれば親や兄弟姉妹)に移るため、他の親族に借金問題が及ぶ可能性がある |
| 管理責任 | なし | 相続財産に属する財産を現に占有している場合、相続放棄後もその財産を管理する責任(民法940条)が生じることがある |
相続放棄は、借金問題から完全に解放される強力な手段ですが、その代償として、親が残したプラスの財産も一切受け取れなくなります。また、一度放棄すると原則として撤回できないため、慎重な判断が必要です。もし、親に借金だけでなく、処分に困るような不動産などがある場合も、相続放棄は有効な選択肢となり得ます。
2.2 限定承認で親の借金と財産を整理する方法
相続放棄が「プラスもマイナスもすべて引き継がない」のに対し、限定承認は「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算し、残ったプラスの財産があればそれを引き継ぐ」という方法です。親の財産に借金があることは分かっているものの、プラスの財産がどれくらいあるか不明な場合や、先祖代々の土地などどうしても残したい財産がある場合に検討されます。
限定承認も、自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。ただし、相続放棄と異なり、相続人全員が共同で申述しなければならないという特徴があります。この点が限定承認の手続きを複雑にする要因の一つです。
限定承認が認められると、家庭裁判所の監督のもと、相続財産から借金を返済する手続き(清算手続き)が行われます。清算の結果、借金が財産を上回ったとしても、相続人が自己の財産から借金を弁済する必要はありません。逆に、借金を返済しても財産が残れば、その残余財産を相続することができます。
しかし、限定承認は手続きが非常に複雑で、専門的な知識が求められます。実務上も利用されるケースは少ないですが、特定の状況下では有効な選択肢となり得ます。必ず弁護士などの専門家に相談し、具体的な手続きや費用、期間について確認しましょう。
2.3 債務整理を検討するケース
親がまだご存命で、親自身が借金に苦しんでいる場合は、親が債務整理を行うことで問題解決を図ることができます。債務整理には、主に「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つの方法があります。それぞれの方法には特徴があり、借金の状況や収入、財産の有無によって最適な選択肢が異なります。
2.3.1 自己破産
自己破産は、裁判所に申し立てを行い、借金の返済が不可能であることを認めてもらうことで、原則としてすべての借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。多額の借金があり、収入だけでは返済が到底見込めない場合に最終手段として検討されます。
メリットとしては、借金がゼロになる点が挙げられます。しかし、デメリットも大きく、一定以上の価値のある財産(持ち家、車、高額な預貯金など)は処分され、債権者への配当に充てられます。また、信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間(通常5~10年)は新たな借り入れやクレジットカードの作成が難しくなります。さらに、一部の職業(弁護士、司法書士、警備員など)に就けない期間が生じることや、官報に氏名・住所が掲載されることもデメリットとして挙げられます。
2.3.2 個人再生
個人再生は、裁判所の認可を得て、借金を大幅に減額(原則として1/5から1/10程度)し、残りの借金を原則3年(最長5年)で分割して返済していく手続きです。自己破産とは異なり、借金がゼロになるわけではありませんが、住宅ローンがある場合に「住宅ローン特則」を利用することで、持ち家を残しながら借金を整理できる可能性があります。
メリットは、持ち家や車などの財産を残せる可能性が高いこと、自己破産のような職業制限がないこと、ギャンブルや浪費による借金でも利用できることなどが挙げられます。デメリットとしては、安定した継続的な収入が必要であること、信用情報機関に事故情報が登録されること、手続きが自己破産と同様に複雑であることなどがあります。
2.3.3 任意整理
任意整理は、裁判所を介さず、債権者(金融機関や貸金業者など)と直接交渉し、将来発生する利息のカットや、返済期間の延長などを求める手続きです。元金そのものが減額されることは稀ですが、利息負担がなくなることで月々の返済額が減り、無理なく返済を続けられるようになることを目指します。
最大のメリットは、裁判所を通さないため手続きが比較的簡易であること、整理する借金を選べること(例:保証人がついている借金は対象外にする)、周囲に知られにくいことなどが挙げられます。デメリットとしては、債権者が交渉に応じない場合があること、信用情報機関に事故情報が登録されること、元金は減らないため、ある程度の返済能力が必要であることなどがあります。
これらの債務整理の方法は、親の借金状況や希望に応じて最適なものが異なります。いずれの方法も専門家である弁護士に相談し、親の状況を詳しく説明した上で、適切なアドバイスを受けることが不可欠です。
2.4 時効援用による解決の可能性
借金には、一定期間が経過すると返済義務がなくなる「消滅時効」という制度があります。この時効が成立している場合、債務者(借金をした人)が債権者(お金を貸した人)に対して「時効の援用」という意思表示をすることで、借金の支払い義務を法的に消滅させることができます。
借金の消滅時効期間は、債権者の種類によって異なります。例えば、消費者金融や銀行からの借金は原則として最終返済日から5年、個人間の借金や信用金庫からの借金は原則として10年とされています。ただし、時効期間が経過していても、自動的に借金がなくなるわけではありません。時効を主張する「時効援用」の意思表示が必要です。
また、時効期間中に「時効の更新事由(旧:時効の中断事由)」が発生すると、時効期間はリセットされ、またゼロから数え直しになります。時効の更新事由には、債務者が借金の一部を返済したり、債務があることを認めたり(承認)、債権者から裁判を起こされたり、差押えが行われたりするケースなどがあります。
親の借金が古いものであれば、時効が成立している可能性があります。しかし、時効の判断は非常に専門的であり、過去の取引履歴や時効更新事由の有無を正確に確認する必要があります。時効援用は、内容証明郵便など書面で行うことが一般的であり、弁護士に依頼することで確実かつ安全に進めることができます。
親が亡くなった後に古い借金が発覚した場合でも、この時効援用が有効な解決策となることがあります。しかし、安易に債権者と接触すると、時効の更新事由を作ってしまうリスクもあるため、必ず専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
3. 親の借金問題 ケース別の対処法

親の借金問題に直面した際、その対処法は親が存命か、既に亡くなっているか、また兄弟がいるかいないかによって大きく異なります。それぞれの状況に応じた適切な対応を取ることが、問題解決への近道となります。
3.1 親が生きている場合の親の借金対処法
親が存命中に借金問題が発覚した場合、最も重要なのは親自身が問題と向き合い、解決に向けて行動することです。子が安易に肩代わりすることは、根本的な解決にならず、かえって問題を複雑化させる可能性があります。
まず、親としっかりと話し合い、借金の全容(金額、債権者、借り入れた経緯、使途など)を正確に把握することが重要です。その上で、以下の対処法を検討します。
- 親自身による債務整理の検討を促す:親が自力での返済が困難な場合、弁護士や司法書士に相談し、任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理手続きを検討するよう促します。これは第2章「親の借金問題を解決するための法的手段」で詳しく解説されている手段です。
- 安易な肩代わりは避ける:子が親の借金を肩代わりすると、親が借金を繰り返す可能性や、子自身が経済的に困窮するリスクがあります。連帯保証人になっていない限り、子に親の借金を返済する法的な義務はありません。
- 家計の見直しと生活習慣の改善をサポート:借金の原因が浪費やギャンブルなどにある場合、親の生活習慣や金銭感覚の改善が必要です。専門家のアドバイスを受けながら、家計の見直しや生活再建をサポートすることも検討できます。
- 詐欺被害の可能性も視野に:もし親が詐欺被害に遭って借金を背負わされた可能性があれば、警察や消費者センターに相談することも重要です。
3.2 親が亡くなった場合の親の借金対処法
親が亡くなった後に借金が発覚した場合、相続という観点から対処法を検討する必要があります。相続には、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金)も含まれます。相続人は、原則として被相続人の一切の権利義務を承継します。
親の死後に借金が判明した場合、相続開始から3ヶ月以内に以下のいずれかの選択をしなければなりません。
| 選択肢 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない。 |
|
| 限定承認 | 相続したプラスの財産の範囲内で借金を返済し、それ以上の返済義務は負わない。 |
|
| 単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する。 |
|
親が亡くなった場合、まず行うべきは遺品整理の際に借金の証拠(督促状、ローン契約書、クレジットカード明細など)がないか徹底的に確認することです。また、金融機関への問い合わせや信用情報機関への情報開示請求を通じて、親の負債状況を正確に把握することも重要です。これらの手続きは複雑なため、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
3.3 兄弟がいる場合の親の借金問題
親の借金問題に兄弟も関わる場合、兄弟間の連携と情報共有が非常に重要になります。特に親が亡くなった後の相続問題では、全員の意思統一が求められる場面が多くなります。
- 情報共有と話し合い:親の借金が発覚したら、速やかに兄弟全員で情報を共有し、今後の対応について話し合う場を設けることが重要です。個々がバラバラに対応すると、混乱を招いたり、不利な状況に陥ったりする可能性があります。
- 相続放棄・限定承認の意思統一:親が亡くなり、相続放棄や限定承認を検討する場合、原則として相続人全員が合意し、手続きを行う必要があります(限定承認の場合)。特定の兄弟だけが相続放棄をすると、その兄弟の分の借金が他の兄弟に回ってくる可能性があります。
- 連帯保証人の確認:兄弟の誰かが親の借金の連帯保証人になっている場合、その兄弟は親が返済できない場合に返済義務を負います。連帯保証人になっている兄弟がいる場合は、その責任の範囲と対処法について、弁護士を交えて検討することが不可欠です。
- 遺産分割協議と借金:親が亡くなった場合、プラスの財産だけでなく、借金も遺産分割協議の対象となり得ます。しかし、借金は相続開始と同時に法定相続分に応じて各相続人に分割されるのが原則であり、遺産分割協議で特定の相続人にのみ負担させることは、債権者に対しては主張できません。債権者への対応と、相続人内部での負担割合は分けて考える必要があります。
- 専門家への共同相談:兄弟間で意見がまとまらない場合や、法的な判断が難しい場合は、兄弟全員で弁護士に相談し、客観的なアドバイスを受けることがトラブル回避につながります。
4. 親の借金問題、どこに相談すべきか
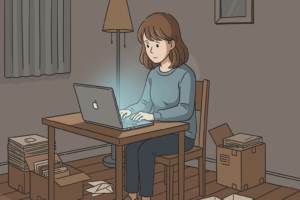
親の借金問題に直面した際、どこに相談すべきか迷うのは当然です。 複雑な法律問題が絡むため、専門家のサポートが不可欠となります。ここでは、親の借金問題の解決に向けて相談すべき専門家とその選び方について詳しく解説します。
4.1 弁護士に相談するメリットと役割
親の借金問題は、法的な知識なしに解決することは極めて困難です。特に相続や債務整理といった専門的な手続きが必要となるため、法律の専門家である弁護士に相談することが最も確実な解決への道となります。
弁護士に相談する主なメリットと、その役割は以下の通りです。
- 法的な選択肢の提示と助言: 親の借金の種類や状況、ご自身の財産状況などを総合的に判断し、相続放棄、限定承認、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)、時効援用など、最適な解決策を具体的に提案してくれます。
- 複雑な手続きの代行: 相続放棄の申立て、債務整理の書類作成や裁判所への申立て、債権者との交渉など、専門知識を要する複雑な手続きを全て代行してくれます。これにより、ご自身の時間的・精神的負担を大幅に軽減できます。
- 債権者との交渉: 債権者からの督促や取り立てに直接対応し、代理人として交渉を進めてくれます。これにより、精神的なストレスから解放され、冷静に問題解決に取り組むことができます。
- 精神的な負担の軽減: 一人で抱え込みがちな借金問題において、専門家が寄り添い、具体的な解決策を示すことで、精神的な安心感を得ることができます。
- トラブルの未然防止: 誤った対応をしてしまうと、新たな問題やトラブルに発展する可能性があります。弁護士は、そうしたリスクを回避し、法的に正しい手順で解決へと導いてくれます。
4.2 弁護士費用の目安と無料相談の活用
弁護士への相談をためらう理由の一つに、費用への不安があるかもしれません。しかし、多くの法律事務所では、相談しやすいように様々な料金体系や無料相談の機会を設けています。
4.2.1 弁護士費用の種類と目安
弁護士費用は、依頼する内容や事務所の方針によって異なりますが、一般的には以下の項目で構成されます。
| 費用の種類 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に法律相談をする際に発生する費用。 | 初回30分~1時間程度は無料の事務所が多い。有料の場合は30分5,000円程度。 |
| 着手金 | 依頼を受けた際に、事件処理の対価として最初に支払う費用。結果に関わらず返還されないのが原則。 | 債務整理の内容や借金の額によるが、10万円~50万円程度が目安。 |
| 報酬金 | 事件解決の成功度合いに応じて、事件終了時に支払う費用。 | 解決した借金の減額幅や、得られた経済的利益に応じて算出されることが多い。 |
| 実費 | 事件処理に必要な印紙代、郵送費、交通費、予納金など。 | 数千円~数万円程度。 |
上記はあくまで目安であり、個別のケースや依頼する法律事務所によって大きく変動します。具体的な費用については、必ず依頼前に見積もりを依頼し、明確な説明を受けるようにしましょう。
4.2.2 無料相談の積極的な活用
多くの法律事務所では、初回相談を無料で実施しています。これは、費用を気にせず気軽に弁護士に相談できる貴重な機会です。 無料相談では、現在の状況を伝え、どのような解決策があるのか、おおよその費用はどのくらいになるのかといった基本的な情報を得ることができます。
また、日本司法支援センター(法テラス)では、経済的に余裕がない方を対象に、無料の法律相談や弁護士費用の立て替え制度を提供しています。利用には一定の条件がありますが、費用面で不安がある場合は検討してみると良いでしょう。お住まいの自治体でも、無料の法律相談会を開催している場合がありますので、広報誌やウェブサイトで確認してみるのも有効です。
4.3 法律事務所選びのポイント
親の借金問題の解決を依頼する法律事務所は、慎重に選ぶ必要があります。以下のポイントを参考に、ご自身に合った信頼できる弁護士を見つけましょう。
- 債務整理や相続問題の実績が豊富か: 借金問題や相続問題は専門性が高く、経験が豊富な弁護士ほど、よりスムーズかつ有利な解決に導いてくれる可能性が高まります。事務所のウェブサイトなどで、解決実績や得意分野を確認しましょう。
- 費用体系が明確か: 相談料、着手金、報酬金、実費など、全ての費用について事前に明確な説明があり、納得できる料金体系であるかを確認しましょう。不明な点があれば、納得いくまで質問することが大切です。
- 説明が分かりやすく丁寧か: 法律用語は難解なものが多く、一般の方には理解しにくい場合があります。専門用語を避け、分かりやすい言葉で丁寧に説明してくれる弁護士を選びましょう。
- 親身に話を聞いてくれるか: 借金問題はデリケートな内容であり、精神的な負担も大きいです。依頼者の気持ちに寄り添い、親身になって話を聞いてくれる弁護士であれば、安心して任せることができます。
- アクセスしやすいか: 事務所の場所や営業時間も考慮しましょう。対面での相談が必要になる場合もあるため、通いやすい場所にあるか、オンライン相談に対応しているかなども確認すると良いでしょう。
- 無料相談を活用して比較検討する: 複数の法律事務所の無料相談を利用し、それぞれの弁護士の対応や説明の分かりやすさ、費用体系などを比較検討することをおすすめします。
5. 親の借金問題による精神的負担を軽減するために
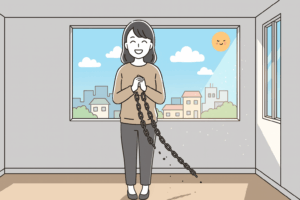
親の借金問題は、金銭的な側面だけでなく、精神的にも大きな負担となり得ます。不安、焦燥感、孤立感、そして親への複雑な感情など、さまざまなストレスが心にのしかかることは珍しくありません。しかし、その負担を一人で抱え込む必要はありません。適切なサポートを得ることで、心の健康を守りながら問題解決へと進む道が開けます。
5.1 家族や周囲への相談の重要性
親の借金問題はデリケートなため、誰にも話せずに抱え込んでしまうケースが少なくありません。しかし、信頼できる家族や友人、パートナーに相談することは、精神的な重荷を軽減する第一歩となります。話を聞いてもらうだけでも、心が軽くなることがありますし、客観的な意見や共感を得られることで、孤立感を解消し、冷静に問題と向き合うための力を得られるでしょう。
特に、兄弟姉妹がいる場合は、互いに協力し合うことで、精神的な負担を分かち合い、解決策を共に探すことが可能になります。家族会議を開き、現状を共有し、今後の対応について話し合う機会を設けることも有効です。ただし、感情的にならず、冷静に事実に基づいた話し合いを心がけることが重要です。
家族内でのコミュニケーションが難しい場合や、さらに深い心のケアが必要と感じる場合は、専門のカウンセリングを受けることも検討しましょう。家族療法や個人のカウンセリングを通じて、感情の整理やストレスへの対処法を学ぶことができます。
5.2 専門家と連携し、一人で抱え込まないこと
親の借金問題の解決には、法律の専門家である弁護士の力が不可欠です。しかし、弁護士は法的な解決策を提供するだけでなく、その過程であなたの精神的な支えにもなり得ます。問題解決の具体的な道筋が見えることで、漠然とした不安が軽減され、安心感を得られるからです。
また、借金問題によるストレスが深刻で、日常生活に支障をきたしている場合は、精神科医や臨床心理士、カウンセラーといった心の専門家への相談も積極的に検討してください。不眠、食欲不振、抑うつ症状、過度な不安などが続くようであれば、早期に専門家のサポートを受けることが、心の健康を守る上で非常に重要です。
専門家と連携することで、あなたは一人で問題に立ち向かうのではなく、チームとして解決に取り組むことができます。それぞれの専門家が異なる側面からサポートを提供することで、法的な解決と精神的なケアの両輪で、より健全な状態へと導かれるでしょう。
| 専門相談先 | 得られるサポート・メリット |
|---|---|
| 弁護士 |
|
| 精神科医・心療内科医 |
|
| 臨床心理士・カウンセラー |
|
| 自治体の相談窓口(精神保健福祉センターなど) |
|
親の借金問題は、決してあなた一人の責任ではありません。一人で抱え込まず、適切なサポートを求める勇気を持つことが、精神的な負担を軽減し、問題解決への第一歩となります。専門家を頼り、心の健康も守りながら、この困難な状況を乗り越えていきましょう。
6. まとめ
親の借金問題は、突然降りかかり、大きな精神的負担となるものです。しかし、原則として親の借金が子に直接的な支払い義務を負わせることはありません。連帯保証人になっている場合など例外はありますが、相続放棄、限定承認、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)など、状況に応じた様々な法的解決策が存在します。一人で抱え込まず、弁護士などの専門家へ早めに相談することが何よりも重要です。無料相談を活用し、適切なアドバイスを得ることで、必ず解決への道が開けます。未来のために、勇気を出して一歩を踏み出しましょう。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を監修したのは…

さくら共同法律事務所 弁護士・弁理士
野崎 智裕(のざき あきひろ)
京都大学文学部人文学科行動・環境文化学系社会学専修卒業後、京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻を経て
平成30年9月 司法試験合格
ミツカン創業家裁判やカルテル巡る関西電力株主訴訟などを担当。顧客の本来利益を追求する姿勢が顧客からの信頼を得ている。








