未登記建物相続の注意点とトラブル回避方法を専門家が解説

未登記建物を相続すると、所有権の証明困難や売却時のトラブル、相続人間の権利争いなど様々な問題が発生する可能性があります。この記事では、未登記建物相続で起こりがちなトラブル事例から、建物表題登記や相続登記の具体的な手続き方法、土地家屋調査士や司法書士への相談タイミングまで、専門家の視点で詳しく解説します。適切な対処法を知ることで、相続トラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続手続きを実現できます。
Contents
1. 未登記建物とは何か

1.1 未登記建物の定義と特徴
未登記建物とは、法務局において建物の表題登記がなされていない建物のことを指します。建物を新築した場合、不動産登記法により、所有者は新築から1か月以内に建物の表題登記を申請する義務があります。しかし、この手続きを怠ったり、忘れたりした結果として未登記建物が生まれます。
未登記建物には以下のような特徴があります。まず、登記簿謄本が存在しないため、公的な書類での所有権の証明が困難になります。また、固定資産税の課税台帳には記載されている場合が多く、税務上の存在は認識されているものの、法的な権利関係が不明確な状態となっています。
未登記建物が発生する主な原因として、建築確認申請を経ずに建てられた建物、増築部分の登記手続きが行われていない場合、相続時に登記手続きが放置されたケースなどが挙げられます。特に古い建物や農村部の建物、小規模な物置や車庫などに未登記の状態が多く見られます。
1.2 登記済み建物との違い
登記済み建物と未登記建物の違いを理解することは、相続手続きを進める上で非常に重要です。以下の表で主要な違いを整理します。
| 項目 | 登記済み建物 | 未登記建物 |
| 登記簿の存在 | 建物登記簿謄本で確認可能 | 登記簿謄本が存在しない |
| 所有権の証明 | 登記事項証明書で公的に証明 | 固定資産税納税証明書等で間接的に証明 |
| 売買の可否 | 通常の売買取引が可能 | 登記後でないと売買が困難 |
| 融資の担保 | 担保設定が可能 | 原則として担保設定不可 |
| 相続手続き | 相続登記で権利移転 | 表題登記後に相続登記が必要 |
登記済み建物では所有権の移転や抵当権の設定などの権利変動を登記によって第三者に対抗できますが、未登記建物では前述の所有権移転登記や抵当権設定登記ができません。このため、不動産取引においては登記の完了が前提条件となることが一般的です。
また、登記済み建物の場合、建物の構造や床面積、建築年月日などの詳細な情報が登記簿に記載されており、建物の現況を正確に把握できます。一方、未登記建物では、固定資産税の課税台帳や建築確認済証などから建物の概要を推測する必要があり、正確な建物情報の特定に時間と労力を要する場合があります。
相続の観点から見ると、登記済み建物は被相続人から相続人への権利移転を相続登記によってスムーズに行うことができます。しかし、未登記建物の場合は、まず建物の表題登記を行い、その後に相続登記を行うという二段階の手続きが必要となり、時間と費用が余分にかかることになります。
2. 未登記建物を相続した場合の問題点

未登記建物を相続すると、様々な法的・実務的な問題が発生する可能性があります。これらの問題を事前に理解しておくことで、適切な対策を講じることができます。
2.1 所有権の証明が困難
未登記建物の最も深刻な問題は、所有権を客観的に証明することが極めて困難である点です。登記済み建物であれば登記事項証明書により所有者が明確に記録されていますが、未登記建物では以下のような証明手段に頼らざるを得ません。
| 証明書類 | 証明力 | 注意点 |
| 建築確認済証 | 高 | 紛失している場合が多い |
| 固定資産税納税通知書 | 中 | 税務上の名義と所有権は別概念 |
| 建築請負契約書 | 高 | 古い建物では保存されていない場合が多い |
| 火災保険証券 | 低 | 補強的な証拠として使用 |
特に相続が発生した場合、被相続人が建物の真の所有者であったことを証明するための資料が不足することが多く、相続人間で争いが生じるリスクが高まります。
2.2 売却時のトラブルリスク
未登記建物の売却は、登記済み建物と比較して多くの困難を伴います。主なトラブルリスクは以下の通りです。
2.2.1 買主への所有権移転ができない
未登記建物では登記による所有権移転ができないため、売買契約を締結しても買主が完全な所有権を取得できない状況が生じます。これにより、買主が購入を躊躇したり、売買代金の減額を要求される可能性があります。
2.2.2 第三者対抗要件の欠如
登記がないことで第三者に対する対抗要件を備えることができず、将来的に所有権を巡る紛争が発生するリスクが常に存在します。買主にとってこのリスクは非常に大きな不安要素となります。
2.2.3 金融機関の融資審査への影響
買主が住宅ローンを利用する場合、未登記建物では担保価値が認められにくく、金融機関から融資を断られる可能性が高いです。これにより売却先が現金購入者に限定され、売却価格の低下を招く要因となります。
2.3 固定資産税の課税問題
未登記建物であっても固定資産税の課税対象となるため、相続により様々な税務上の問題が発生します。
2.3.1 課税名義と実際の所有者の不一致
固定資産税は市町村が把握している納税義務者に課税されますが、未登記建物では実際の所有者と課税台帳上の名義人が異なるケースが頻繁に発生します。相続発生後も被相続人名義で課税され続ける場合があり、相続人が適切な手続きを行わないと税務上のトラブルが生じる可能性があります。
2.3.2 相続税評価への影響
未登記建物の相続税評価においては、建物の存在や価値を客観的に証明する資料が不足しがちです。このため、税務署との間で評価額について見解の相違が生じるリスクがあります。
| 評価方法 | 適用条件 | 問題点 |
| 固定資産税評価額 | 市町村で把握されている場合 | 実際の建物価値と乖離する場合がある |
| 再建築価額方式 | 固定資産税評価額がない場合 | 建築年次や構造の特定が困難 |
| 類似建物比準方式 | 近隣に類似建物がある場合 | 比較対象の選定で争いが生じやすい |
2.3.3 住宅用地特例の適用問題
住宅用地に対する固定資産税の特例措置は、原則として登記された建物が存在する土地に適用されます。未登記建物の場合、特例の適用が認められない可能性があり、土地の固定資産税が大幅に増加するリスクがあります。相続後に建物を解体する場合も、事前に登記を行っていないと特例が適用されず、相続人に予想外の税負担が生じる可能性があります。
3. 未登記建物相続で発生しやすいトラブル事例

未登記建物を相続した場合、法的な権利関係が不明確になることで様々なトラブルが発生する可能性があります。実際の相続現場で起こりやすい具体的な事例を詳しく解説します。
3.1 相続人間での権利関係の争い
未登記建物の相続では、建物の所有権を証明する公的な書類が存在しないため、相続人間で権利関係をめぐる深刻な争いが発生することがあります。
最も典型的なケースは、被相続人が建物を建築した際の経緯や費用負担について、相続人それぞれが異なる認識を持っている場合です。例えば、長男が「父が一人で建てた建物だから自分が単独で相続する」と主張する一方で、次男が「建築費用の一部を自分が負担したから共有持分がある」と主張するような事例があります。
このような争いでは、以下の証拠収集が困難になります:
| 証明すべき事項 | 通常必要な証拠 | 未登記建物での問題点 |
| 建築時期 | 建築確認済証、検査済証 | 書類が紛失している場合が多い |
| 建築費用の負担者 | 領収書、銀行振込記録 | 古い記録の保存が困難 |
| 所有者 | 登記事項証明書 | 登記がないため客観的証明不可 |
さらに、建物が増築や改築を繰り返している場合、どの部分を誰が建築したかの特定が極めて困難になり、相続人間の対立が長期化する傾向があります。
3.2 第三者への対抗要件の不備
未登記建物は、第三者に対してその所有権を主張することができないという重大な問題があります。これは民法における対抗要件の原則に基づくものです。
具体的なトラブル事例として、以下のようなケースがあります:
3.2.1 隣地所有者との境界紛争
隣地の所有者が「その建物は境界を越境している」と主張してきた場合、未登記建物の所有者は建物の正確な位置や建築時期を客観的に証明することが困難です。登記がある建物であれば、建物図面や各階平面図によって建物の位置を明確にできますが、未登記建物ではこれらの図面が存在しません。
3.2.2 建物買取請求への対応困難
土地の所有者が変更された際に、新しい土地所有者から建物買取請求を受けるケースがあります。しかし、未登記建物の場合、建物の所有権を証明できないため、適正な買取価格の算定や交渉において不利な立場に置かれることになります。
3.2.3 権利関係の複雑化
建物の一部を第三者に貸し出していた場合、賃借人との権利関係も不安定になります。賃借人が「建物の所有者が誰か分からない」として賃料の支払いを拒否したり、逆に複数の相続人がそれぞれ賃料を請求したりするトラブルが発生することがあります。
3.3 金融機関からの融資拒否
未登記建物を担保として活用することは実質的に不可能であり、金融機関からの融資を受ける際に深刻な障害となります。
3.3.1 担保価値の問題
銀行や信用金庫などの金融機関は、融資の際に不動産を担保として設定することが一般的ですが、未登記建物では以下の理由により担保設定ができません:
- 抵当権設定登記ができない
- 建物の正確な評価額算定が困難
- 権利関係が不明確で回収リスクが高い
3.3.2 事業資金調達への影響
特に個人事業主や中小企業経営者の場合、事業資金の調達において未登記建物が大きな制約となります。銀行は融資審査において、申込人の保有する不動産を重要な判断材料としますが、未登記建物は資産として評価されないため、融資限度額の減額や融資そのものの拒否につながることがあります。
3.3.3 住宅ローンへの影響
相続した未登記建物を建て替える際の住宅ローンにおいても問題が生じます。金融機関は土地と建物の両方を担保として設定することが多いですが、建物が未登記の場合、土地のみを担保とする融資となり、融資条件が不利になる可能性があります。
また、建築工事の進行に合わせた分割実行を行う住宅ローンでは、既存建物の解体証明が必要になる場合がありますが、未登記建物では解体登記ができないため、手続きが複雑化することがあります。
4. 未登記建物相続の適切な手続き方法

未登記建物を相続した場合、適切な手続きを踏むことで将来的なトラブルを回避できます。手続きは複数の段階に分かれており、それぞれ異なる専門家や機関が関与します。
4.1 建物表題登記の申請手順
未登記建物の相続では、まず建物表題登記を行うことが最重要です。この登記により建物の物理的状況を法務局に記録し、不動産登記簿に建物の存在を明確にします。
4.1.1 申請前の準備作業
建物表題登記を申請する前に、以下の調査と準備が必要です:
- 建物の現況調査(面積、構造、用途の確認)
- 敷地の測量および境界確定
- 建築確認申請書類の有無確認
- 相続関係の整理と確認
4.1.2 建物表題登記の申請手続き
建物表題登記の申請は、建物の所在地を管轄する法務局で行います。申請期限は建物の新築から1か月以内ですが、未登記建物の場合は遅滞なく申請する必要があります。
| 申請手順 | 内容 | 所要期間 |
| 1. 建物調査 | 土地家屋調査士による現地調査 | 1〜2週間 |
| 2. 図面作成 | 建物図面・各階平面図の作成 | 1週間 |
| 3. 申請書類準備 | 登記申請書および添付書類の準備 | 3〜5日 |
| 4. 法務局申請 | 管轄法務局への申請書提出 | 1〜2週間 |
4.2 相続登記の手続き
建物表題登記が完了した後、相続を原因とする所有権保存登記または所有権移転登記を行います。2024年4月から相続登記が義務化されており、相続開始から3年以内に手続きを完了する必要があります。
4.2.1 相続登記の種類と選択
未登記建物の相続登記では、以下のいずれかの方法を選択します:
- 所有権保存登記:建物表題登記後、初めて所有権を登記する場合
- 所有権移転登記:既に権利関係が明確で、相続により所有権が移転する場合
4.2.2 遺産分割協議と登記申請
相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行い、未登記建物の帰属を決定します。協議が成立した場合は遺産分割協議書を作成し、これを登記申請の添付書類として使用します。
協議がまとまらない場合は、法定相続分による共有登記を行った後、改めて分割協議または調停・審判手続きを進めることも可能です。
4.3 必要書類と費用の詳細
4.3.1 建物表題登記に必要な書類
建物表題登記申請時に必要となる主な書類は以下の通りです:
| 書類名 | 取得先 | 注意点 |
| 登記申請書 | 法務局または作成 | 土地家屋調査士が作成することが一般的 |
| 建物図面・各階平面図 | 測量により作成 | 正確な測量に基づく図面が必要 |
| 建築確認済証 | 建築時の書類 | 紛失の場合は建築台帳記載事項証明書で代用可能 |
| 相続関係証明書類 | 市区町村役場 | 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等 |
| 住民票 | 市区町村役場 | 申請人の現在の住所を証明 |
4.3.2 相続登記に必要な書類
相続登記では、建物表題登記の書類に加えて以下の書類が必要です:
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 遺産分割協議書(遺産分割を行った場合)
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に実印で押印した場合)
- 固定資産評価証明書
4.3.3 登記手続きにかかる費用
未登記建物の相続登記にかかる費用は、以下の要素で構成されます:
| 項目 | 費用目安 | 備考 |
| 建物表題登記 | 10万円〜15万円 | 土地家屋調査士報酬含む |
| 相続登記 | 5万円〜10万円 | 司法書士報酬含む |
| 登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% | 相続登記の場合 |
| 書類取得費 | 1万円〜3万円 | 戸籍謄本等の取得費用 |
総費用は建物の規模や複雑さにより20万円〜40万円程度が一般的な目安となります。ただし、相続人の数や相続関係の複雑さ、建物の構造等により費用は変動します。
4.3.4 費用軽減のための制度
一定の条件を満たす場合、登録免許税の軽減措置を受けることができます。相続により取得した不動産のうち、市街化区域外の土地で価額が10万円以下の場合等は、登録免許税が非課税となる制度もあります。
5. トラブルを回避するための対策

5.1 早期の登記手続きの重要性
未登記建物を相続した場合、相続発生から可能な限り早期に登記手続きを完了させることが最も重要な対策となります。放置期間が長くなるほど、相続関係が複雑化し、手続きが困難になる傾向があります。
早期手続きが重要な理由として、まず相続人の増加リスクが挙げられます。時間が経過すると相続人が死亡し、その子や孫が新たな相続人となることで、権利関係が複雑化します。また、相続人の居住地変更や連絡先不明により、遺産分割協議の実施が困難になる可能性も高まります。
建物表題登記については、相続開始を知った日から1年以内に申請することが不動産登記法で義務付けられています。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料が科される場合があります。
| 手続き種類 | 期限 | 放置した場合の影響 |
| 建物表題登記 | 相続開始から1年以内 | 過料(10万円以下)、所有権証明困難 |
| 相続登記 | 相続開始から3年以内 | 過料(10万円以下)、権利関係複雑化 |
| 遺産分割協議 | 法定期限なし | 相続人増加、合意形成困難化 |
5.2 専門家への相談タイミング
未登記建物の相続において、適切なタイミングで専門家に相談することで、手続きの複雑化やコスト増大を防ぐことができます。相談すべき時期と専門家の使い分けを理解しておくことが重要です。
相続発生直後の相談が最も効果的です。この段階では選択肢が多く残されており、最適な手続き方法を選択できます。建物の状況調査、必要書類の確認、手続きスケジュールの策定など、全体的な方針を決定できる時期です。
土地家屋調査士への相談は、建物の現況調査や建物表題登記が必要な場合に行います。建物の構造や面積、附属建物の有無などの専門的な調査が必要な際は、早期の相談が重要です。
司法書士への相談は、相続登記や遺産分割協議書の作成が必要な場合に行います。相続人が複数存在する場合や、相続関係が複雑な場合は、遺産分割協議の開始前に相談することが推奨されます。
相談を先延ばしにした場合のリスクとして、手続き費用の増大、選択肢の減少、トラブル発生時の解決困難化などが挙げられます。特に相続人間で意見の相違が生じ始めた段階では、早急な専門家への相談が必要となります。
5.3 遺産分割協議での注意点
未登記建物を含む遺産分割協議では、建物の評価方法と分割方法について事前に十分な検討を行うことが重要です。登記済み建物とは異なる特殊性があるため、慎重な協議が必要となります。
建物の評価については、固定資産税評価額、時価査定、再建築費用など複数の評価方法があります。未登記建物の場合、正確な評価が困難であることが多いため、専門家による評価を行うことで、相続人間の公平性を確保することが可能です。
分割方法の選択肢として、現物分割、代償分割、換価分割があります。未登記建物の現物分割は権利関係が複雑になりやすく、後のトラブル原因となる可能性があります。代償分割では適正な評価額の算定が重要となり、換価分割では売却前の登記手続きが必要となります。
| 分割方法 | メリット | デメリット・注意点 |
| 現物分割 | 建物を残せる、手続きが比較的簡単 | 共有関係発生リスク、管理責任不明確 |
| 代償分割 | 単独所有実現、権利関係明確 | 評価額算定困難、資金準備必要 |
| 換価分割 | 公平な分割可能、現金化 | 登記費用先行負担、売却困難リスク |
遺産分割協議書の作成では、未登記建物の特定方法に特に注意が必要です。所在地番、家屋番号がない場合の建物特定方法、構造・床面積・建築年月日等の記載、土地との関係性の明記など、後のトラブルを防ぐための詳細な記載が重要となります。
協議の進行において、全相続人の合意形成に時間をかけすぎると、相続関係がさらに複雑化するリスクがあります。一方で、性急な合意は後のトラブルの原因となるため、適切なバランスを保ちながら協議を進めることが重要です。
6. 専門家に相談すべきケース

未登記建物の相続手続きは複雑で専門的な知識が必要となるため、適切なタイミングで専門家に相談することが重要です。特に以下のようなケースでは、専門家への依頼を検討すべきでしょう。
6.1 土地家屋調査士に依頼する場合
土地家屋調査士は建物の表題登記を専門とする国家資格者です。未登記建物の相続では、まず建物表題登記が必要となるため、以下の状況では土地家屋調査士への相談が不可欠です。
建物の現況測量が必要な場合、土地家屋調査士が建物の位置、構造、床面積などを正確に測定し、法務局に提出する図面を作成します。特に増築や改築を繰り返している建物では、現在の状況と建築当初の状況が大きく異なることが多く、専門的な調査が必要です。
また、建物の構造や種類が複雑な場合も土地家屋調査士の専門知識が求められます。木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの構造判定や、居宅、店舗、工場などの種類判定は、登記における重要な要素となります。
| 依頼すべきケース | 理由 | 想定期間 |
| 建物の現況測量が必要 | 正確な位置・面積の確定 | 2~4週間 |
| 増改築歴がある建物 | 現状との相違確認 | 3~6週間 |
| 複数棟の建物が存在 | 各棟の特定と区分 | 4~8週間 |
| 隣地境界が不明確 | 境界確定測量の実施 | 2~6ヶ月 |
6.2 司法書士に依頼する場合
司法書士は登記手続きの専門家として、相続登記や所有権移転登記を担当します。建物表題登記完了後の所有権保存登記や相続登記では、司法書士への依頼が効率的です。
相続人が複数いる場合、遺産分割協議書の作成や相続関係説明図の作成など、法的な手続きが複雑になります。司法書士は相続に関する法的知識を有しており、適切な手続きを進めることができます。
特に以下のような状況では、司法書士への相談が重要となります。相続人の中に行方不明者がいる場合、海外居住者がいる場合、相続放棄を検討している相続人がいる場合など、通常とは異なる手続きが必要となるケースです。
債務超過の可能性がある相続案件では、司法書士が相続放棄の手続きや限定承認の検討についてアドバイスを提供できます。未登記建物に関連する債務や税金滞納などの問題も含めて、総合的な判断が必要となります。
6.3 費用対効果の考え方
専門家への依頼費用は決して安くありませんが、適切な手続きを行わないことによるリスクと比較して検討する必要があります。
土地家屋調査士への依頼費用は、建物の規模や複雑さによって異なりますが、一般的な住宅の場合は10万円から30万円程度が相場です。司法書士への依頼費用は、相続人の人数や手続きの複雑さによって5万円から20万円程度となることが多いです。
専門家費用を節約しようとして手続きを誤った場合のリスクは非常に大きくなります。登記の取り直しが必要となれば、費用は倍増し、時間も大幅にかかることになります。また、相続税の申告期限に間に合わない場合は、延滞税や加算税が発生する可能性もあります。
| 専門家 | 主な業務内容 | 費用相場 | 期間 |
| 土地家屋調査士 | 建物表題登記、現況測量 | 10~30万円 | 1~3ヶ月 |
| 司法書士 | 相続登記、所有権保存登記 | 5~20万円 | 2週間~2ヶ月 |
| 税理士 | 相続税申告、税務相談 | 20~100万円 | 3~6ヶ月 |
建物の評価額が高い場合や相続税の申告が必要な場合は、税理士への相談も検討すべきです。未登記建物の評価は複雑で、適切な評価を行わないと過大な相続税を支払うことになる可能性があります。
最終的な費用対効果を判断する際は、将来的な建物の利用予定や売却予定も含めて総合的に検討することが重要です。長期間保有する予定であれば、適切な登記を行うことで将来のトラブルを回避できます。一方、近い将来に売却予定がある場合は、売却時の手続きも含めて専門家と相談することが効率的です。
7. まとめ
未登記建物を相続した場合、所有権の証明困難や売却時のトラブル、相続人間の争いなど様々な問題が発生するリスクがあります。これらのトラブルを回避するためには、建物表題登記と相続登記を早期に完了させることが重要です。手続きが複雑な場合は、土地家屋調査士や司法書士などの専門家に相談し、適切な対応を取ることで将来的な問題を防ぐことができます。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を監修したのは…
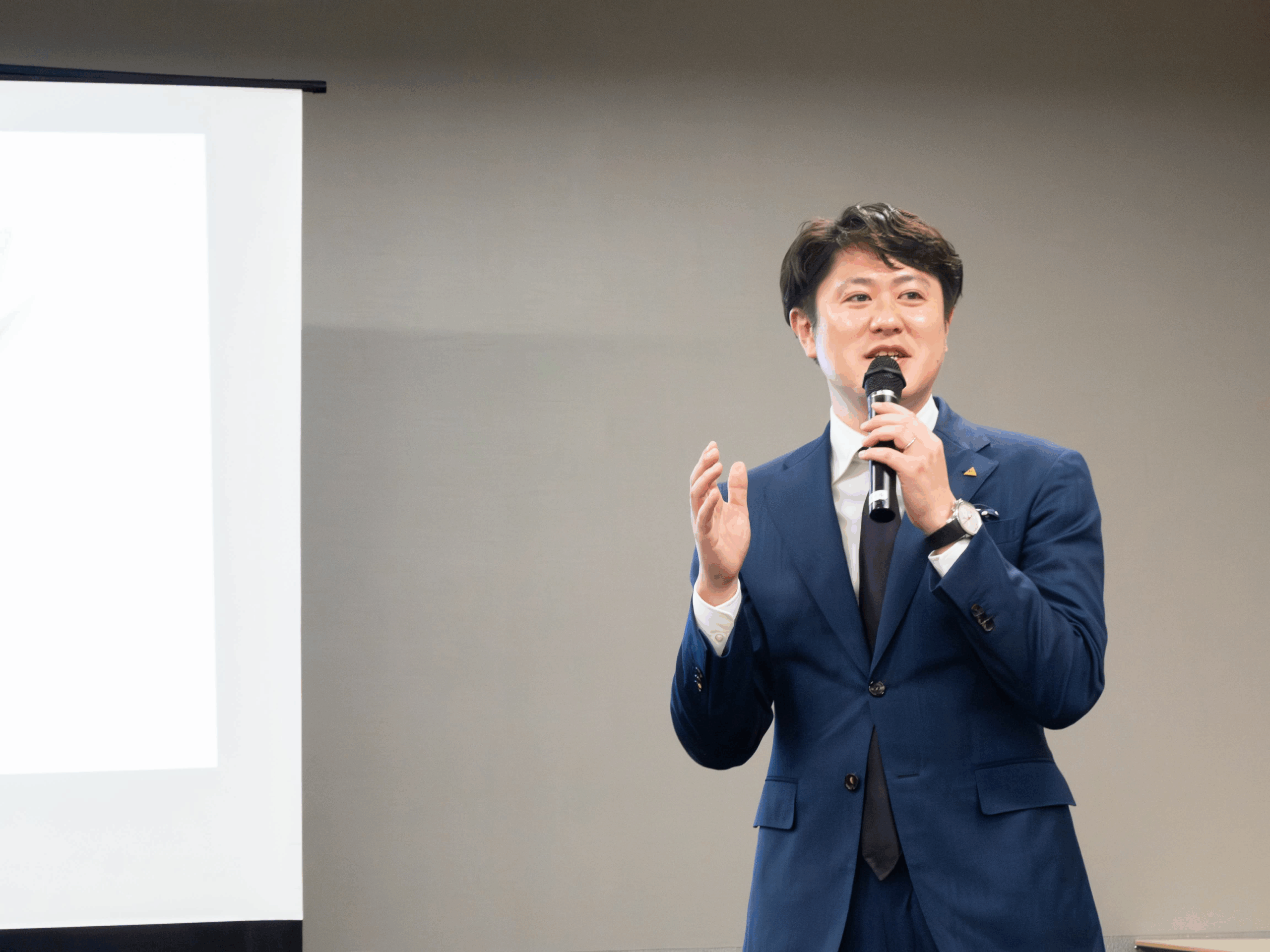
司法書士法人・行政書士あかりテラス代表、株式会社あかりテラス代表、 一般社団法人債務整理相談センター
宮村 和哉(みやむら かずや)
司法書士・行政書士宮村和哉は、相続手続きに精通した司法書士として、地域密着型のサービスを展開。相続トラブルにしないためには「事前準備」が大切であるとの想いで、情報発信を積極的に行っている。年間相談件数700件、終活セミナー年間80会場。熊本を拠点に、福岡などにも支店を構え、多くの相続相談に対応してきた実績を持つ。親しみやすい人柄と的確なアドバイスで信頼を集めている。
サイトURL:https://office-akariterrace.com/ https://www.instagram.com/akariterrace.hohoemi/








