遺留分を渡したくない場合の方法5選!遺留分額を減らす方法も解説!

Contents
遺留分とは?遺留分の計算方法や請求方法をご紹介!
そもそも遺留分とは何なのか、そして遺留分の計算方法や遺留分の請求方法について解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことを言います。これは、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることがありません。
遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は遺留分を算定するための財産の価額の3分の1(民法1042条1項1号)、それ以外の場合(直系卑属のみの場合、直系卑属と配偶者の場合、直系尊属と配偶者の場合、配偶者のみの場合)は同財産の価額の2分1(同条1項2号)となっています。
なお、同順位の相続人が複数いる場合は、遺留分は均等の割合になります(民法1042条2項)。
遺留分の計算方法
遺留分は、遺留分を算定するための財産の価額に、3分の1又は2分の1を掛け、この計算結果に、遺留分権利者の法定相続分を掛けて求めます(民法1042条)。
つまり、遺留分は以下の計算方法により算定します。
遺留分=(遺留分を算定するための財産の価額)×(3分の1又は2分の1)×(遺留分権利者の法定相続分)
例えば、妻と子の2人が相続人であれば、遺留分の具体的な割合は、以下のように計算します。
配偶者が4分の1((2分の1)×(法定相続分=2分の1))、子1人ずつが8分の1((2分の1)×(法定相続分=2分の1)÷2)
「遺留分を算定するための財産の価額」は、被相続人が相続開始時に有する価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を差し引いた額です(民法1043条1項)。
そして、相続人以外の第三者に対し相続開始前の1年間にされた贈与は、その価額が「遺留分を算定するための財産の価額」に加えられます(民法1044条1項)。
また、相続人に対し相続開始前の10年間にされた贈与は、その価額(婚姻もしくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限ります)が「遺留分を算定するための財産の価額」に加えられます(民法1044条3項)。
要するに、以下のような計算方法になります。
遺留分を算定するための財産の価額=(相続開始時における被相続人の積極財産(遺贈財産を含む)の額)+(相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内))+(第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内))-(被相続人の債務の額)
遺留分の請求方法
遺留分を請求する権利を「遺留分侵害額請求権」と言います。
遺留分権利者は、遺留分を侵害された場合、被相続人から遺贈や贈与を受けた者を相手方として、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます(民法1046条1項)。
特定財産承継遺言により財産を承継した相続人又は相続分の指定を受けた相続人も、遺留分侵害額請求の相手方となります(民法1046条1項。以下、遺留分侵害額請求の相手方となる者を「遺留分侵害者」と言います)。
遺留分侵害額請求権は、形成権ですので、遺留分権利者が遺留分侵害者に対して遺留分に関する権利を行使する旨、内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
遺留分侵害額は、以下の計算方法により算定します(民法1046条2項)。
遺留分侵害額=(遺留分)-(遺留分権利者の特別受益の額)-(遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額)+(遺留分権利者が相続によって負担する債務の額)
なお、上記の特別受益とは、遺贈、婚姻又は養子縁組のための贈与のほか、生計の資本としての贈与、つまり、居住用の不動産の贈与又はその取得のための金銭の贈与、営業資金の贈与、借地権の贈与など、生計の基礎として役立つような財産上の給付を言います(民法901条1項)。
どうしても相続させたくない相続人がいる場合、相続権を奪うことは可能?

どうしても相続させたくない相続人がいる場合、相続権を奪うことは可能なのでしょうか。
民法は、相続欠格(民法891条)及び相続廃除(民法892条、893条)という制度を設け、相続権を奪うことを認めています。
具体的な内容は、後述する通りです。
遺留分を渡したくない!相続人に遺留分を渡さなくていい方法とは?
被相続人に、遺留分を渡したくない相続人がいる場合、被相続人がその相続人に遺留分を渡さなくて済む方法はあるのでしょうか。
その方法としては、遺留分の放棄、遺留分を放棄してほしいとする遺言の付言事項、遺留分の剥奪、遺留分の消滅、事業承継における遺留分の算定に係る合意の5つが考えられます。詳しく見てみましょう。
遺留分の放棄
まず考えられるのが、被相続人が遺留分を渡したくない相続人にお願いして、遺留分を放棄してもらうという方法です。
民法は、遺留分の放棄が濫用されないように、「相続の開始前における遺留分の放棄」は家庭裁判所の許可を要するとしています(1049条1項)。あくまでもお願いですから、当該相続人がこれに応じない場合には、遺留分の権利は残ったままになります。
しかし、当該相続人が遺留分を放棄する代償として、被相続人から贈与を受けていた場合には、被相続人の生前に遺留分を放棄することが期待できるでしょう。
また、家庭裁判所の許可を受け遺留分の放棄が認められたとしても、遺留分の放棄は遺留分侵害額請求権を有しないというだけで、相続人の地位を失うわけではありませんので、相続することはできます。
相続させたくない場合には、被相続人が、遺留分を放棄した相続人以外の相続人に財産を相続させる遺言を残しておけば、遺留分を放棄した相続人に財産を与えないことは可能となります。
なお、相続開始後の遺留分の放棄や、遺留分侵害額請求権の放棄は自由であり、家庭裁判所の許可なしに可能です。
遺留分を放棄してほしいとする遺言の付言事項
被相続人に、遺留分を渡したくない相続人がいる場合には、遺言の付言事項で、その相続人に相続を放棄してほしい旨をお願いする方法です。
遺言の付言事項には法的効力がありませんので、あくまでも当該相続人の意思に任せることになります。その相続人がこれに応じなければ、遺留分は残ったままになります。
しかし、その相続人が遺留分を放棄する代償として被相続人から贈与を受けていた場合には、当該相続人が遺言の付言事項に従い、遺留分を放棄することもあり得るといえます。
遺留分の剥奪
民法は、相続欠格及び相続廃除という制度を設け、相続権の剥奪を認めています。相続権が剥奪されれば、当然遺留分も剥奪されます。
遺留分権利者であっても、欠格事由がある場合(民法891条)、推定相続人から廃除された場合(民法892条、893条)には、相続権も、そして遺留分や遺留分侵害額請求権も失うことになります。
まず、民法は相続人となることができない相続欠格について、以下の5つの欠格事由を定めています(891条)。
①故意に被相続人又は先順位・同順位の相続人を死亡に至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者(1号)
②被相続人が殺害されたことを知って告発せず、又は告訴しなかった者(2号)
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者(3号)
④詐欺又は強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者(4号)
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(5号)
その中でも、実務で実際に問題となるのは、⑤が多いとされています。
次に、民法は相続廃除について、推定相続人の廃除(892条)及び遺言による推定相続人の廃除(893条)の規定を設けています。
推定相続人の廃除の事由としては、推定相続人による被相続人への虐待、重大な侮辱、推定相続人にその他の著しい非行があった時の3種類が定められています。
被相続人は、生存中に推定相続人の廃除を家庭裁判所に申し立てることになります。廃除を認める家庭裁判所の審判が確定すれば、廃除対象者は相続権を失いますので、当然遺留分も認められません。
また、遺言による推定相続人の廃除の場合は、遺言の効力が生じた後に、遺言執行者が遅滞なくその廃除を家庭裁判所に申し立てなければなりません。遺言廃除の効果は、相続開始時にさかのぼって生じます(民法893条後段)。
ただし、相続欠格者及び相続廃除者の子は、いずれも代襲相続することができます(民法887条2項)。
以上からも、遺留分の剥奪はハードルが高いことが分かります。
遺留分の消滅
巣留分権利者が、遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示をしない時、遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年を経過した時に時効となり消滅します(民法1048条前段)。また、遺留分侵害額請求権は、相続開始時から10年が経過すれば消滅します(除斥期間・同条後段)。
以上の要件を満たせば遺留分は消滅しますが、期間の経過が必要ですので、これもハードルが高いといえます。
事業承継における遺留分の算定に係る合意
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」中の「遺留分に関する民法の特例」の規定においては、中小企業者のうち一定の要件を満たす「特例中小会社」、又は個人である中小企業者(以下「個人事業者」といいます)の後継者が、所要の手続きを経ることを前提として、以下の特例などの適用を受けることができる旨が定められています。
①特例中小会社の場合
❶後継者が特例中小会社の旧代表者からの贈与等により取得した自社株式や事業用資産について、遺留分を算定するための財産から除外する旨の合意をすることができます(除外合意)。
❷後継者が特例中小会社の旧代表者からの贈与等により取得した自社株式や事業用資産について、遺留分を算定するための財産に、算入する価額を合意時の価額に固定する旨の合意をすることができます(固定合意)。
②個人事業者の場合
後継者が旧個人事業者からの贈与等により取得した事業用資産について、遺留分を算定するための財産から除外する旨の合意をすることができます(除外合意)。
上記の手続きを利用するためには、特例中小会社の旧代表者又は旧個人事業者の推定相続人(兄弟姉妹及び甥・姪を除きます)及び後継者全員で合意書面を作成し、その合意をした日から1か月以内に、後継者が経済産業大臣に対して、合意についての確認の申請を行う必要があります。
後継者は、その確認を受けた日から1か月以内に、家庭裁判所に「遺留分の算定に係る合意の許可」の申立てをする必要があります。
家庭裁判所は、その合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ合意を許可することができません。許可の審判が確定すると、合意の効力が生じます。
以上のように、上記の合意をすることができれば、相続紛争や自社株式・事業用資産の分散を防ぎ、後継者にスムーズに事業を承継させることができます。
遺留分を請求されたら?請求に応じないことは可能?

遺留分を請求されたら、これに応じなければならないのでしょうか。また、遺留分が原因でどのようなトラブルが起きるのか、遺留分を巡るトラブルの回避方法(対策)はあるのかについても、見てみましょう。
遺留分を請求されたら?
遺留分は、遺留分権利者にとって、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分の確保が約束されたものです。従って、遺留分を有する相続人(民法1042条)が「遺留分権を行使する」意思は尊重されなければなりません。
遺留分を請求するということは、遺留分権利者が遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することを意味します。
遺留分権利者から上記の金銭の支払いを請求されたら、遺留分侵害者はその請求に応じなければなりません(民法1046条1項、1047条1項)。
遺留分の請求に応じないことは可能?
上述したように、遺留分の請求に応じなければなりません。
つまり、遺留分侵害者は遺留分の請求を拒否することはできないのです。
遺留分侵害者が遺留分侵害額の請求に応じない場合には、遺留分権利者はまず、調停前置主義により、家庭裁判所の遺留分侵害額請求調停(家事事件手続法244条、257条1項)を申し立てます。
調停でも解決することができない場合、遺留分権利者は、遺留分侵害を理由とする金銭給付請求の訴えを起こすことになります。
ところで、遺留分侵害額に相当する金銭給付の請求を受けた遺留分侵害者は、裁判所に対し、金銭債務の全部又は一部の支払いにつき相当の期限の許与の請求をすることができます(民法1047条5項)。これは、遺留分侵害者が金銭を直ちに準備することができない場合に、支払い期限の猶予を求めることができるとするものです。
さらに、遺留分権利者と遺留分侵害者が話し合った結果、円満な解決策を見いだし、遺留分侵害額請求を取り下げてもらうことは可能といえます。
遺留分が原因でどのようなトラブルが起きるのか
遺留分が原因のトラブルとしては、以下のような場合が考えられます。
①遺留分を放棄した相続人が、その代償として贈与を受けていたため、遺留分を侵害された他の遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受け、代償としての贈与を確保することができなくなる場合に、その請求を拒否してトラブルとなることが考えられます。
②相続開始後に、把握していない相続人(相続開始前に認知された婚外子)が現れたものの、既に遺言に基づき全ての遺産の分割が終了していたため、当該婚外子からの遺留分の請求を受けた場合に、どう対応するかでトラブルとなることが考えられます。
なお、民法910条は、相続が開始し遺産分割等が既に終了している場合について、相続開始後の認知(認知の訴え又は遺言認知)によって相続人となった者は、その相続分に応じた価額支払請求権を有するにすぎないとしています。
③被相続人は相続人と遺産の分け方について相談し、遺留分が侵害されることになる相続人も含め、相続人全員の同意を得て遺言書を作成した。ところが、被相続人が亡くなった後、遺留分侵害のあった相続人が気が変わったとして、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求をしたものの、請求された相続人にはその金銭を支払うだけの資金がない場合に、その支払いを巡ってトラブルとなることが考えられます。
遺留分を巡るトラブルの回避方法
遺留分を巡るトラブルを回避するためには、以下のような方法があります。
①上述した「❶遺留分の放棄、❷遺留分を放棄してほしいとする遺言の付言事項」は、遺留分を巡るトラブルを回避する方法となります。
②被相続人が自己を被保険者とし、相続人中の特定の者を生命保険金受取人と指定した場合、指定された者は固有の権利として生命保険金請求権を取得しますので、遺産分割の対象となりません。
そこで、多くの財産を相続して遺留分侵害額請求をされる者に、生命保険金を受け取れるようにしておけば、生命保険金額を遺留分の支払原資とできるため、遺留分を巡るトラブルを回避することができます。
③被相続人が遺留分権利者に対し、10年以内の生前贈与を含め少なくとも遺留分に相当する財産を残しておけば、遺留分を巡るトラブルを回避することができます。
遺留分額をゼロにはしないけれど減らしたい!遺留分額を減らす方法を解説!
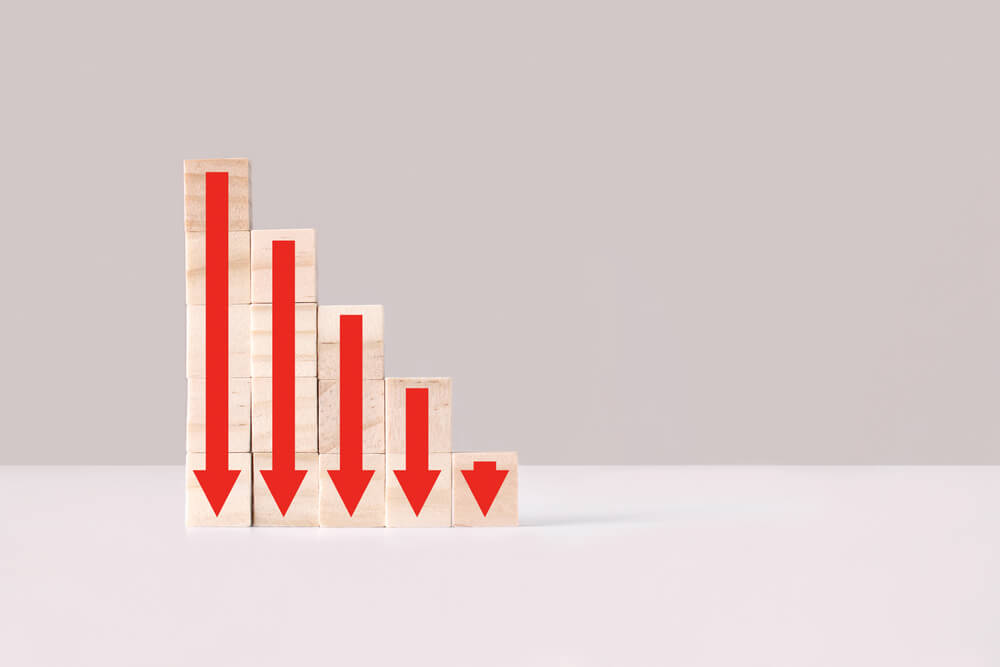
遺留分額をゼロにはしないけれど減らしたい場合の、遺留分額を減らす方法について解説します。
①上述したように、特定の相続人を生命保険金の受取人と指定した場合、指定された相続人は固有の権利として生命保険金請求権を取得するため、遺産分割の対象となりません。従って、被相続人は上記の生命保険に加入し保険料を支払うことによって、全体の遺留分額を減らすことができます。
ただし、生命保険金は原則として特別受益とはなりませんが、特別受益に準じて持戻しの対象となる場合もありますので注意が必要です(最高裁判所決定平成16.10.29民集58・7・1979)。
②養子縁組をすることにより相続人を増やせば、遺留分額を減らすことができます。
しかし、相続人が増えれば法定相続分の割合が低くなるため、遺産の分割などを巡り争いが起こらないとも限りません。
しかも、養子縁組の効力が争われることも危惧されます。ただ、推奨されるものではないでしょうが、遺留分額を減らすという観点からは、ひとつの方法とはいえます。
③マイナスの財産が増えれば、遺留分額を減らすことができます。
被相続人が、意図して遺留分額を減らすために銀行から借入れをしたり、住宅ローンや自動車ローンの契約をしたりすることはまず考えられないことです。しかし、必要なこととして、このようなマイナスの財産が増えれば、全体の遺産が減るため遺留分額が減ることにはなります。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください








