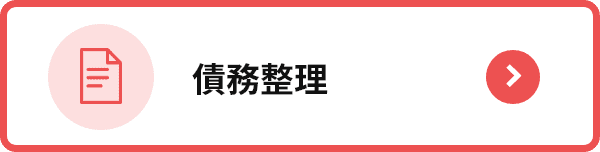相続財産とは?何が含まれるか、相続税の対象になるものはどれかを具体例で解説

相続財産とは
相続財産とは、被相続人が死亡時に所有していた財産や負債のことを指します。これらは相続人に引き継がれ、遺産分割や相続税の計算の基礎となります。
相続財産に含まれるもの
相続財産は、大きく分けてプラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)に分類されます。
プラスの相続財産(積極財産)
次のものは、積極財産に含まれます。
- 現金・預貯金:被相続人が所有していた現金や銀行口座の残高。
- 不動産:土地や建物などの不動産資産。
- 株式・投資信託:証券会社などで保有していた株式や投資信託。
- 貴金属・美術品:金や銀、宝石、絵画などの高価な動産。
- 自動車:被相続人名義の車両。
マイナスの相続財産(消極財産)
次のものは、消極財産に含まれます。
- 借金・ローン:住宅ローンやカードローンなどの未払い債務。
- 未払いの税金:所得税や住民税などの未納分。
- 保証債務:被相続人が第三者の借入れの連帯保証人となっている場合の債務。
相続財産に含まれないもの
すべての財産が相続の対象となるわけではありません。以下のものは相続財産に含まれません。
被相続人の一身専属権(民法896条)
被相続人個人に専属する権利や義務、例えば扶養請求権や身元保証人としての地位などは相続の対象外です。
生命保険金や死亡退職金(相続人が固有に取得する権利)
被相続人が契約者であった生命保険の死亡保険金や、勤務先から支給される死亡退職金は、受取人固有の権利として相続財産には含まれません。
祭祀に関する権利(民法897条)
墓地や仏壇、位牌などの祭祀財産は、慣習に従って承継され、相続財産には含まれません。
相続財産の種類と具体例
一口に相続財産といっても、その種類は多岐にわたります。以下に具体例を挙げて解説します。
プラスの相続財産の具体例
まずは、プラスの相続財産の具体例を見ていきましょう。不動産や預貯金をはじめ、株式などの有価証券なども含まれます。
不動産(土地・建物)
被相続人が所有していた自宅や賃貸物件、土地などが該当します。これらは固定資産税評価額や路線価などを基に評価されます。
現金・預貯金
銀行や信用金庫などの金融機関に預けられている預貯金や、自宅に保管されている現金が含まれます。
株式や投資信託などの金融資産
証券会社を通じて保有している株式、投資信託、国債などの金融商品が該当します。評価は相続開始日の時価で行われます。
事業の承継に関する財産
被相続人が個人事業主であった場合、その事業用資産や営業権なども相続財産となります。
借地権・借家権
被相続人が土地や建物を借りていた場合の賃借権も財産として評価され、相続の対象となります。
交通事故の損害賠償請求権
被相続人が生前に交通事故などで被害を受け、その損害に対して加害者へ請求できる損害賠償請求権は、相続財産に含まれます(民法896条)。これは、金銭的な補償を受ける権利として評価され、プラスの財産(積極財産)に分類されます。たとえば、入院費用・治療費・慰謝料などの請求が未了だった場合、相続人が引き継ぐことになります。
ただし、損害賠償請求権が死亡によって発生したものである場合(例:被相続人が事故で亡くなった場合)、その請求権が確定していれば相続財産に含まれ、遺産分割や相続税の対象になります。
マイナスの相続財産の具体例
次に、マイナスの相続財産の具体例を見ていきましょう。マイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討した方がよいかもしれません。
借金やローン
被相続人が生前に借り入れていた借金や住宅ローン、事業資金などの債務は、相続財産のうちマイナスの財産(消極財産)として相続人に引き継がれます。たとえ相続人が契約に直接関わっていなくても、相続によって債務も承継されます。借金の金額が大きい場合、相続放棄や限定承認を検討すべき重要な判断ポイントです。
未払いの税金
固定資産税や所得税など、被相続人が生前に支払うべきだった税金で未納のものがある場合、それも相続人に引き継がれます。納税義務は死亡によって消えるわけではないため、これらも相続財産の一部として扱われます。
保証人としての債務
被相続人が他人の借入れに対する連帯保証人になっていた場合、その保証債務も相続の対象です。実際に請求があるかどうかに関係なく、法的には相続時点で「債務」としてカウントされます。保証債務は把握しづらいため、相続財産の調査時には注意が必要です。
みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、被相続人の死亡を原因として相続人が取得する財産のうち、「法律上は相続によって得たものではないが、相続税の課税対象になるもの」を指します(相続税法第3条)。実際の相続財産ではないため遺産分割の対象にはなりませんが、税務上は課税対象となるため注意が必要です。
死亡保険金
生命保険金は、保険契約者(被相続人)が死亡したときに、受取人に支払われるものです。受取人固有の権利として取得するため、原則として相続財産には含まれませんが、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。ただし、法定相続人の人数に応じて非課税枠(500万円×法定相続人の数)が設けられています(相続税法12条1項5号)。
死亡退職金
被相続人が会社などに勤めていた場合、死亡後に支払われる退職金(死亡退職金)も、死亡を原因として支払われるため「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象です。これも保険金と同様に、非課税枠が設けられており、一定額までは相続税がかかりません(500万円×法定相続人の数)。
相続開始前3年以内の生前贈与財産
被相続人が死亡する3年以内に、相続人へ贈与していた財産は、相続税の計算上「相続財産に加算」されます(相続税法第19条)。これにより、本来は贈与税の対象であったものも、相続税の課税対象に組み込まれる仕組みとなっています。
相続時精算課税制度による贈与財産
相続時精算課税制度を適用して生前に贈与を受けた財産も、相続時に「すべて相続財産として課税対象」になります。この制度は、贈与時点で2,500万円まで非課税になるものの、相続時に精算課税として一括して計算されます。
相続財産の調査方法
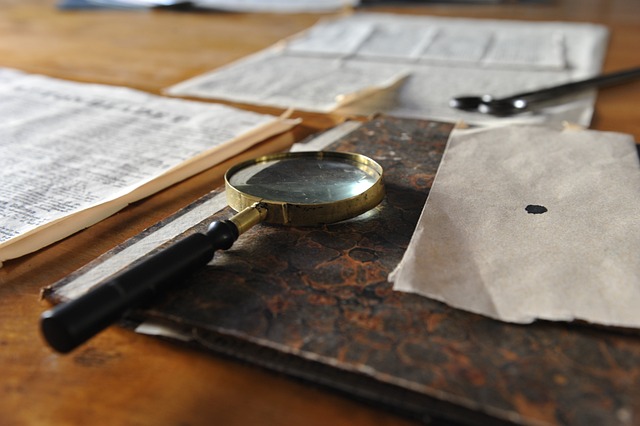
相続人が相続財産の内容を把握しないまま遺産分割や放棄を行うと、後に思わぬトラブルや税務リスクが生じることがあります。そのため、相続開始後は速やかに財産の調査を行うことが重要です。
財産の存否を調べる方法
以下に、具体的な財産ごとの調査の方法を解説します。調査が難しい場合には、専門家に依頼することをお勧めします。
不動産の調査(登記簿・固定資産税情報)
被相続人が所有していた土地や建物の有無を調べるには、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を法務局で取得します。登記簿では所有者・所在地・面積などが確認でき、遺産分割や相続登記に必要です。加えて、市区町村役場で固定資産税の課税明細を取得することで、評価額の把握も可能です。
預貯金の調査(金融機関の残高証明書)
被相続人名義の銀行口座については、金融機関に「残高証明書」を請求することで確認できます。必要書類として、被相続人の死亡が確認できる戸籍や、相続人であることを証明する戸籍謄本などが求められます。口座が多数ある場合は、通帳やキャッシュカード、郵送物などの手がかりをもとに網羅的に調査しましょう。
株式・投資信託の調査
証券口座に関しては、証券会社に連絡して「取引残高報告書」や「評価証明書」を取得します。近年はオンライン証券も多いため、郵便物やメールの履歴を確認することも有効です。また、上場株式の評価額は「相続開始日の終値」が基準となるため、相続税申告時にも影響します。
相続財産の評価方法
相続税の計算や遺産分割協議の際には、各財産を適正に評価する必要があります。不動産は「路線価」または「固定資産税評価額」、株式は「相続時の終値」などを用いて評価され、評価方法によって税額が変わる場合があります。評価が難しい場合は、税理士のサポートを受けることをおすすめします。
財産調査を弁護士に依頼するメリット
相続財産の調査に不安がある場合、弁護士に依頼することで、見落としなく確実に調査できます。弁護士は、家庭裁判所での相続放棄の手続き支援や、遺産分割協議の代理人も務められるため、相続人間のトラブルを未然に防ぐという意味でも重要です。また、専門家に依頼することで、法定相続分や遺言、遺留分とのバランスを見ながら適切な遺産分割が可能となります。
当サイト「円満相続ラボ」では、相続に関する基本知識やトラブル回避の方法をわかりやすくお伝えし、専門家によるサポートを提供しています。円満な相続を実現するための最適なご提案をいたします。
相続に関する疑問がある方には、相続診断士による無料相談窓口もご利用いただけます。どうぞお気軽にご相談ください。
相続税の対象となる財産
相続税は、被相続人から相続や遺贈によって取得した財産に課税される税金です(相続税法第1条)。ただし、すべての財産が対象となるわけではなく、課税対象となるもの・非課税のものに分かれています。
相続税がかかる財産
以下のような財産は、相続税の課税対象になります。それぞれについて詳しく解説します。
相続や遺贈によって取得した財産
相続や遺贈によって取得した財産は、相続税の課税対象です。
被相続人が亡くなった時点で所有していた土地・建物・預金・株式・事業資産などのプラスの財産や、相続人が承継する権利(借地権、損害賠償請求権など)、遺言書により取得した財産(遺贈)も含まれます。
相続開始前3年以内の贈与財産
被相続人が生前に相続人へ贈与した財産は、死亡前3年以内であれば「みなし相続財産」として相続税に加算されます(相続税法第19条)。
※2027年以降、加算期間は段階的に最大7年へ延長予定(2024年度税制改正)。
相続時精算課税制度による贈与財産
生前に2,500万円の非課税枠で贈与した財産でも、最終的に相続財産として合算され、相続税の対象となります。
家族名義の預金
被相続人が管理・運用していた預金が他人名義(配偶者・子など)であっても、実質的に本人の財産とみなされる場合には課税対象になります。
借地権
被相続人が借地権付きの土地を利用していた場合、その借地権(つまり土地を借りる権利)は財産的価値のある「権利」と見なされ、課税対象となります。
相続税がかからない財産
国税庁の定める「相続税法」や「相続税基本通達」において、相続税が課されない「非課税財産」が明確に定められています。
これらは、社会的・宗教的な観点や公益性を理由に、課税の対象から除かれているものであり、相続人にとっては非常に重要なポイントです。
ここでは、相続税がかからない主な財産について、それぞれの理由や注意点を交えながら詳しくご紹介します。
祭祀に関する財産(墓地、仏壇など)
墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚などの祭祀財産は、相続税法第12条に基づき、非課税とされています。これらは日本の宗教・慣習に根差したもので、財産的価値を有していたとしても、金銭的な評価をしないことが一般的です。
弔慰金・花輪代
被相続人が会社勤務だった場合、会社から遺族に対して支払われる弔慰金・花輪代・香典などは、一定額まで非課税です。
具体的には、以下のとおり非課税限度額が設けられています(相続税法基本通達3-19)
- 業務上の死亡の場合:死亡時の給与等の3年分相当額まで非課税
- 業務外の死亡の場合:給与等の半年分相当額まで非課税
上記を超える金額は課税対象になるため、弔慰金等の通知書には支払理由や計算根拠を明記してもらうのがおすすめです。
公益目的で寄付された財産
相続人の意思により、公益法人(学校法人、社会福祉法人、NPO法人など)や国・地方公共団体に公益目的で寄付された財産も非課税です(相続税法第12条第1項3号等)。
対象となる寄付には以下の要件があります。
- 相続開始後に、正式な手続きにより寄付されたものであること
- 寄付先が税法上の「特定の公益法人等」であること
- 寄付目的が公益性を有するものであること
非課税にするには、相続税の申告時に寄付証明書等の添付が必要です。
心身障害者共済制度に基づく給付金
地方自治体等が実施する「心身障害者扶養共済制度」に基づいて支払われる給付金(いわゆる障害者年金)も、被相続人の死亡をきっかけに支払われた場合、非課税財産として扱われます(相続税法施行令第1条の5)。
これは、障害を抱える家族の将来の生活を保障するための制度であり、相続税負担を避ける配慮がされています。
損害賠償金
被相続人が交通事故などで死亡し、加害者から支払われる損害賠償金(死亡慰謝料・逸失利益など)は、被相続人に属する遺産ではなく、相続人個人の固有財産とみなされます。
したがって、これらの損害賠償金は、相続税の課税対象から除外されます。
ただし、損害賠償金が支払われる前に被相続人が死亡していた場合、賠償請求権そのものが遺産となり、相続税の対象になるケースもあります。請求権か給付金かで取り扱いが変わるため、実務上の確認が必要です。
相続税の計算方法
相続財産が一定額を超える場合、相続税の申告と納付が必要になります。
ここでは、相続税の対象となる財産の金額(課税価格)を算出する流れから、最終的な相続税の額をどのように計算するのかまで、段階的にわかりやすく解説します。
各人の課税価格の算出
まず、相続人ごとに取得した財産の「課税価格」を求めます。これは、以下の計算式で算出されます。
課税価格=取得した財産の価額+みなし相続財産の価額-非課税財産の価額+相続時精算課税による贈与財産の価額-債務および葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産の価額
ここでいう「みなし相続財産」には、生命保険金や死亡退職金など、相続によって直接取得したわけではないが、実質的に相続に準じた財産が含まれます。
相続税の総額の計算
次に、すべての相続人の課税価格を合計し、「課税遺産総額」を求めます。
課税遺産総額=正味の遺産総額-基礎控除額
基礎控除額は以下の計算式で求められます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
この課税遺産総額を、民法に定められた法定相続分で分割したと仮定し、それぞれの取得額に応じて税率をかけて、仮の税額(算出税額)を出します。
税率は取得額に応じて10%~55%の累進課税となっており、金額が大きいほど税率も高くなります。
各人の相続税額の算出
実際の遺産分割に基づき、相続税の総額を各人の課税価格の割合に応じて按分します。
相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計=各人の税額(基礎額)
各人の納付税額の計算
最後に、控除の適用と2割加算を踏まえて、各人の最終的な納付税額を計算します。
主な加算・控除は以下のとおりです。
- 2割加算:配偶者・子・父母以外の相続人(例:兄弟姉妹や孫など)は、税額に20%加算されます。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が取得した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円までの部分は非課税。
- 未成年者控除:20歳までの年数×10万円
- 障害者控除:85歳までの年数×一定額(一般障害者は10万円、特別障害者は20万円)
- 相次相続控除:被相続人が10年以内に別の相続を受けた場合、その際に支払った相続税の一部を控除
- 贈与税額控除:過去に贈与税を支払っていた場合、その分を相続税から差し引くことができる
最終的な納付税額は以下のように計算されます。
各人の税額(+2割加算)-各種控除=納付すべき相続税額
遺産分割の方法
相続が発生すると、被相続人が遺した相続財産をどのように分けるかを相続人間で決める必要があります。これを「遺産分割」といいます。遺産分割の方法は、遺言の有無によって大きく異なります。
遺言書がある場合
被相続人が遺言書を残していた場合、その内容に従って遺産分割が行われます。遺言書は被相続人の最終意思を尊重するものであり、法定相続分よりも優先されます。遺言書には以下のような形式があります。
- 自筆証書遺言:本人が全文を手書きして作成する形式(※2020年から一部の財産目録はパソコン作成が可能に)
- 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成する形式
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま、公証人に存在だけを証明してもらう形式
ただし、内容に不備があったり、形式が法律に合致していない場合は無効となる可能性があるため、注意が必要です。
遺言書がない場合
遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産をどれだけ受け取るかを話し合いで決めます。協議の結果を「遺産分割協議書」として書面にまとめ、相続登記や銀行手続きなどに使用します。
遺産分割協議は、以下の要件を満たす必要があります。
- 相続人全員が参加すること
- すべての相続人の同意があること
- 署名・押印(実印)が必要で、印鑑証明書を添付すること
相続人が一人でも欠けていると協議は無効となり、再協議が必要になります。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議とは、被相続人が遺言書を残していない場合に、相続人全員で相続財産の分け方を話し合い、合意を形成する手続きです。協議が円滑に進むかどうかで、相続手続き全体のスピードや円満さが大きく左右されます。以下は、遺産分割協議の一般的な進め方です。
1.相続人の確定
まず行うべきは、法定相続人が誰であるかを正確に把握することです。被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を収集し、相続人の続柄や人数を確定します。
2.相続財産の把握・調査
次に、相続の対象となる財産を調査・把握します。不動産や預貯金、有価証券、借金など、プラス・マイナスを問わず全ての財産を一覧にまとめ、「財産目録」を作成しておくと便利です。
3.分割方法の協議
財産の内容と評価額が判明したら、各相続人が何をどの割合で受け取るかを話し合います。以下のような分割方法があります。
- 現物分割:実際の財産をそのまま分ける方法(例:不動産をAさん、預金をBさん)
- 換価分割:財産を売却して現金化し、金銭で分ける方法
- 代償分割:一人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法
遺留分(法定相続人に認められた最低限の取り分)にも配慮しながら、全員が納得する案を模索します。
4.遺産分割協議書の作成
協議がまとまったら、その内容を書面に残します。これが「遺産分割協議書」です。協議書には以下の要素を盛り込みます。
- 相続人全員の氏名・住所・実印押印
- 各相続人が取得する財産の内容
- 作成年月日
- 被相続人の氏名と死亡日
5.各種名義変更・申告手続き
協議書に基づいて、不動産の相続登記や銀行口座の名義変更、相続税の申告などを行います。相続税が発生する場合は、被相続人の死亡日から10か月以内に申告・納税が必要です(相続税法第27条)。
相続財産に関するQ&A
相続財産に関してよくある疑問や、実際の相続手続きで多くの方がつまずくポイントを、Q&A形式で詳しく解説します。
財産目録とは何か?作成は必須か?
財産目録とは、相続財産の全体像を一覧にまとめた書類です。相続税申告や遺産分割協議を円滑に進めるために、作成を強く推奨されますが、法律上は必須ではありません。
財産目録には、不動産・預貯金・有価証券・借金など、プラスの財産・マイナスの財産の両方を記載します。相続人全員が内容を共有することで、トラブルの防止にもつながります。
司法書士や税理士に依頼して作成してもらうことも可能です。
相続財産管理人(相続財産清算人)が必要となるケース
相続人が誰もいない、または全員が相続放棄をした場合など、遺産を管理・清算する人がいないときに、家庭裁判所が「相続財産管理人(または清算人)」を選任します(民法第951条)。
この人物が、被相続人の財産を調査・管理し、債務の清算や残余財産の処理を行います。必要に応じて利害関係人(例:債権者や知人)からの申立ても可能です。
相続財産の評価方法
相続税の申告を行う際、財産の価値を評価する必要があります。評価方法は、国税庁の「財産評価基本通達」に基づき、次のように定められています。
- 不動産:路線価方式または倍率方式(固定資産税評価額に倍率をかける)
- 預貯金:死亡日時点の残高
- 上場株式:相続開始日の終値、または前後数日間の平均値など
- 非上場株式・事業資産:財務内容や業種等に基づく特別な算定方法
評価に不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。
相続財産から葬儀費用を支払った場合の税務上の扱い
相続人が葬儀費用を負担した場合、その金額は相続税の課税価格から控除することが可能です(相続税法第14条)。ただし、控除できるのは以下のような費用に限られます。
- 通常の葬儀・通夜・火葬に関する費用
- 死亡通知・香典返しの費用
※一方、法要(四十九日など)や墓石購入費、仏壇代などは控除の対象外です。
亡くなった人の未支給年金は相続財産に含まれるか?
原則として、未支給年金は相続財産には含まれません。
遺族が「未支給年金請求書」を年金事務所に提出することで、死亡当月分までの年金を受け取ることができます(国民年金法第19条の2など)。この金額は「遺族固有の権利」であり、相続財産ではないため、相続税の課税対象にはなりません。
ただし、受け取る人の続柄や手続き期限(死亡から5年以内)などに注意が必要です。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を書いたのは…

弁護士・ライター
中澤 泉(なかざわ いずみ)
弁護士事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続といった幅広い分野の案件を担当した後、メーカーの法務部で企業法務の経験を積んでまいりました。
事務所勤務時にはウェブサイトの立ち上げにも従事し、現在は法律分野を中心にフリーランスのライター・編集者として活動しています。
法律をはじめ、記事執筆やコンテンツ制作のご依頼がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。