相続放棄受理証明書とは?必要なケースや申請方法、費用や注意点を解説
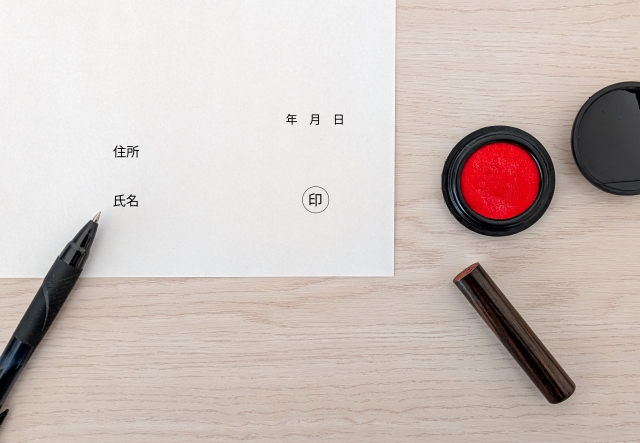
Contents
相続放棄申述受理証明書とは何か
相続放棄申述受理証明書とは、相続人が相続を放棄する旨の申述を家庭裁判所に提出し、それが正式に「受理」されたことを証明する書類です。被相続人の相続に関与しない意思を第三者に示すために必要となる場面があり、相続税、登記、債権者対応など幅広く使われます。
相続放棄が受理された事実を文書で「確認」できるこの証明書は、申述人本人または一定の利害関係者が申請により取得することができます。証明書は、裁判所から自動的に送られる「通知書」とは異なり、用途に応じて必要な部数を請求・取得する仕組みとなっています。
証明書の目的と法的効力
この証明書の最大の目的は、第三者に対して「相続放棄が法的に有効である」と証明することです。家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、裁判所の記録として保管されます。証明書を取得すれば、金融機関、不動産登記、債権者対応などにおいて、相続放棄の事実を公式に示すことが可能です。
なお、この証明書は単なる私的な文書ではなく、家庭裁判所が発行する正式な「証明書類」であり、登記申請や相続関係の紛争回避などにも役立ちます。
申述受理通知書との違い
「通知書」と「証明書」は似ていますが、取得方法や使い道が異なります。
家庭裁判所は、相続放棄の申述が受理されると、「申述受理通知書」を申述人に送付します。しかし、これはあくまで本人通知であり、他人に対して証明する効力は限定的です。一方、証明書は裁判所が交付する正式な証明文書であり、第三者に提出しても法的に通用する点で異なります。
通知書と証明書の取得対象者の違い
申述受理通知書は相続放棄をした本人にしか送付されませんが、証明書は第三者でも取得できる点がポイントです。
たとえば、放棄した相続人の兄弟姉妹や債権者などの利害関係人も、所定の申請書を提出すれば証明書を取得できます。これにより、相続放棄の事実を周囲の関係者にも明示できるようになります。
自動送付の有無と発行回数の違い
通知書は一度しか届かず再発行できませんが、証明書は申請するたびに交付を受けられます。
通知書は「通知」であり、家庭裁判所からの一方向的な送付となるため、再取得ができません。証明書は何度でも発行可能で、用途に応じて複数部取得することもできます。提出先ごとに必要になることがあるため、使い分けが重要です。
費用の有無と使い道の違い
通知書は無料で送付されますが、証明書は有料で、かつ第三者に提出する用途に使われます。
証明書の発行には、収入印紙による手数料が必要です。費用は全国共通で1通につき150円と定められており、裁判所の窓口や郵送での申請時に必要となります。
また、証明書は不動産の相続登記に添付したり、債権者に放棄の事実を説明したりする際に活用されます。通知書は本人確認程度の効力しか持たないため、第三者対応には証明書の取得が不可欠です。
相続放棄申述受理証明書が必要になる具体的な場面
証明書は、相続放棄の事実を第三者に説明する必要がある場合に使われます。以下のような具体的なケースでは、証明書の提出を求められることがあります。
相続債権者に対して相続放棄を証明する場合
被相続人に借金や未払金がある場合、債権者から請求を受けることがあります。そんなとき、相続人が放棄した事実を証明書で示すことで、責任を免れることが可能です。
債権者に対して相続放棄の証明書を提出することで、「自分には相続財産も債務も一切引き継いでいない」という立場を明確にできます。通知書では足りず、法的に効力ある証明書を求められるのが通常です。
不動産の名義変更(相続登記)を行う場合
相続人のうち一部が相続放棄をした場合、残された相続人で不動産登記の手続きを進める必要があります。このとき、放棄した人の証明書が必要になります。
たとえば、兄弟3人のうち1人が放棄した場合、残る2人で遺産分割協議を行いますが、法務局では「なぜ1人いないのか」を確認するために証明書の提出を求められます。
金融機関などで相続手続きをする場合
預貯金や保険金の払い戻し手続きを行う際も、相続放棄があった場合は証明書が必要です。
銀行や証券会社などでは、すべての相続人の関与を確認したうえで手続きを進めるため、放棄した人がいる場合は、その事実を公式に確認できる書類が求められます。通知書では不十分な場合が多く、証明書の提出が必須となることがあります。
次順位の相続人へ放棄の事実を伝える場合
相続放棄が行われると、次の順位の相続人に権利が移るため、その人たちに証明書を提示することがあります。
たとえば、子どもが相続放棄をすると、被相続人の親や兄弟姉妹が新たな相続人となります。その際、家庭裁判所が発行する証明書があれば、「すでに相続放棄が成立している」という事実を明確に伝えることができます。
証明書の取得方法と申請手続き

相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所に所定の申請書類を提出することで取得できます。申述人本人だけでなく、一定の利害関係を有する第三者も申請することが可能です。
申述人本人が申請するケース
申述人が自ら証明書を取得したい場合は、相続放棄の申述を行った家庭裁判所に申請書を提出することで入手できます。
申請の流れ
まず、相続放棄の申述を行った家庭裁判所の書記官室に「相続放棄申述受理証明書の申請書」を提出します。申請は窓口または郵送で行うことができ、収入印紙(1通につき150円)を貼付したうえで提出します。
郵送で申請する場合は、申請書・収入印紙・返信用封筒(切手貼付)・本人確認書類の写しが必要です。
必要な書類
申述人が申請する際の主な書類は次のとおりです。
- 相続放棄申述受理証明書の申請書(裁判所所定様式)
- 収入印紙(1通150円)
- 返信用封筒(郵送の場合)
- 本人確認書類の写し(運転免許証など)
相続人以外の利害関係人が申請するケース
債権者や次順位の相続人など、申述人以外でも利害関係があれば証明書の申請が可能です。
申請の流れ
申述人以外が申請する場合も、基本的な手順は同様ですが、相続放棄との「利害関係」を示す書類の添付が必要です。たとえば、債権者であれば債務に関する契約書や請求書の写しなどが該当します。
家庭裁判所は、申請内容に合理性があるかどうかを審査した上で、証明書を交付します。
必要な書類
利害関係人が申請する場合に必要な書類は以下の通りです。
- 相続放棄申述受理証明書の申請書
- 収入印紙(1通150円)
- 利害関係を示す書類(債権者であれば請求書、相続人であれば戸籍など)
- 返信用封筒(郵送の場合)
- 本人確認書類の写し
申請に関する重要な注意点
証明書の取得手続きにはいくつか注意点があります。申請前に確認しておくことで、不要な手戻りや時間のロスを防げます。
即日交付はできない
証明書は、原則として申請したその日に交付されるものではありません。
家庭裁判所では申請内容の確認や記録の照合を行うため、証明書の発行までに数日かかることがあります。特に郵送申請の場合は、書類のやり取りに時間がかかるため、余裕をもって手続きすることが大切です。
事件番号が不明だと手続きが進まない
相続放棄の申述時に付された「事件番号」が不明な場合、証明書の発行がスムーズに進まないことがあります。
事件番号は、相続放棄申述受理通知書に記載されています。通知書を紛失した場合は、氏名・被相続人・申述日などから家庭裁判所が記録を特定できることもありますが、時間がかかる可能性があるため、申述時の情報はなるべく正確に控えておきましょう。
証明書の交付は何度でも可能
相続放棄申述受理証明書は、必要な部数を何度でも申請して取得することができます。
不動産登記や金融機関への提出、相続人間の協議など、提出先が複数ある場合には、それぞれに応じた証明書を用意する必要があります。そのため、「1回しかもらえない」という誤解は禁物です。
裁判所の保存期間は30年
相続放棄の申述記録は、家庭裁判所で原則30年間保存されます。
したがって、相続放棄から年月が経っていても、保存期間内であれば証明書を取得することが可能です。ただし、家庭裁判所ごとに保存体制が異なるため、詳細は各裁判所に照会してください。
通知書を紛失した場合は申述の照会が必要
相続放棄申述受理通知書を紛失してしまった場合でも、証明書は取得できますが、事前に裁判所への照会が必要となることがあります。
本人確認や事件記録の検索に時間がかかる場合があるため、手続きに日数がかかる可能性を想定しておきましょう。申述時の正確な情報(申述日、裁判所名、被相続人名など)がわかると、対応がスムーズになります。
費用や再発行に関する情報
相続放棄申述受理証明書の取得には費用がかかります。また、必要に応じて何度でも再発行が可能です。手続きの負担やコストを把握しておきましょう。
証明書発行にかかる手数料
証明書の交付には、1通につき150円分の収入印紙を申請書に貼付する必要があります。
この金額は全国の家庭裁判所で統一されており、申請者が申述人本人であっても、利害関係人であっても同様です。なお、郵送申請の場合は、返信用封筒と切手も忘れずに準備してください。
申請書の様式は、裁判所の公式サイトからダウンロードするか、窓口で入手できます。
再発行は可能かとその手順
証明書は、必要に応じて何度でも再申請・再発行が可能です。
たとえば、不動産登記、銀行手続き、債権者対応など、提出先が複数ある場合や、誤って紛失してしまった場合でも、再度申請書を提出すれば発行してもらえます。
再発行の手順は初回の申請と同様で、特別な理由の記載や追加費用は不要です。ただし、同一家庭裁判所に限られる点、事件番号などの情報を正確に記載する必要がある点には注意してください。
専門家に相談すべきケースとそのメリット
相続放棄申述受理証明書の取得は、基本的には個人でも可能ですが、状況によっては弁護士や司法書士といった専門家に相談した方がスムーズに進む場合があります。
弁護士や司法書士のサポートが役立つ場面
手続きが煩雑な場合や、利害関係人として証明書を申請する場合は、専門家のサポートを受けることで安心して対応できます。
たとえば、相続関係が複雑なケース、債権者との対応が必要なケース、他の相続人との間にトラブルがある場合などは、弁護士のアドバイスによって、今後の紛争を未然に防ぐことができます。また、司法書士は不動産登記や戸籍調査に精通しており、登記申請とあわせて証明書取得を代行してもらえることもあります。
書類作成・申請ミスのリスクを減らすために
家庭裁判所の申請書類は、記載ミスや証明資料の不足によって差し戻しになることがあります。
とくに事件番号の記載や利害関係を証明する添付資料の内容が不十分な場合、証明書が交付されないこともあるため注意が必要です。専門家に相談することで、こうしたミスを未然に防ぎ、手続きを円滑に進めることができます。
「円満相続ラボ」では、相続に関する基本知識やトラブル回避の方法をわかりやすくお伝えし、専門家によるサポートを提供しています。円満な相続を実現するための最適なご提案をいたします。
相続に関する疑問がある方には、相続診断士による無料相談窓口もご利用いただけます。どうぞお気軽にご相談ください。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください








