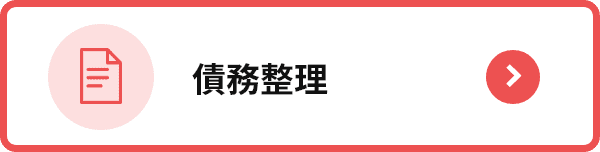相続登記の登録免許税について解説!計算や納付の方法、免税制度を紹介
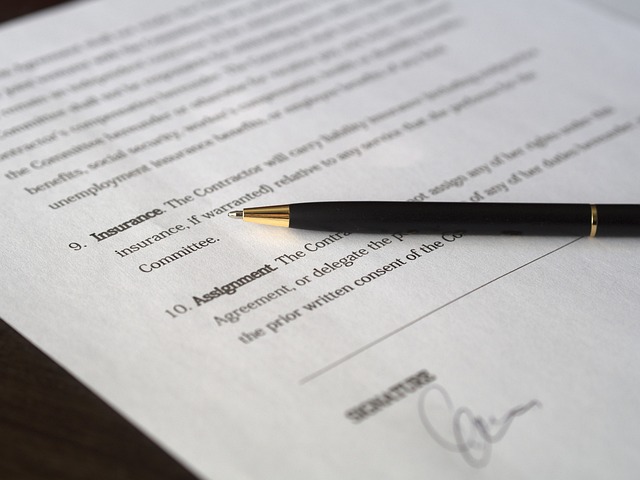
Contents
相続登記に伴う登録免許税の基礎知識
相続登記における登録免許税とは、不動産を相続した人が相続登記をする際にかけられる税金のことです。
土地や建物も、評価額に1,000分の4をかけて算出します。たとえば、相続登記の対象となる土地が評価額1,000万円である場合は、4万円の登録免許税がかかります。
詳細は、下記の記事にて解説しています。
「相続登記の登録免許税とは?納税・計算・免除の3つのポイントを解説!」
相続登記とは何か
相続登記とは、被相続人から相続人に不動産の名義を移すために必要な法的手続きです。
登記を行わなければ、不動産の売却や担保提供ができず、相続人間のトラブルにもつながりかねません。2024年4月からは相続登記の義務化が始まり、登記を怠った場合には、過料の対象となる可能性もあります
登録免許税の負担も考慮しながら、できるだけ早期に対応することが大切です。
必要書類の確認や登記内容の把握は、専門家への相談も視野に入れるとよいでしょう。
登録免許税とは
登録免許税とは、不動産の名義変更などの登記を行う際に課される国税の一つです。
相続による所有権移転登記の場合、課税標準額に対して税率0.4%(1,000分の4)を乗じて計算します。
この課税標準額は、不動産の固定資産税評価額をもとに算出され、1,000円未満は切り捨てです。
評価額の記載は市区町村が発行する評価証明書で確認でき、土地と建物で分けて記載されます。
課税対象となる手続きには、法定相続、遺言、遺産分割協議など多様なケースが含まれます。
課税されるタイミングと対象となる手続き
登録免許税は、登記の申請を行うタイミングで納付する必要がある税金です。
申請書を提出する際に、同時に税金の納付(収入印紙の貼付や電子納付)が求められます。納付が確認できないと、登記手続きが進まないため注意が必要です。
また、どのような手続きかによって課税の有無や税率が異なる点にも注意しましょう。
相続登記において登録免許税が課される代表的なケースは以下のとおりです。
- 法定相続分による相続登記
登記原因が「相続」となるため、通常どおり課税標準額(固定資産税評価額)×税率(0.4%)で登録免許税が発生します。 - 遺産分割協議による登記
協議により相続人の1人または数人が不動産を取得する場合でも、登記原因は「相続」のままであるため、税率は0.4%です。 - 遺言書に基づく登記(受遺者が相続人)
被相続人が相続人に対して不動産を遺贈する旨を定めた遺言による登記も、相続に準ずる扱いとなり、税率は0.4%です。 - 遺言書に基づく登記(受遺者が第三者)
相続人以外の第三者に不動産を遺贈する場合は、登記原因が「遺贈」となり、税率が2.0%に上がるため注意が必要です。 - 相続放棄をした場合の登記
相続放棄をしている人については登記上の権利変動が生じないため、登録免許税の課税対象にはなりません。 - 信託を利用した不動産の移転登記
信託による登記も別途登録免許税がかかる可能性があります。相続と併用する場合は、手続きごとに個別の税率が適用されるため注意しましょう。
このように、手続きの内容によって課税対象となる登記の種類や税率が変わるため、事前に自分のケースがどれに該当するのかを把握しておくことが大切です。
登録免許税の申請手続きと必要書類
相続登記の申請書に決まった形式はなく、必要事項が正しく記載されていれば問題ありません。法務省のホームページなどから雛形をダウンロードして使用するのもよいでしょう。
申請書に記載する基本情報
申請書には、登記の目的や原因、被相続人・相続人の情報などを正確に記載する必要があります。
登記の目的・原因
まずは登記の目的を記載します。被相続人が対象の不動産を単独で所有している場合と、誰かと共有している場合とで、記載する文言は異なります。
- 単独所有の場合:所有権移転
- 共有の場合:◯◯持分全部移転(◯◯の部分は被相続人の氏名を記載します)
登記原因には、相続を開始した日、つまり被相続人の死亡日を記載します。死亡後に取得した戸籍を確認し、そのとおりに記載します。死因が孤独死などで死亡日がはっきりしない場合も、戸籍の記載に従ってそのまま記載します。
被相続人・相続人の情報
被相続人の氏名を正式名で記載します。戸籍のとおりに記載するとよいでしょう。
不動産を相続する人の氏名、住所、日中連絡のつく連絡先も記載しましょう。複数存在する場合は、それぞれの持分も記載します。
申請に不備があった場合は、記載した連絡先に法務局から連絡が入ります。連絡のつきやすい番号を記載しましょう。
申請日・申請先・不動産の表示
実際に申請する日を記載します。郵送による申請の場合は、申請書類一式をポストに投函した日で問題ありません。
申請人の住所地ではなく、対象の不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。不動産が複数あり、たとえば◯◯市に土地2筆、△△市にも土地2筆あるといった場合には、◯◯市を管轄する法務局と△△市を管轄する法務局それぞれに申請する必要があります。
相続の対象となる不動産の情報も記載します。全部事項証明書を取得し、そのとおりに記載すれば問題ありません。
課税価格と登録免許税額
課税価格は、評価証明書に記載されている固定資産評価額をもとに記載します。そのままの金額ではなく、1,000円未満を切り捨てた金額です。
登録免許税については、免税措置の適用を受けて非課税にする際は、非課税となる根拠を登記申請書に記載する必要があります。
免税措置を受けるには、以下の文言を記入します。
- 租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税
- 租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
非課税となる根拠を記載しなければ、免税措置が適用されないことに注意が必要です。必ず記載するようにしましょう。
添付書類の違いによる分類
相続登記の際に添付する書類は、どういった方法で相続をするかによって異なります。
法定相続分による場合
法定相続分による場合は、以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍、住所を表すもの
- 相続人全員の戸籍、住所を表すもの
- 評価証明書
被相続人の最後の住所と登記簿記載の住所が異なる場合は、それぞれ証明できるものが必要です。戸籍の返却を希望する場合は、相続関係説明図を添付します。法定相続情報証明制度を利用し、法定相続情報一覧図の写しを添付することで、戸籍の添付を省略できます。
遺産分割協議による場合
遺産分割協議による場合は、以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍、住所を表すもの
- 相続人全員の戸籍、住所を表すもの
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 評価証明書
相続人全員の印鑑証明書は、被相続人の死亡日以降に取得されたものであれば、古いものでも問題ありません。
遺言書による場合
遺言書による場合は、以下の書類が必要です。
- 被相続人の死亡事項記載の戸籍
- 受遺者の戸籍
- 遺言書の正本または謄本
公正証書遺言以外で法務局で保管されていない場合は、家庭裁判所にて検認を受け、検認済みの証明文が付された遺言書でなければなりません。
また、遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者の印鑑証明書など、ケースによってほかの書類も必要です。
必要書類の取得にあたって
相続登記を行うには、各種書類の取得が必要です。
戸籍謄本や評価証明書など、自治体で発行される公的な書類が多く、入手には時間がかかることもあります。手続きをスムーズに進めるためにも、あらかじめ必要書類を確認し、計画的に準備することが重要です。
固定資産税評価額の確認方法
固定資産税評価額は、各市区町村の役所や出張所で発行される「固定資産評価証明書」に記載されています。この評価額をもとに、登録免許税の課税標準額を算出します。
評価証明書の請求には、不動産所在地や所有者情報が必要となるため、登記簿謄本(全部事項証明書)などを事前に確認しておくとよいでしょう。
評価額がない土地や共有不動産の扱い
一部の山林や私道などは、市区町村で評価額がつけられていない場合があります。
このような土地については、個別に法務局や自治体に確認し、課税対象かどうかを判断してもらう必要があります。
また、共有不動産については、各相続人の持分に応じて登録免許税を按分計算することになります。共有者間での協議が必要になる場合もあるため、注意が必要です。
登録免許税の計算方法
登録免許税の計算は、評価額と税率のかけ算で求められます。正確に計算するためには、評価額の確認と税率の理解が欠かせません。
登録免許税の算出ステップ
登録免許税の算出は以下の3ステップで行います。
- 固定資産税評価額の確認
- 1,000円未満を切り捨てて課税標準額を確定
- 税率0.4%(1,000分の4)を掛け算して税額を計算
免税措置の対象であれば、非課税の根拠条文を申請書に記載し、税額は「0円」となります。
課税標準額の導き方
課税標準額は、不動産の固定資産評価証明書に記載された金額をもとに決まります。
ただし、そのままの金額を使うのではなく、1,000円未満は切り捨てて記載します。
たとえば評価額が9,998,800円の場合、課税標準額は9,998,000円になります。
税率の適用と端数処理
相続登記の場合、税率は一律で0.4%です。課税標準額にこの税率を掛け、1円未満は切り捨てます。
たとえば課税標準額が9,998,000円であれば、税額は39,992円となります。
金額に誤りがあると申請が受理されない場合があるため、慎重に計算しましょう。
ケース別の登録免許税シミュレーション
登録免許税は、評価額に基づいて算出されるため、相続する不動産の種類や所有形態によって金額が異なります。
ここでは、よくある4つのパターンごとに、実際の計算例を交えて解説します。自分のケースに近いものを参考にして、相続登記に必要な費用を試算してみましょう。
土地のみを相続した場合
相続する不動産が土地だけである場合、評価額は固定資産税評価証明書の「土地」に記載されている金額を使用します。
たとえば、評価額が1,000万円の場合、登録免許税は以下のとおりです。
- 課税標準額:1,000万円(1,000円未満切り捨て不要)
- 税率:0.4%(1,000分の4)
- 登録免許税:1,000万円×0.004=4万円
土地だけの相続であっても、評価額が大きければ登録免許税の負担も大きくなります。
また、相続する土地が複数筆に分かれている場合は、それぞれの評価額を合算して課税標準額を計算します。
建物付き土地(戸建て)を相続した場合
建物付きの土地、いわゆる戸建て住宅を相続する場合は、「土地」と「建物」の評価額を分けて計算し、それぞれに登録免許税をかけます。
たとえば、土地の評価額が800万円、建物が400万円だったとします。この場合の登録免許税は以下のとおり。
- 土地:800万円×0.004=32,000円
- 建物:400万円×0.004=16,000円
- 合計:32,000円+16,000円=48,000円
このように、建物付き土地を相続すると、建物の分も課税対象となるため、単純な土地相続よりも登録免許税は高くなる傾向があります。
また、固定資産税評価額は土地より建物の方が劣化により年々下がる傾向があります。評価証明書の取得時期によっても若干変動するため注意が必要です。
マンション(敷地権付き区分所有)を相続した場合
マンションを相続する場合は、「建物部分」と「敷地権(共有の土地持分)」に分けて課税されます。
建物の評価額は専有部分(各部屋)の面積に基づき、敷地権はマンション全体の土地に対する持分割合によって決まります。
たとえば、専有部分の評価額が600万円、土地の持分に相当する評価額が200万円だった場合、
- 建物:600万円×0.004=24,000円
- 敷地権:200万円×0.004=8,000円
- 合計:32,000円
マンションの場合、登記簿に「敷地権の表示」があるため、登記の際にはその内容も正確に記載し、必要書類にも注意が必要です。区分所有法の適用を受けるため、特殊な登記形式になるケースもあります。
一部の土地のみを相続した場合
遺産分割や遺言によって、相続人のうちの1人が土地の一部のみを取得するケースもあります。このような場合は、その相続人が取得する持分に応じて、課税標準額も按分計算することになります。
たとえば、土地全体の評価額が1,200万円で、持分2分の1を相続した場合:
- 相続持分:1,200万円×1/2=600万円
- 登録免許税:600万円×0.004=24,000円
土地の一部を共有で相続する場合、複数の相続人がそれぞれの持分に応じて登記申請を行う必要があります。持分ごとに登録免許税が計算されるため、それぞれの負担額も異なります。
登録免許税が免除される特例と注意点

登録免許税には、一定の要件を満たせば免除される特例制度があります。
制度の対象となれば、通常数万円かかる税金が「0円」になることもあり、大きな節税効果が期待できます。
ただし、適用要件や申請書への記載方法を間違えると、免除が受けられないので注意が必要です。
免除対象となるケース
ここでは、具体的にどのようなケースで免除が認められるのか、代表的な3つのパターンを紹介します。
土地の評価額が100万円以下
当初は、市街化区域以外かつ評価額10万円以下の土地に限り免税措置の対象でした。
ところが、令和4年の税制改正により市街化区域内の土地も対象となり、評価額も10万円から100万円に引き上げられたことで、より多くの土地への適用が可能となりました。
100万円以下の土地というとまだまだかなり限られてしまう現状はありますが、該当する場合は免税措置が適用されます。
| 要件 | ・相続の対象が土地である ・土地の評価額が100万円以下である |
| 適用される場合 | 上記の要件を2つとも満たしている場合 |
| 免税を受ける方法 | 相続登記申請の際、申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載 |
| 税率 | 免税が受けられない場合は評価額の1,000分の4 |
| 適用期間 | 令和3年(2021年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで |
相続登記をせずに死亡した場合(数次相続)
相続により土地を取得した人が相続登記をせずに死亡し、さらに相続が発生した場合にも適用されます。
主なケースとして、数次相続が発生している場合などが該当します。この場合、最初に発生した相続にかかる登録免許税に対してのみ免税措置が適用され、そのあとに発生した相続については免税になりません。
| 要件 | ・相続人が相続によって土地を取得していること ・相続登記前に相続人が死亡していること ・死亡した相続人を名義とする登記であること |
| 適用される場合 | たとえば、以下のようなケースが該当します。 土地所有者が死亡し、その相続人である妻と子との間で遺産分割協議をする前に妻も死亡したケース |
| 免税を受ける方法 | 相続登記申請の際、申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載 |
| 税率 | 免税が受けられない場合は評価額の1,000分の4 |
| 適用期間 | 平成30年4月1日から令和9年3月31日まで |
上記の事例で、たとえば土地の評価額が1,000万円だった場合の登録免許税は以下のとおりです。
- 土地所有者から妻と子に2分の1ずつ所有権移転(相続)登記する
→土地の評価額1,000万円×0.4%=4万円 - 妻の持分2分の1を子に所有権移転(相続)登記する
→土地の評価額500万円(1,000万円の2分の1)×0.4%=2万円
本来であれば、一次相続の際にかかる登録免許税4万円と、二次相続の際にかかる登録免許税2万円を合わせて6万円がかかります。
しかし、免税措置が適用されることで一次相続の際の妻への登録免許税が免税され、子への移転持分のみに課税されるので、一次相続は2万円かかり、二次相続の登記である妻から子への移転の際に2万円かかります。
表題部所有者が死亡しており、相続人が保存登記を行う場合
土地の表題部所有者がすでに亡くなっており、その相続人が所有権保存登記をする場合も該当します。
登記簿(全部事項証明書)は、表題部と権利部の2段構造になっています。
現在であれば、表題登記のあと所有権保存登記に進むことが一般的であるため、長期にわたって権利部が未登記のままになることはあまりありません。しかし、中には表題部の登記のみで所有権保存登記がされていない土地も存在します。
表題部の所有者が死亡している場合、相続人名義での所有権保存登記が可能です。評価額が100万円以下であれば、その登記にかかる登録免許税に対して免税措置が適用されます。
| 要件 | ・相続の対象が土地である・土地の表題部が未登記で、表題部所有者がすでに亡くなっている・所有権保存登記を、表題部所有者の相続人名義でする・土地の評価額が100万円以下である |
| 適用される場合 | 上記の要件を4つとも満たしている場合 |
| 免税を受ける方法 | 相続登記申請の際、申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載 |
| 税率 | 免税が受けられない場合は評価額の1,000分の4 |
| 適用期間 | 平成30年11月15日から令和7年3月31日まで |
免税制度の適用条件と申請時の注意点
免税制度は非常にありがたい制度ですが、適用されるには細かな要件を満たす必要があります。
また、制度を正しく使うには、申請書への正確な記載や添付書類の準備など、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。
この章では、登録免許税の免除を受けるために必要な条件や、手続き時のポイントについて詳しく解説します。
記載すべき条項と書式上の留意点
具体的には以下のような文言を記載します。
- 「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
- 「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」
これらの文言がない場合、免税制度は適用されず、通常どおり登録免許税が課税されてしまいます。
文言は登記原因の欄や登録免許税額の備考欄に記載します。誤字脱字があると無効になることもあるため、慎重に記載しましょう。
また、申請書の様式は法務局の公式サイトから雛形をダウンロードすることができます。書式は原則自由ですが、不動産の表示や持分の記載など、必要な情報に漏れがないように気をつけましょう。
免税措置の実施期間と延期の背景
相続登記における登録免許税の免税期間は、平成30年4月1日から令和9年3月31日までです。
登録免許税の免税期間は、当初は令和3年3月31日までの予定でしたが、延長されています。
理由としては、免税措置の適用前と比べ、相続登記の申請件数や筆数が増加していることが挙げられます。相続登記を促すための方策として十分効果を上げているといえる結果であり、今後も引き続き必要な措置であるとの判断から、このように繰り返し延長されています。
免税手続きの注意事項
免税制度を活用するには、単に申請書に記載するだけでなく、必要書類の添付やケースに応じた申立てが求められる場合があります。
たとえば、数次相続での免税を受けるには、「相続関係を証明する戸籍一式」「相続関係説明図」などを添付する必要があります。
また、評価額の証明として、土地や建物の「固定資産評価証明書」は必須です。
さらに、各法務局によって実務上の運用に差異があるため、事前に法務局の窓口や電話で確認することをおすすめします。
少しでも不明点があれば、登記に詳しい司法書士や弁護士に相談することで、手続きをより確実に進められます。
登録免許税の納付方法と期限
登録免許税は、相続登記の申請時に必ず支払わなければならない国税です。納付のタイミングや方法を誤ると、申請が受け付けられなかったり、登記が遅れる可能性もあります。
ここでは、登録免許税の具体的な納付手段と、支払期限について詳しく解説します。
納付方法の種類
登録免許税の納付方法は、主に3種類あります。
それぞれの方法によって準備するものや注意点が異なるため、自分の手続きに合った方法を選ぶことが大切です。
収入印紙による納付
もっとも一般的なのが、法務局へ提出する申請書に収入印紙を貼って納付する方法です。収入印紙は、郵便局や法務局、コンビニなどで購入できます。
申請書の登録免許税額欄に記載した金額と、貼付する印紙の額が一致していなければ、登記が受理されない可能性もあります。
また、収入印紙には「割印(消印)」を押す必要があり、押し忘れると不備扱いとなります。
現金納付の流れ
一部の法務局では、現金で登録免許税を納めることも可能です。この場合は、法務局の窓口で納付書を記載し、現金を直接支払います。
ただし、すべての法務局が現金対応しているわけではないため、事前に管轄法務局へ問い合わせて確認しましょう。
現金納付の場合、領収書をもらえる点は安心ですが、郵送申請と組み合わせにくいデメリットもあります。
オンライン納付(電子申請)
近年では、インターネットによる電子申請とオンライン納付の利用が広がっています。
法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を通じて、Pay-easyやインターネットバンキングを利用して登録免許税を納付することが可能です。
利用には事前の登録と環境設定が必要ですが、自宅から手続きできるというメリットがあります。郵送や法務局訪問が難しい方にとっては、便利で効率的な選択肢といえるでしょう。
納付期限と遅延の影響
登録免許税は、登記申請と同時に納付が必要です。
たとえば、郵送で申請する場合は、ポストに投函したその日が申請日となり、同日付で納付が行われたものと扱われます。
そのため、収入印紙の貼り忘れや不足、オンライン納付の遅れなどがあると、申請が無効になったり、補正が必要となる場合があります。
納付が遅れれば、登記完了までの期間が長引くだけでなく、申請日が変更されることで、他の相続人や利害関係者とのトラブルに発展することもあります。
とくに相続登記の義務化以降は、「登記義務を怠った日」から過料が発生するリスクもあるため、納付期限は厳守する必要があります。
登録免許税以外にかかる相続登記の費用
登録免許税は相続登記の中核的な費用ですが、それ以外にもさまざまな支出が発生します。
たとえば、必要書類の取得費用や専門家(司法書士)への依頼費用など、見落としやすいコストも少なくありません。
ここでは、実際に登記手続きに必要となるその他の費用について具体的に解説します。
書類取得にかかる費用
相続登記では、戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書など、複数の公的書類が必要です。
これらはすべて役所で発行してもらう必要があり、取得には手数料がかかります。
たとえば、
- 戸籍謄本:1通450円程度
- 住民票:1通300円程度
- 評価証明書:1通400円前後(市区町村による)
また、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があるため、本籍地が複数ある場合や改製原戸籍が必要な場合は、1件あたり1,000円以上かかるケースも珍しくありません。
相続人が複数いる場合は、各人の分を集めるため、想定以上に費用がかさむ可能性があります。
専門家(司法書士)への依頼費用
書類の不備や手続きのミスを防ぐため、相続登記を司法書士に依頼する人も多くいます。
司法書士に登記申請を依頼した場合の費用は、不動産の数や評価額、書類の取得代行の有無などによって異なりますが、相場として5万円~10万円程度です。
また、登記する不動産が複数の法務局にまたがる場合や、相続人が海外在住などの特殊事情がある場合は、追加費用が発生することもあります。
初回相談が無料の司法書士事務所も多いため、費用感が不安な方は見積もりを依頼してから検討すると安心です。
また、司法書士事務所に相談する前に、相続登記について情報収集しておくことも大切です。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続に関する基本知識やトラブル回避の方法をわかりやすくお伝えし、専門家によるサポートを提供しています。円満な相続を実現するための最適なご提案をいたします。
相続に関する疑問がある方には、相続診断士による無料相談窓口もご利用いただけます。どうぞお気軽にご相談ください。
よくある質問と実務上の注意点
相続登記に関する疑問は多くの人が抱えるものです。ここでは、実務上よくある質問に対して、法律的な観点と実務的なアドバイスを交えてお答えします。
登記義務化や過料の話題も含め、手続き前に知っておくべきポイントをまとめました。
相続登記の義務化と対象となるケース
2024年4月から、相続登記が法律上の義務となりました。不動産を相続で取得した人は、「相続が発生したことを知った日から3年以内」に登記しなければなりません。
この義務は、「遺産分割協議がまとまっていない」「相続人が話し合い中」などの理由があっても免除されません。正当な理由なく義務に違反した場合は、最大で10万円の過料が科されるおそれがあります。
対象となるのは、「被相続人が亡くなったことを知ってから3年以内に、相続によって不動産を取得したすべての相続人」です。たとえば、長年放置されていた土地を名義変更せずにいた場合でも、今回の法改正により登記が求められます。
遺産分割が未了の場合でも登記すべきか
遺産分割協議がまだまとまっていない場合でも、相続登記を放置しておくのは危険です。2024年4月から相続登記は義務化されており、正当な理由なく登記をしないままでいると、最大10万円の過料が科される可能性があります。
そのため、協議が成立するのを待って登記を先延ばしにするよりも、まずは法定相続分に従って一時的に登記を済ませておくのが現実的な対応といえます。この方法なら、後から遺産分割協議がまとまった時点で「持分の変更登記」をすればよく、当初の法定登記を無駄にせず義務を果たせます。
また、どうしてもすぐに名義変更の登記ができない事情がある場合には、「相続人申告登記(相続人である旨の申出)」という制度の利用も検討できます。この制度は、自分が相続人であることを法務局に届け出ることで、登記義務を履行したとみなされるものです。申出の内容が登記簿に記載されるだけで所有権の名義変更にはなりませんが、申出を行うことで過料の対象にはならず、手続きも比較的簡便です。たとえば、必要な戸籍などの最低限の書類と申出書を提出することで済み、登録免許税もかかりません。
ただし、申出をしただけでは不動産の売却や担保設定などはできませんので、相続人の間で話し合いがまとまった段階で、正式な相続登記を改めて行う必要があります。
このように、登記の方法には複数の選択肢があり、状況に応じて使い分けることが重要です。登記をまったく行わない状態が続くと、相続人全体に不利益を及ぼすことにもなりかねません。過料のリスクを回避する意味でも、まずは何らかの形で登記の意思を示しておくことが、今後のトラブル防止につながります。
高齢者や手続き困難な場合の対応策
相続登記の義務化により、登記をしなければならない人の中には、高齢の方や体調不良などで手続きが難しい人も含まれます。しかし、本人の事情にかかわらず、義務は全ての相続人に等しく課されるため、「できないからやらない」では済まされないのが現状です。そこで重要になるのが、代理人の活用や専門家への依頼といった現実的な対応です。
たとえば、本人が外出困難な場合には、家族や信頼できる親族を代理人として登記を申請してもらうことが可能です。登記申請そのものは代理で行うことが認められており、委任状や必要な書類を整えれば、本人が法務局へ行く必要はありません。近年では、郵送や電子申請も広く利用されており、自宅にいながら手続きを進められる環境が整っています。
また、戸籍の収集や書類作成などに不安がある場合には、司法書士や弁護士に依頼するのが安心です。費用はかかりますが、登記に関する一連の手続きを一括で任せられるため、ミスなく確実に手続きを完了させることができます。とくに、相続人が複数いる場合や、土地・建物が複数の市区町村にまたがっている場合などは、専門家のサポートが強く推奨されます。
さらに、本人が認知症などで判断能力を欠いている場合には、「成年後見制度」の利用も検討されます。家庭裁判所に申し立てることで後見人が選任され、後見人が本人の代わりに登記手続きを行うことが可能です。ただし、後見制度の利用には時間がかかるため、早めに検討しておく必要があります。
このように、年齢や健康状態にかかわらず、相続登記を行う方法は必ずあります。無理をして自分だけで進めようとせず、家族や専門家の力を借りながら、期限内に手続きを済ませることが、法的にも実務的にも非常に大切です。
登録免許税の納付時期はいつか
登録免許税の納付時期については、原則として相続登記の申請と同時に支払う必要があります。
登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局に対して行うもので、申請書類に貼付する収入印紙によって納付するケースが一般的です。郵送での申請であっても、ポストに投函した日が申請日となり、その日に納付が行われたとみなされます。
したがって、収入印紙の貼り忘れや金額の誤りがあると、法務局から補正や差し戻しを求められる可能性があるため、事前のチェックが非常に重要です。
電子申請を利用する場合も同様に、申請時に納付手続きが必要です。インターネットバンキングやPay-easyを活用したオンライン納付であれば、登記申請と同時に納付が完了するため、よりスムーズに手続きを進めることができます。申請後に納付するのではなく、「申請と納付はセット」という原則を押さえておきましょう。
過料と免税制度、どちらが得か
最後に、多くの方が悩むポイントとして、「過料と登録免許税、どちらが負担が大きいか」という問題があります。相続登記の義務を怠った場合の過料は最大10万円とされています。
一方、登録免許税は不動産の評価額に税率0.4%をかけて計算されます。たとえば評価額が1,000万円の土地であれば、登録免許税は4万円となります。
このように比較すると、登録免許税の方が負担が軽いケースも多く、しかも過料は支払っても登記が完了するわけではないという点で、過料よりも先に正規の登録免許税を支払って登記を済ませた方が得策です。さらに、登録免許税には免除制度もありますが、過料には一切の軽減措置がない点も大きな違いです。
「どうせお金を払うなら、意味のある支出にしたい」と思う方が大半でしょう。そうであれば、期限内に登記を済ませて、安心して不動産を管理・活用できる状態にしておくことが、最も合理的な選択といえます。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を監修したのは…
司法書士
御法川 明(みのりかわ あきら)
平成20年司法書士試験合格