相続廃除を徹底解説!認められる要件や手続きの流れ、法的効果や注意点について
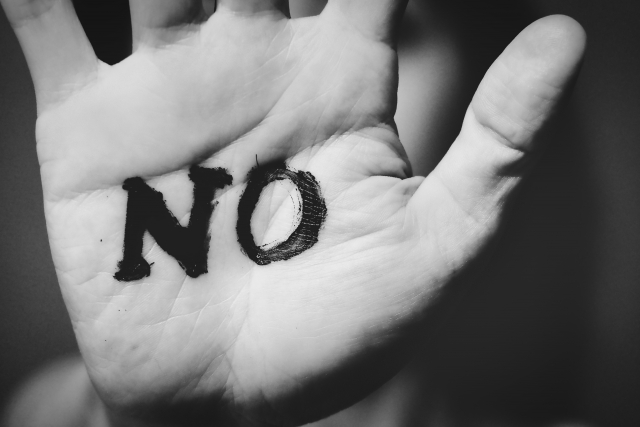
Contents
相続廃除とは何か?制度の基本を理解する
まずは、相続廃除の定義、制度の概要、遺留分との関係、誰が相続廃除を行えるかについて、説明します。
相続廃除とは:特定の相続人の相続権を無効にする制度
相続廃除は、家庭裁判所に申し立てを行う制度です。民法892条(推定相続人の廃除)で規定されており、相続「排除」ではない点に注意します。
民法では相続人を排除するという意図や考えはなく、審判により相続権を制限するという意味で「廃除」という別の漢字を当てています。
相続廃除においては申立人と被申立人に分かれます。申立人と被申立人では立場が異なり、相続廃除はどのように見えるのかを比較します。
申立人から見た相続廃除
申立人になれるのは、被相続人本人です。申立人から見た相続廃除とは推定相続人から相続権を剝奪することができる制度です。
冒頭でお伝えしたように、配偶者や子でありながら自分の財産を相続させたくないなどと思ったときに、家庭裁判所に配偶者や子などを推定相続人から廃除するように請求することができます。
ただし、100%被相続人の主張が認められるわけではなく、家庭裁判所が相当の理由があると判断した場合に、相続の廃除が認められることになります。
間違いのない申し立てを行い、希望する結果を得るためにも、申し立てる前に一度、専門家に相談されることを強くおすすめします。
被申立人から見た相続廃除
被申立人となりうるのは、推定相続人に限られます。被申立人から見た相続廃除とは、資産がある親・配偶者などから、いきなり相続権を取り上げられてしまう制度です。
実際には、家庭裁判所を通じて、推定相続人廃除について呼び出されたり、反論を求められたりしたあと、審判の結果を言い渡されます。
相続廃除制度の対象となる推定相続人と遺留分との関係
相続廃除制度の対象となる推定相続人についてですが、実はすべての推定相続人が対象ではありませんので、その点を詳しくお伝えします。
また、推定相続人の廃除の審判が確定したのち、遺留分がどのような取り扱いになるのかについても見ていきましょう。
相続廃除制度の対象となる推定相続人
推定相続人の廃除について定めた民法892条には「遺留分を有する推定相続人が…」と記されています。
条文から読み解くかぎり、相続開始後、遺留分を有する相続人が相続廃除制度の対象者ということになります。
遺留分とは、遺言の内容に関係なく、最低限度受け取ることができる法定相続分のことです。
例えば、配偶者と子が相続人となるケースでは、配偶者が全体の2分の1、子が残りの2分の1を法定相続(子が複数いる場合は均分)可能です。
ところが、遺言によって法定相続での遺産分割が認められないケースも起こりえます。その場合、それぞれ2分の1の半分の4分の1ずつ遺留分を主張できます。
遺留分は、すべての相続人に認められている権利ではなく、兄弟姉妹以外の相続人に認められています(民法1042条)。
つまり、遺留分を有する推定相続人とは、配偶者や子、孫・親(父母、祖父母)といった直系にあたる方が該当するのです。
そして、配偶者・直系であるにもかかわらず、被相続人に対して下記に掲げる行為をしたと家庭裁判所が判断した場合は、相続権を奪われることになります。
- 虐待
- 重大な侮辱
- 著しい非行
相続廃除された推定相続人と遺留分の関係
家庭裁判所から推定相続人の廃除の審判が下り、確定すると、推定相続人から廃除されてしまうことになります。
そして、廃除された推定相続人は、すべての相続権を失います。相続権の中には、遺留分権も含まれますので遺留分放棄や遺留分侵害額の請求調停、遺留分減殺による物件返還請求調停の当事者になることもできません。
相続廃除できるのは被相続人に限られる理由
相続廃除申立権者を、被相続人のみとしているのには、3つの理由が考えられます。
まず、被相続人の意思を尊重するためです。次に被相続人の資産をめぐり、相続人が自己利益の最大化や不当に利益を得ようと画策しないようにするためです。
相続はしばしば「争族」と表現されるように、相続をめぐり、相続人どうしが揉め、仲違いすることも少なくありません。
相続人同士による申し立てが可能になると、被相続人の意思とは無関係に相続人が廃除されてしまうだけではなく、係争にも発展しかねないため、申し立てができる人を被相続人に限定しているといえます。
そして、憲法で保障されている財産権を守るためです。憲法29条には「財産権は、これを侵してはならない」と定めており、何人も被相続人の財産について、その権利を侵すことはできないのです。
相続廃除の成立条件と認められる具体的な要件
被相続人が、家庭裁判所に推定相続人の廃除を申し立てたとき、100%その主張が認められるわけではありません。
本章では、相続廃除が認められる事由、実際に相続廃除が認められた判例とその背景、相続廃除が認められなかった判例とその理由についてもご紹介していきます。
相続廃除が認められる主な理由
推定相続人の廃除について定めた民法892条では、
- 被相続人への虐待行為があった場合
- 被相続人に対して重大な侮辱を加えた場合
- その他、著しい非行に該当する行動をとった場合
に家庭裁判所に請求できると規定しています。各項、詳しく解説します。
被相続人への虐待行為があった場合
家庭裁判所が、推定相続人による被相続人への虐待があったと認定すると、推定相続人は相続権を奪われます。
一般的に被相続人=高齢の親、相続人=子というケースが相続では多く見られるため、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律で定義されている「虐待」について見ていきます。
同法2条4項では、以下を虐待行為としています。
一 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為
イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
二 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
推定相続人が、被相続人に対し上記に掲げる行為をしていた場合は、相続廃除の審判が確定する可能性が高くなるでしょう。
被相続人に対して重大な侮辱を加えた場合
侮辱とは、あなどり、はずかしめることで、相手のことを軽視し、相手の気持ちを考えない言動や態度をとることです。
ただし、被相続人が単に侮辱された事実を示しただけでは、家庭裁判所が推定相続人を廃除するに至る判断を下すのは困難といえます。
相続廃除が認められるには「重大な」侮辱があったことを示す必要があります。
具体的には、侮辱されたことによって被相続人が「多大な精神的苦痛を強いられた」「被相続人の名誉を著しく傷つけられた」と家庭裁判所が判断するような内容であることが求められるのです。
その他、著しい非行に該当する行動をとった場合
虐待、重大な侮辱には当たらないものの、その他の著しい非行があった場合も、相続廃除の審判が下ります。非行とは、道義に外れた行い・反社会的行為・違法行為・不正行為を指します。
具体的には、下記のような行為が著しい非行と判断されるでしょう。
- 同居や連絡を望んでいたが長期に渡り音信不通となっている
- 何度も警察に逮捕され刑務所を出たり入ったりを繰り返している
虐待や重大な侮辱、著しい非行があり、それによって被相続人と相続人の信頼関係が断絶し、家庭が崩壊するような深刻な影響があったことが必要です。
相続廃除が認められた判例とその背景
高等裁判所が「重大な侮辱があった」と判断し、廃除を認めた事例を見ていきます。
企業の会長職だった被相続人である夫と妻の抗告により、幼い頃から非行を繰り返し、暴力団関係者との婚姻に至った二女の相続の廃除が認められた判例が過去にあります。
家庭裁判所は当初、二女が非行に走った点については被相続人にも責任があるとし、故郷に帰り運転手として勤務している元暴力団関係者となった夫と結婚生活を送ることも、相続関係の維持が社会的に酷なものとは認められず、廃除理由にはあたらないとしていました。
その審判を受け、被相続人は抗告を行うのですが、同時期に二女夫婦は夫の父と結婚に反対する被相続人の名を連ね、結婚披露宴の招待状を被相続人の知人らにも送付したのです。
抗告審において、その事実が加えられ、高等裁判所は被相続人らに多大な精神的苦痛と、名誉棄損があったのは明白で、親子関係も修復困難な状況にあり相続廃除に至る理由があるとして、第一審で認めないとした原審判を取り消しました。
判例:東京高等裁判所 平成4年12月11日決定
相続廃除が認められなかった判例と理由
ここでは、高等裁判所が「廃除事由にはあたらない」と判断した事例を取り上げます。
嫁姑問題に端を発し、被相続人の長男が推定相続人から遺言廃除されたのを受け、抗告した結果、第一審で認めた相続廃除を覆した判例です。
嫁・姑が不仲で口論が絶えず、お互いの悪口を言う、お互いに嫌がらせをすることが日常的となっていました。被相続人や長男も、そのいさかいに巻き込まれ口論に発展し、お互いに不信感や嫌悪感を抱く状況になったと認定しました。
たとえ被相続人・推定相続人間で、乱暴な振る舞いや侮辱ともとれる言動があったとしても、それは常態化していた感情的な対立及び口論の延長線上で起きたものであり、長男によって一方的に行われたものではなく、長男だけに責任を負わせるのは不当としたのです。
また裁判所は、同居は被相続人から依願されたもので、長男が改築費用を負担し、家業も手伝い、長年、同居を解消することなく家族関係を維持する努力をしてきたと認め、相続的共同関係が破壊された状態とはいえないと判断し、廃除の理由にはあたらないとしました。
判例:東京高等裁判所 平成8年9月2日決定
ここまで2つの判例を見てきましたが共通していえることは、裁判所が被相続人の主観的な感情に基づく審理を行い、推定相続人の廃除を認めることはないということです。
被相続人・推定相続人間で虐待、重大な侮辱、著しい非行があったとしても、そこに至る経過や原因、一過性のものかどうか、被相続人の落ち度、推定相続人の日頃の行い、人間関係も含め、総合的に判断されることになります。
相続廃除の2つの実施方法と手続きの流れ
相続廃除には、以下2つの方法があります。
- 生前廃除
- 遺言廃除
ここでは、それぞれの概要や手順、その影響についても解説します。
生前廃除とは:被相続人が生前に申立てる方法
生前廃除は、被相続人が生きているうちに、特定の相続人に「遺産を相続させない」と家庭裁判所の審判を通じて、意思表示することです。
以下、必要書類・審判・役所への手続きについて見ていきます。
必要書類と申立ての準備
推定相続人の廃除の申し立ては、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。生前廃除における必要書類は、次のとおりです。
- 審判申立書
- 申立人(被相続人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 廃除を求める推定相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 収入印紙(推定相続人1名につき800円)
- 切手(500円×4枚、80円×10枚、20円×4枚、10円×10枚など 裁判所による)
参考:名古屋家庭裁判所:申立添付書類等一覧表(家事受付センター)
審判申立書は、裁判所ホームページからダウンロードできるものもありますが、推定相続人の廃除に関する審判申立書は公開されていませんので、住所地を管轄する家庭裁判所に直接問い合わせ、指示を仰ぎます。
家事審判に詳しい弁護士に依頼すると、審判申立書の作成から、戸籍謄本の取得代行(職務上請求)もしてもらえる場合があります。推定相続人を廃除すべき理由の説明、証明方法についても精通しているでしょう。
戸籍謄本は、本籍のある市区町村役場にて取得しますが、遠方にあるといった理由で申し立て前に入手できない場合は、申し立て後に追加提出すれば足ります。
郵送請求のほか、オンライン請求が可能な自治体もありますので、詳細は自治体のホームページをご確認ください。
家庭裁判所での審理と判断
家庭裁判所にて申し立てが受理されると、推定相続人を廃除すべきかの審理が始まります。
申立書や証憑(証拠)を精査するほか、必要に応じて申立人(被相続人)・被申立人(推定相続人)を家庭裁判所まで呼び出し、話を聞きます(審問)。
推定相続人を廃除する相当の理由があると判断した場合、家庭裁判所は審判を確定させます。審判確定を証する書類として、家庭裁判所は「審判書」「確定証明書」を交付するのです。
市区町村役場への届出の手順
審判が確定したのち、審判確定の日から10日以内に、申立人が、廃除した推定相続人の本籍地もしくは届出人の住所地である市区町村役場に出向き、以下の書類を提出します。
- 推定相続人廃除届書
- 「審判書」の謄本および「確定証明書」(家庭裁判所から交付を受けたもの)
遺言廃除とは:遺言書で相続廃除を行う方法
遺言廃除は文字通り、被相続人が生前、遺言書に特定の相続人を廃除する旨を明記し、相続人から遺留分権を含むすべての相続権を取り上げる方法です。
本項では、遺言書に明記すべき内容と注意点と遺言執行者による家庭裁判所への申立てについて解説します。
遺言書に明記すべき内容と注意点
遺言廃除時にも、生前廃除時の審判申立書と同様に、遺言書には明確に廃除すべき相続人、廃除する旨、廃除する理由を記すようにしてください。
自分が相続人から廃除したいと思う配偶者や子などから受けた虐待、重大な侮辱、著しい非行について具体的かつ詳細に明記します。
生前廃除と同様に、遺言書にしたためたからといって、必ずしも相続人から廃除する審判を家庭裁判所が下すわけではありませんので、遺言や相続廃除に詳しい弁護士や相続診断士に相談して、遺言書を作成したほうが安心です。
なお、遺言書は自筆証書遺言ではなく公正証書遺言にすることも大切です。法律に詳しくない素人が作成した自筆証書遺言は、主に以下の理由で無効となりえるからです。
- 直筆ではない
- 作成日が明記されていない
- 署名・押印がない
- いかようにも解釈できる文章(「相続させない」など内容が不明瞭なもの)
- 夫婦連名で署名・押印した共同遺言書(民法に禁止規定あり)
また、自宅に遺言書を保管すると、相続人が見つけて人知れず破棄・処分したり、引っ越しや生前整理の際に紛失・誤って破棄したりしてしまうこともありえます。
さらに死後、相続人が遺言書の存在に気がつかないまま、遺産分割協議を行い、被相続人の意思が反映されないまま、相続が進む可能性もあります。
現在、自筆証書遺言書の原本は法務局または地方法務局にある遺言書保管所に預けることができ、関係相続人もしくは指定者に通知もしてくれます。
一方で、公正証書遺言の原本の保管場所は公証役場となりますが、公証役場には、相続人に対し遺言書がある旨の通知を行う義務はありません。
なお、遺言執行者を選定しておくと、遺言執行者は遺言書の存在を必ず相続人らに知らせてくれます。
遺言書保管所に預けない、遺言執行者を定めない場合は、信頼できる相続人がいれば「遺言書を作った」「自分の死後、問い合わせてほしい」と公証役場・弁護士事務所・円満相続ラボなどの連絡先を渡しておくといいでしょう。
大切なのは、廃除すべき相続人とその理由を明確に示し「廃除する」とはっきり記すことです。
また、遺言書の存在を信頼できる相続人に知らせておく、そして遺言執行者を指名しておくことで、被相続人の意思である廃除手続きが進むこととなります。
遺言執行者による家庭裁判所への申立て
家庭裁判所への申立ての流れは基本、生前廃除と同じと考えて問題ありません。
ただし、必要書類が若干異なり、被相続人が申立人になることができず、家庭裁判所の審判の結果を見届けることができないという違いがあります。遺言執行者が被相続人に代わり相続開始地を管轄する家庭裁判所に申し立て、以下の必要書類を提出します。
- 審判申立書
- 遺言者の死亡が記載された戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
- 廃除を求める推定相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 遺言書の写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
- 遺言執行者選任の審判書謄本(家庭裁判所の審判により選任された遺言執行者が申し立てる場合)
- 収入印紙(推定相続人1名につき800円)
- 切手(500円×4枚、80円×10枚、20円×4枚、10円×10枚 裁判所による)
参考:名古屋家庭裁判所:申立添付書類等一覧表(家事受付センター)
審判後の届出
相続人の廃除の審判が確定したら、審判確定の日から10日以内に、申立人が、廃除した推定相続人の本籍地もしくは届出人の住所地である市区町村役場に出向き、以下の書類を提出します。
- 推定相続人廃除届書
- 「審判書」の謄本及び「確定証明書」(家庭裁判所から交付を受けたもの)
そして、届出が受理されたのち、生前廃除・遺言廃除ともに廃除された人の戸籍謄本には「推定相続人廃除」と記載されます。
相続廃除がもたらす法的効果と影響

相続廃除の審判が確定したのち、被相続人、廃除となった者にどのような法的効果や影響があるのかについて、整理していきます。
廃除された相続人が失う権利と戸籍への記載
被相続人が家庭裁判所に推定相続人の廃除を申し立て、審判が確定した場合、相続権はもちろん遺留分権も失い、以降、推定相続人・相続人ではなくなります。
市区町村役場に届け出たあとは、廃除された人の戸籍謄本には「推定相続人廃除」と記載されます。そのため担当者が戸籍謄本を見れば誰でも相続権がないことがわかりますので、法務局や銀行などでの相続手続きももちろん、拒否されるでしょう。
遺留分請求ができなくなる理由
通常、被相続人が推定相続人に自分の財産を相続させたくないのであれば、遺言をしたためて、推定相続人の取り分をゼロと記せば事足りるように思えます。
しかし、遺言書で「取り分をゼロにする」と明記していても、実は遺留分の権利は生きており当然、遺留分を有する配偶者や子などは遺言上の取り分がなくても、遺留分侵害額を請求したり、遺留分減殺による物件の返還を請求することで、財産を相続できてしまうのです。
例えば、配偶者と子で相続する場合はそれぞれ資産全体の4分の1にまで遺留分権が及ぶなど、1円たりとも相続させたくないと考える被相続人の意思に反する結果となるでしょう。
相続廃除制度は、そういった事態が起こるのを阻止し、被相続人の意思を尊重して推定相続人の遺留分権までもを奪う点に、その存在意義があるといえるのです。
廃除された相続人の子が代襲相続するケース
推定相続人が死亡したとき、その方が有していた(まだ開始していない)相続権は、その子に引き継がれることになります。つまり推定相続人に子がいれば、権利がそのまま移ることになり、これを代襲相続といいます。配偶者や直系尊属は代襲相続人になれません。
推定相続人が廃除されたときも同様で、その方は相続権を失いますが、その子が権利を引き継ぎます。推定相続人に子がいなければ、他の推定相続人の取り分が増えることになりますが、子がいれば、他の推定相続人の取り分が変わることはありません。
相続廃除の対象となるのは、遺留分を有する推定相続人であることから、代襲相続した子にも当然、遺留分権が引き継がれます。
ただし推定相続人の子についても被相続人に対し、虐待や重大な侮辱を行っていた事実があり、著しい非行も見られるなら、廃除の申し立てができます。
相続廃除に関する留意事項
ここまで、相続廃除について理解が深まったところで、被相続人の方に改めて留意しておいたほうがよい事柄について、お伝えしていきます。
相続廃除はいつでも取消し可能
断腸の思いで相続権を剥奪したあと、対象者が深く後悔し、反省して心を入れ替えることもあります。対象者が改心した姿を見て、心を痛める被相続人もいることでしょう。
一度、推定相続人を廃除したものの、被相続人の意思によって、いつでも家庭裁判所に申し立てて廃除を取り消し、対象者の相続権を回復させてあげることが可能です(民法894条)。
相続廃除を取り消すことで生じる効果
被相続人の申し立てにより廃除の取消しが決定した対象者は、推定相続人の廃除がなされた時点まで遡り、推定相続人の地位と権利を取り戻すことができます(民法894条2項及び893条の準用)。
相続廃除を取り消すことで生じるリスク
- 虐待・重大な侮辱・著しい非行の再開
- 家庭裁判所への生前廃除の再申し立て
- 廃除が認められない
- 廃除の取消しをしたことを後悔する
相続廃除を取り消すことで、上記4つのリスクが、生じえます。特に対象者からの虐待などに苦しんだ方は、相続廃除を取り消すことで、同様の事態を繰り返すことがないか、慎重に検討すべきです。
「そうなったときには、また推定相続人の廃除を申し立てればいい」と考えるかもしれませんが、専門家への問い合わせ・相談料など、裁判所に申し立てる時間と費用が再度、必要となります。
なによりも、廃除を取り消したあとの推定相続人の言動について、家庭裁判所が再び廃除事由に当たると判断してくれる保証もありません。
こういったリスクを考慮しながら、廃除を取り消すかどうかを決めていただきたいです。
相続廃除した対象者に遺贈することが可能
実は被相続人は、相続権を奪った相手に遺贈することが可能です。国税庁は遺贈について、次のとおり説明しています。
遺贈とは、被相続人の遺言によってその財産を移転することをいいます
引用元:国税庁 相続税のあらまし
被相続人が生きているうちに対象者の相続権を回復させてあげることにはなりませんが、法的に相続廃除対象者への遺贈を妨げる条文は、どこにもありません。
遺贈というかたちで相続させるためには、有効な遺言を用意する必要があり、遺言や相続に詳しい弁護士や専門家に相談・依頼されるといいです。
相続廃除した対象者への遺贈にかかる相続税
相続税制度では2割加算されるケースがあるのですが、相続廃除対象者への遺贈は、2割加算の対象外です。なお、2割加算される対象者は次のとおりです。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます
推定相続人の廃除を受けると遺留分権・相続権は剝奪されますが、一親等の血族であることや配偶者であることには変わりがないため、2割加算対象者からは除外されるのです。
そのため、廃除の取消しの代替手段として遺贈を選択するのも悪くなく、どちらがいいかで悩んだ場合は、弁護士に相談するといいのかもしれません。
相続廃除を検討する際の弁護士活用のすすめ
相続廃除は被相続人の意思を尊重する制度ですが、家庭裁判所が100%その主張を認め、推定相続人の廃除の審判を確定させるわけではありません。
生前廃除を選択し、申し立てを行った結果、被相続人と推定相続人の関係性にさらなる亀裂が入り、修復不可能な状態になることも想定しておく必要があります。
推定相続人を確実に廃除できるか、生前廃除と遺言廃除どちらがいいか、推定相続人の廃除が有効となる遺言を作成するにはどうすればよいかなどとお悩みなら、弁護士の資格も併せ持つ相続診断士に相談することをおすすめします。
円満相続ラボでは、相続・終活の専門家である相続診断士に無料で相談できるほか、司法書士、税理士とも提携していますので、不動産登記や相続税についてのお悩みも、解決可能です。
まずは、お気軽に電話・メールでお問い合わせください。
相続廃除と似た制度との比較
相続廃除に近い制度としては「相続欠格」があります。ここでは、相続欠格と相続廃除の違い、相続廃除以外に推定相続人から相続権を奪う方法があるかについても、お伝えします。
相続欠格と相続廃除の相違点
相続欠格とは、民法で相続人となることができないと定めている相続人の欠格事由のことです。被相続人の意思と家庭裁判所の審判により決まる相続廃除とは異なり、被相続人の意思とは関係なく欠格事由に当てはまれば100%相続権を剥奪されます。
相続人の欠格事由として、民法891条には次の5つが定められています。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続廃除以外に推定相続人から相続権を奪う方法
廃除を検討するに至った推定相続人が配偶者の場合は離婚、養子・養親であれば離縁という方法もあります。
被相続人は、離婚・離縁手続きと同時並行で、推定相続人の廃除の申し立てを行うことも可能です。
相続廃除に関するよくある質問
最後に、円満相続ラボに寄せられる相続廃除に関するよくある質問を7つ、ご紹介いたします。
配偶者によるDVを理由とする相続廃除は認められる?
はい。被相続人がDV(ドメスティック・バイオレンス)によってケガをした、PTSDを発症した事実をもって、家庭裁判所は廃除の事由があると判断し、相続廃除を認める可能性は高いでしょう。
家族による介護放棄で相続廃除は認められる?
はい。被相続人が要介護状態にあるにもかかわらず、食事を与えない、風呂に入れない、同居人による虐待を放置したことなどが明らかであれば、家庭裁判所は廃除の事由があると判断し、相続廃除を認める可能性は高いでしょう。
認知症の被相続人による相続廃除の申し立ては可能?
はい。被相続人が、たとえ認知症であったとしても、申し立ては可能です。
また、被後見人など法律行為を制限されている方も、法定代理人を立てることなく本人が出向き、家庭裁判所へ申し立てを行うことが可能です。
申し立てから廃除の審判が確定するまでの期間は?
申し立て時における家庭裁判所の事件取扱件数(混み具合)や、申し立ての内容、推定相続人による反論の有無などで大きく異なります。
比較的スムーズに進んだ場合で数カ月、相手方から反論があり、争う姿勢が見られた場合は1年以上かかることも大いにありえます。
相続廃除はどの程度の確率で認められている?
令和5年司法統計年報3家事編によると既済222件中、認容されたのは52件、却下されたのは90件、取り下げに至ったのは72件となっています。相続廃除及び取消しが認められている割合は、わずか23%です。
戸籍への記載はどのように行われる?
推定相続人の廃除の審判が確定したのち、確定の日から10日以内に申立人(被相続人もしくは遺言執行人)が、市区町村役場に届出を行います。
届出が受理されると、推定相続人から廃除された方の戸籍の「身分事項」の欄に「推定相続人の廃除」と記されます。
代襲相続はどのような場面で発生する?
廃除が認められた推定相続人に子がいる場合に、発生します。廃除を原因とする代襲相続では、推定相続人の子に相続権・遺留分権が移ることになります。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を監修したのは…

さくら共同法律事務所 弁護士・弁理士
野崎 智裕(のざき あきひろ)
京都大学文学部人文学科行動・環境文化学系社会学専修卒業後、京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻を経て
平成30年9月 司法試験合格
ミツカン創業家裁判やカルテル巡る関西電力株主訴訟などを担当。顧客の本来利益を追求する姿勢が顧客からの信頼を得ている。








