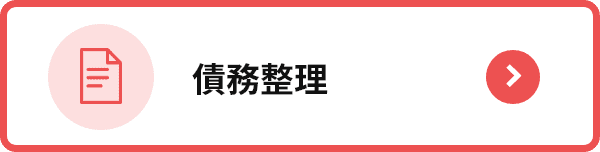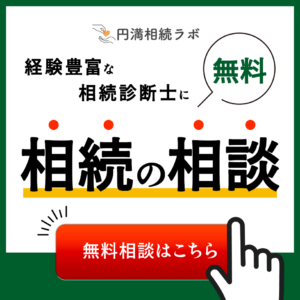小規模宅地の特例とは?同居していない場合でも適用される条件や、家なき子特例との使い分け

Contents
小規模宅地等の特例と家なき子特例の概要
ここでは、小規模宅地等の特例と家なき子特例の概要、適用要件などについてくわしく解説します。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方が住んでいた土地や事業用・賃貸用の土地を相続する際、一定の条件を満たすことで相続税の評価額が大幅に引き下げられる制度です。
この特例は、故人の配偶者であれば条件なく利用できますが、子どもなどの親族の場合は、故人と同居していることが主な条件となります。
家なき子特例とは?
親族が故人と同居していなくても、小規模宅地等の特例を利用できる場合があります。この例外的な措置は「家なき子特例」として知られており、特定の条件を満たせば適用が可能です。
それぞれの特例が適用される理由
「小規模宅地等の特例」は、亡くなった人の自宅を相続した家族が、生活の拠点を失わないようにするために作られた制度です。この特例により、自宅として使われていた土地の相続税が大幅に軽減されます。家族が安心してその家に住み続けられることを目的としています。
一方、「家なき子の特例」は、持ち家を持たない人を支援し、実家を受け継ぐことを奨励するための制度です。また、仕事や介護などの事情で親と別居していた人でも、特例を利用できるようになっています。この特例は、やむを得ない事情で家を離れていた人への配慮として設けられています。
家なき子特例の適用要件
家なき子特例を利用できれば、親族は小規模宅地等の特例と同じく、相続税の課税評価額の80%を減額できます。しかし、事業・賃貸用の土地には家なき子特例が利用できず、居住用の宅地のみが対象です。
被相続人に配偶者や同居親族がいないこと
「家なき子の特例」を利用するには、亡くなった人に配偶者や同居していた親族がいないことが条件となります。
まず、「配偶者がいない」とは、亡くなった人が独身だった場合や、結婚していても先に配偶者が亡くなっていた場合を指します。夫婦のどちらかが亡くなった後の相続は「二次相続」と呼ばれます。このような場合で、さらに亡くなった人が同居していた親族もおらず一人暮らしだった場合には、他の条件を満たせば「家なき子の特例」を適用することができます。
相続開始前3年以内に持ち家に住んでいないこと
相続する人が過去3年以内に自分の持ち家に住んでいないことも条件のひとつです。たとえば、賃貸アパートやマンションに住んでいる場合が該当します。
さらに、相続する人だけでなく、その配偶者も持ち家がないことが必要です。たとえば、夫名義の家に住んでいる妻が、自分の親の相続で「家なき子の特例」を利用することはできません。この特例は、完全に持ち家がない人を対象にしています。
相続開始時に住んでいる家を過去に所有していないこと
この要件は、意図的に「持ち家がない」状態を作り出すことを防ぐために設けられています。たとえば、過去に自分が所有していた家を名義変更して親族や関係会社に移し、その家に賃貸契約で住み続けるといった行為がこれに該当します。
改正前は、こうした家を売却し名義を変えた場合でも、売却から3年以上経過していれば特例を利用することができました。しかし、相続税を減らす目的で名義を操作するケースが増えたため、このような行為を制限するルールが追加されました。この要件により、過去に所有していた家に住んでいる場合は特例が使えなくなります。
相続した宅地を相続税申告期限まで保有すること
「家なき子の特例」を利用するには、相続した土地を、相続開始から申告期限である10カ月間、売却せずに保有していることが条件となります。
この特例は、相続した土地や家に住み続ける人を支援するために作られた制度です。そのため、特例を利用して相続税を減らしたあとにすぐ売却するのは、制度の趣旨に合いません。土地を売却する予定がある場合、この条件に違反しないよう注意が必要です。
申告手続きを行うこと
小規模宅地等の特例や家なき子特例を利用するには、相続税の申告が必須です。対象となる条件を満たしていても、申告をしなければ税金の軽減を受けられません。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった翌日から10カ月以内です。たとえば、1月1日に亡くなった場合、申告期限は11月1日となります。ただし、期限日が土日祝日の場合は、次の平日が期限です。
期限を過ぎたり、財産を少なく申告したりすると、加算税や延滞税が発生します。正確に申告し、適切な金額を納めることが重要です。
申告書は、被相続人が住んでいた地域を管轄する税務署に提出します。納税は税務署だけでなく、銀行などの金融機関でも行えますので、事前に手続きを確認しましょう。
2018年の税制改正後の要件変更点
2018年の改正前は次の3要件を満たす必要がありました。
- 故人に配偶者や同居の親族はいない
- 宅地を相続した親族が、その3年前までに自己または自己の配偶者の持家に住んだ経験がない
- 相続した宅地は相続税の申告期限(被相続人が死亡を知った日の翌日から10カ月以内)まで保有している
改正後の要件として、新たに次の条件が追加されました。
まず、「被相続人が亡くなる前の3年間に、相続人が3親等以内の親族や特別な関係がある法人が所有する家に住んでいないこと」。さらに、「相続人が現在住んでいる家を、過去に自分自身で所有していたことがないこと」も条件となっています。
改正の背景と目的
家なき子特例は、相続税を減らす方法として広く活用されるようになり、特に宅地を引き継いだ相続人に利用されるケースが目立つようになりました。これを受けて、2018年には特例の適用条件がより厳しく改正されています。
同居が条件とされない家なき子特例は、大幅な節税が可能なことから、相続税の負担を軽減したい人々に注目されてきました。しかし、その背景には特例を利用した不適切な節税の方法が多く見られました。
たとえば、相続人が自分の持ち家を購入後に孫の名義へ変更し、意図的に自分に持ち家がない状態を作り出す方法がありました。このようにして家なき子特例を適用させ、相続税を軽減するケースが報告されています。
さらに、持ち家を第三者に売却したものの、自分はその家に住み続け、名義上は賃貸物件として扱うことで所有者でない状態を装う方法も見られました。このような作為的な手法は税負担の公平性を損なうとされ、政府は対策として家なき子特例の条件を厳しくする改正に踏み切りました。
三親等内親族や特定法人の持ち家への居住制限
家なき子特例の適用条件が厳しくなり、新たに以下の要件が加えられました。「相続人が過去3年間、自分または配偶者が所有する持ち家に住んだ経験がないこと」に加えて、「相続人の3親等以内の親族が所有する家」や「相続人と特別な関係がある法人の所有する家」にも住んでいないことが求められるようになりました。
この改正により、たとえば親名義の家や子供の名義に変更した家に住んでいた場合でも、特例の対象にはならなくなります。
さらに、「相続開始時に住んでいる家を過去に一度も所有したことがないこと」という新しい条件も追加されました。このため、以前に所有していた家を一度売却し、その後賃料を払って住み続けるなど、意図的に持ち家がない状態を作る手法も適用対象外となります。
適用要件の厳格化と経過措置
「家なき子の特例」は、2018年4月1日の税制改正で適用要件が厳しくなりました。一部の人が要件を無理に整えて特例を利用し、相続税を大幅に減額するケースがあったためです。
たとえば、相続する人やその配偶者が持ち家を持たないという条件を満たすため、持ち家の名義を親族の経営する会社や孫に移す行為が行われていました。このように、実際には持ち家があるのに名義変更で条件を満たす行為は特例の趣旨から外れており、租税回避として問題視されました。その結果、これらを防ぐために適用要件が見直されました。
改正に伴い、経過措置も設けられています。2018年3月31日までに改正前の条件を満たしていた人は、2020年3月31日までに発生した相続について、改正前の特例を適用することが可能です。この措置は、突然のルール変更による影響を緩和する目的で実施されました。
相続の発生時期は予測できませんが、改正前の条件を満たしていた方は、相続が発生した時期を確認し、特例を利用できるか確認してください。
持ち家の購入手続き中に相続した場合の特例適用の考え方
家なき子特例の要件は厳格化されましたが、適用されれば、相続人にとって有効な節税措置となります。具体例をあげながら、家なき子特例の利用の可否を解説していきましょう。
家なき子特例が認められるケース
持家の購入は前から決まっていたが、結果的に相続人の死亡後の購入となった(相続開始時から申告期限までに持家を購入した)ケースです。
- 被相続人A:配偶者が既に死亡し以後一人暮らし、2022年10月1日に死亡。
- 相続人B:2000年6月に独立し、以来ずっと賃貸物件に居住。2021年に持家購入を決意、2022年11月1日に購入。
このケースでは、相続人のマイホームの購入は相続開始の1年前から計画されていたものの、Aが亡くなってから持家を購入しています。相続開始前の3年間に持家へ住んだ経験がないと判断されるため、家なき子特例を受けられます。
また、以下のようなケースでも家なき子特例が認められます。
被相続人から宅地を相続したが、そこを賃貸物件で活用したいケースです。
- 被相続人A:配偶者が既に死亡し以後一人暮らし、2022年10月1日に死亡。
- 相続人B:相続した土地をその後も所有し続け、賃貸物件に活用したいと考えている。
この場合は、相続人Bがずっと相続した宅地の所有を希望しており、相続税の申告期限(被相続人が死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)まで保有すれば、家なき子特例が認められます。
もちろん宅地を売却してしまうと、相続人Bの所有でなくなるので特例対象外となります。しかし、所有中に賃貸物件として利益を得る行為や、リフォームを行っても所有権の移転にはあたりません。
要件では必ず宅地の上に住まなければいけないということ、賃貸の禁止も要求されていないので、特例の利用は可能です。
家なき子特例が認められないケース
相続人が所有していた別荘を他人に貸し、自分は賃貸物件に住んでいたケースです。
- 被相続人A:配偶者が既に死亡し以後一人暮らし、2022年10月1日に死亡。
- 相続人B:2010年8月2日に別荘を購入、相続開始の3年前から他人へ別荘を貸し出し、自分は賃貸物件に住む。
こちらでは、相続人Bが収益物件である別荘を相続開始の3年前から貸し出し、所有している物件に相続開始前の3年間住んでいないので、本特例が受けられるように思われます。
しかし、次のような経緯で賃貸契約を結ぶ場合が想定されます。たとえば相続人Bが3年前から被相続人Aの入院・容体悪化を把握しており、死期が近いことを予測、友人や知人に相続税を軽減したいので借りてもらいたいと懇願し、賃貸契約をしたケースです。
このような事実が判明すれば、あからさまな節税行為とみなされ本特例が認められない場合があります。
家なき子特例の適用に必要な書類
家なき子特例は相続税の申告と共に税務署で手続きを進めます。たとえ相続税の非課税が確実であったとしても、特例を利用する場合、相続税の申告は必須となる点に注意しましょう。
必要書類の一覧
納税地を所轄する税務署へ次の必要書類を、被相続人が死亡を知った日の翌日から10カ月以内に提出します。
共通書類
家なき子特例は小規模宅地等の特例の例外措置なので、まずは小規模宅地等の特例の申告に必要となる書類を集める必要があります。
小規模宅地等の特例の申告に必要となる共通の書類は次の通りです。
- 相続税の申告書:税務署の窓口または国税庁のホームページで取得
- 遺言書の写し:故人が遺言書を残していた場合に必要
- 遺産分割協議書の写し:相続人間で遺産分割を決めた場合に必要
- 相続人全員の印鑑証明書:1通300円、住所地の市区町村役場で取得
- 世帯全員の住民票:1通300円、住所地の市区町村役場から取得
- 被相続人の住民票除票:1通300円、最後の住所地の市区町村役場から取得
- 被相続人の戸籍謄本(相続開始日から10日以降に作成された書類):1通450円、本籍地の市区町村役場から取得
- 遺産分割協議の分割見込書:遺産分割協議書が相続税の申告期限に間に合わない場合
特例ごとの追加書類
家なき子特例を利用する際には、更に追加で次の3点を揃える必要があります。
- 戸籍の附票の写し
相続人の過去の住所変遷が明記された書類で、相続開始前3年以内の住所を証明するため必要です。本籍地の市区町村役場から取得します。1通300円で取得できます。 - 賃貸借契約書
相続人が賃貸住宅に住んでいることを証明するために必要です。ご自宅で大切に保管している賃貸借契約書を準備します。なお、賃貸借契約書を探したが見つからない場合、不動産会社に相談すれば書類の再発行を行ってくれるかもしれません。 - 相続家屋の登記事項証明書
故人の家屋であった事実を証明するための書類です。家屋の住所地を管轄する法務局で取得します。窓口請求の場合は1通600円、インターネット請求なら1通500円(窓口受取480円)です。
老人ホーム入居時の追加書類
被相続人が老人ホームに入居していても、条件を満たせば小規模宅地等の特例を利用できます。ただし、通常の書類に加えて特別な書類を準備する必要があります。
特例を適用するための条件は、以下の通りです。
- 被相続人に関する条件
被相続人が要介護認定または要支援認定を受けていること。さらに、老人福祉法などに基づく老人ホームに入所していたこと。 - 亡くなる前の自宅の状況
老人ホーム入所後、自宅が空き家になっている場合。このようなケースで、別居している親族が相続する際に特例を適用できます。
追加で必要な書類 特例を受けるには、通常の相続書類に加え、以下の書類を相続税申告時に添付する必要があります。
- 戸籍の附票の写し
被相続人の死亡後に作成されたもの。 - 介護の証明書類
介護保険被保険者証や障害福祉サービス受給者証の写しなど、要介護認定を受けていたことを示すもの。 - 入所施設に関する書類
入所契約書や施設の名称・所在地が記載された書類。
これらの書類が揃っていないと特例を受けられない可能性があります。必要な書類を事前に確認し、確実に準備しましょう。
家なき子特例の申告に必要な書類の複雑さ
「家なき子特例」を使うには、多くの書類を準備する必要があります。これらの書類には細かい条件があるため、不備があると特例が適用されない可能性もあります。
書類準備時の注意点と対応策
書類をそろえる際には、以下の点に注意してください:
- 必要書類の種類や内容を事前にしっかり確認する。
- 書類の期限や記載内容を間違えないようにする。
書類作成や手続きに不安がある場合は、専門家に相談することを検討してみてください。
弁護士や司法書士は、相続にくわしい専門家であり、スムーズに進めるためのアドバイスやサポートを提供してくれます。また、下記で紹介する「相続診断士」への相談もおすすめです。
不明点を解消するための専門家相談の重要性
小規模宅地等の特例や家なき子特例を利用したい場合、いろいろな不明点や疑問も出てきます。そんな時は「相続診断士」へ相談してみましょう。
相続診断士は相続全般の知識を有する専門資格者であり、無料で相談ができるので、相談者の事情に応じた的確なアドバイスが期待できます。
「円満相続ラボ」では、相続に関する基本知識やトラブル回避の方法をわかりやすくお伝えし、専門家によるサポートを提供しています。円満な相続を実現するための最適なご提案をいたします。
相続に関する疑問がある方には、相続診断士による無料相談窓口もご利用いただけます。どうぞお気軽にご相談ください。
小規模宅地等の特例の適用条件と注意点
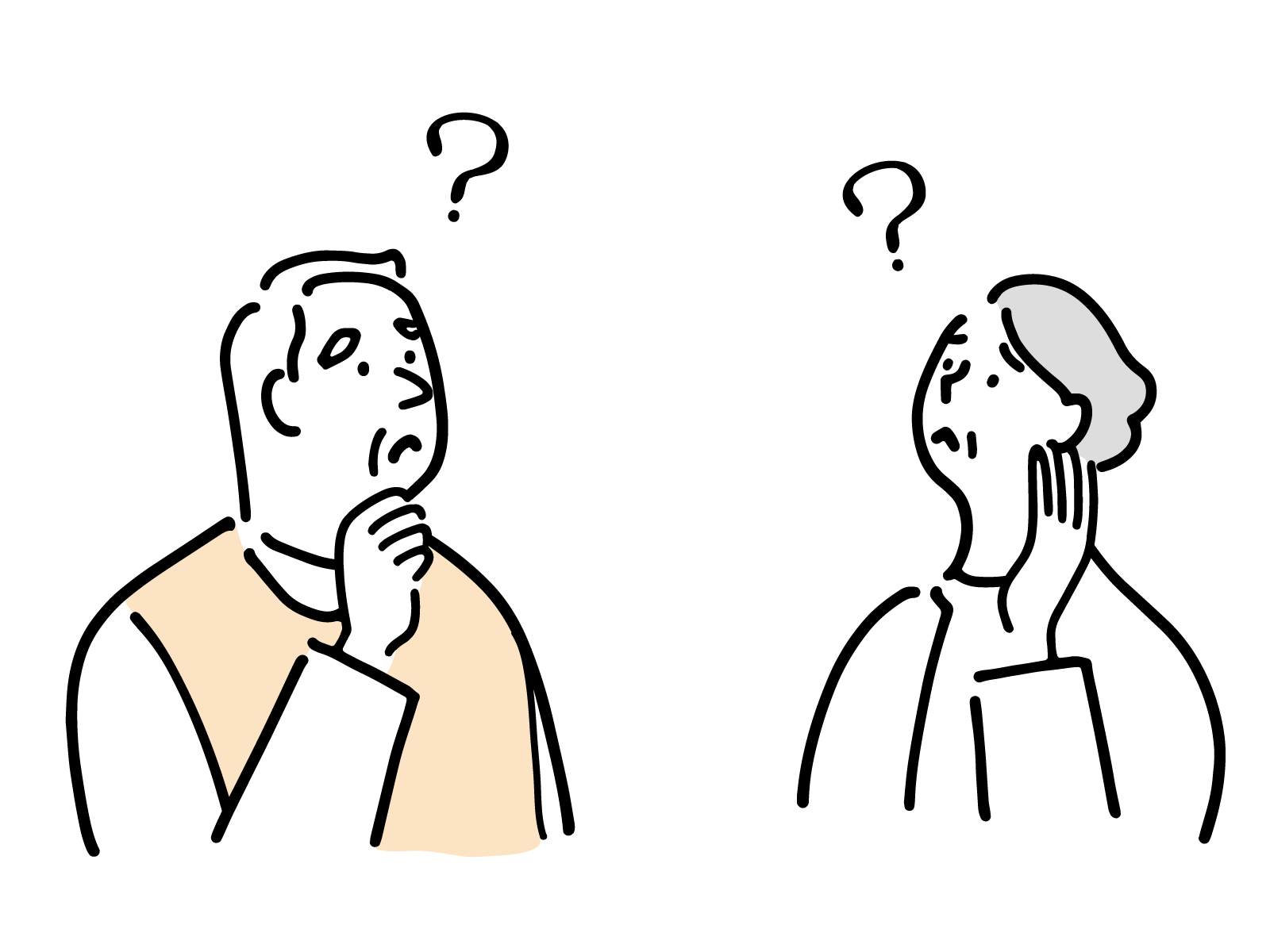
ここでは、小規模宅地等の特例が提供される宅地の種類について、それぞれの特徴や適用要件を含め、注意点も併せて解説します。
適用される宅地の種類
小規模宅地等の特例が適用できる宅地には制限があります。
特定居住用宅地等
特定居住用宅地等は、亡くなった人(被相続人)や、その人と生活費を共有していた親族が住んでいた土地を指します。たとえば、親の自宅がある土地がこれに当たります。
この特例を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。土地を取得する人によって条件が異なります。
- 被相続人が住んでいた土地の場合
・配偶者が取得する場合
条件なしで特例を利用できます。
・同居していた親族が取得する場合
被相続人と同じ家に住んでいたこと。
申告期限(亡くなった日から10か月以内)までその家に住み続け、土地を所有し続けること。
・その他の親族(「家なき子」)が取得する場合
以下の条件をすべて満たす必要があります。
被相続人に配偶者がいないこと。
被相続人と同居していた法定相続人がいないこと。
相続開始前3年間、自分や配偶者、親族が所有する家に住んだことがないこと。
相続開始時に住んでいた家を過去に所有していないこと。 - 被相続人と生活費を共有する親族が住んでいた土地の場合
・配偶者が土地を取得すること。
・親族が取得し、申告期限まで住み続けて土地を保有すること。
二世帯住宅も条件を満たせば特例を適用できます。以下の条件があります。
- 一つの建物内で親子が住んでいること。
- 親が敷地の名義人で、子どもが親に家賃を払っていないこと。
- 区分所有登記がされていない場合は親子で特例の適用が可能。
この特例では、330㎡までの土地について80%の評価減が適用されます。対象となる土地の例は以下の通りです。
- 一軒家が建つ土地
- 購入したマンションが建つ土地
- 二世帯住宅が建つ土地
特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、亡くなった人(被相続人)や一緒に生活費を共有していた親族が事業に利用していた土地のことです。
この特例を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 被相続人が事業に使っていた土地
事業を引き継いだ親族がその土地を相続する場合に適用されます。 - 親族が事業に使っていた土地
被相続人と生活費を共有し、その土地を使って事業をしていた親族が相続する場合に適用されます。
どちらの場合も、相続税の申告期限までに事業を続け、土地を保有していることが条件です。また、2のケースでは、土地や建物を無償で借りていたことが必要です。
なお、2019年4月1日以降、相続開始の3年以内に新しく事業に使い始めた土地は特例の対象外です。ただし、土地の上にある事業用の建物や設備の価値が、土地の価値の15%以上である場合は対象となります。
この特例では、400㎡までの土地について80%の評価減が適用されます。ただし、不動産貸付業は対象外です。
貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等とは、亡くなった人(被相続人)やその生活費を共有していた親族が、賃貸マンションやアパート、貸駐車場などの貸付事業に利用していた土地のことを指します。
この特例を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 被相続人が貸付事業に使っていた土地
被相続人が運営していた貸付事業の土地を引き継ぐ場合に適用されます。 - 親族が貸付事業に使っていた土地
被相続人と生活費を共有していた親族が、その土地で貸付事業を行っていた場合に適用されます。
どちらの場合も、相続税の申告期限(亡くなった日の翌日から10か月以内)まで貸付事業を継続し、土地を保有していることが必要です。また、親族が土地を借りている場合は、地代や家賃を支払っていないことが条件です。
なお、2018年4月1日以降、新たに貸付事業を始めた土地は特例の対象外です。ただし、3年以上前から事業を続けている場合は、この特例を利用できます。
この特例を使うと、200㎡までの土地について50%の評価減が受けられます。
適用条件における「同居」の定義
同居親族とは、被相続人が亡くなる直前に、同じ家で生活していた親族のことを指します。法律では「共に居住していた」と表現されます。
同居かどうかは、以下の4つのポイントで判断されます。
- 日常生活の状況
実際に一緒に生活していたか。 - 家へ入居した目的
その家で暮らすために入居したのか。 - 家の構造や設備
同じ建物内で生活空間を共有していたか。 - 他に生活拠点がないか
生活の中心がその家にあるかどうか。
同居とみなされるかは実態で判断されます。見た目が似たケースでも、「同居」と認められる場合とそうでない場合があります。しっかり条件を確認しましょう。
同居として認められるケース
以下のケースは、同居として認められる可能性が高いです。
- 被相続人が死亡した後に相続人が単身転勤した場合
- 相続人が仕事のため単身赴任中だった場合
- 被相続人が老人ホームに入居していた場合
- 完全分離型の二世帯住宅に住んでいた場合
同居として認められないケース
以下のケースは、同居として認められないことが多いです。
- 区分登記された二世帯住宅に住んでいた場合
- 週末だけ同居していた場合
- 一時的に同居していた場合
- 住民票のみが同一の場合
パターン別に見る同居の可否
ここでは、それぞれのパターン別に、同居に該当するか否かを解説します。
単身赴任中の場合
被相続人とその家族が一緒に住んでおり、相続人が仕事のため単身赴任中だった場合も同居と認められます。この判断は、単身赴任が終われば相続人が再び家族と暮らすことが前提となっているためです。現状は別居でも、生活の基盤が家族と同じ家にあるとみなされます。
被相続人が老人ホームに入居していた場合
被相続人が老人ホームに入居して亡くなった場合でも、家族がその家に住み続けていれば同居として認められます。これも2014年の税制改正によって適用が可能になりました。ただし、老人ホーム入居後にその家を賃貸したり、他の親族が住み始めたりした場合は、同居として扱われません。
二世帯住宅の場合
- 完全分離型の二世帯住宅
二世帯住宅には「完全同居型」「部分共有型」「完全分離型」の3種類があります。このうち、完全分離型は親と子が全く別々の生活空間を持つため、同居とは見なされないように思えます。しかし、2014年の税制改正以降、住宅の構造にかかわらず同居として認められるようになりました。これにより、完全分離型でも小規模宅地等の特例を利用できます。 - 区分登記された二世帯住宅
二世帯住宅で親子が同じ建物に住んでいても、登記が分けられている場合は同居とみなされません。たとえば、1階と2階を別々に所有する「区分所有登記」をしていると、法律上は別々の家として扱われます。一方、建物全体を親子で共有する「共有登記」であれば、同居として認められます。
一時的な同居の場合
別居している親族が介護などのために被相続人の家に泊まり込んでいた場合、その期間中に被相続人が亡くなっても同居とは認められません。また、被相続人死亡後に遺品整理のために住み続けた場合も同様に適用外です。
住民票のみ同一の場合
住民票が同じでも、実際に一緒に生活していないと同居にはなりません。逆に、住民票が異なっていても実際に同居している場合は認められることがあります。税務署は郵便物の送付先や水道・光熱費、通勤状況などから実際の生活状況を調査します。
同居していない親族の特例利用
同居していない親族でも、「家なき子特例」の条件を満たせば、小規模宅地の特例を利用できます。くわしい条件については、上記の説明を参考にしてください。
家なき子特例と小規模宅地等の特例の使い分け
家なき子特例と小規模宅地等の特例は、適用条件が違います。それぞれ、どういった場合に使えばいいのか解説します。
家なき子特例が優先されるケース
被相続人と同居していない親族が、故人が住んでいた土地、事業・賃貸用の土地を相続する場合、一定の条件を満たせば、家なき子特例が適用されます。
小規模宅地等の特例が適用される場合
被相続人と同居している親族が、故人が住んでいた土地、事業・賃貸用の土地を相続する場合、一定の条件を満たせば、小規模宅地等の特例が適用されます。
複数の特例が選択可能な場合の注意点
相続税の負担を軽減するため、小規模宅地等の特例を活用することは重要です。ただし、特例を適用する土地が複数ある場合や、複数種類の特例が併用できる場合には注意が必要です。
被相続人が複数の土地を所有していた場合、小規模宅地等の特例(居住用、事業用、貸付事業用など)は、限度面積内で併用可能です。ただし、各特例の「限度面積」が定められており、組み合わせ方によっては適用面積が制限される場合があります。
たとえば、居住用宅地と事業用宅地を併用する場合、それぞれの限度面積(330㎡と400㎡)まで適用できます。一方、貸付事業用宅地が含まれる場合には、合計面積に制限がかかるため、適用の優先順位が重要になります。
特例の適用順序を変えることで、適用可能な面積や税額軽減の効果が異なります。以下は具体例です。
- 居住用を優先する場合:居住用の特例が限度面積の範囲で優先的に適用されます。結果として、他の土地に適用できる特例面積が減少する可能性があります。
- 貸付事業用を優先する場合:貸付事業用の面積を先に計算し、残りを他の特例に割り当てます。この場合、減額割合が高い特例を十分に活用できないこともあります。
配偶者には「税額軽減制度」があり、1億6,000万円または全相続財産のどちらか低い額まで非課税となります。この場合、配偶者が小規模宅地等の特例を利用せず、他の相続人に特例を適用させる方が、相続税全体の負担を減らせる場合があります。
どの組み合わせが最適かは、土地の評価額や面積、減額割合などにより異なります。そのため、複数パターンを試算し、最も減額効果の高い方法を選ぶことが大切です。
特例の選択は相続税額に大きな影響を与えるため、専門家に相談することをおすすめします。税理士や相続診断士などの専門家とともに検討することで、最適な選択が可能になります。
家なき子特例および小規模宅地等の特例を活用する際の注意事項
ここでは、家なき子特例、小規模宅地等の特例を活用する際に知っておきたい注意点についてくわしく紹介します。
節税効果を最大化するためのポイント
特例を併用する場合、まず各宅地の相続税評価額を正確に計算しておきましょう。ただ面積や減額割合を考慮するだけでは効果を十分に確認できません。
路線価方式を利用し、「1㎡あたりの路線価 × 土地面積」で評価額を算出します。
たとえば、貸付事業用宅地と居住用宅地について小規模宅地等の特例を併用する場合、一見すると減額割合が高い居住用宅地を優先するのが良さそうですが、土地の評価額次第では逆に貸付事業用宅地を優先した方が有利になる場合もあります。
また、配偶者は「配偶者控除」を利用することで、1億6,000万円または法定相続分まで相続税を非課税にできます。この控除と小規模宅地等の特例は併用可能ですが、配偶者の相続分が1億6,000万円以下であれば、特例を使わずとも節税が可能です。
配偶者の財産が多すぎると、配偶者が亡くなった際に相続税が高額になる可能性があります。このため、自宅や賃貸物件は子どもが相続する方が全体の節税につながる場合もあります。
税制改正後の適用リスク
2020年4月1日以降、家なき子特例の適用条件が厳しくなりました。持ち家の範囲が広がり、相続人やその親族、関係する会社が所有する家に住んでいる場合は特例が受けられません。また、「現在住んでいる家を過去に所有していたことがない」という条件が新たに追加され、名義変更やリースバックなどの方法で要件を整える節税対策も通用しなくなりました。
この改正により、以前よりも特例を使いづらくなっています。2020年3月31日以前に発生した相続には旧制度が適用されましたが、それ以降は改正後のルールに従う必要があります。
適用できるかどうかの判断は複雑な場合が多いため、迷ったときは早めに税理士や専門家に相談することをおすすめします。特例を使えるかどうかで、節税額が大きく変わる可能性があります。
専門家への相談の重要性
家なき子特例や小規模宅地等の特例は、相続税を大幅に軽減できる非常に有益な制度です。しかし、適用条件が細かく定められており、一見すると要件を満たしているようでも、実際には対象外となる場合があります。また、どの特例を優先して利用するかによって節税効果が変わるため、的確な判断が求められます。
このように複雑な制度を最大限に活用するためには、税理士や相続診断士など、相続にくわしい専門家への相談が欠かせません。専門家は財産評価や適用可能な特例の組み合わせをシミュレーションし、最適な節税プランを提案してくれます。また、遺産分割や相続税申告の手続きもスムーズに進められるようサポートしてくれるので、相続人間のトラブルを未然に防ぐことも可能です。
特例の適用に少しでも不安がある場合や、条件が複雑なケースでは、早めに専門家のアドバイスを受けましょう。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を書いたのは…

弁護士・ライター
中澤 泉(なかざわ いずみ)
弁護士事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続といった幅広い分野の案件を担当した後、メーカーの法務部で企業法務の経験を積んでまいりました。
事務所勤務時にはウェブサイトの立ち上げにも従事し、現在は法律分野を中心にフリーランスのライター・編集者として活動しています。
法律をはじめ、記事執筆やコンテンツ制作のご依頼がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。