法定相続情報一覧図の必要書類を完全解説!取得から提出まで徹底ガイド

法定相続情報一覧図の取得には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の現在戸籍謄本など、複数の書類が必要です。この記事では、必要書類の詳細な一覧から取得方法、申請書の作成方法、法務局への提出手続きまで、法定相続情報一覧図の取得に関するすべての情報を網羅的に解説します。手数料無料で取得でき、相続手続きを大幅に簡素化できる制度を活用して、スムーズな相続手続きを実現しましょう。
Contents
1. 法定相続情報一覧図とは
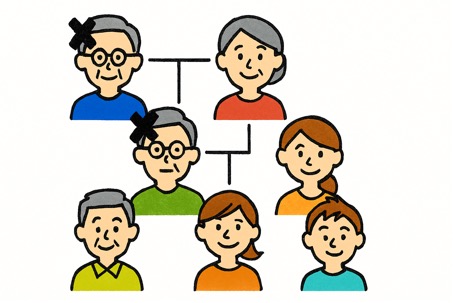
1.1 法定相続情報一覧図の概要
法定相続情報一覧図は、平成29年5月29日から開始された法務局の新しいサービスで、被相続人と相続人の関係を一枚の図にまとめた公的な証明書類です。この制度は、相続手続きの簡素化を目的として法務省が導入しました。
従来の相続手続きでは、銀行や証券会社、不動産登記など各種手続きのたびに、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などの大量の書類を提出する必要がありました。しかし、法定相続情報一覧図を取得することで、これらの複雑な戸籍関係書類の束に代わって、1通の証明書で相続関係を証明できるようになりました。
法定相続情報一覧図には、被相続人の氏名、生年月日、最後の住所、死亡年月日と、相続人全員の氏名、生年月日、続柄が記載され、法務局の認証文と登記官の押印により公的な証明力を持ちます。
1.2 利用するメリット
法定相続情報一覧図を利用することで、相続手続きにおいて以下のようなメリットが得られます。
| メリット | 詳細 |
| 手続きの簡素化 | 各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなる |
| 時間の短縮 | 複数の金融機関で同時に手続きを進められる |
| 費用の削減 | 戸籍謄本を何通も取得する必要がなく、発行手数料が削減できる |
| 書類の管理が簡単 | 1枚の証明書で済むため、紛失リスクが減る |
| 無料で取得可能 | 法定相続情報一覧図の交付に手数料はかからない |
特に複数の相続手続きを並行して進める場合、従来は戸籍謄本を複数セット用意する必要がありましたが、法定相続情報一覧図であれば必要な通数を無料で交付してもらえるため、大幅な時間短縮と費用削減が実現できます。
また、相続税申告においても、令和元年4月1日以降は法定相続情報一覧図の写しを戸籍謄本等に代えて添付することができるようになり、税務手続きでも利便性が向上しています。
1.3 どんな手続きで使用できるか
法定相続情報一覧図は、相続に関する様々な手続きで戸籍謄本等の代わりとして使用できます。ただし、利用可能な手続きは各機関が個別に判断するため、事前に確認することが重要です。
現在、以下のような手続きで利用が可能です。
| 手続き分野 | 具体的な手続き内容 |
| 金融機関での手続き | 預貯金の相続手続き、証券口座の名義変更、生命保険金の請求 |
| 不動産関係 | 相続登記、不動産の名義変更 |
| 税務手続き | 相続税申告、準確定申告 |
| 年金関係 | 遺族年金の請求、未支給年金の請求 |
| その他公的手続き | 各種許認可の承継手続き、自動車の名義変更 |
金融機関については、全国銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、全国労働金庫協会、農林中央金庫、全国共済農業協同組合連合会が利用可能であることを表明しており、多くの金融機関で活用できる状況が整っています。
ただし、一部の手続きでは従来通り戸籍謄本の提出を求められる場合もあります。また、法定相続情報一覧図には相続放棄や遺産分割協議の内容は記載されないため、これらの情報が必要な手続きでは別途書類の準備が必要となります。
2. 法定相続情報一覧図の必要書類一覧
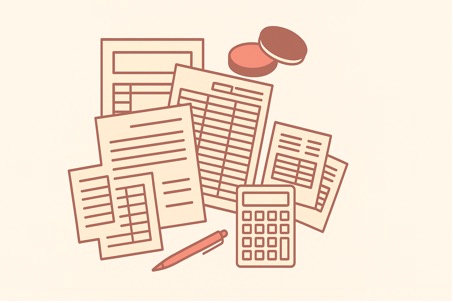
法定相続情報一覧図の申請には、被相続人と相続人それぞれに関する証明書類の提出が必要です。必要書類は相続の状況や申請者によって異なる場合がありますが、基本的な書類は以下の通りです。
2.1 被相続人に関する必要書類
被相続人(亡くなった方)に関しては、出生から死亡まですべての戸籍関係書類と住所を証明する書類が必要となります。
| 書類名 | 必要性 | 取得先 | 備考 |
| 出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 必須 | 各本籍地の市区町村役場 | 転籍がある場合は複数の市区町村から取得が必要 |
| 住民票の除票または戸籍の附票 | 必須 | 最後の住所地の市区町村役場または本籍地の市区町村役場 | 被相続人の最後の住所を証明するため |
戸籍謄本等の取得は時間がかかる場合があります。特に、被相続人が生前に何度も転籍している場合や、古い戸籍が関わる場合は、複数の市区町村役場に請求する必要があり、取得完了まで数週間を要することもあります。
2.2 相続人に関する必要書類
相続人全員分の現在の戸籍関係書類と、申請を行う人の住所証明書類が必要です。
| 書類名 | 対象者 | 必要性 | 取得先 |
| 戸籍謄本または戸籍抄本 | 相続人全員 | 必須 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 住民票の写し | 申請人(代表相続人) | 必須 | 申請人の住所地の市区町村役場 |
| 委任状 | 代理人申請の場合 | 代理申請時のみ | 申請人が作成 |
| 代理人の身分証明書 | 代理人申請の場合 | 代理申請時のみ | 運転免許証、マイナンバーカード等 |
相続人の戸籍謄本については、被相続人との続柄が確認できる現在のものであれば戸籍抄本でも構いません。ただし、相続人が複数いる場合は、全員分の戸籍書類が必要となります。
2.3 申請に必要なその他の書類
戸籍関係書類以外にも、申請手続きに必要な書類があります。これらの書類は申請者が作成するものです。
| 書類名 | 作成者 | 内容 | 注意点 |
| 申請書(法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書) | 申請人 | 申請の基本情報を記載 | 法務局指定の様式を使用 |
| 法定相続情報一覧図 | 申請人 | 相続関係を図示した書類 | A4用紙に記載、手書きまたはパソコン作成可 |
申請書と法定相続情報一覧図は法務局が提供する様式を使用する必要があります。法務局のホームページからダウンロードすることができ、記載例も併せて確認できます。
申請時には、原本とコピーの両方を持参することをお勧めします。原本は申請受理後に返却されますが、手続きの確認のためコピーも用意しておくと安心です。また、相続人が多数いる場合や相続関係が複雑な場合は、事前に管轄の法務局に相談することで、スムーズな申請手続きが可能となります。
3. 被相続人の必要書類の詳細と取得方法

法定相続情報一覧図の申請において、被相続人に関する必要書類は相続関係を証明するための最も重要な書類です。被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍関係書類と住所を証明する書類が必要となります。
3.1 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本は、相続人を確定するために最も重要な書類です。出生から死亡まで連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を全て揃える必要があります。
| 戸籍の種類 | 内容 | 取得が必要な理由 |
| 現在戸籍謄本 | 現在の戸籍制度による戸籍 | 最新の身分関係を確認 |
| 除籍謄本 | 全員が除籍された戸籍 | 過去の身分関係を確認 |
| 改製原戸籍謄本 | 戸籍法改正前の古い様式の戸籍 | 戸籍制度変更で削除された情報を確認 |
これらの戸籍謄本により、被相続人の配偶者、子、両親、兄弟姉妹などの相続人を漏れなく特定することができます。戸籍に記載された全ての相続人が法定相続情報一覧図に反映されるため、正確性が求められます。
3.1.1 戸籍謄本の取得先
戸籍謄本の取得先は、被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場です。被相続人が生前に転籍や結婚により本籍を変更している場合は、複数の市区町村から取得する必要があります。
| 取得方法 | 手続き場所・方法 | 必要なもの | 手数料 |
| 窓口申請 | 本籍地の市区町村役場 | 申請書、本人確認書類、相続関係を証明する書類 | 戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍謄本750円 |
| 郵送申請 | 本籍地の市区町村役場へ郵送 | 申請書、本人確認書類のコピー、定額小為替、返信用封筒 | 同上+郵送料 |
| コンビニ交付 | コンビニエンスストア | マイナンバーカード | 戸籍謄本400円(一部市区町村のみ) |
相続人であれば直系血族や配偶者は戸籍謄本を取得可能ですが、兄弟姉妹や代襲相続人の場合は、相続関係を証明する書類の提示が求められることがあります。
3.1.2 戸籍謄本取得時の注意点
戸籍謄本を取得する際は、以下の点に注意が必要です。
連続性の確認が最も重要です。取得した戸籍謄本に記載されている従前戸籍の表示を確認し、出生から死亡まで途切れることなく戸籍が繋がっているかを確認してください。戸籍に空白期間があると、法定相続情報一覧図の申請が受理されません。
戸籍の読み方と解釈にも注意が必要です。古い戸籍は手書きで記載されており、文字が判読困難な場合があります。また、戸籍法の改正により記載方法が変更されているため、養子縁組や認知の事実を見落とさないよう慎重に確認する必要があります。
複数の市区町村から戸籍を取得する場合は、取得順序を工夫することで効率的に進められます。最新の戸籍から遡って取得し、従前戸籍の本籍地を確認しながら順次古い戸籍を取得することをお勧めします。
3.2 被相続人の住民票の除票
被相続人の住民票の除票は、被相続人の最後の住所地を証明するために必要な書類です。法定相続情報一覧図には被相続人の最後の住所を記載するため、この住民票の除票で確認します。
住民票の除票は、被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場で取得できます。死亡届が提出されると住民票から除票され、除票として保管されます。
| 項目 | 詳細 |
| 取得先 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 |
| 保存期間 | 除票となった日から5年間(改正後は150年間) |
| 記載事項 | 住所、氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄、死亡年月日など |
| 手数料 | 1通300円程度(市区町村により異なる) |
住民票の除票が取得できない場合は、戸籍の附票の除票で代用できます。戸籍の附票は本籍地の市区町村で管理されており、戸籍と住所の変遷を記録した書類です。被相続人が転居を繰り返していた場合でも、戸籍の附票により住所の履歴を確認できます。
住民票の除票を取得する際は、本籍地の記載があるものを請求してください。法定相続情報一覧図の作成において、被相続人の戸籍謄本と住民票の除票の整合性を確認するために本籍地の記載が必要となる場合があります。
4. 相続人の必要書類の詳細と取得方法
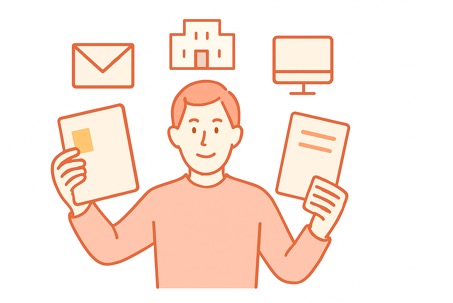
法定相続情報一覧図の申請において、相続人に関する必要書類は申請の成否を左右する重要な要素です。相続人全員分の書類が必要となるため、事前に漏れなく準備することが大切です。
4.1 相続人全員の現在戸籍謄本
相続人全員の現在戸籍謄本または戸籍抄本の提出が必要です。これは被相続人との続柄を証明し、現在も生存していることを確認するための重要な書類です。
| 対象者 | 必要書類 | 取得先 | 有効期限 |
| 配偶者 | 現在戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 発行から3か月以内 |
| 子(実子・養子) | 現在戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 発行から3か月以内 |
| 父母・祖父母 | 現在戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 発行から3か月以内 |
| 兄弟姉妹 | 現在戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 発行から3か月以内 |
相続人の戸籍謄本取得時の注意点として、被相続人が死亡した日以降に発行されたものでなければなりません。また、相続人が婚姻や養子縁組により戸籍が変更されている場合は、最新の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場でのみ取得可能です。本籍地が遠方の場合は、郵送請求を利用することができます。郵送請求の際は、申請書、身分証明書のコピー、定額小為替、返信用封筒を同封して送付します。
4.2 申請人の住民票
法定相続情報一覧図を申請する申請人の住民票が必要です。申請人は相続人の中から選ばれ、通常は代表相続人が申請人となります。
住民票の取得要件は以下のとおりです:
- 発行から3か月以内のもの
- 本籍地の記載は不要(住所と氏名の記載があれば十分)
- 世帯全員分または申請人のみの住民票いずれでも可
- 住民票コードの記載は不要
住民票は住所地の市区町村役場で取得できます。マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアでも取得可能で、手数料は通常300円程度です。
4.3 代理人が申請する場合の書類
相続人以外の代理人が申請する場合、または相続人の一人が他の相続人の代理として申請する場合には、追加の書類が必要となります。
| 代理人の種類 | 必要書類 | 注意事項 |
| 親族(相続人)による代理 | 委任状 代理人の住民票 代理人の身分証明書 | 委任者の実印押印 印鑑登録証明書添付 |
| 弁護士・司法書士 | 委任状 資格証明書 職印 | 職務上請求書の使用可能 |
| 行政書士 | 委任状 資格証明書 職印 | 相続業務の範囲内での代理 |
代理申請における委任状には、申請の目的、代理人の氏名住所、委任者の署名押印が必要です。委任状に使用する印鑑は、実印を使用し、印鑑登録証明書(発行から3か月以内)を添付します。
専門家に依頼する場合のメリットとして、書類の不備による再申請のリスクを軽減できる点、複雑な相続関係でも適切に対応してもらえる点があります。ただし、専門家報酬が別途必要となるため、費用対効果を検討して判断することが重要です。
代理申請では、申請後の証明書受領も代理人が行うことになります。郵送での受領を希望する場合は、申請時にその旨を申し出て、適切な送付先を指定する必要があります。
5. 申請書類の作成方法
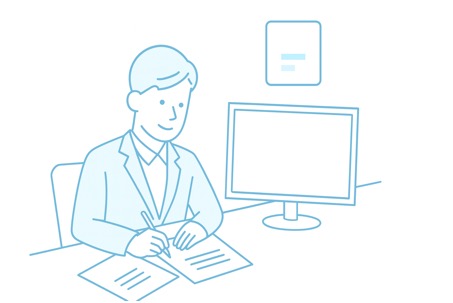
法定相続情報一覧図を取得するためには、申請書と法定相続情報一覧図を正確に作成する必要があります。ここでは、それぞれの書類の作成方法について詳しく解説します。
5.1 申請書の記載事項
法定相続情報一覧図の申請書(正式名称:「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」)には、以下の項目を正確に記載する必要があります。
| 記載項目 | 記載内容 | 注意点 |
| 申出人の氏名・住所 | 申請者本人の情報 | 住民票記載どおりに正確に記入 |
| 申出人と被相続人との続柄 | 配偶者、子、親など | 戸籍謄本で確認できる続柄を記載 |
| 被相続人の氏名・本籍・最後の住所 | 亡くなった方の基本情報 | 戸籍謄本・住民票の除票と一致させる |
| 被相続人の死亡年月日 | 死亡診断書記載の日付 | 戸籍謄本記載の日付と一致させる |
| 交付を求める通数 | 必要な証明書の部数 | 各種手続きで使用する分を考慮 |
申請書は黒色のボールペンまたは万年筆で記入し、修正液や修正テープは使用しないよう注意してください。誤記した場合は、該当箇所を二重線で削除し、正しい内容を記入した上で訂正印を押印します。
5.2 法定相続情報一覧図の作成方法
法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を一目で分かるよう図示した書類です。以下の要領で作成します。
記載必須事項は次のとおりです:
- 被相続人の氏名、出生年月日、死亡年月日、最後の住所
- 相続人全員の氏名、出生年月日、住所、続柄
- 被相続人との続柄(配偶者、子、直系尊属など)
作成時の重要なポイント:
| 項目 | 作成ルール |
| 用紙 | A4サイズの白紙を使用 |
| 記入方法 | 手書きまたはパソコンでの作成可能 |
| 文字 | 黒色で明瞭に記載 |
| 配置 | 被相続人を上部中央に配置し、相続人を下部に配置 |
| 続柄表示 | 線で結び、続柄を明記 |
相続人の範囲は戸籍謄本で確認できる法定相続人のみを記載し、相続放棄をした人がいる場合でも、その旨の記載は不要です。ただし、相続放棄の事実がある場合は、別途その旨を申請書に記載する必要があります。
複数ページにわたる場合は、各ページに「○ページ中○ページ目」と記載し、製本テープなどで綴じて一体性を保ちます。
5.3 申請書のダウンロード先
法定相続情報一覧図の申請に必要な様式は、法務省のウェブサイトから無料でダウンロードできます。主要な様式は以下のとおりです。
- 法務省「法定相続情報証明制度について」から各種様式をダウンロード
ダウンロード可能な主な様式:
| 様式名 | 用途 | ファイル形式 |
| 申出書 | 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出 | PDF、Word |
| 法定相続情報一覧図(記載例) | 作成時の参考資料 | |
| 委任状 | 代理人が申請する場合 | PDF、Word |
申請書は最新版を使用することが重要です。法務省ウェブサイトでは随時様式の更新が行われているため、申請前には必ず最新版をダウンロードしてください。
また、各法務局でも申請書の配布を行っており、窓口で直接受け取ることも可能です。不明な点がある場合は、管轄の法務局に電話で問い合わせることをお勧めします。
記載例も同時に公開されているため、初回申請時には必ず記載例を参考にして作成することで、不備による再提出を避けることができます。
6. 申請手続きの流れ

6.1 申請前の準備
法定相続情報一覧図の申請を行う前に、必要書類の収集と申請書の作成を完了させておく必要があります。申請前の準備段階で不備があると、後の手続きで時間を要することになるため、入念な確認が重要です。
まず、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、住民票の除票、相続人全員の現在戸籍謄本、申請人の住民票など、必要書類がすべて揃っているかを確認します。戸籍謄本については、改製により複数の市区町村から取得する必要がある場合があるため、漏れがないよう注意深く確認してください。
次に、法定相続情報一覧図を作成します。この一覧図は被相続人と相続人の関係を図式化したもので、正確な続柄の記載と漏れのない相続人の記載が求められます。作成時は法務省のホームページで提供されている記載例を参考にし、続柄や氏名の表記に誤りがないか複数回確認することが大切です。
申請書についても同様に、記載漏れや誤記がないよう慎重に作成します。特に申請人の住所・氏名、被相続人との続柄、交付を希望する通数などは重要な項目です。
6.2 法務局への申請方法
法定相続情報一覧図の申請は、窓口申請と郵送申請の2つの方法から選択できます。どちらの方法を選択する場合でも、事前に申請先の法務局を確認しておく必要があります。
6.2.1 窓口申請
窓口申請では、申請書と必要書類を直接法務局に持参して提出します。申請時に書類の不備をその場で確認できるため、修正が必要な場合も迅速に対応できるメリットがあります。
申請可能な法務局は以下のいずれかです:
- 被相続人の本籍地を管轄する法務局
- 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
- 申請人の住所地を管轄する法務局
- 被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局
窓口での申請時間は、法務局の開庁時間内(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)に限られます。申請時は本人確認書類として運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書を持参してください。
窓口申請の場合、申請書類の確認後に受付票が交付されます。この受付票は証明書の受け取り時に必要となるため、大切に保管してください。
6.2.2 郵送申請
郵送申請は、申請書と必要書類を封筒に入れて法務局宛てに送付する方法です。法務局への来庁が困難な場合や遠方からの申請に適しています。
郵送申請時の注意点として、以下の事項があります:
| 項目 | 注意点 |
| 封筒 | A4サイズの書類が入る大きさで、宛先を明記 |
| 返信用封筒 | 証明書受け取り用の封筒と切手を同封 |
| 送付方法 | 書留郵便など追跡可能な方法を推奨 |
| 本人確認書類 | 申請人の身分証明書のコピーを同封 |
郵送申請では書類の到達確認ができるよう、書留郵便やレターパックプラスなどの利用を推奨します。また、証明書の受け取りを郵送で希望する場合は、返信用の封筒に適切な金額の切手を貼付して同封する必要があります。
6.3 審査期間と取得までの日数
法定相続情報一覧図の申請から証明書の交付まで、通常1週間程度の期間を要します。ただし、この期間は申請内容や法務局の繁忙状況によって変動する場合があります。
審査過程では、提出された戸籍謄本等の内容確認と法定相続情報一覧図の記載内容の照合が行われます。書類に不備がある場合や記載内容に疑義がある場合は、法務局から申請人に連絡があり、追加書類の提出や訂正が求められることがあります。
審査期間を短縮するためには、以下の点に注意して申請することが重要です:
- 必要書類の漏れや記載ミスをなくす
- 戸籍謄本の連続性を確実にする
- 法定相続情報一覧図の続柄表記を正確にする
- 申請書の記載事項を完全にする
急ぎで証明書が必要な場合は、窓口申請を選択し、申請時に交付予定日を確認することをお勧めします。また、平日の午前中に申請することで、比較的早期の交付が期待できる場合があります。
なお、一度交付を受けた法定相続情報一覧図の証明書は、その後5年間は再交付の申請が可能です。初回申請時に複数通の交付を受けることも可能なため、今後の手続きで必要となる見込み数を考慮して申請することも検討してください。
7. 提出先と手数料
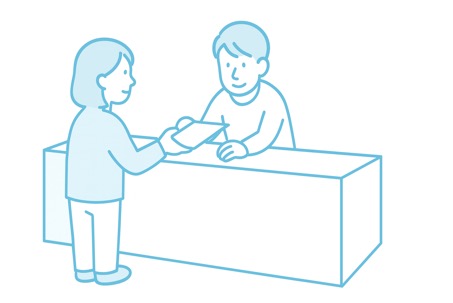
法定相続情報一覧図の申請は法務局で行いますが、どこの法務局でも申請できるわけではありません。申請先となる法務局や手数料について詳しく解説します。
7.1 申請可能な法務局
法定相続情報一覧図の申請は、以下のいずれかの法務局(登記所)に行うことができます。
| 申請可能な法務局 | 詳細 |
| 被相続人の本籍地を管轄する法務局 | 被相続人が最後に本籍を置いていた市区町村を管轄する法務局 |
| 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局 | 被相続人が死亡時に住民票を置いていた市区町村を管轄する法務局 |
| 申請人の住所地を管轄する法務局 | 法定相続情報一覧図の申請を行う相続人の住所地を管轄する法務局 |
| 被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局 | 相続財産に不動産がある場合、その不動産の所在地を管轄する法務局 |
最も利用しやすい申請先を選択することができるため、申請人の住所地を管轄する法務局を選ぶケースが多くなっています。ただし、各法務局によって取扱業務が異なる場合があるため、事前に確認することをお勧めします。
申請前には、選択した法務局が法定相続情報証明制度に対応しているか確認しましょう。全国の法務局で対応していますが、出張所等では取り扱っていない場合があります。
7.2 手数料と支払方法
法定相続情報一覧図の申請および証明書の交付に手数料は一切かかりません。この制度は相続手続きの簡素化を目的として創設されたため、無料で利用できます。
| 項目 | 手数料 |
| 法定相続情報一覧図の申請 | 無料 |
| 法定相続情報一覧図の写しの交付 | 無料(必要な通数分) |
| 再交付申請 | 無料 |
| 記載事項の変更・訂正 | 無料 |
ただし、申請に必要な添付書類(戸籍謄本、住民票等)の取得には、各市区町村で定められた手数料が必要です。これらの費用は別途負担する必要があります。
郵送で申請する場合は、返送用の切手代は申請人が負担します。証明書の通数に応じて適切な切手を同封しましょう。
7.3 証明書の交付方法
法定相続情報一覧図の写しの交付方法は、申請方法に応じて選択できます。
| 申請方法 | 交付方法 | 注意事項 |
| 窓口申請 | 窓口での受取り | 申請人本人または代理人が直接受け取り |
| 窓口申請 | 郵送による受取り | 返送先住所を申請書に記載し、返信用封筒と切手を添付 |
| 郵送申請 | 郵送による受取り | 必ず返信用封筒と切手を同封 |
必要な通数は申請時に指定でき、同時に複数通の交付を受けることができます。相続手続きで複数の金融機関や役所に提出する必要がある場合は、あらかじめ必要な通数を申請しておくと効率的です。
証明書には法務局の認証印が押印され、偽造防止のための特殊用紙が使用されます。有効期限の定めはありませんが、各種手続きにおいて「発行から○か月以内」といった制限がある場合があるため、使用予定に合わせて申請することをお勧めします。
再交付を希望する場合は、最初の申請から5年以内であれば、簡易な手続きで追加の証明書を取得できます。この場合も手数料は無料です。
8. よくある質問と注意点
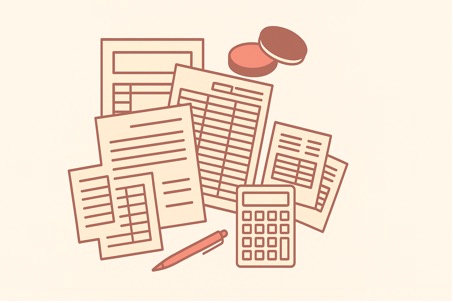
8.1 必要書類で困ったときの対処法
法定相続情報一覧図の申請において、必要書類の準備で困ったときは以下の対処法を参考にしてください。
8.1.1 戸籍謄本が取得できない場合の対処法
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の中で、戸籍が廃棄されている場合や戦災で焼失している場合があります。このような状況では、以下の書類で代替可能です。
| 状況 | 代替書類 | 取得先 |
| 戸籍の廃棄・焼失 | 戸籍謄本等交付請求書に「廃棄証明書」添付 | 該当市区町村役場 |
| 除籍謄本の保存期間経過 | 改製原戸籍謄本 | 該当市区町村役場 |
| 本籍地が不明 | 戸籍附票の写し | 住所地の市区町村役場 |
8.1.2 住民票の除票が取得できない場合
被相続人の住民票の除票は保存期間が150年に延長されましたが、平成26年3月31日以前に消除された住民票の除票は保存期間が経過している可能性があります。この場合、戸籍の附票の写しで代替することができます。
8.1.3 相続人の戸籍謄本で注意すべき点
相続人全員の現在戸籍謄本を取得する際、以下の点に注意が必要です。
- 婚姻により姓が変わった相続人は、現在の戸籍謄本だけでなく、被相続人との続柄が分かる戸籍謄本も必要
- 養子縁組をしている相続人は、養子縁組の記載がある戸籍謄本が必要
- 未成年の相続人がいる場合は、親権者の同意書や家庭裁判所の許可書が必要な場合がある
8.2 申請が却下される主な理由
法定相続情報一覧図の申請が却下される理由を事前に把握し、適切な申請を行いましょう。
8.2.1 書類不備による却下理由
最も多い却下理由は書類の不備です。以下の点を確認してから申請してください。
| 却下理由 | 具体的な問題 | 対処法 |
| 戸籍謄本の不備 | 出生から死亡まで連続していない | 欠けている期間の戸籍謄本を追加取得 |
| 住所の不一致 | 戸籍と住民票の住所が異なる | 住民票の除票または戸籍附票で住所を証明 |
| 申請人の資格不備 | 申請人が相続人でない | 相続人からの委任状を取得 |
| 一覧図の記載ミス | 相続人の記載漏れや誤記 | 正確な一覧図を再作成 |
8.2.2 法定相続情報一覧図の記載エラー
法定相続情報一覧図の記載内容に誤りがある場合も申請が却下されます。特に以下の点に注意が必要です。
- 被相続人と相続人の氏名、生年月日、続柄の正確性
- 相続人の住所記載の有無(住所記載は任意だが、記載する場合は正確に)
- 法定相続分の計算ミス
- 相続放棄をした相続人の取り扱い
8.2.3 申請書の記載不備
申請書の記載項目に不備がある場合も却下の原因となります。
- 申請人の署名・押印漏れ
- 交付を受ける通数の記載漏れ
- 申請する法務局の管轄間違い
- 添付書類一覧の記載漏れ
8.3 再交付を受けたい場合の手続き
法定相続情報一覧図の写しは、最初の申請から5年間は再交付を受けることができます。
8.3.1 再交付の申請方法
再交付の申請は最初に申請した法務局でのみ受け付けています。他の法務局では再交付を受けることができませんので注意してください。
再交付の申請に必要な書類は以下の通りです。
- 法定相続情報一覧図の写しの交付申請書(再交付用)
- 申請人の本人確認書類
- 申請人が相続人でない場合は、相続人からの委任状
8.3.2 再交付時の注意点
再交付を申請する際は、以下の点に注意してください。
| 項目 | 内容 | 注意事項 |
| 申請期限 | 最初の申請から5年間 | 期限を過ぎると新規申請が必要 |
| 申請者の資格 | 最初の申請者と同一人物または相続人 | 第三者は委任状が必要 |
| 手数料 | 無料 | 再交付も無料で受けられる |
| 交付方法 | 窓口受取または郵送 | 郵送の場合は返信用封筒が必要 |
8.3.3 5年経過後の対応
最初の申請から5年が経過した場合は、新規申請として再度すべての必要書類を準備する必要があります。この場合、以下の点を考慮してください。
- 被相続人の戸籍謄本等は再取得が必要
- 相続人の現在戸籍謄本も最新のものを取得
- 申請人の住民票も現在のものを準備
- 法定相続情報一覧図も新たに作成
ただし、相続関係に変更がない場合は、以前作成した一覧図を参考にして作成時間を短縮することは可能です。
9. まとめ
法定相続情報一覧図の取得には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票の除票、相続人全員の現在戸籍謄本など多くの必要書類があります。事前に必要書類を正確に把握し、不備のないよう準備することが重要です。法務局での審査期間を考慮して早めに申請手続きを行い、相続手続きの効率化を図りましょう。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を監修したのは…

さくら共同法律事務所 弁護士・弁理士
野崎 智裕(のざき あきひろ)
京都大学文学部人文学科行動・環境文化学系社会学専修卒業後、京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻を経て
平成30年9月 司法試験合格
ミツカン創業家裁判やカルテル巡る関西電力株主訴訟などを担当。顧客の本来利益を追求する姿勢が顧客からの信頼を得ている。








