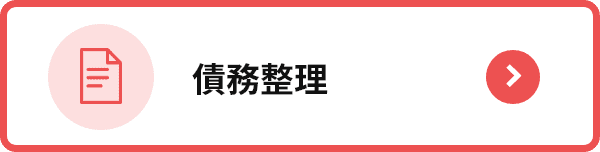夫婦間の贈与税はどこまで非課税?課税となる事例、節税対策、無申告リスクについて

Contents
夫婦間の贈与と贈与税の基本
夫婦間であっても財産を譲渡すれば、原則として贈与税の課税対象となります。本章では、贈与税の仕組みとその発生する理由、申告が必要なケースについて解説します。
夫婦間でも贈与税がかかる理由とは?
贈与税は、個人が他人から財産を無償でもらったときに課税される税金であり、夫婦間であっても例外ではありません。相続税法第21条の3第1項により、配偶者間の贈与も課税対象とされます。たとえば現金や不動産、高価な物品などを贈与した場合、その価値に応じて贈与税が課されることになります。
贈与税の申告が必要になるケースとは?
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。これを超える価値の贈与を受けた場合、贈与を受けた人が申告と納税をする必要があります。申告期間は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです(相続税法第27条)。期限を過ぎると加算税や延滞税などのペナルティが発生するため注意が必要です。
夫婦間で贈与税がかからないケースと注意点
夫婦間であっても、配偶者へ無償で財産を譲渡した場合には原則として贈与税が課税されます。
しかし、必ずしも贈与税がかかるとは限りません。以下では贈与税が非課税となるパターンについて解説していきます。
贈与税が非課税となる条件とは?
贈与税が非課税とされる主な条件には、以下のようなものがあります。これらの条件に該当するかどうかを確認することが重要です。
年間110万円以下の贈与は非課税
贈与税の基礎控除額は110万円です。つまり、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計が110万円以下であれば、贈与税は課されません。ただし、複数の贈与者から受け取った場合は合算されるため注意が必要です(相続税法第21条の5)。
生活費・教育費としての贈与は課税対象外
通常、必要な生活費や教育費については贈与税が非課税とされています。
生活費とは、通常生活において必要なものをいい、食費のほかに治療費や養育費なども非課税とされています。
通常生活に必要な範囲内の生活費とは、下記内容のものが挙げられます。
- 一人暮らしをしている子供への食費や家賃などの仕送り
- 配偶者への仕送り
- 結婚に必要な挙式代や新婚後に必要な家具などの結婚資金
- 出産費用
以上のようなものは生活費に該当するため、これらの贈与税は非課税とされています。
教育費についても通常必要な範囲内の金額であれば贈与税は非課税となります。具体的には下記内容のものが挙げられます。
- 子供の学費や習い事などにかかる資金
- 修学旅行にかかる費用
- 通学にかかる交通費
贈与税の基礎控除と適用範囲
贈与税の場合には110万円の基礎控除額というものがあります。
この基礎控除額によって、110万円以下の財産を無償で譲渡した場合には贈与税はかかりませんが、110万円を超えた場合には贈与税がかかってきます。
この場合には贈与を受けた側が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの期間において、贈与税の納付及び贈与税申告書の提出が必要になってきます。
共通口座での資金管理は贈与に当たるのか?
夫婦の共通口座を利用している場合でも、実質的に片方が入金し、もう片方が自由に使っている場合には、贈与とみなされる可能性があります。特に税務調査では、口座名義と実際の資金提供者が一致しているかがチェックされるため注意が必要です。
離婚後の財産分与と贈与税の関係
離婚に伴う財産分与は、民法に基づく権利行使とされ、原則として贈与税は課されません。ただし、分与額が過大と判断されると、贈与とみなされることもあります。
夫婦間で贈与税が発生するケースと注意すべきポイント
次に、夫婦間で贈与税が発生する代表的な事例を紹介します。思わぬ課税を避けるためにも、事前に知っておくことが大切です。
知らずに贈与税が発生する事例とは?
夫婦間の金銭や資産の移動は、日常的であるがゆえに課税対象になるという意識が薄れがちです。以下のようなケースでは贈与税が発生するおそれがあります:
- 高額な宝石や車のプレゼント
- 住宅ローンの肩代わり
- 不動産の名義変更
高額な資産や現金の移動による課税リスク
1回の贈与額が110万円を超える現金や資産を移動させた場合、原則として贈与税が課税されます。例えば、配偶者名義の預金に高額な入金をするなどは、税務署に把握される可能性が高いです。
高額なプレゼントを贈った場合の注意点
記念日やお祝いの際に高額なプレゼント(例えばブランドバッグや高級時計)を贈る行為も、贈与と判断される可能性があります。形式的には贈与税の対象となるため、110万円を超える場合は注意が必要です。
不動産の名義変更や取得費用の負担割合による課税
不動産を夫婦共有名義にする際、実際の負担割合と登記上の割合が異なると、贈与とみなされる可能性があります。特に購入費用を一方が全額負担しながら、登記を共有名義にした場合は注意が必要です。
住宅ローンの返済を配偶者が行った場合の扱い
住宅ローンの返済を配偶者が代行する場合も、元の債務者に対する贈与とみなされる可能性があります。特に毎月の返済が高額な場合は、累積により贈与税の対象となることがあります。
生命保険の契約者・受取人の関係による課税リスク
生命保険において、契約者と保険料負担者、受取人が異なる場合には、贈与税または相続税の課税対象になることがあります。契約内容を確認し、必要に応じて税理士など専門家に相談しましょう。
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)とは?

贈与税には非課税とされるものがあります。
夫婦間において、一定の要件を満たした場合には非課税となる、おしどり贈与の特例について解説していきます。
婚姻期間20年以上の配偶者への不動産贈与は特例あり
おしどり贈与の特例とは、婚姻期間が20年以上ある夫婦間において、居住用不動産などを購入するための資金を贈与した場合において、2,000万円までは贈与税が非課税とされる特例になります。
この特例の適用を受けるためには下記に挙げられる一定の条件を満たす必要があります。
配偶者控除の適用要件と注意点
ただし、おしどり贈与(配偶者控除)を適用するには、いくつかの注意点があります。それぞれ解説していきます。
要件①婚姻期間が20年以上
戸籍上の婚姻期間が20年以上であることが条件です。事実婚は対象外となるので、注意が必要です。
要件②居住用不動産または購入資金の贈与
贈与の対象は、現に居住している、または居住の用に供する見込みのある不動産またはその取得資金である必要があります。
要件③贈与後一定期間その住居に居住する
贈与を受けた日から原則として贈与税の申告期限まで、実際にその不動産に居住していることが必要です。
要件④過去に配偶者控除を利用していないこと
この特例は一生に一度しか使えません。過去に同じ特例を受けたことがある場合は再利用できません。
配偶者控除を受けるための申告手続き
配偶者控除を受けるためには、申告手続きをしなければなりません。必要書類や期限と合わせて解説します。
必要な書類と申告の流れ
配偶者控除を適用するには、贈与税の申告書に必要な書類を添付し、所轄の税務署に期限内に提出する必要があります。
- 贈与税の申告書(第一表・第二表)
控除額の適用を明記し、適用の旨を記載します。 - 戸籍謄本
婚姻期間が20年以上であることを証明します。 - 登記事項証明書
贈与の対象が居住用不動産であることを示します。 - 不動産の売買契約書や領収書
購入資金の贈与である場合、その用途を明確にします。 - 住民票の写し
居住実態の確認に用います。
申告書類が揃ったら、税務署へ郵送または電子申告(e-Tax)で提出可能です。
申告の期限と注意点
申告期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。期限を過ぎてしまうと、配偶者控除の適用が認められない場合があります。また、不動産を贈与した際には、贈与契約書の作成とともに不動産の名義変更登記も必要になります。司法書士への依頼が必要になることもあるため、早めに準備を進めましょう。
以上が配偶者控除を受けるための具体的な申告手続きとなります。申告の不備や遅れがないよう、必要書類の確認とスケジュール管理を徹底することが大切です。
夫婦間贈与の節税対策と相続税対策
贈与税は工夫次第で節税することが可能です。ここでは、夫婦間贈与を行う際の節税方法と、相続税対策との関係について見ていきましょう。
贈与税の基礎控除を活用する方法
贈与税の基礎控除は年間110万円です。この控除を毎年活用すれば、長期的に財産の移転が可能になります。たとえば、毎年110万円ずつ現金を贈与すれば、10年間で1,100万円を非課税で配偶者に移転できることになります。暦年課税制度を活かした計画的な贈与は、将来の相続税対策としても有効です。
ただし、形式的に贈与契約書を作成する、名義変更を確実に行うなど、実態を伴う贈与として認識されるよう注意が必要です。
配偶者控除を活用した節税対策
前述のとおり、婚姻期間が20年以上の配偶者に対して居住用不動産等の贈与を行った場合、最大2,000万円まで非課税となる配偶者控除の特例を利用することができます。この制度をうまく活用すれば、財産の大部分を生前に配偶者に移転することも可能です。
ただし、この制度は一生に一度しか使えないため、適用のタイミングや財産の内容を十分に検討してから実行に移す必要があります。
相続税の配偶者軽減措置との違い
相続税には「配偶者の税額軽減」という制度があり、配偶者が相続する財産については、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかかりません(相続税法第19条の2)。
一方、贈与税の配偶者控除は生前贈与に適用される制度です。
両者の主な違いは次のとおりです。
| 比較項目 | 贈与税の配偶者控除 | 相続税の配偶者軽減 |
|---|---|---|
| 対象時期 | 生前贈与 | 相続(被相続人の死亡) |
| 非課税限度額 | 最大2,000万円(+110万円) | 最大1億6,000万円または法定相続分 |
| 利用回数 | 一生に一度限り | 制限なし(相続ごと) |
相続時精算課税制度との併用や、他の制度との比較検討も含め、事前に税理士等へ相談するのが望ましいです。
夫婦間贈与の無申告リスクと税務調査
贈与税の申告を怠ると、思わぬペナルティや税務調査の対象となることがあります。ここでは無申告によるリスクや、実際の税務調査で見られるポイントを整理します。
無申告の贈与税が発覚するケース
以下のような場合、贈与税の無申告が税務署に発覚することがあります。
- 預金や不動産の名義が変更された場合
- 資産の動きが不自然な場合(収入に対して高額な買い物など)
- 税務署の資産調査で贈与履歴が明らかになった場合
銀行口座の監視や、不動産登記情報などの公的データベースを通じて、税務署はかなりの情報を把握しています。
税務署の調査対象となるポイント
税務署の調査対象となるポイントは、以下のとおりです。
- 不動産の取得と資金源の不一致
- 配偶者の急激な預金残高の増加
- 110万円を少し下回る贈与が毎年繰り返されている
- 贈与契約書の作成がない贈与
こうした点が見受けられると、贈与が意図的に隠されていたと判断され、調査対象となる可能性が高まります。
悪質な無申告とその影響
贈与税の申告を意図的に怠り、しかも隠蔽や仮装があった場合には、「重加算税」が課されます。通常の延滞税や加算税に比べ、税率が高くなるため、リスクは非常に大きいです。
申告漏れが発覚した場合のペナルティと対応策
贈与税を申告しなかった場合にはペナルティが発生します。ペナルティとしては、下記内容が挙げられます。
延滞税とは、納付期限に遅れた場合に課される税金です。法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、以下の割合で延滞税が課されます。
令和4年1月1日から12月31日までの期間においては、法定納期限の翌日から2カ月経過する日までは、年2.4%となっています。なお、法定納期限の翌日から2カ月経過した日以後は、年8.7%となっています。
過少申告加算税とは、本税の確定申告を法定納期限内に申告したものの、本来納めるべき納税額より少なかったために、修正申告や更正によって追加の納税額が発生した場合に課される税金です。
過少申告加算税の税率は、追加の納税額に対して10%が課されます。
また、期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分に対しては15%が課されます。
無申告加算税とは、法定納期限までに確定申告をせず、さらに本来であれば納付すべき税額があった場合に課される税金です。
ただし、法定納期限から1カ月以内に自主的に確定申告を行い、納付すべき税額を納め、過去5年に無申告加算税や重加算税を課税されたことがなく、当初期限内申告をする意思があったと認められる場合には、無申告加算税は課税されません。
無申告加算税の税率は、追加の納税額の50万円までに対しては15%が課され、50万円を超える税額に対しては20%が課されます。
なお、税務署から指摘される前に納付した場合には5%の税率となります。
重加算税とは上記3つの税金が課される前提として、事実の全部または一部を仮装・隠蔽により確定申告を行ったと認識された場合に課される税金です。
重加算税の税率は、過少申告加算税や不納付加算税の代わりに追加納税額の35%が課されます。
また、無申告加算税が課される場合には、無申告加算税の代わりに追加納税額の40%が課されます。
さらに、資金の移動をした場合にも贈与と判断されるので、基礎控除額の110万円以下の金額で贈与するようにしておきましょう。
夫婦間で贈与したことを申告しないと上記のようなペナルティを支払う必要がありますので、必ず申告期限内に申告するようにしましょう。
贈与税に関する疑問とよくあるトラブル
夫婦間贈与には、制度や手続き以外にも多くの誤解やトラブルが潜んでいます。以下では、よくある疑問やトラブル事例を紹介します。
専業主婦のへそくりは贈与税の対象になる?
夫の収入をもとに専業主婦が自由に貯めた「へそくり」は、場合によっては贈与とみなされることがあります。特にへそくりの金額が大きく、長期間にわたって蓄積されていた場合は、税務署の調査対象となる可能性があります。
夫婦で貯めた資産の贈与はどう扱われる?
夫婦で共同生活するなかで築いた資産であっても、形式上の名義が一方に偏っている場合、その名義変更や取り分の移動が贈与とみなされるケースがあります。財産形成の経緯や実質的な出資割合を踏まえて、贈与に該当するか慎重に判断する必要があります。
事実婚のパートナーへの贈与は課税対象?
事実婚は法律上の婚姻とは異なるため、贈与税の配偶者控除などの特例は適用されません。したがって、事実婚のパートナーに対して財産を贈与した場合は、たとえ長年の内縁関係であっても、一般の贈与税が課税されます。
夫婦間の贈与トラブルを防ぐためのポイント
以下の対策によって、後の相続時や税務調査時のトラブルを回避することができます。
- 贈与の内容・時期・金額を明文化する(贈与契約書の作成)
- 年間110万円以内の贈与に抑える
- 配偶者控除の適用時は要件と証拠書類を確認
- 贈与後の資産の使途を明確にする
専門家(税理士)に相談すべきタイミングとは?
夫婦間の贈与に関して不明点がある場合は、早めに専門家へ相談することが重要です。たとえば、以下のようなケースでは税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
- 贈与額が年間110万円を超える場合
- 不動産や保険契約など複雑な資産が絡む贈与
- 贈与税申告に不安があるとき
- 将来的な相続対策として贈与を検討している場合
専門家に相談することで、誤った申告や無駄な課税を防ぐだけでなく、より効率的な節税対策や資産承継のプランニングが可能になります。
「円満相続ラボ」では、相続に関する基本知識やトラブル回避の方法をわかりやすくお伝えし、専門家によるサポートを提供しています。円満な相続を実現するための最適なご提案をいたします。
相続に関する疑問がある方には、相続診断士による無料相談窓口もご利用いただけます。どうぞお気軽にご相談ください。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を書いたのは…

弁護士・ライター
中澤 泉(なかざわ いずみ)
弁護士事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続といった幅広い分野の案件を担当した後、メーカーの法務部で企業法務の経験を積んでまいりました。
事務所勤務時にはウェブサイトの立ち上げにも従事し、現在は法律分野を中心にフリーランスのライター・編集者として活動しています。
法律をはじめ、記事執筆やコンテンツ制作のご依頼がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。