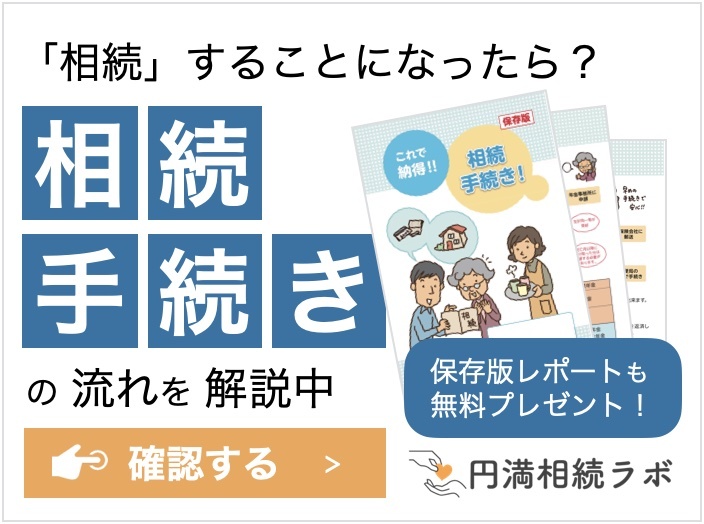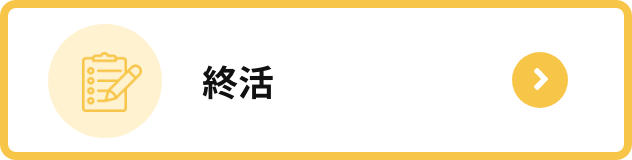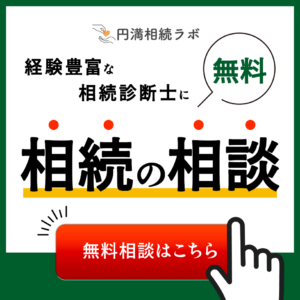贈与が年間110万円以内は非課税?申告不要でも証拠は残しておくべき!

年間110万円までなら贈与税がかからないって本当?
贈与者から贈与を受けた人(受贈者)に課せられる税金が贈与税です。
ただし、贈与を受けたら必ず贈与税が課せられるわけではなく、基礎控除額110万円が用意されています。
贈与された財産の合計額から、基礎控除額を差し引いた残りの金額が贈与税の対象です。この仕組みは「暦年課税」と呼ばれています。なお、1年間の贈与額合計が110万円以下に収まれば、非課税となります。
贈与税の基礎控除額110万円の意味を分かりやすく解説!
贈与税は贈与を受けた人(受贈者)が対象となるので、基礎控除額110万円は「贈与を受けた人」の贈与財産の合計額から差し引きます。
対象となる期間は1年間(1月1日〜12月31日まで)に受け取った、贈与された財産の合計額です。そのため、複数人の贈与者から贈与を受けた場合、それぞれの贈与額が110万円以内に収まっても、贈与税が課される可能性もあります。
例をあげると次の通りです。
(例)2022年3月1日、祖父A・父Bは子(孫)Cにそれぞれ100万円相当の贈与をした。Cは2022年にそれ以外の贈与を受けていない。
- 祖父A:贈与額100万円
- 父B:贈与額100万円
いずれの贈与も基礎控除額110万円を下回っていますが、Cの受け取った1年間の贈与額の合計が110万円を超えています。
(祖父Aの贈与額100万円+父Bの贈与額100万円)-110万円=90万円
このケースでは90万円が課税対象です。
貰った額が年間110万円を超えなければ必ず非課税になる?例外はある?
贈与額が基礎控除額110万円に収まれば、必ず非課税になるとは限りません。次のような例外もあるので注意しましょう。
定期贈与とみなされてしまった場合
定期贈与とは契約書を作成し、一定期間・一定の財産を贈与する方法です。例えば「15年間にわたり毎年100万円をあげる」という贈与契約書を作成して贈与するケースがあげられます。
定期贈与の場合総額1,500万円を贈与する契約が先にあり、それを毎年分割により贈与していくので、分割した贈与額が毎年110万円以下に収まっても、総額1,500万円に対して贈与税が課されます。
毎年、同じ時期・同じ金額を同じ受贈者に対し、継続的に贈与していると、税務署から「まとまったお金を単に分割して支払っている。」と疑われるおそれもあります。
そのため、たとえ1年間の贈与額が110万円以内に収まっても、税務署から申告・納税するよう指摘される可能性があります。
相続時精算課税制度を利用した場合
相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子(孫)へ贈与が行われる際に、子(孫)の選択により利用できる制度です。
この制度には2,500万円の特別控除があり、特別控除の限度額に達するまで贈与税が課されません。ただし、限度額を超えてしまうと超過分に一律20%の贈与税がかかります。
また、本制度は2,500万円分が税金の免除対象となるのではなく、相続が発生するまで納税が猶予される仕組みです。相続時に贈与分も課税対象となります。
その他、相続時精算課税と暦年課税の併用はできず、「贈与額が2,500万円の特別控除を超えたら、今度は基礎控除額110万円を利用する。」という方法も認められません。
そのため、特別控除が適用されなくなった後、たとえ年間の贈与額が110万円以内に収まっても、課税対象となる可能性があります。
貰った額が年間110万円を超えたらどうなる?贈与税はどれくらい?
贈与税がかかる場合、贈与を受けた人(受贈者)が税務署へ申告しなければいけません。贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日の間に申告・納税を行います。
なお、贈与税を申告していなかった場合は「無申告加算税」、贈与税を少なく申告した場合は「過少申告加算税」、納期限に遅れたら「延滞税」等のペナルティが課せられるので気を付けましょう。
贈与税の計算方法は「特例贈与財産」「一般贈与財産」に区分されます。
特例贈与財産
受贈者(贈与年の1月1日で18歳以上の人、2022年3月31日以前の贈与の場合は20歳以上の人)が、直系尊属(例:父母・祖父母等)から贈与で得た財産を対象とします。
(例)1月1日~12月31日までの1年間で、30歳の受贈者が祖父から910万円の贈与を受け取った
910万円-110万円=800万円
800万円×30%-90万円=150万円
贈与税額は150万円となります。
特例贈与財産の税率や控除額は下表の通りです。
| 特例税率 | 基礎控除後の課税価格 | 控除額 |
| 10% | ~200万円 | 0円 |
| 15% | ~400万円 | 10万円 |
| 20% | ~600万円 | 30万円 |
| 30% | ~1,000万円 | 90万円 |
| 40% | ~1,500万円 | 190万円 |
| 45% | ~3,000万円 | 265万円 |
| 50% | ~4,500万円 | 415万円 |
| 55% | 4,500万円超~ | 640万円 |
※国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」を参考に作成
一般贈与財産
受贈者が贈与で得た特例贈与財産以外の財産を対象とします。
(例)1月1日~12月31日までの1年間で、16歳の受贈者が祖父から910万円の贈与を受け取った
910万円-110万円=800万円
800万円×40%-125万円=195万円
贈与税額は195万円となります。
一般贈与財産の税率や控除額は下表の通りです。
| 特例税率 | 基礎控除後の課税価格 | 控除額 |
| 10% | ~200万円 | 0円 |
| 15% | ~300万円 | 10万円 |
| 20% | ~400万円 | 25万円 |
| 30% | ~600万円 | 65万円 |
| 40% | ~1,000万円 | 125万円 |
| 45% | ~1,500万円 | 175万円 |
| 50% | ~3,000万円 | 250万円 |
| 55% | 3,000万円超~ | 400万円 |
※国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」を参考に作成
贈与額が申告不要の年間110万円以下でも証拠は残しておくべき?

税務署から定期贈与と疑われないためにも、毎年、贈与者と受贈者が贈与契約書を作成しましょう。それぞれ契約書に署名・押印して贈与が行われていれば、税務署へ定期贈与ではないことを示す証拠になります。
贈与契約書に記載する内容は、主に次の通りです。
- 贈与者・受贈者の氏名・住所
- 贈与金額
- 贈与する期限
- 贈与方法(指定口座への入金等)
なお、現金を贈与する場合は銀行振り込みを利用した方が良いでしょう。なぜなら、銀行振り込みにすれば履歴が残り、契約書通りの内容で贈与された事実が一目でわかるからです。
110万円以下の生前贈与をするときの注意点を解説!
贈与の際は贈与契約書の作成の他、気を付けなければいけない点も存在します。
贈与税の税負担に注意する
贈与税が暦年課税となるとき、誰でも利用できる控除は、基本的に基礎控除額110万円しかありません。そのため、贈与を受け取ると贈与税が課される可能性は高くなります。
一方、相続税の場合は法定相続人が取得する相続財産に、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が適用されます。
つまり、法定相続人が1人だけでも相続時に3,600万円もの控除額を利用できるわけです。
その他、相続税の税率・控除額は下表の通りです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ‐ |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
※国税庁「相続税の税率」を参考に作成
取得金額によっては7,000万円を超える控除額が適用される場合もあります。一方、贈与税が課される場合の控除額は最高で640万円(特例贈与財産・贈与額4,500万円超の場合)です。
相続税の基礎控除額および課税される場合の控除額と比較してみると、贈与税の基礎控除額や課税される場合の控除額が低い分、贈与の方が重い税負担となるおそれもあります。
相続開始前3年以内の贈与は相続財産にカウントされる
贈与者(被相続人)が基礎控除額110万円を利用し贈与する方法で、コツコツ財産を譲渡し、相続税の節税対策を実行している場合もあります。
しかし、相続開始前3年以内の贈与は110万円を超えなくても、相続人の相続税課税価格にこの贈与額が加算されます(生前贈与加算)。
つまり、相続財産に相続開始前3年以内の贈与分を含め、相続税を計算しなければいけません。そのため、贈与者がこの方法で相続税対策を進めたいならば、なるべく早く贈与を実行に移した方が無難です。
基礎控除額110万円を上手く活用して節税する方法をご紹介
贈与税を軽減したい場合は、条件が限定されているものの、特定の控除制度と基礎控除(110万円)との併用が可能なケースもあるので、参考にしてみてください。4つのケースを取り上げました。
贈与税の配偶者控除制度
居住用の不動産を購入する際、夫婦間での贈与が行われたケースで利用できる控除制度です。基礎控除との併用が可能なので、最高2,110万円まで非課税となります。
| 贈与税の配偶者控除 | 控除制度の内容・条件等 |
| 控除額 | 2,000万円 ※基礎控除と併用可能 |
| 控除対象 | 居住用の不動産、購入資金のいずれでも可 |
| 条件 | ・婚姻期間20年以上 ・受贈する配偶者が住む不動産かその資金 ・受贈配偶者は受贈した翌年の3月15日までに居住、継続して居住する見込みである |
| 注意点 | 同一の配偶者間で、一生に一度のみ適用可 |
| 申請方法 | 贈与税の申告の際に申請 |
住宅取得資金贈与の控除制度
直系尊属(親・祖父母等)から住宅の新築等のため、資金贈与を受けた場合に利用できる控除制度です。基礎控除と併用が可能です。
| 住宅取得資金贈与の控除 | 控除制度の内容・条件等 |
| 控除額 | ・省エネ等住宅:最高1,000万円 ・それ以外の住宅:最高500万円 ※基礎控除と併用可能 |
| 控除対象 | 住宅の新築・取得又は増改築等のため資金贈与を受けた場合 |
| 対象贈与期間 | 2022年1月1日から2023年12月31日まで |
| 受贈者の合計所得金額 | 2,000万円以下 |
| 条件 | 次のいずれかに該当 ・断熱性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上 ・耐震等級2以上もしくは免震建築物 ・高齢者等配慮対策等級3以上 |
| 申請方法 | 贈与税の申告の際に申請 |
教育資金の一括贈与の控除制度
直系尊属が30歳未満の子・孫の教育資金に充てる目的で、教育資金口座開設をした場合に適用される控除制度です。基礎控除と併用が可能です。
| 教育資金の一括贈与の控除 | 控除制度の内容・条件等 |
| 控除額 | ・学校:最高1,500万円 ・学校以外の塾や習い事:最高500万円 ※基礎控除と併用可能 |
| 対象贈与期間 | 2013年4月1日から2023年12月31日まで |
| 条件 | 次のいずれかに該当 ・贈与者から信託受益権を取得した ・贈与者から書面による贈与で取得した金銭を銀行等へ預入した ・贈与者から書面による贈与で取得した金銭等で証券会社等から有価証券を購入した |
| 申請方法 | 受贈者が、口座開設をした金融機関等の営業所等を経由し、教育資金非課税申告書を提出する |
結婚・子育て資金の一括贈与の控除制度
直系尊属が20歳〜50歳未満の子・孫の結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等で結婚・子育て資金口座開設をした場合に適用される控除制度です。基礎控除と併用が可能です。
| 結婚・子育て資金の一括贈与の控除 | 控除制度の内容・条件等 |
| 控除額 | ・結婚以外:最高1,000万円 ・結婚:最高300万円 ※基礎控除と併用可能 |
| 対象贈与期間 | 2015年4月1日から2023年12月31日まで |
| 条件 | 次のいずれかに該当 ・贈与者から信託受益権を取得した ・贈与者から書面による贈与で取得した金銭を銀行等へ預入した ・贈与者から書面による贈与で取得した金銭等で証券会社等から有価証券を購入した |
| 申請方法 | 受贈者が、口座開設をした金融機関等の営業所等を経由し、結婚・子育て資金非課税申告書を提出する |
【2023年に税制改正】従来と何が変わる?
2023年の相続税改正により、生前贈与加算が3年から7年に延長されます。2024年1月1日以降の贈与からの適用です。この改正で相続財産が増加し、相続税が重くなるケースも想定されます。
ただし、2024年1月1日からの適用なので、7年分の延長にカウントされるのは、最短で2031年1月1日の相続からとなります。また、延長された4年間で合計100万円が控除可能です。
もし、贈与税や相続税に関してわからない点があれば、税理士に相談してみましょう。税理士は税に関する豊富な専門知識を有しているので、依頼者の悩みや質問に的確なアドバイスを行ってくれるはずです。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください