空き家の火災保険は必要?保険料相場と加入条件を徹底解説

空き家を所有している方にとって火災保険への加入は重要な検討事項です。本記事では、空き家でも火災保険が必要な理由から保険料相場、加入条件、補償内容まで詳しく解説します。木造・鉄骨造別の保険料目安や保険会社による条件の違い、契約時の告知義務や管理責任についても具体的にご紹介。空き家の火災保険選びで失敗しないためのポイントと注意点を理解し、適切な保険選択ができるようになります。
Contents
1. 空き家の火災保険の必要性とメリット

1.1 空き家でも火災保険は必要な理由
空き家であっても火災保険への加入は資産保護と法的責任の観点から極めて重要です。多くの方が「誰も住んでいないから火災保険は不要」と考えがちですが、これは大きな誤解です。
まず、空き家は人が住んでいる住宅よりも火災リスクが高い傾向にあります。定期的な点検や管理が行き届かないため、電気設備の劣化、配線の老朽化、放火などのリスクが増大します。総務省消防庁の統計によると、空き家での火災件数は年々増加傾向にあり、その多くが電気的要因や放火によるものです。
また、空き家の所有者には民法上の工作物責任が課せられています。空き家から発生した火災が近隣の建物に延焼した場合、重過失がなくても損害賠償責任を負う可能性があります。この責任は非常に重く、場合によっては数千万円から億単位の賠償額となることもあります。
| 空き家の火災リスク要因 | 具体的な内容 | 発生確率 |
| 電気設備の劣化 | 配線の老朽化、漏電による発火 | 高 |
| 放火 | 不審者による意図的な放火 | 中 |
| 自然災害 | 落雷、台風による被害 | 中 |
| 管理不備 | 雑草の繁茂、ゴミの放置 | 高 |
1.2 空き家の火災保険に加入するメリット
空き家の火災保険加入には、単なるリスク回避以上の多面的なメリットがあります。
最も重要なメリットは財産価値の保護です。空き家であっても建物には資産価値があり、相続や売却時の重要な財産となります。火災保険に加入することで、火災や自然災害による損失から大切な資産を守ることができます。
次に、第三者への損害賠償責任をカバーできる点も大きなメリットです。個人賠償責任特約を付帯することで、空き家から発生した事故による近隣への損害を補償できます。これにより、高額な賠償金支払いによる経済的破綻を防ぐことができます。
さらに、火災保険に加入していることで金融機関からの信頼度が向上します。空き家を担保とした融資を受ける際や、将来的な活用計画を立てる際に、適切な保険加入は重要な評価要素となります。
管理面でのメリットとして、保険会社によっては空き家管理サービスの紹介や割引を提供している場合があります。これにより、適切な空き家管理につながり、物件の劣化防止にも寄与します。
1.3 火災保険未加入時のリスク
空き家の火災保険に未加入の場合、所有者が直面するリスクは深刻かつ多岐にわたります。
最も直接的なリスクは全損失の可能性です。火災により空き家が全焼した場合、建物の再建費用はすべて自己負担となります。木造住宅の場合、坪単価60万円から80万円程度の再建費用が必要となり、30坪の住宅であれば1,800万円から2,400万円の負担となります。
さらに深刻なのは近隣への延焼による損害賠償責任です。都市部の住宅密集地では、1件の火災が複数の建物に延焼することが珍しくありません。隣接する住宅が全焼した場合の賠償額は、建物の再建費用に加えて、住民の仮住まい費用、家財道具の補償、営業損失(店舗兼住宅の場合)など、総額で数千万円に達することもあります。
法的リスクとして、刑事責任を問われる可能性もあります。空き家の管理を怠り、それが原因で火災が発生し人的被害が生じた場合、業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。
経済的影響として、保険未加入による損失は相続や家計に長期的な影響を与えます。高額な損害賠償や再建費用の支払いにより、他の資産の売却を余儀なくされたり、借入金による家計圧迫が生じたりする可能性があります。
| 未加入リスクの種類 | 想定される損失額 | 支払い期限 |
| 建物の再建費用 | 1,500万円〜3,000万円 | 即時 |
| 近隣への損害賠償 | 1,000万円〜1億円 | 即時〜1年以内 |
| 仮住まい・宿泊費 | 100万円〜500万円 | 3ヶ月〜2年 |
| 法的手続き費用 | 50万円〜300万円 | 6ヶ月〜3年 |
これらのリスクを総合的に考慮すると、空き家の火災保険加入は必要経費としての投資価値が非常に高いといえます。年間数万円の保険料で、数千万円から億単位の損失リスクを回避できるため、費用対効果の観点からも合理的な選択となります。
2. 空き家の火災保険料相場

空き家の火災保険料は、建物の構造や所在地、補償内容によって大きく変動します。一般的に空き家の保険料は居住中の住宅よりも高く設定される傾向があります。これは空き家特有のリスクが考慮されるためです。
2.1 木造住宅の保険料相場
木造の空き家における火災保険料は、建物の所在地や保険金額によって幅があります。以下の表は一般的な相場の目安です。
| 保険金額 | 年間保険料(目安) | 月額換算 |
| 1,000万円 | 30,000円~50,000円 | 2,500円~4,200円 |
| 1,500万円 | 45,000円~75,000円 | 3,750円~6,250円 |
| 2,000万円 | 60,000円~100,000円 | 5,000円~8,300円 |
木造住宅は火災リスクが高いとされるため、他の構造に比べて保険料が高く設定されるのが一般的です。特に築年数が古い木造住宅の場合、さらに保険料が上がる可能性があります。
2.2 鉄骨造・RC造の保険料相場
鉄骨造や鉄筋コンクリート造(RC造)の空き家は、木造に比べて火災リスクが低いとされるため、保険料も相対的に安くなります。
| 構造 | 保険金額1,000万円あたりの年間保険料(目安) |
| 鉄骨造 | 20,000円~35,000円 |
| RC造 | 15,000円~30,000円 |
鉄骨造やRC造は耐火性能が高いため、木造と比較して保険料を抑えることができるメリットがあります。ただし、空き家であることによる割増は構造に関係なく適用される場合が多いです。
2.3 保険料を左右する要因
空き家の火災保険料は複数の要因によって決定されます。主な要因を以下にまとめました。
| 要因 | 保険料への影響 | 詳細 |
| 建物構造 | 大 | 木造>鉄骨造>RC造の順で保険料が高い |
| 所在地 | 大 | 災害リスクの高い地域は保険料が上がる |
| 築年数 | 中 | 古い建物ほど保険料が高くなる傾向 |
| 空き家期間 | 中 | 長期間空き家の場合、割増料率が適用される |
| 管理状況 | 中 | 定期的な管理の有無で保険料が変わる |
| 補償範囲 | 大 | 火災のみか水災等も含むかで大きく変動 |
特に所在地による影響は大きく、台風や洪水のリスクが高い地域では保険料が大幅に上昇することがあります。また、最寄りの消防署からの距離や周辺環境も保険料算定の要素となります。
空き家期間については、6ヶ月以上の空き家状態が続く場合に割増料率が適用される保険会社が多いです。この割増率は保険会社によって異なりますが、通常の保険料の1.2倍から1.5倍程度となることが一般的です。
保険料を抑えるためには、定期的な建物の点検・清掃を行い、保険会社に適切な管理状況を報告することが重要です。また、複数の保険会社から見積もりを取得し、補償内容と保険料のバランスを比較検討することをおすすめします。
3. 空き家の火災保険加入条件

3.1 一般的な加入条件
空き家の火災保険に加入するためには、通常の住宅用火災保険とは異なる条件が設けられています。空き家の定義として、30日以上連続して人が住んでいない状態の建物が一般的な基準となります。
主な加入条件は以下の通りです:
| 加入条件 | 詳細内容 |
| 建物の構造 | 木造、鉄骨造、RC造など構造に応じた条件設定 |
| 築年数制限 | 築30年以内または築40年以内など保険会社により異なる |
| 管理状況 | 定期的な巡回・清掃・メンテナンスの実施 |
| 建物の状態 | 雨漏りや構造的欠陥がないこと |
| 所有者の居住地 | 空き家から一定距離内に居住していること |
多くの保険会社では、空き家の管理状況を重視しており、月1回以上の点検や清掃を条件としているケースが多く見られます。また、電気・ガス・水道などのライフラインの維持についても確認される場合があります。
3.2 保険会社による条件の違い
火災保険会社によって空き家への対応は大きく異なり、一部の保険会社では空き家への新規加入を受け付けていない場合もあります。主要な保険会社の条件を比較すると以下のような違いがあります:
3.2.1 大手損害保険会社の特徴
東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険、損害保険ジャパンなどの大手保険会社では、比較的厳格な条件を設けています。築年数制限や管理状況の確認が詳細に行われ、保険料も割高に設定される傾向があります。
3.2.2 中堅・地方保険会社の特徴
地域密着型の保険会社では、空き家の事情を理解した柔軟な対応を行うケースがあります。地域特性を考慮した条件設定や、空き家活用予定がある場合の特別プランを提供している会社もあります。
3.2.3 共済の場合
JA共済や全労済などの共済では、組合員・会員に対して比較的寛容な条件で空き家の火災保険を提供している場合があります。ただし、加入には組合員・会員資格が必要となります。
| 保険タイプ | 築年数制限 | 管理頻度要求 | 保険料水準 |
| 大手損保 | 築30年以内 | 月1回以上 | 高め |
| 中堅損保 | 築35年以内 | 月1回以上 | やや高め |
| 共済 | 築40年以内 | 2か月に1回 | 比較的安価 |
3.3 加入時に必要な書類
空き家の火災保険加入時には、通常の住宅用火災保険よりも多くの書類提出が求められます。空き家の状況を正確に把握するため、詳細な書類確認が必要となります。
3.3.1 基本的な必要書類
- 火災保険申込書(空き家用)
- 建物登記簿謄本または登記事項証明書
- 固定資産税納税通知書
- 建物の現況写真(外観・内部)
- 建築確認済証または建築確認通知書
- 住民票除票(前居住者の転出証明)
3.3.2 管理状況に関する書類
空き家の管理状況を証明するために、以下の書類が必要となる場合があります:
- 空き家管理計画書
- 管理業者との契約書(委託管理の場合)
- 定期点検記録書
- 近隣住民からの状況確認書
- 電気・ガス・水道の契約状況証明書
3.3.3 建物の状態に関する書類
建物の安全性や構造的問題がないことを証明するため、以下の書類提出を求められることがあります:
| 書類名 | 取得先 | 用途 |
| 建物状況調査報告書 | 建築士・不動産鑑定士 | 構造的欠陥の有無確認 |
| 既存住宅売買瑕疵保険の検査記録 | 住宅瑕疵担保責任保険法人 | 建物の安全性証明 |
| 耐震診断書 | 建築士事務所 | 耐震性能の確認 |
| シロアリ点検報告書 | 害虫駆除業者 | 建物の健全性確認 |
これらの書類は、空き家の現状と将来的なリスクを評価するために使用され、保険料の算定や補償内容の決定に影響します。書類の不備がある場合は加入を断られる可能性もあるため、事前に必要書類を確認し、準備を整えることが重要です。
4. 空き家の火災保険の補償内容

4.1 基本的な補償範囲
空き家の火災保険では、建物に対する基本的な補償が提供されます。火災、落雷、破裂・爆発による損害は、すべての火災保険で基本補償として含まれています。
多くの保険会社では、基本補償に加えて以下の災害による損害も補償範囲に含めています:
| 補償項目 | 補償内容 | 空き家での注意点 |
| 風災・雹災・雪災 | 台風や竜巻、雹、雪の重みによる損害 | 定期的な点検・管理が必要 |
| 水濡れ | 給排水設備の事故による水濡れ損害 | 水道の元栓管理が重要 |
| 盗難 | 建物付属設備の盗難被害 | 防犯対策の強化が推奨 |
| 破損・汚損 | 偶然な事故による破損や汚損 | 管理頻度により補償可否が変わる場合あり |
ただし、空き家の場合は適切な管理が行われていることが補償の前提となります。長期間放置されている状態での損害については、補償対象外となる可能性があります。
4.2 特約で追加できる補償
基本補償に加えて、空き家の状況に応じて特約を付帯することで、より手厚い補償を受けることができます。
4.2.1 個人賠償責任特約
個人賠償責任特約は空き家所有者にとって重要な補償です。空き家から飛散した瓦や看板などが第三者に損害を与えた場合の賠償責任をカバーします。保険金額は1億円程度に設定されることが一般的です。
4.2.2 施設賠償責任特約
空き家の建物自体に起因する事故による賠償責任を補償します。建物の老朽化による外壁の落下や塀の倒壊などが該当します。
4.2.3 類焼損害特約
空き家からの出火により近隣住宅に延焼した場合の損害を補償する特約です。失火責任法により法的責任がない場合でも、道義的責任として補償を提供できます。
4.2.4 費用保険金特約
災害発生時の様々な諸費用を補償する特約には以下があります:
- 残存物取片づけ費用:損害を受けた建物の取り壊し費用
- 損害防止費用:災害拡大防止のための緊急措置費用
- 仮修理費用:応急的な修理にかかる費用
4.3 地震保険との関係
地震保険は火災保険とセットで加入する必要があり、地震・噴火・津波による損害は火災保険では補償されません。空き家においても地震保険の加入は可能ですが、いくつかの制約があります。
4.3.1 地震保険の補償内容
地震保険では、地震による建物の損害を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階で評価し、それぞれ保険金額の100%、60%、30%、5%が支払われます。
| 損害程度 | 認定基準(建物) | 保険金支払割合 |
| 全損 | 建物の主要構造部の損害額が時価の50%以上 | 100% |
| 大半損 | 建物の主要構造部の損害額が時価の40%以上50%未満 | 60% |
| 小半損 | 建物の主要構造部の損害額が時価の20%以上40%未満 | 30% |
| 一部損 | 建物の主要構造部の損害額が時価の3%以上20%未満 | 5% |
4.3.2 空き家における地震保険の注意点
空き家の地震保険加入にあたっては、以下の点に注意が必要です:
- 保険金額は火災保険金額の30%~50%の範囲内で設定
- 建物1棟につき5,000万円が上限
- 保険料は建物の所在地と構造により決定
- 割引制度(耐震等級割引、免震建築物割引など)の適用可能性
地震保険料は地域の地震リスクに応じて設定されており、東京都や神奈川県などの首都圏では保険料が高く設定されています。一方で、地震保険料控除により所得税・住民税の軽減効果も期待できます。
5. 空き家の火災保険選びのポイント

空き家の火災保険選びでは、通常の住宅用火災保険とは異なる観点での検討が必要です。空き家特有のリスクや条件を理解した上で、最適な保険商品を選択することが重要となります。
5.1 保険会社の比較方法
空き家の火災保険選びでは、保険会社ごとに大きく条件や保険料が異なるため、複数社の比較検討が必須です。比較の際は以下の要素を総合的に判断しましょう。
| 比較項目 | チェックポイント | 重要度 |
| 空き家の引受可否 | 空き家専用商品の有無、引受条件の確認 | 高 |
| 保険料水準 | 同条件での年間保険料の比較 | 高 |
| 補償範囲 | 基本補償と特約の充実度 | 高 |
| 管理義務の内容 | 定期点検や清掃の頻度・内容 | 中 |
| 事故対応体制 | 24時間受付、現地調査の対応力 | 中 |
主要な損害保険会社では、東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険などが空き家向けの商品を提供しています。各社の条件を詳細に比較し、自身の空き家の状況に最も適した保険会社を選択することが大切です。
5.1.1 一括見積もりサービスの活用
効率的な比較のためには、火災保険の一括見積もりサービスの利用も有効です。ただし、空き家の場合は特殊な条件となるため、一般的な一括見積もりサービスでは対応できない場合があります。空き家専門の保険代理店や、空き家対応可能な保険会社に直接問い合わせることをおすすめします。
5.2 補償内容の選び方
空き家の火災保険では、空き家特有のリスクを考慮した補償選択が重要です。人が住んでいない建物は、通常の住宅とは異なるリスクが高くなるため、適切な補償範囲の設定が必要となります。
5.2.1 基本補償の選択基準
| 補償項目 | 空き家での必要性 | 選択理由 |
| 火災・落雷・爆発 | 必須 | 放火リスクが高く、発見が遅れる可能性 |
| 風災・雹災・雪災 | 必須 | 屋根や外壁の損傷発見が遅れがち |
| 水災 | 立地により判断 | ハザードマップでの確認が重要 |
| 破損・汚損 | 推奨 | 不法侵入や器物損壊のリスク |
| 盗難 | 推奨 | 設備機器の盗難リスク |
5.2.2 空き家に特に重要な特約
空き家では以下の特約の付帯を検討しましょう。
- 施設賠償責任特約:空き家の建物や塀の倒壊により第三者に損害を与えた場合の補償
- 残存物取片付け費用特約:火災後の残存物処理費用の補償
- 損害防止費用特約:火災の拡大防止のために支出した費用の補償
- 臨時費用特約:火災発生時の宿泊費や交通費等の補償
施設賠償責任特約は空き家では特に重要な補償です。管理が行き届かない空き家では、建物の劣化による第三者への損害リスクが高くなるためです。
5.3 保険金額の設定方法
適切な保険金額の設定は、過不足のない補償を得るために重要です。保険金額が不足すると十分な補償が受けられず、過剰設定では無駄な保険料を支払うことになります。
5.3.1 建物の評価方法
空き家の保険金額設定では、再調達価額での評価が一般的です。これは同等の建物を新築する場合の費用を基準とした評価方法です。
| 評価方法 | 内容 | メリット・デメリット |
| 再調達価額 | 同等建物の新築費用 | 十分な復旧資金を確保可能、保険料は高め |
| 時価額 | 減価償却を考慮した現在価値 | 保険料は安いが、復旧資金が不足する可能性 |
| 協定再調達価額 | 保険会社と協定した再調達価額 | 適正な評価額で安定した補償、評価に時間要 |
5.3.2 適正な保険金額の算出
建物の保険金額は以下の要素を総合的に考慮して設定します。
- 延床面積:建物の規模を表す基本要素
- 構造:木造、鉄骨造、RC造等による単価の違い
- 築年数:建築年代による仕様の違い
- 地域:建築費の地域差
- 設備:設備機器の種類と価値
一般的な算出方法として、延床面積×構造別単価による概算があります。木造住宅の場合、1平方メートルあたり15万円から20万円程度が目安となりますが、地域や仕様により大きく異なるため、正確な評価には専門家による査定が必要です。
5.3.3 家財の保険金額設定
空き家でも最低限の家財が残っている場合は、家財保険の検討も必要です。空き家の家財評価では以下の点に注意しましょう。
- 実際に保管されている家財の価値を正確に把握
- 貴重品は別途明記が必要
- 不要な家財は事前に処分し、保険金額を適正化
- 季節用品や工具類も評価に含める
空き家の家財保険金額は、居住中の住宅と比較して大幅に少なくなることが一般的です。過大な設定は保険料の無駄となるため、実態に即した適正な金額設定が重要です。
6. 空き家の火災保険加入時の注意点
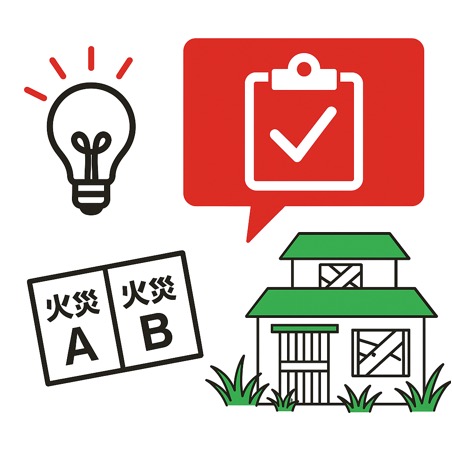
6.1 契約時の告知義務
空き家の火災保険に加入する際は、契約時の告知義務を正確に履行することが極めて重要です。保険会社への告知不備や虚偽申告は、保険金が支払われない原因となる可能性があります。
6.1.1 告知が必要な主な項目
| 告知項目 | 具体的な内容 | 注意点 |
| 建物の使用状況 | 空き家である旨、空き家期間、今後の利用予定 | 居住中と偽らず正確に申告する |
| 建物の構造・築年数 | 木造・鉄骨造・RC造、建築年月 | 登記簿謄本で正確な情報を確認 |
| 建物の管理状況 | 定期的な点検・清掃の実施状況 | 管理の頻度や方法を具体的に説明 |
| 過去の事故歴 | 火災・水害・盗難等の被害経験 | 軽微な損害でも申告が必要 |
特に重要なのは、建物が現在空き家状態であることを正確に伝えることです。居住用住宅として申告した後に空き家になった場合も、速やかに保険会社に連絡して契約内容の変更手続きを行う必要があります。
6.1.2 告知義務違反のリスク
告知義務に違反した場合、以下のようなリスクが発生します:
- 保険契約の解除
- 保険金の支払い拒否
- 既に支払われた保険金の返還請求
- 将来の保険加入への影響
6.2 空き家期間中の管理義務
火災保険に加入した空き家であっても、契約者には適切な管理義務が課せられます。管理を怠った場合、保険金の支払いが制限される可能性があります。
6.2.1 必要な管理業務
| 管理項目 | 推奨頻度 | 具体的な作業内容 |
| 外観点検 | 月1回以上 | 屋根・外壁・雨樋の損傷確認、不法投棄物の除去 |
| 内部点検 | 月1回以上 | 雨漏り・カビ・害虫の発生確認、換気の実施 |
| 設備点検 | 3か月に1回 | 電気・ガス・水道設備の動作確認、配管の凍結防止 |
| 清掃・整備 | 必要に応じて | 室内清掃、庭木の剪定、雑草の除去 |
管理の実施状況を記録しておくことも重要です。点検日時、発見した問題、対処した内容を記録簿に残しておけば、保険金請求時に適切な管理を行っていた証拠として活用できます。
6.2.2 管理不備による保険金減額のリスク
以下のような管理不備があった場合、保険会社は保険金の支払いを拒否または減額する可能性があります:
- 長期間の放置により建物の劣化が進行
- 雨漏りや配管の不具合を放置した結果の損害拡大
- 防犯対策を怠った結果の盗難や破損
- 害虫や小動物による被害の放置
6.3 保険金請求時の注意点
空き家で事故が発生し保険金を請求する際は、通常の住宅とは異なる手続きや注意点があります。適切な対応を行わなければ、保険金の支払いが遅れたり減額されたりする可能性があります。
6.3.1 事故発生時の初動対応
| 対応順序 | 実施内容 | 期限・注意点 |
| 1 | 保険会社への連絡 | 事故発生から遅滞なく(通常24時間以内) |
| 2 | 現場の保全 | 損害状況を変更せず、証拠を保持 |
| 3 | 関係機関への届出 | 火災は消防署、盗難は警察署へ |
| 4 | 損害の拡大防止 | 二次被害を防ぐ応急措置の実施 |
6.3.2 必要書類の準備
保険金請求時には以下の書類が必要となります:
- 保険金請求書
- 事故証明書(消防署・警察署発行)
- 損害状況の写真・動画
- 修理見積書
- 建物の登記簿謄本
- 空き家管理の記録簿
- 近隣住民の証言書(必要に応じて)
6.3.3 査定時の立会いポイント
保険会社の損害査定員が現地調査を行う際は、以下の点に注意して立会いを行います:
- 事故の経緯と発見時の状況を正確に説明
- 日頃の管理状況を記録簿を用いて具体的に報告
- 損害箇所と事故以前の状態の違いを明確に示す
- 査定員の質問には正直かつ詳細に回答
空き家特有の事情として、事故の発見が遅れることが多いため、発見の経緯と事故発生時期の推定根拠を整理して説明できるよう準備しておくことが重要です。
7. 空き家の火災保険でよくある質問

7.1 解体予定の空き家でも加入可能か
解体予定の空き家であっても、解体までの期間中は火災保険への加入が可能です。ただし、保険会社によって条件や制限が異なるため、事前に確認が必要です。
解体予定の空き家における火災保険加入時の主な条件は以下の通りです。
| 項目 | 条件・注意点 |
| 契約期間 | 解体予定日まで、または最長1年間の短期契約 |
| 保険料 | 通常の空き家より割高になる場合がある |
| 告知義務 | 解体予定であることを必ず申告する |
| 管理義務 | 解体まで適切な管理を継続する必要がある |
解体予定の建物でも、隣接する建物への延焼リスクや第三者への損害賠償責任は残るため、火災保険への加入は重要です。特に住宅密集地では、火災が発生した場合の周辺への影響が大きくなる可能性があります。
解体工事開始後は通常の火災保険は適用されないため、工事業者が加入する工事保険でカバーされることになります。解体工事の契約時には、工事期間中の保険についても確認しておくことが大切です。
7.2 賃貸予定の空き家の保険選び
将来的に賃貸に出す予定の空き家では、賃貸開始時の保険切り替えを考慮した保険選びが重要です。空き家期間中と賃貸期間中では、必要な補償内容が異なるためです。
賃貸予定の空き家における火災保険選びのポイントを以下に示します。
| 期間 | 保険の種類 | 主な補償内容 |
| 空き家期間 | 住宅火災保険・住宅総合保険 | 建物の火災・風災・水災等 |
| 賃貸期間 | 賃貸住宅火災保険 | 建物・家賃収入・賠償責任 |
賃貸予定の空き家では、以下の特約の検討も重要です。
- 家賃収入特約:火災等により賃貸できなくなった場合の家賃収入を補償
- 施設賠償責任特約:建物の欠陥により入居者等に損害を与えた場合の賠償責任
- 修繕費用特約:入居者の故意・過失による損害の修繕費用
賃貸開始時には保険の見直しが必要になるため、保険会社によっては空き家から賃貸への切り替えサービスを提供している場合があります。事前に確認しておくことで、スムーズな移行が可能になります。
また、賃貸募集中の空き家では、内見者や工事業者の出入りが増えるため、通常の空き家よりもリスクが高まることも考慮する必要があります。
7.3 相続した空き家の保険手続き
相続により空き家を取得した場合、被相続人が加入していた火災保険の名義変更手続きが必要です。相続発生後速やかに手続きを行わないと、保険金の支払いに支障が生じる可能性があります。
相続した空き家の火災保険手続きの流れは以下の通りです。
7.3.1 名義変更手続きの流れ
| 手順 | 内容 | 必要書類 |
| 1 | 保険会社への連絡 | 保険証券 |
| 2 | 名義変更書類の入手 | 被相続人の死亡診断書 |
| 3 | 必要書類の準備 | 戸籍謄本、印鑑証明書 |
| 4 | 書類の提出 | 相続関係書類一式 |
| 5 | 新契約者での契約継続 | 新契約者の本人確認書類 |
相続した空き家の火災保険で注意すべき点は以下の通りです。
相続発生から3か月以内に名義変更手続きを完了することが一般的な要件となっています。期限を過ぎると保険契約が無効になる場合があるため、早急な対応が必要です。
複数の相続人がいる場合は、不動産の相続人が保険契約を引き継ぐことになります。相続人が決まらない場合でも、暫定的に代表相続人を設定して手続きを進めることが可能です。
7.3.2 相続時の保険見直しポイント
相続を機に保険内容の見直しも検討することが重要です。被相続人の契約内容が現在の建物状況や相続人のニーズに合わない場合があるためです。
- 保険金額の適正性:建物の現在価値に見合った保険金額の設定
- 補償内容の見直し:空き家として使用する場合の適切な補償
- 保険料の比較:他社との保険料比較による最適化
相続した空き家を将来的に売却予定の場合は、売却までの期間を考慮した短期契約も選択肢の一つです。不動産会社と相談しながら、売却時期を見据えた保険選びを行うことが大切です。
8. まとめ
空き家であっても火災保険への加入は重要です。放火や自然災害による被害リスクがあり、未加入時は高額な損害を自己負担することになります。保険料は木造住宅で戸建て年間1万円~6万円程度が相場で、建物の構造や立地条件により変動します。加入時は空き家であることを正しく告知し、定期的な管理を怠らないことが大切です。複数の保険会社を比較検討し、補償内容と保険料のバランスを考慮して最適な火災保険を選択しましょう。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を監修したのは…

合同会社RunSmile 代表社員 愛媛相続診断士協会会長
浜田 政子(はまだ まさこ)
長年保険業に携わっている経験を生かしい、生命保険、相続、終活などコンサル及びライフプラン作成を通じお客様へ常に寄り添い、悩みや相談、希望をお聞きし士業とともに解決へ導く道先案内人として愛媛より全国へ笑顔をお届けする活動しております。
よろしくお願いします。
サイトURL:https://run-smile.com








