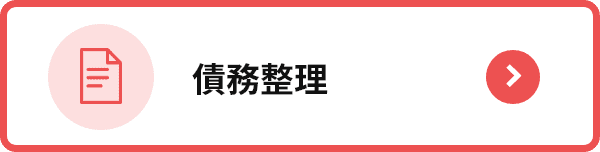家族信託の手続きとは?メリットやデメリット、流れ・費用・活用事例を解説
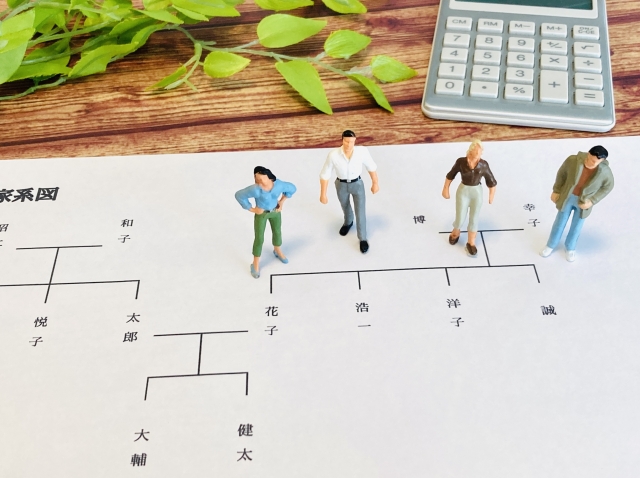
Contents
家族信託の基礎知識と注目される背景
まずは、家族信託がどのようなものであるか、注目されている理由、仕組みと登場人物、必要とするケースなどについて解説します。
家族信託とは何か
家族信託とは、今ある資産(例えば不動産や預金など)を信頼のできる家族に託して、ご自身に代わって、管理・運用などをしてもらうことです。
政府統計(種類別 土地に関する登記の件数及び個数 )によると、信託に関する登記件数は、2015年4,257件、2019年10,071件、2023年20,321件と件数が増加しており、家族信託への注目も、高まっているといえます。
なぜ家族信託が注目されているのか
まず、家族信託は、認知症による資産の凍結を回避する方法として注目を集めています。
認知症による資産の凍結とは、資産の管理・運用・処分ができなくなることで、お金の流れが止まることを意味します。
厚生労働省研究班の調査で、日本の認知症患者数が2022年の443万人を大きく上回り、2030年には推計523万人となる見込みであることが公表されています。
認知症の診断を受けた場合、意思能力を有さないとみなされ、契約などの法律行為は、無効となります(民法3条の2)。そのため土地の売却や、建物を賃貸に供することも困難になるのです。
金融機関は顧客が認知症患者であると判明した場合は、その口座を凍結します。
そのほか保険や証券の解約や、生前贈与といった相続税対策もできなくなりますので、注意が必要です。
認知症の診断を受けて法律行為ができなくなる、口座を凍結される前に、資産を家族信託に切り替えることで、認知症診断で生じえる不利益を回避できるようになります。
次に、家族信託は、任意後見制度に代わる財産管理手段としても、注目を集めています。
任意後見制度もまた、認知症の診断を受ける前に、任意後見契約を締結するのですが、任意後見監督人が第三者となりやすい点や、任意後見契約公正証書に記した内容での財産管理を余儀なくされる点が、家族から見ると自由度が低くデメリットにほかなりませんでした。
家族信託を選ぶと、家族だけが当事者となりえ、認知症の診断を受けても引き続き、状況に合わせた柔軟な資産の運用・管理・処分ができます。
家族信託を選択することは、任意後見制度利用を妨げるものではありませんので、実際に併用される方もおられます。
家族信託には備わっていない身上監護機能を、任意後見制度で補完ができる点も、家族信託の魅力のひとつとなっています。
そして、相続対策の有効な手段としても、熱い視線が注がれています。
家族信託に委ねたあとの資産について、受託者が所有権を有することになるため、委託者が死亡した場合、その資産は遺産分割すべき財産に組み込まれることはなく、相続税もかかりません。
ただし、受益権を持っていた方が死亡した場合は、受益権は相続税の対象となりますので、覚えておきましょう。
遺言では財産の承継者を指定できるのは一代限りとなっていますが、家族信託では受益者を順番で引き継がせることが可能となります。これを受益者連続型家族信託といいます。
例えば、ご自身が建てた家や設立した会社の株式を家族信託に委ね、まずは長男に受託させ、長男が亡くなった場合は次男に受託させるという契約にすることで、長男の配偶者や子に所有権が移転しないように調整することが可能となります。
家族信託の仕組みと主な登場人物
家族信託においては、少なくとも次の3者が登場し、関与することになります。
- 委託者
- 受託者
- 受益者
家族信託における委託者とは、資産の所有者で、信頼できる家族に託す人となります。受託者とは、委託者から家族信託を通じ財産の管理・運用・処分を任された人です。
そして受益者は、家族信託に付された財産から利益を受ける権利(受益権)を有している人となります。
委託者は受託者に対し、どの財産をどのように管理・運用・処分するかについて、信託契約書で指定することが可能です。
また、委託者は受託者についての選任権を持ち、適切ではなかったと判断した場合は、合意や契約に基づき解任し、新しい受託者を選ぶ権利も有しています(信託法58条)。
受託者は、委託者から財産の管理・運用・処分を任せられた人で、信託契約書で方法の指定を受けた場合は、その内容に忠実に従い、管理・運用・処分する義務を負います。
そして、受益者は、受託者による財産の管理・運用・処分で発生した利益を得る人です。
委託者が受益者となることもできますし(自益信託)、委託者ご自身を含めて夫婦で受益者となることも、ご自身で受け取ることはせずお孫さんを受益者に設定することも可能です(他益信託)。
家族信託が必要なケースと不要なケース
本項では家族信託が必要なケースを4つ、 家族信託が不要なケースを3つ、ご紹介します。
家族信託が必要なケース1 要資産保護
家族信託は、資産保護に有効で、多額の資産を保有している方、高収入を得ている方、事業会社を営んでいる方は、活用すべき制度です。
遺産分割により、広大な土地は分筆されて狭い土地に変わり、保有していた会社の株式が分散し経営権を失い、相続税納付のために資産を売却して他人の手に渡るといった事態を回避したいと思う場合に有効です。
家族信託で、これまで築き上げてきた資産をそのまま維持させることができます。
資産を家族信託に委ねることで、その名義が受託者に変わりますので、個人保証していた事業会社が破産・倒産しても、債務者に資産をとられる心配がなくなります。
家族信託が必要なケース2 争族対策
家族信託は、大切なご家族を相続で争族にしないようにすることも可能です。
資産保有者である一家の長が家族会議を開き「今ある資産をバラバラにしない」「収益は推定相続人全員に平等に配る」「相続税が発生しない」などと表明・説得すれば、相続ではなく家族信託で話がまとまる可能性が高まります。
結果、相続手続きの簡略化や、家族信託に委ねなかった相続財産についても、揉めることなく遺産分割が進むことを期待できるのです。
家族信託が必要なケース3 相続税対策
家族信託では、相続税の発生を回避できる設計を立てることも可能で、全資産のうち、価値のある不動産をすべて家族信託に委ねることで、多額の相続税が発生するのを防ぐことができます。
国税庁によると相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」としていますので、頭の片隅に置いておきましょう。
家族信託が必要なケース4 経済的サポート
家族信託財産の管理・運用・処分によって得られる収益を、お子さんやお孫さんの教育や医療、住宅、生活費に充てるよう、指定することもできます。
現在、未成年の子がいる、身体的・精神的な障がいや難病等を抱えていて、社会生活を送るうえで、何かと制約を受けることが多いご家族がいるのであれば、収益物件を信託に回し、そこから得た金銭を充てて、ご家族が困らないように設計することも可能なのです。
家族信託が不要なケース1 資産が少ない
家族の資産が自宅や車などしかなく、管理も簡単に済む場合は、家族信託を設立して得られるメリットは、ほぼないに等しいでしょう。
家族信託の手続きや、その管理・運用・処分にはコストと時間がかかりますので、資産が多く、管理しきれないものでなければ、コストや時間をかけて管理する必要性はないはずです。
家族信託が不要なケース2 相続で揉める可能性なし
家族の仲が良く、信頼関係があり、相続で揉めることがなさそうであれば、家族信託を検討しなくても問題ないでしょう。
推定相続人全員で「現金だけ分割して、不動産は長兄が管理する」などと話がまとまっていて、資産をバラバラにすることなく大切に管理してもらえるという確信が持てているなら、家族信託は不要と思料します。
家族信託が不要なケース3 倒産隔離の必要なし
家族信託で使用する信託口口座には、倒産隔離機能も備わっているのですが、事業会社を営んでおり個人保証で多額の借金がある場合などに有効です。
倒産によって資産を債権者に取られてしまうおそれが現状ないのであれば、家族信託手続きによる対策をしなくても問題はないはずです。
家族信託を始める前に考慮すべきポイント
本章では、家族信託の手続きを開始する前に、考えていただきたいポイントについて、解説します。
信託を始める目的と動機の明確化
前章で解説したように、認知症による資産の凍結を回避するため、未成年の子、障がいや難病のある子や孫の経済的サポートを行うため、事業会社の倒産などから家族の資産を守るためなど「なぜ家族信託を始めるのか?」その目的と動機を明確にしましょう。
目的や動機に合わせて、家族信託のかたちを設計し、信託契約書に記載すれば、望む管理・運用・処分が実現しやすくなります。
家族信託の対象となる財産の選定
財産目録があればそれを基に、なければ作成して、家族信託に委ねる財産の選定を行います。
家族信託に委ねることができる資産と、できない資産がありますので、以下、覚えておきましょう。
家族信託へ移行可能な財産
家族信託の対象となりうる主な資産例は、次のとおりです。
- 現金
- 株式
- 国債
- 不動産
- 知的財産権(特許権・著作権など)
家族信託に移行できない財産
家族信託の対象となりえない資産例は、以下となっています。
- 預貯金
- 債務
- 農地
- 年金受給権
預貯金は解約して現金化し、農地は宅地などにする農地転用の手続きを行うことで家族信託に委ねることが可能です。
家族信託における受託者・受益者の選び方とその責任
ここでは、受託者や受益者を誰にすべきか、受託者となった場合に生じえる責任について解説していきます。
家族信託における受託者の選び方
受託者は未成年者でないことを要します(信託法7条)が、基本的に信頼できる方、任務を全うできる方なら問題ありません。
受益者が受託者となるような家族信託を設計しないよう、注意する必要があります。
なぜなら、信託の終了事由に「受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき」という定めがあり(信託法163条)、家族信託の長期継続が難しくなるからです。
これは、家族信託における「1年ルール」と言われています。
家族信託における受益者の選び方
受益者は誰でもなることができます。個人や法人、未成年者や胎児も設定可能なのです。委託者自身も設定すれば、受益者になることができますし、ひとりだけではなく委託者夫婦や、受託者以外の家族全員を受益者にするなど、複数人を設定することもできます。
大切なのは家族信託を始めようと決めたきっかけに沿って、受益者を指定することです。
家族信託における受託者の責任
受託者が、委託者の期待に反してその任務を怠り、信託財産に損失や変更を生じさせた場合、信託法40条では受益者は、その責任を問えるとしています。受託者は、損失補填や原状回復というかたちで、責任をとらなければなりません。
そのため受託者は信頼できる方、任務を全うできる方が適役なのです。
家族信託の期間と終了後の財産帰属先の設定
家族信託の期間は、信託契約書に明記することで定めることが可能ですが、信託法などで定められた期間に関する制限はありません。
ただし、受益者連続型家族信託に関しては特例が設けられており、信託設定時から30年を経過し、以後に他の受益者が受益権を順次承継した場合は、その受益者の死亡もしくは受益権の消滅をもって信託が終了することになります(信託法91条)。
これは、家族信託における「30年ルール」といわれていますので、前出の1年ルールとともに覚えておきましょう。
家族間での合意形成と信託内容の確認
委託者は、まず受託者に家族信託を行いたい旨と、その目的や動機、受託者としての任務内容、報酬、責任が生じることも併せて説明し、打診を行います。
次に家族信託に委ねなければ、相続財産となるはずだった資産については、将来的にトラブルにならないように、推定相続人を集め、家族会議を開き、合意を取り付けることが大切です。その際、家族信託にするメリット・デメリットも説明すべきです。
なお、受益者については、本人の意向に関係なく設定することができます。
家族全員の同意を得たら、家族信託手続きへと進めていきます。
家族信託手続きの全体的な流れと準備
本章では、家族信託を実行に移す際の手続きの流れや、注意点について言及していきます。
家族信託に必要な契約書の作成
前項の家族会議で取り決めを行った内容を「信託契約書」に反映させていきます。本項では、信託契約書作成の手順やポイントをまとめていきます。
信託契約書作成のポイント
- タイトルを「信託契約書」の5文字とする
- 委託者と受託者を住所含め明記し委託者と受託者が契約を交わす内容にする
- 誤字・脱字で意味合いなどが変わり無効となる場合もあるので注意する
信託契約書に記載すべき内容
信託契約書には委託者と受託者で合意をした次の内容等を記します。
- 契約の趣旨(委託者が財産を受託者に信託し受託者が引き受けた旨を記載する)
- 契約の目的(なぜ信託契約を交わすのかをわかりやすくまとめる)
- 委託者・受託者・受益者の情報(住所・氏名・生年月日を記載する)
- 家族信託に委ねる財産(すべて記載する)
- 財産の管理・運用・処分方法(できるかぎりわかりやすく書く)
- 受託者の権限と義務と責任(信託法26条~47条を参考にする)
- 受託者の報酬
- 信託の終了事由(信託法163条を参考にする)
- 家族信託に委ねた財産の帰属先(信託終了後に財産を誰の所有に戻すのかを書く)
仕事柄、法律に詳しい、契約実務に慣れている場合は、ご自身で準備されるといいのですが、ネット上にあるひな形を入手して見よう見まねで作成するレベルでしたら、専門家や公証人に相談して、作成したほうが安心です。
ひな形は個々のケースに対応したものではありませんので、そのまま流用するのはおすすめできません。
信託契約書は公正証書にする
家族信託で大切なことは、家族間の合意を得ることと第三者に財産を奪われることがないように対抗できるようにすることです。信託契約書に不備があると、法的に無効となる場合があり、財産を奪われかねません。
弁護士や行政書士、司法書士(登記を伴う場合)に契約書作成と公正役場での手続きもお願いすると、間違いありません。
契約書だけ作成してもらい、ご家族で公証役場に行き、署名・押印を行う方法もありますが、信託口口座(しんたくぐちこうざ 詳細は次項)の開設について、契約書を作成した専門家を通じて行うと決めている金融機関もあります。
したがって、専門家にすべてお願いしたほうがスムーズです。
信託用の銀行口座開設と注意点
法的に有効な信託契約書が完成したら、ここからは受託者が中心となって動くことになります。まずは、信託口口座の開設手続きを行います。
金融機関で信託口口座を開設
信託口口座とは、端的に表すと家族信託用の口座のことで、家族信託契約に基づき選任された受託者が、自身の固有財産と委託者から引き受けた信託財産であるお金をきっちりと分けて管理するための口座です。
信託口口座は、受託者が死亡した場合や差し押さえを受けた場合でも口座が凍結されることがありません。
金融機関にもよりますが、開設するためには次の書類等が必要です。
- 信託契約書
- 届出印
- 身分証明書
事前に金融機関のホームページを確認したり、電話で問い合わせると持参すべき書類を教えてくれるでしょう。
開設を終えたら、委託者と受託者が連携して管理・運用・処分をお願いすることにしたお金を移します。
信託口口座を開設できない金融機関もあるので注意
信託口口座は、すべての銀行が取り扱っているわけではありません。
普段、利用している銀行に問い合わせて取り扱いがなければ、最寄りの信託銀行や信託契約書の作成をお願いした専門家に訊いてみることをおすすめします。
信託口口座でも「倒産隔離機能」を有していない場合もありますので、細心の注意が必要です。金融機関に必要書類を確認する前に、必要であれば倒産隔離機能を有しているかどうかも尋ねるようにします。
信託口口座を取り扱っていない金融機関から、信託専用口座の開設を勧められることはないと思いますが、信託専用口座は信託口口座とは別物であり、受託者が死亡すると凍結されてしまいますので、必ず「信託口口座」の開設を行わなければなりません。
不動産を信託する際の登記手続き
家族信託に委ねる財産に不動産がある場合、登記が必要となります。
信託契約書を作成しても、登記をしなければ第三者に権利を主張できません。そのため、できるかぎり早急に法務局への登記も行うようにしてください。
以下、手順や必要書類について、確認します。
法務局での申請手順
不動産の登記は、住所を管轄する法務局の不動産登記部門で行います。そして家族信託に伴う不動産登記は①所有権移転登記、②信託登記という2つの申請を同時に行います。
本来は、不動産登記の申請書様式についてというページで記載例などを確認できるのですが、信託に伴う登記については、法務局に直接、問い合わせるようにしましょう。
不動産登記を依頼者に代わって行えるのは、司法書士だけですので、信託契約書の作成も含めて依頼されると、登記完了まで安心して任せることができます。
登記に必要な書類
不動産登記を行う場合は、以下の書類などが必要といわれています。
- 登記申請書(所有権移転登記、信託登記)
- 信託契約書公正証書
- 信託目録に記録すべき情報
- 登記済証または登記識別情報
- 固定資産税評価証明書
- 委託者の印鑑証明書・実印
- 受託者の住民票・実印(認印も可)
- 委託者と受託者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
上記以外にも必要なものが出てくる場合もありますので、住所を管轄する法務局の不動産登記部門や、信託契約書作成を依頼した司法書士にお尋ねください。
家族信託における不動産登記の登録免許税
信託に伴う不動産登記では、所有権移転登記の登録免許税が不要となります。信託登記における登録免許税は、次のとおりです。
- 土地 固定資産税評価額の0.4%
- 建物 固定資産税評価額の0.3%
信託開始に伴う実務的手続き
信託口口座の開設と不動産の信託登記を終えたら、受託者が以下の事務を行っていきます。
保険・公共料金の名義変更
受託者は、委託者から引き受けた不動産の火災保険・地震保険、公共料金の契約者の名義と引き落とし口座の変更を行います。引き落とし口座は、先で作成した信託口口座にします。
収益物件の契約関係の整理
委託者から引き受けた財産の中に収益物件があれば、居住者などに新所有者として振込先が信託口口座に変わる旨も通知します。
収益物件でも保険や公共料金、管理会社などとも契約をしているはずですので、名義や引き落とし口座の変更を行う必要があります。
家族信託 受託者の管理・運用・処分に関する業務
本章では、主に家族信託の受託者に向けて、管理業務に必要な情報をまとめていきます。
受託者による契約締結と注意点
信託開始後、信託財産について何かしらの契約を行う場合は、すべての相手方に「受託者」であることを明確に伝え、書面にも「受託者 氏名」と肩書を併記して締結する必要があります。
信託財産の追加と管理方法
信託開始後、当初想定していた家族信託による恩恵を受益者が手に入れられないケースも起こりえます。
そういった事態を考慮して、家族信託では委託者・受託者双方が合意すれば家族信託に委ねる資産を新たに追加することが可能です。
これを追加信託といいますので、このような管理手法があることも、委託者・受託者ともに覚えておかれることが望ましいです。
信託帳簿や信託資産の状況報告書の作成と保管
信託帳簿とは、信託財産に関するお金の流れを示した帳簿のことで、受託者は書類または電磁的記録により作成しなければなりません。
特に受益者の教育や医療、住宅、生活費に供する場合は都度、支出額や使途、支払先などを記録として残しておくことが肝要です。
信託資産の状況報告書とは、主に貸借対照表、損益計算書のことで、そのほか法務省令で定める書類も合わせて年に一度、作成することが求められています。
信託帳簿、信託資産の状況報告書と受託者が作成したものだけではなく、信託財産に関して契約の相手方などから取得した書類も、作成・取得の日から10年間、保管する義務があります(信託法37条)。
収益不動産の運用と収入管理
信託を受けたアパートやマンションの一室など、不動産物件から収益を得ている場合は、受託者は大家として管理会社や賃貸希望者と契約を交わしたり、入居者の求めに応じて必要な修繕を行います。
受託者は物件収入を維持管理していく責任がありますので、委託者が元気なうちに、教えを請い、物件管理の基本や収益を上げるコツを学んでおくとプラスになります。
また、受託者は税務署に毎年1月31日までに「信託の計算書」を提出しなければなりません。ただし、収益が年間3万円以下であれば、その提出義務を免れます。
信託終了時の対応と注意点

家族信託も、委託者と受益者の合意や、信託法163条及び信託契約書に記載された「信託の終了事由」などに従い、終了のときを迎えます。
本章では、受託者が信託終了に伴い、行うべき清算について、説明します。
清算受託者による清算業務の内容
家族信託は終了しても、それで終わりではありません。信託を清算し終えてはじめて、その幕を引くことが可能となります。
受託者は、清算受託者として現務整理(結了)などを行います。
現務整理(結了)
これまで行ってきた信託財産の運用・管理・処分をすべてストップさせ、清算すべき債権・債務と残余財産があるかを確認し、整理します。
債権債務清算
信託財産について、債権があれば清算受託者は債務者から回収し(取り立て)、債務があれば債権者に弁済します。
残余財産の処理
債権・債務を清算してもなお、残余財産があれば、信託契約書の取り決めに従い、受益者や帰属先に引き渡します。
信託財産を帰属先に引き渡す際の不動産登記方法と特例
通常、委託者兼受益者であった父親が死亡し、信託が終了し、帰属先が母親であった場合、受託者である長男は、母親と共同で所有者移転登記申請を行い、信託登記の抹消を受託者として単独で申請します。
しかし、父親が委託者兼受益者で、一人息子が受託者、母親も既に他界していた場合、父親の死亡で家族信託が終了し、残余財産である不動産の帰属先が相続によって清算受託者である息子となります。
息子が受託者兼帰属者(同一人物)となるこのケースにおいては、共同ではなく単独で信託財産から固有財産に変更となる旨の登記を行うのが適切で、登録免許税も課さない旨も合わせて確認されました(法務省民二第16号令和6年1月10日付書面)。
専門家の支援を受ける重要性
信託財産は、漫然と管理しているだけでは目減りしていく一方ですし、運用するにしてもリスクが生じます。信託財産の管理・運用・処分はもちろん、信託が終了して清算する際も専門家のサポートがなければ、スムーズかつ正確に手続きを行うのは至難の業です。
円満相続ラボは、相続・終活に詳しい相続診断士に無料で相談できるほか、家族信託のプロとも提携しています。
また弁護士、司法書士、税理士とも提携しており、信託契約書作成や不動産登記、税のお悩みについてもお答えできますので、電話・メールでお気軽にお問合せください。
家族信託の費用と税金に関する知識
資産を家族信託に移す場合、その費用はいかほどになり、どのような名目の税金が課されるのでしょうか?本章では、家族信託手続きにかかる実費、税金について、一例をご紹介していきます。
家族信託の実費と専門家報酬
本項では、公証役場での公正証書作成、法務局での不動産登記、弁護士などに1時間「家族信託手続き」について相談した場合の費用について、ご紹介します。
役所から取得する書類
信託契約書作成時、不動産登記申請時に必要となります。
- 戸籍謄本または抄本 1通450円
- 印鑑証明書 1通300円
- 固定資産税評価証明書 300円
公正証書作成
日本公証人連合会では、
契約やその他の法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的の価額により定められています
と説明されています。一例を挙げますと、目的価額が1,000万円~3,000万円の場合、手数料は23,000円となっています。
信託口口座開設手数料
金融機関により異なりますが、55,000円、110,000円など決して安い価格帯ではありません。
登記手数料
信託に伴う不動産登記では、所有権移転登記の登録免許税が不要となります。信託登記における登録免許税は、次のとおりで、不動産ごとに課されます。
- 土地 固定資産税評価額の0.4%
- 建物 固定資産税評価額の0.3%
専門家への相談費用
各弁護士事務所が定めた報酬規程によりますが、日本弁護士連合会によると、顧問契約なし特殊専門分野の相談料は、1時間あたりの平均額が17,634円となっています。
司法書士や行政書士の場合も、事務所によりますが、1時間あたり10,000円は見ておきましょう。
信託に伴う税金の種類と対策
本項では、家族信託手続きにおける税金について、まとめます。
贈与税・相続税・所得税・登録免許税など
家族信託にかかる税金については、基本、信託財産から支払われることになるのですが、委託者など登場人物別に、どのような税金がかかるのかについて、下表にまとめました。
| 委託者 | 原則発生しない |
| 受託者 | 登録免許税固定資産税 |
| 受益者 | 贈与税(委託者兼受益者を除く) 所得税 譲渡所得税(資産を売却した場合) 相続税(委託者死亡後に受益者になった人に課税される) |
家族信託を自分でする場合と専門家に依頼する場合の費用比較
家族信託に委ねる資産の内容、依頼する専門家などによって異なりますが、実費以外に100万円前後がかかると考えておきましょう。
費用はかかりますが、専門家による知識・情報の提供、価値のある提案、プロによる書類作成、各所への連絡・相談の代行をしてくれるため、依頼人が手間暇をかけることはありません。
間違った場合は、やり直すための時間に費用もダブルでかかることを考慮すると、最初から専門家に委ねて、お任せしたほうが賢いです。
自分で手続きする場合のメリット・デメリット
家族信託手続きは「自分でできたら」と思われている方も多いと思いますので、本章では、専門家にお願いする場合と自分で手続きする場合のメリット・デメリットをお伝えしていきます。
コスト削減やプライバシー保持の利点
家族信託手続きは専門性が高く、長期化も考えられますので、専門家にお願いすると、やはり100万円前後はかかります。
弁護士など業務を受任する専門家は当然、守秘義務についても契約時に自ら課すはずですので基本、心配する必要はありませんが、財産目録、家族構成、家族しか知りえない関係性や障がい、病気についても知らせる必要があるケースも想定できます。
手間暇はかかりますが、ご自身でされると、その分の費用が削減可能ですし、いわゆる家庭の事情を第三者に知られることもありませんので、自力で対応する場合は、コスト・プライバシー面にメリットがあります。
契約書ミスやトラブルリスクの懸念
家族信託手続きには、信託契約書が必要ですが、誤字・脱字が許されないのはもちろん、内容の不備があることで、信託口口座の開設ができない、不動産の登記ができない事態は起こりえます。
公正証書にする際、公証人は家族信託に委ねる資産について知る由もありませんので、1つだけ不動産が抜けたまま公証に至る可能性があります。そうなると信託契約書にない不動産の登記はできませんので、仕切り直しとなるのです。
多くの受託者は「一度くらいは仕方がない」と理解を示すと思いますが、なかには「面倒くさい」と感じ、受託者を辞退するなどのトラブルも起こりえますので、ご自身で契約書を作成する場合は家族全員で点検するなど、慎重な対応が求められます。
専門家に依頼するメリットと安心感
専門家に依頼すると、費用はかかり、資産状況などを開示することになりますが、倫理観の高い専門家が業務上知りえた秘密を故意に漏らすことはありません。
契約書についても、社内で稟議して誤字・脱字、内容漏れがないかなどについても確認したうえ、公証人にも意見を求めますので、契約書のミスはほぼないといっていいでしょう。
自分で行った場合に起こりうる失敗例
前項までの説明で、ご自身で家族信託手続きを推し進める際には、細心の注意が必要ということがおわかりいただけたと思うのですが、以下、よくある失敗例を4つ、ご紹介していきます。
書類の不備
例えば、家族信託手続きに必要な書類が足りない(取得していない)、別の書類を取得している、書類の内容に誤りがあると手続きができず、交通費だけが飛んでしまうこともありえます。
もちろん交通費だけではなく、手続きの遅延、後日改めて時間を設定してもらうなど受託者、公証役場や金融機関の担当者にも迷惑をかけることになりますので、避けたいところです。
法的要件の無視
家族信託は、信託法や不動産登記法などに基づく法的な手続きであり、法律をよく読み込み、正しく解釈する力が求められます。
信託法などに示されている要件などを読み込むことなく(無視)、読み込んでも都合よく解釈し(誤解)結果、要件をクリアしないまま手続きを推し進め、途中で信託の効力が失われたり、問題が発生したりして、失敗に終わる可能性が高まります。
目的や目標の不適切な設定
家族信託は「相続税対策になる」「子や孫のためになる」などと漠然とした目的・曖昧な目標設定で、手続きを推し進めると失敗します。
家族信託に資産を委ねた結果、どのような収益が入り、受益者がどのようなメリットを享受できるかなど具体的な目的・目標を立てて、全体図を設計してあげることではじめて、正しく機能することになるのです。
相続人の権利の侵害
家族信託に委ねようとする資産の中には、推定相続人が将来的に得られるはずだった相続分や遺留分が含まれていますので、権利を侵害されたと憤る家族がいても、おかしくはありません。
受益者とならない推定相続人が、家族信託手続きに反対する可能性は濃厚です。ときには、反対する推定相続人を説得したり、対価となりえるような条件を提示してあげる必要も出てくるでしょう。
家族のための家族信託で、家族が分断しないよう、相談する順番や反対表明してきた場合の代案を事前によく考え、争いとならないように手続きを行う必要があります。
家族信託を成功させるためのポイント
本章では、家族信託を成功させるためのポイントについて、お伝えしていきます。
信託契約書の記載方法と公証対応
信託契約書は、枚数が嵩んでも構いませんので見やすいフォント・文字サイズにして、適切な行間を空けるように心がけましょう。小さい文字で行間も詰めてしまうと、誤字・脱字、内容の不備も見逃しやすくなります。
公証役場に持って行く契約書は1通で、原本は公証役場が保管します。委託者と受託者は各1通、正本の交付を受けましょう。謄本は必要に応じていただくようにします。
いきなり契約書を持って行かず、公証役場の方に素案を見てもらえますので、事前に必ず相談するようにしましょう。
家族信託が強制終了となるケース
信託の目的を達成したとき、受託者が受益権の全部を1年以上、固有財産で保有するに至ったとき、受託者不在となり1年以上、新しい受託者が就任しなかったときに、家族信託は強制終了となりえます。
対応できない手続きの存在
家族信託における受託者は、委ねられた範囲で財産管理に関する手続きを行うことは可能ですが、委託者が認知症の診断を受けたあとの身上監護に関する手続きはできませんので、総合的な支援を受けたい場合は、成年後見制度の併用も検討しましょう。
身上監護とは,ご本人の生活や健康の維持,療養等に関する仕事です。例えば,ご本人の住まいの確保,生活環境の整備,施設に入所する契約,ご本人の治療や入院の手続を行うことですが,食事の世話や実際の介護などは含まれていません
引用元:旭川家庭裁判所:成年後見Q&A
適切な受託者と権限設定の重要性
家族とはいえ、散財傾向が強い、多額の借り入れがある方を受託者にするのは適切とは言いきれません。また不動産の管理など、巡回や関係各所への連絡などこまめに対応できる方が適任で、自発的に動けない方、対応が遅い方だと資産を目減りさせてしまうでしょう。
不動産や知的所有権などは、信託契約書上、処分権限を除外しておくことを推奨します。不適切な受託者だった場合、勝手に売却処分してしまう可能性があるためです。
手間はかかりますが、信託契約書には細かく資産一つひとつに、どのような権限を付与するかを明記することが大切です。
専門知識を要する場合も
例えば、特許権が家族信託に組み込まれていると、ライセンス契約を求めてきた企業などに対し、技術を教授したり、価格交渉に応じたりしなければなりません。
そのため、技術の基礎はもちろん応用方法、市場価値などの専門知識を習得している方でないと受託者は務まりません。
家族信託に関するよくある質問と対応策
ここでは、円満相続ラボによく寄せられる質問と回答を、ご紹介していきます。
家族信託手続きは個人でも可能か?
はい。個人でも家族信託の手続きは可能です。しかし、信託契約書の作成、公証役場での手続き、不動産の登記などは、専門家に依頼したほうが間違いがなくスムーズです。
家族信託が「危険」と言われる理由とは?
家族信託に委ねる資産には通常、相続権や遺留分権があるため、反対する推定相続人が出てきてもおかしくありません。
家族信託をめぐり家庭内が分断し、相続開始前に争族となる危険性があるからです。
他の認知症対策との違い
任意成年後見と家族信託の違いは、下表のとおりです。
| 任意後見制度 | 家族信託 | |
| 当事者 | 家族(本人・任意後見人) 第三者(任意後見監督人) | 家族だけ |
| 契約内容 | 任意後見契約 | 信託契約 |
| 財産管理者 | 任意後見人 | 受託者 |
| 財産管理の自由度 | 低 | 高 |
委託者が死亡した後の処理
委託者が死亡した場合、以下の処理ケースが考えられます。
- 委託者=受益者(自益信託)の場合→信託は継続し受益者の権利が相続開始となる
- 受益者連続型家族信託の場合→次の順位の承継者に引き継がれ相続税が発生する
- 信託契約書上の終了事由に該当→信託は終了となり清算に入る
一般家庭にとっての必要性
親子、兄弟姉妹の仲が良好ではなく、将来的に相続で揉めることが予見できる場合は、たとえ自宅1軒だけが資産だったとしても、家族信託に委ねて円満に引き継いでもらうという意味合いでは、家族信託を利用するのも悪くはありません。
家族への切り出し方の工夫
全員集めて、いきなり切り出すよりも一人ひとりに相談すると、家族間の意見の対立やトラブルを誘発しにくいのは、たしかです。
配偶者そして信頼できる子、遠方にいる子の順で話していき、意見交換しながら、ゆっくりと外堀を埋めたほうがいいでしょう。
切り出すときの理由は、次章の活用例を参考にしてみてください。
家族信託の活用事例と他制度との比較
本章では、上手に家族信託を活用するための事例を、挙げていきます。
障がい者支援としての活用例
障がいのために、フルタイムで働けない次男を受益者にして、収益物件を家族信託に委ね、長男が受託者として、収益を管理している。
今は実家に住んでおり、本人の障害年金やパートの収入があるため、生活には困っていないが、将来の万が一の事態に備えて、ストックしている。
事業承継での活用例
自ら経営する会社の後継者を三男にすると決めていたが、経営を任せるのは時期尚早と考えていたところ、株式を家族信託に委ねることができるとわかり、受託者を顧問弁護士にして、自分を委託者兼受益者にした。
まだまだ先の事ではあるが、信託契約書には病気やケガで経営ができなくなったとき、認知症を発症したとき、死亡したときに受益権が三男に移るように設定し、遠く離れた場所で生活している長男・次男には、会社の株式の相続や遺留分の主張をできない旨、伝えた。
親の介護資金確保のための活用例
兄弟で集まり、介護資金の負担について話し合っていたところ、認知症になると口座が凍結して引き出せなくなることや、家族信託のことを知り、信託口口座にお金を移すよう両親を説得することに決めた。
両親に話を切り出したところ、両親もまた家族信託のことを調べており、長男を受託者、両親を委託者兼受益者とする信託契約書を交わし、無事、家族信託を開始できた。
遺言や後見制度など他制度との使い分け
家族信託・後見制度・遺言は、下表のような使い分けが可能です。
| 家族信託 | 後見制度 | 遺言 | |
| 財産管理 | 可能 | 可能ではあるが家族信託を選択する | 家族信託に委ねなかった財産については遺言で分割方法を記す |
| 身上監護 | 不可のため後見制度を併用する | 可能 | ー |
| 争族対策 | 遺留分含め相続が争族になる可能性は低い | ー | 法定相続ではない場合は遺留分について係争に発展する可能性が高い |
信頼できる専門家の選び方と相談時に必要な情報
最後に、上記を踏まえ、専門家の選び方と、相談時に必要な情報について、まとめます。
実績ある専門家の見極め方
家族信託について、公式サイトで積極的に情報を提供している専門家は、実績があると考えていいでしょう。また電話でお問い合わせしたときに質問攻めにあった場合は、業務マニュアル・フォーマットができあがっていて、実績があると推定できます。
依頼を検討している側から質問したときに、回答に行き詰まり、調べて折り返すとの返事があった場合は、実績があるかどうかを慎重に見極めるべきです。
しかしながら、家族信託支援業務の実績がある専門家であれば、信託口口座が開設できる銀行を知っているはずですので、地元ではどこがおすすめかを尋ねてみて即答であれば、実績があると確信していいはずです。
相談前に準備しておくべき情報
上記に掲げた必要書類など、すべての情報を準備できたら、それに越したことはありませんが、家族信託の検討に至った経緯や目的・動機、次に財産目録、委託者・受託者・受益者の情報は最低限、準備しておくようにしましょう。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を監修したのは…

認知症大家対策アドバイザー
岡田 文徳(おかだ ふみのり)
人生100年時代を生き抜くために大家さんの認知症対策を行なう専門家である。
コンサルティングだけでなく、実際に家族信託を実施し、賃貸経営を行う現役大家でもある。
学歴:東京大学大学院 修士(工学)
資格:宅地建物取引士、相続診断士、家族信託コーディネーター®他
サイトURL:https://dimetel.jp