終活はおひとりさまにこそ必要!やるべきことや終活を支える制度、サービスとは?

Contents
おひとりさまが終活を始めるべき理由と背景
おひとりさまの終活には、家族がいないからこそ生じる不安や課題に対応するための大切な意味があります。ここでは、その背景と必要性について詳しく見ていきましょう。
なぜ独り身の高齢者に終活が必要なのか
おひとりさまは、配偶者や子どもといった身近な家族がいないことから、医療や介護、死後の手続きまで、すべてを自分自身で計画・準備しておく必要があります。
誰かに相談することも難しく、財産管理や施設の手続きなどで困るケースが多く見られます。
また、緊急時に代わりに判断してくれる人がいないことで、命に関わる問題が生じることもあります。
だからこそ、おひとりさまにとっての終活は、自身の人生と尊厳を守るための大切な「対策」なのです。
「終活」とは何か?基本的な意味と目的
「終活」とはどのような事なのでしょうか?
「終活」には、人生の終わりを迎えた時に、周囲の方が困らないようにしておく事、延命治療の希望、葬儀や埋葬など自分らしい最期を迎えるための準備という意味があります。
ただ、筆者は「終活」の本当の効果は別にあると考えます。それは「終活」を行うと、これからの人生が輝いてくるという側面です。
「終活」を進める中で、自分らしい人生の最期を迎える準備が完了します。そうすると将来への不安が減る事で人生の最期が来るまでの今後の生活に目を向けやすくなります。
「終活」のなかで、感謝を伝えたい人や行ってみたかった場所、人生でやり残している事などが思い浮かび今後の人生の目標が増えていきます。「終活」は終わりのための活動と同時に、これからの人生を前向きに楽しく生きるための活動とも言えるのです。
独居高齢者が直面する現代的なリスク
一人暮らしの高齢者が増加する現代社会では、「誰にも看取られないまま亡くなる」孤独死のリスクや、介護・医療に関する手続きが進められないといった深刻な問題が発生しています。
さらに、死後に身内がいないことから、役所への届け出や葬儀、遺品整理なども放置されるケースがあり、行政が対応に追われる事例もあります。
こうしたリスクに備えるには、身元保証や後見制度、信頼できるサービスの利用を含めた「総合的な終活」が求められます。
おひとりさまだからこそ、元気なうちから現実的な備えを始めることが重要なのです。
孤独死や生活困窮の増加
最近では、親族との交流がなく、長期間誰にも気づかれずに亡くなる「孤独死」が増えています。
発見が遅れることで死後の処理が難航し、周囲にも影響を及ぼすケースが多く見られます。
また、年金だけでは生活が厳しい高齢者も多く、経済的困窮から生活保護に至るケースも少なくありません。
早い段階で介護・医療・金銭面の対策を取ることが、安心して暮らし続けるための鍵となります。
医療・介護手続きの対応困難
病院への入院時や介護施設に入所する際には、保証人や緊急連絡先を求められることが一般的です。
しかし、おひとりさまの場合、こうした役割を担ってくれる家族がいないことも多く、入院や入所がスムーズに進まないおそれがあります。
医療・介護に関する意思表示を明文化し、任意後見制度や身元保証サービスを活用することで、必要な対応を準備しておくことが重要です。
死後の手続きや遺品整理の課題
亡くなった後には、死亡届の提出や年金の停止、保険の請求、公共サービスの解約など、さまざまな手続きが必要になります。
遺品整理についても、誰がいつ対応するかを決めておかなければ、空き家問題や資産放置につながるリスクがあります。
死後事務委任契約を活用すれば、信頼できる人に事務処理を依頼でき、残された人への負担も大きく軽減されます。
また、生前のうちに財産の所在を整理しておくことも忘れずに行いましょう。
生前に考えられるお困りごととは?
以下のような問題は、とくにおひとりさまにとって現実的なリスクとなります。
- ケガ病気等で入院する事になった場合、病院に届ける保証人をどうするか?
- 一人で自宅にいるとき動けなくなってしまった場合の対処方法。
- 留守宅の管理をどうするか?
- もしペットを飼っていたら、ペットの世話をどうするか?
- 体が不自由になってしまった場合、日常生活や財産の管理をどうするか?
- 認知症になってしまった場合、施設等の入居や財産管理をどうするか?
など、様々なお困りごとが発生します。
亡くなった後のお困りごととは?
死後の手続きや処理にも、事前に決めておかなければならないことが多くあります。
- 葬儀や埋葬をどうするか?亡くなった事を伝えたい連絡先は?
- 役所への届け出(死亡届や健康保険の届け出等)をどうするか?
- 利用しているサービス(ガス・電気・電話・インターネット等)の解約手続き。
- ペットを飼っていたら、ペットの預け先をどうするか?
- 遺された財産の相続方法(遺贈寄付等も含めて)。
- 自宅の遺された遺品の整理をどうするか?
など、やはり沢山のお困りごとが発生することが分かりますね。
上記の通り、生前も亡くなった後も数多くのお困りごとが発生します。しかも、ご自身の意思を示したい事ばかりですよね。
これを見ていただくと、立つ鳥跡を濁さずではないですが、ご自身の意思でこの様なお困りごとが起きないように準備する事の大切さを判っていただけると思います。
終活を行うことで得られるメリット
終活は「亡くなる準備」ではなく、「これからの人生を安心して生きるための準備」です。
とくにおひとりさまにとっては、終活によって自分の人生の整理と同時に、将来の不安を軽減する大きな効果が得られます。
老後への不安を軽減できる
財産管理や医療、介護、葬儀といった将来の不安を、具体的な準備によって解消できるのが終活の大きな魅力です。
たとえば、任意後見契約や財産管理契約を結んでおけば、認知症などで判断力が低下した際にも安心して暮らすことができます。
また、財産の使い道や希望する最期の形を整理することで、「何が起きても大丈夫」という心の余裕が生まれます。
老後を前向きに、そして自分らしく生きるための土台が整うのです。
自分の意思を反映した準備が可能になる
終活では、遺言書やエンディングノート、死後事務委任契約を通じて、自分の意思を明確に残すことができます。
「延命治療を望まない」「自然葬を希望する」「遺産の一部を寄付したい」
そうした気持ちを生前に文書化することは、遺された人の混乱や負担を軽減することにもつながります。
自分で人生の最期をデザインすることで、誰にも迷惑をかけず、安心して生きる準備ができます。
周囲や第三者への負担を減らせる
終活をせずに亡くなってしまった場合、役所への届け出や公共料金の解約、遺品の整理など、多くの手続きを第三者が担うことになります。
とくにおひとりさまの場合、これを誰がやるのか決まっていないと、親戚や自治体が混乱し、トラブルに発展することもあります。
生前に契約や手続きを整えておけば、こうした負担を確実に減らすことができます。
行政書士や弁護士といった専門家のサポートを受けるのもおすすめです。
生活の安心感や自立につながる
終活によって自分の考えや希望を整理し、必要な支援を検討しておくことで、「一人でも大丈夫」という実感が得られます。
これは、日々の生活に安心感と自信をもたらし、自立した老後を支える大きな力となります。
終活を進めることで、現在の生活を見直すきっかけにもなり、より快適で無理のない暮らし方に整えていくことができるのです。
終活を後回しにすることで起こるリスク
「まだ元気だから」「そのうちやろう」と思っているうちに、終活のタイミングを逃してしまう方も少なくありません。
しかし、おひとりさまの場合はとくに、判断能力や体力のあるうちに準備を進めておかないと、大きなリスクが生じる可能性があります。
認知症発症後の対応が困難に
認知症を発症すると、自分の意思を明確に伝えることが難しくなります。
この状態では、遺言書の作成や契約手続きなどの重要な判断ができないと判断され、希望していた準備が進められないことがあります。
たとえば、任意後見契約や財産管理契約は、本人の判断能力がある段階でしか締結できません。
認知症発症後に必要となる成年後見制度は、家庭裁判所の選任により第三者が後見人となる可能性もあり、自分の意思や希望が反映されないことがあります。
早い段階での備えが、人生の選択肢を守るために大切です。
死後に希望が叶わない可能性がある
「家族にこうしてほしい」「葬儀はシンプルにしてほしい」「延命治療はしたくない」などの希望があっても、それが他人に伝わっていなければ実現されません。
遺言書やエンディングノートを作成していないと、死後の手続きや供養の方針は、親戚や行政、あるいは業者の判断に任せざるを得なくなります。
その結果、自分が望んでいなかった方法で供養されたり、大切な財産が意図しない相続人に渡ったりすることも起こり得ます。
「伝えなかった」ではなく「伝えられなかった」とならないために、生前の意思表示は欠かせません。
財産が国庫に帰属するおそれ
おひとりさまの中には、法定相続人がいないケースもあります。
こうした場合、遺言書がないまま亡くなると、相続財産は一時的に管理人が選任され、最終的には国庫に帰属します(民法第959条)。
自分が築いた財産を信頼できる知人に遺贈したい、あるいは寄付したいと考えていたとしても、遺言書がなければその希望は実現しません。
財産の行き先を自分で決められるのは、生きているうちだけ。お金の使い道も自分の人生の一部として、大切に考えておきたいところです。
おひとりさまの終活でやるべきこと
終活には多くの項目がありますが、焦る必要はありません。ひとつずつ優先順位を決めながら進めていくことで、着実に準備が整っていきます。
ここでは、とくにおひとりさまが重視すべき取り組みを分野ごとにご紹介します。
日常生活の整備
毎日の生活を見直し、必要なモノや情報を整理しておくことが、終活の第一歩です。不要な持ち物を断捨離したり、生活環境を整えたりすることで、転倒や事故のリスクも減らせます。
同時に、財産や契約の情報を明確にしておくことで、将来の介護や相続の場面でも混乱を避けることができます。
「今、誰にも見せられない場所」は、将来もそのまま残ります。元気なうちに整える習慣が、安心につながります。
断捨離・生前整理の実施
これは、元気な今しかできない事です。
明日認知症になってしまった場合、又は亡くなってしまったと想定して考えてみましょう。
整理しておきたいもの、断捨離したいものが見えてきます。
たとえば
- 生活用品や家具についても不要なものは無いか?
- 金融機関の数やクレジットカードの数など、必要以上に保有していないか?
- 必要性のない不動産を所有していないか?
- ペットを飼っている場合、その子の行先は?
など、人それぞれですが様々な事があります。
近隣住民との関係性の構築
孤立を防ぐためには、近隣とのつながりを大切にすることが非常に重要です。
普段から挨拶を交わす、町内会や地域行事に参加するなど、小さな関わりの積み重ねが「見守り」の役割を果たします。
突然の病気や災害時に助け合える関係性があれば、一人暮らしでも安心感が大きくなります。
家族がいないからこそ、地域との「ゆるやかなつながり」が終活の支えになります。
地域活動や見守りサービスの活用
自治体や民間企業では、高齢者の孤立を防ぐための見守りサービスを多数提供しています。
たとえば、定期訪問・電話連絡・センサーによる異常検知などの仕組みがあります。
地域包括支援センターや社会福祉協議会では、安否確認・生活相談などの支援も受けられます。
シルバー人材センターや地域ボランティアに参加することで、社会との関わりも維持できます。
これらの制度やサービスは、情報を得たときから使える安心の道具になります。
孤独死の対策
近年増えているのが「孤独死」です。文字通りの事ですが、亡くなっていることを周囲が気づかずかなりの期間を経て発見されるケースが増えています。
対策としては次の事が考えられます。
- 老人ホームやサービス付き高齢者住宅の利用。
- 地域のサークル活動やシルバー人材センターに登録し参加する。
- ご近所さんとのお付き合いを大事にする。
- 自治体によっては、安否確認等で訪問活動を行っている自治体もあります。
- 定期的にお弁当を宅配してくれるサービスもあります。
- セキュリティ会社では、様々なセンサー等で安否確認を行うサービスもあります。
- 見守り契約を結び、定期的な安否確認を行うサービスもあります。
など、ご自身でできることから自治体や企業でも様々な「孤独死」を防ぐサービスを展開していますので、ご自身に合った方法で検討されるとよいと思います。
医療・介護に関する備え
おひとりさまにとって、病気やけがをしたとき、あるいは介護が必要になったときに備えておくことは非常に重要です。
元気なうちは意識しづらい分野ですが、入院や施設入所の場面では、緊急連絡先や保証人、医療方針などを求められます。
自分で判断できなくなってからでは遅いため、事前に希望を明確にし、支援体制を整えておくことが安心につながります。
書面で意思を残すだけでなく、信頼できる第三者や専門家にサポートを依頼しておくと、より確実です。
かかりつけ医や介護施設の事前選定
医療・介護の準備は、まず信頼できる医師や相談先を持つことから始まります。
日頃から健康状態を把握してくれている「かかりつけ医」がいれば、いざという時も安心して治療を受けることができます。
また、将来的に介護が必要になった場合を想定して、施設の種類(特別養護老人ホーム、グループホーム、有料老人ホームなど)や費用、場所も調べておきましょう。
見学や資料請求をしておくことで、いざという時に慌てずに済みます。
入院時・介護時の代理手続き準備
病院や施設では、入院契約や同意書の署名など、本人に代わって手続きする人が求められます。
おひとりさまの場合、こうした代理を任せる人がいないと、受け入れ自体が断られるケースもあるため要注意です。
そのため、事前に「財産管理等委任契約」や「任意後見契約」を結び、信頼できる人に手続き権限を与えておくことが有効です。
書面化しておくことで、医療・介護現場でスムーズな対応が可能になります。
身元保証人や尊厳死宣言の検討
高齢者が入院や施設に入る際、身元保証人の提示が必要になることが多くあります。
しかし、家族がいない場合、代わりに「身元保証サービス」を提供する民間業者やNPO法人を利用する方法があります。
また、「延命治療を希望しない」などの意思を明確にしておきたい方は、「尊厳死宣言書(リビングウィル)」を作成しておくのも有効です。
これらは、医師や施設スタッフが判断に迷わないための重要な意思表示になります。
財産と金銭管理
財産の管理は、終活において中心的なテーマの一つです。
自分の預貯金・不動産・保険・証券などの資産がどこにどれだけあるのかを把握し、必要な手続きや整理をしておくことで、老後も死後もトラブルを防ぐことができます。
また、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、誰に管理を任せるかを明確にしておくことも欠かせません。
財産の一覧表を作成し、必要資金の見積もりや支出の見直しも検討しておきましょう。
財産の整理と把握
まずは、自分が保有している財産をすべてリストアップすることから始めましょう。
預金口座、保険、年金、不動産、株式・投資信託、借入金の有無などを整理しておくと、いざという時にスムーズに対応できます。
家族がいない場合でも、遺言書やエンディングノートで管理情報を残しておけば、信頼できる人が処理を引き継ぎやすくなります。
特にネット銀行や証券会社、仮想通貨など、見落とされやすい資産も忘れずに記録しましょう。
必要資金の見積もり
老後の生活資金として必要な金額を把握しておくことも重要です。
介護施設の入居費用や、医療費、見守りサービスや保証人サービスの利用料など、おひとりさまに特有の出費があるため、余裕を持った見積もりが必要です。
あわせて、家計の見直しや、不要な支出を減らす工夫も取り入れていきましょう。
将来的な収支を見える化しておくと、安心して老後のプランを立てられます。
財産管理契約・任意後見契約の締結
認知症などで判断能力が低下した場合に備え、自分が信頼できる人に財産や生活に関する事務を任せる「財産管理等委任契約」や「任意後見契約」が有効です。
これらは本人の判断能力があるうちに公正証書で結んでおく必要があります。
将来の金銭管理や生活支援を第三者に依頼したい場合は、司法書士や弁護士と相談して準備しておきましょう。
不安なときに頼れる仕組みを作っておくことで、老後の暮らしに安心感が生まれます。
死後に備える手続き
自分の死後に起きる事務処理や対応について、あらかじめ準備をしておくことも終活の大きな柱の一つです。
遺言書の作成や、死後の事務を任せる契約を結んでおくことで、自分の意思を確実に伝えることができます。
葬儀や供養、ペットの行き先まで、自分の人生を自分で締めくくる準備は、残された人たちの負担を軽減するだけでなく、何より「自分自身が安心できる」ことにもつながります。
遺言書の作成と保管
遺言書は必要なのか?よくある質問です。
筆者は「遺言書は、100%の人が書いたほうが良いと思います」とお伝えしています。
人が亡くなられた後、その方が遺された財産は法定相続人が相続することになります。
その際、財産の分け方について、法定相続人全員で協議をします。
簡単に言うとこの様な順番です。
- まずは、財産のすべてをテーブルの上に並べています(イメージ)
- 次に誰が何をどのくらいもらうかを話し合いで決めます。
- 決めた結果で遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書が無いと、銀行の手続きや不動産の登記等の財産を動かす手続きはできません。
話し合いがすんなりと付くケースなら良いのですが、中には、不動産や宝石などきっちりと分けられない財産も数多くありますし、それぞれの相続人の思惑等もあり、揉め事も多くなります。
なかなか一筋縄ではいかない感じがしますね。相続で揉めた親族は、その後なかなか元通りにはならないと言います。
筆者は、打開策として遺言書をおすすめしています。
遺言書があれば、上記のような遺産分割協議自体を開く必要がないというメリットがあります。
同時に亡くなった方の遺志の通り財産を分ける事ができます。遺言書があれば揉め事も減りそうですし、ご自身の遺産をご自身の思った通りの方法で分ける事ができます。
100%の人に遺言書は必要という意味も判っていただけたかと思います。
葬儀・納骨・供養方法の決定
最期の時を迎えた場合、理想の追悼の仕方についてどの様な方法を望むでしょうか?
たとえば
- 亡くなったことを伝える連絡先(葬儀に来てほしいかどうかも含めて)とその方法。
- 葬儀の方法と取り仕切ってもらう人(喪主)への依頼。
- 遺影写真の準備。
- 葬儀社を決めているか(互助会等への加入など)
- ご自身のお墓又は先祖代々のお墓が有るかどうか?そのお墓の墓守はどうしますか?
- お墓を購入しますか?最近では樹木葬や海洋散骨を選択される方もいらっしゃいます。
など、準備し意思表示しておく事で、周囲の方が困らないのと同時にご自身も理想とする送られ方が実現できます。
デジタル遺品や不用品の処理方法を明確に
スマートフォンやパソコン、ネットバンキング、SNSなどの「デジタル遺品」は、近年とくに重要な整理項目になっています。
IDやパスワード、利用サービス名、削除希望の有無などを一覧にしておくと、死後のトラブルを防げます。
また、写真データやブログなど、残すものと消したいものを明確にしておくと、遺された人にも分かりやすくなります。
紙の遺品と同様に、デジタルの整理も「自分らしい終活」に欠かせないポイントです。
死後事務委任契約の活用
「死後事務委任契約」とは、亡くなった後の手続き(葬儀、納骨、公共料金の解約、病院費用の支払いなど)を、あらかじめ第三者に委任しておく契約です。
おひとりさまにとっては、死後の混乱を防ぐための非常に有効な手段です。
この契約を結んでおくことで、行政や親族が代わりに処理を行う必要がなくなり、自分の希望通りに事務処理を進めてもらえます。
弁護士や司法書士、NPO法人などが対応している場合もあるため、早めに相談しておくと安心です。
ペットの今後についての取り決め
ペットを飼っているおひとりさまの場合、万が一の際にその子がどうなるかを考えておく必要があります。
ペットは法的には「財産」として扱われるため、遺言書で引き取り手を指定したり、「ペット信託」という仕組みを活用したりすることができます。
ペットの性格や健康状態、好きな食べ物や習慣をまとめておくと、引き取り手がスムーズに世話を続けられます。
大切な家族の一員であるペットの未来も、しっかり守ってあげましょう。
終活を始める時期と進め方のコツ
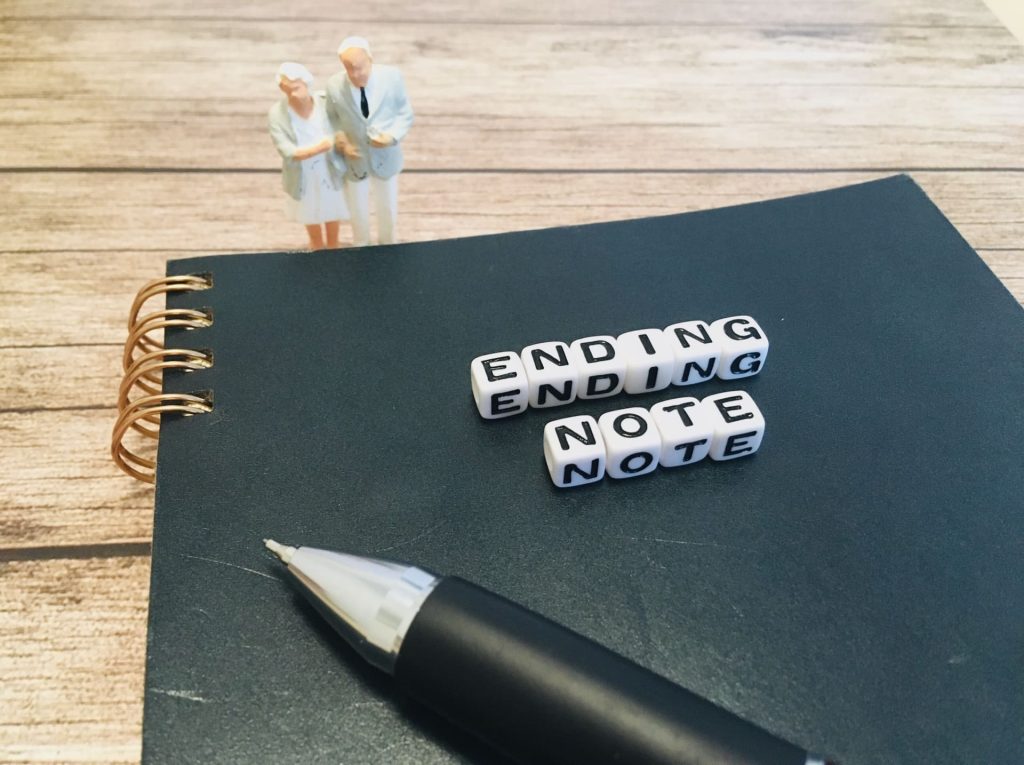
終活と聞くと、「高齢者になってから」と考える方が多いかもしれませんが、実は50代からでも早すぎることはありません。
むしろ、心身に余裕があるうちから段階的に準備を進めることで、より納得のいく形で「自分らしい終活」が可能になります。
ここでは、始めるタイミングと無理なく進める方法についてご紹介します。
50代からでも早すぎない理由
終活は、老いや死に直面してから始めるものではなく、元気なうちに「これからをどう生きるか」を考える前向きな活動です。
50代のうちは、まだ体力や判断能力もあり、心身ともに余裕をもって準備ができます。
また、定年退職や子どもの独立、親の介護など、人生の転機を迎える時期でもあり、自分の人生を見つめ直すきっかけにもなります。
この時期に財産や医療、老後の暮らし方を考えておくことで、60代以降を安心して過ごせるようになります。
まずはエンディングノートから始めよう
今まで案内してきた事をはじめとして、ご自身の理想の最期や想いを周囲に伝える方法の一つに、エンディングノートがあります。
一冊のノートに生前から亡くなった後までのことをまとめておけますので、終活をしていくうえで欠かせないパートナーとなります。
エンディングノートについては、「過去」「現在」「将来」についてまとめていきます。
《「過去」について》
- 自分のルーツや親族関係をまとめる。
家系図や親族関係図を作成する事で、法定相続人や後見人の候補、遺産分割先の検討等をすることはもちろん、ご自身のルーツを改めて確認できます。
- ご自身がどの様な人生を歩んで来たか振り返ってみる。
親御さんや親族の方はもちろんですが、学校関係など自分史を振り返る気持ちでエピソードや思い出を書き出してみます。自分の人生を振り返ってみる、いいきっかけになります。
《「現在」について》
・現在の交友関係
いざという時頼りたい人、連絡先等を記載します。
・財産関係(判り易くまとめるのと同時に、なるべく整理し必要最小限にしておく事が大事)
預貯金をしている金融機関の名前・支店名・口座番号等。
クレジットカードの枚数と保管場所。
有価証券を保有している場合は。証券会社名。
不動産について、種類や用途を詳細に。
公的な年金について、種類や基礎年金番号等。
保険について、保険会社や証券番号。
その他財産について
・医療関係
かかりつけのお医者さんや薬局。処方されている薬など。
《「将来」について》
最期の迎えた時の事について
葬儀や埋葬方法の希望
遺品の整理
遺贈や寄付等の希望
遺産の分割方法 など
現在から最期までの過ごし方
これから行ってみたい場所や会っておきたい人を思い浮かべる。
感謝の気持ちをまとめてみる。
※エンディングノートはこの様に様々な項目を記しておくことができます。また、最期の時の準備をすることで気持ちが落ち着き、これからの人生の事をより深く考える事ができ、人生が充実していくことを実感される方も多くいらっしゃいます。
この様な実感から、筆者は、これからの人生の充実感を得ることが「終活」の最大の目的であると考えています。
終活の進め方:段階的に取り組む方法
一度にすべてをやろうとすると、終活は大きな負担に感じてしまいます。
そこでおすすめなのが、「分野別に少しずつ取り組む」段階的な進め方です。
たとえば、最初の1ヶ月は持ち物の整理、次は医療方針、次に財産リスト作成……というようにテーマごとに計画を立てると、無理なく進められます。
必要に応じて、専門家(弁護士・司法書士・ファイナンシャルプランナーなど)にも相談しながら進めていくと、より安心です。
「終活リスト」や「スケジュール表」を作っておくのもおすすめです。
終活に必要な費用とその内訳
終活では、断捨離や財産整理といった日常的なことだけでなく、専門家への依頼や契約、葬儀・納骨といった死後の費用も発生します。
おひとりさまの場合はとくに、頼れる家族がいない分、契約サービスやサポートの利用が多くなる傾向があり、必要な費用を事前に把握しておくことが安心につながります。
ここでは、終活にかかる主な費用と、その負担を軽減するための工夫について解説します。
主な費用の分類と目安
終活にかかる費用は、大きく分けて以下の3つに分類できます。それぞれの費用は選ぶサービスや支援の範囲によって異なりますが、事前に概算を知っておくことで、無理のない準備が可能になります。
①生前の準備費用
自分自身が元気なうちに行う準備にかかる費用です。
これは日常生活の整理や意思表示、供養の予約などが該当します。
- エンディングノート作成
市販のノートであれば1,000から2,000円前後。
無料テンプレートもありますが、しっかりした構成のものは有料で販売されています。 - 生前整理・遺品整理業者への依頼
1Kの部屋で5万から10万円、2LDK以上で20万円以上かかる場合もあります。
自分で片づける場合は無料ですが、体力に不安がある場合は業者に依頼したほうが安心です。 - お墓・永代供養の事前契約
一般墓:50から200万円程度(場所・石材による)
永代供養墓:10から50万円前後
樹木葬:15から40万円程度
生前に契約しておけば、死後の費用を家族や第三者に負担させずに済みます。 - 葬儀の事前契約・互助会加入
葬儀社との生前契約で10から30万円の預託金が必要なケースもあります。
また、葬儀互助会に加入することで費用の分割払いが可能です。
②死後の手続き費用
亡くなったあとに発生するさまざまな手続きや儀式にかかる費用です。
家族がいないおひとりさまにとっては、これらの費用をカバーする備えが重要になります。
- 葬儀費用
一般葬:120から200万円程度(通夜、告別式、火葬を含む)
家族葬:50から100万円程度
火葬式・直葬:15から40万円程度(儀式を省略し火葬のみ) - 納骨・埋葬費用
既存のお墓への納骨:3から10万円程度(納骨料・石材彫刻代など)
永代供養:10から50万円前後(管理費不要のケースが多い)
散骨(海洋・山林など):5から20万円程度(委託・同行型で変動) - 死後事務処理費用
電気・ガス・水道などの契約解除手続き
賃貸物件の解約や原状回復費用
行政手続き(死亡届・年金停止など)
→個人で行えば無料ですが、委任契約で業者に依頼した場合は10から30万円程度が相場です。
③財産管理・契約費用
自身の財産を安全に管理し、将来的に信頼できる第三者に託すための法的契約に関する費用です。
おひとりさまが安心して老後を過ごすうえで、非常に重要な準備となります。
- 遺言書の作成費用
自筆証書遺言:基本的に無料(ただし書き方ミスに注意)
公正証書遺言:5から10万円(財産額により変動、公証人手数料込み)
専門家に依頼する場合:15から20万円前後が相場(作成支援含む) - 任意後見契約・財産管理等委任契約
契約書作成(公正証書):1件につき3から5万円
後見人への報酬(月額2から5万円前後)
→長期契約になる場合は、年間30万円前後かかる可能性もあります。
登記費用:数千円〜1万円程度(登記所への届け出時) - 身元保証サービスの利用費用
契約内容や保証範囲によって異なりますが、20から50万円が一般的。
緊急対応・入退院付き添い・死後事務込みの場合は、さらに加算されることもあります。
→NPO法人や行政委託業者による低価格サービスも存在します。
このように、終活にかかる費用は自分の希望する内容やサービスによって大きく異なります。
重要なのは「必要な準備にどこまでお金をかけるか」「どこを自分で、どこを専門家に任せるか」を明確にしておくことです。
費用が心配な方は、最低限必要な部分から段階的に取り組むことをおすすめします。
費用を抑える工夫と支援制度
終活には一定の費用がかかりますが、工夫次第で経済的な負担を軽くすることが可能です。
また、収入や年齢に応じて利用できる公的支援制度も存在するため、情報収集と早めの手続きが重要です。
ここでは、費用を抑える具体的な工夫と活用できる支援制度をご紹介します。
①サービス内容を明確にして「必要なことだけ」に絞る
終活関連のサービスは多岐にわたりますが、すべてを利用する必要はありません。たとえば、「お墓はいらない」と考える方であれば、永代供養や散骨など簡素な方法を選ぶことで、数十万円単位で費用を抑えることができます。
また、「遺言書は自筆で十分」という方は、公正証書にせずとも無料で準備できます(ただし法的な形式ミスに注意)。
自分にとって本当に必要なことは何かを明確にし、「あれもこれもやらなければ」と思わないことが、節約につながります。
②比較・見積もりをしっかり取る
同じような内容のサービスでも、提供会社によって価格は大きく異なります。葬儀社、納骨堂、死後事務委任の代行業者などを選ぶ際には、必ず複数の見積もりを取りましょう。
価格だけでなく、サービス内容や実績、アフターサポートの有無も比較検討し、納得できる業者を選ぶことが重要です。終活関連の一括見積もりサイトや自治体による業者紹介制度も、活用する価値があります。
③公的支援制度を活用する
経済的に余裕がない場合は、各種の公的支援制度を利用することで、終活にかかる費用を軽減できます。
- 葬祭費の支給(国民健康保険・協会けんぽ)
被保険者が亡くなった際に、葬祭を行った人に対して1万円〜7万円程度が支給される制度です。
自治体によって金額や申請手続きが異なるため、事前に役所へ確認しましょう。 - 生活保護受給者への葬儀扶助制度
生活保護を受けている場合、葬儀に必要な最低限の費用が自治体から全額支給される制度があります。
利用には事前の申請・承認が必要です。 - 公営納骨堂・公営墓地の利用
民間の墓地に比べて大幅に安価に利用できるケースが多く、管理費も抑えられます。
申し込みには居住条件や抽選制などの制約があるため、事前に募集情報を確認しておきましょう。 - 成年後見制度利用促進法による支援制度
経済的に後見制度の利用が困難な方に対して、各自治体や社会福祉協議会などが費用の一部を助成している場合もあります。
④地域包括支援センターや社会福祉協議会への相談
「何から始めればいいかわからない」「どの制度が使えるのかわからない」という方は、地域包括支援センターや社会福祉協議会に相談してみましょう。
終活や老後の生活設計に関するアドバイスを無料で受けられるだけでなく、信頼できる専門家の紹介や、地元の支援制度の案内もしてもらえます。
とくにおひとりさまの場合、情報が不足しがちなので、こうした公的な窓口を積極的に利用することが安心につながります。
このように、費用の負担を抑えるためには「情報を得ること」「必要なサービスを見極めること」「公的制度を活用すること」がポイントになります。
早い段階での準備と相談が、経済的にも精神的にもゆとりある終活につながるのです。
利用できる制度・サービス
おひとりさまが終活を進める上で頼れるのが、法律に基づいた制度や専門的な支援サービスです。
これらをうまく活用すれば、生前・死後に発生する不安や負担を大きく軽減できます。
ここでは、代表的な4つの制度とその違い、活用方法について解説します。
成年後見制度の活用
認知症などで判断能力が低下した場合に備えて利用できるのが「成年後見制度」です。
家庭裁判所が選任した後見人が、本人に代わって財産の管理や契約などを行う制度で、法的な安全性が高いのが特徴です。
- 法定後見:すでに判断能力が衰えた人のために家庭裁判所が後見人を決定
- 任意後見:元気なうちに信頼できる人を自分で選び、契約を結んでおくタイプ
おひとりさまにとっては、自分の意思が反映されにくくなる「法定後見」よりも、自由に後見人を選べる「任意後見契約」の利用が安心です。
任意後見は公正証書での契約が必要で、後見人には弁護士や司法書士など専門家を選任するケースもあります。
家族信託制度の特徴と活用例
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族などに託し、定めた目的に従って財産を管理・処分してもらう仕組みです。
信託法に基づく柔軟な財産管理が可能で、将来的な介護費用や医療費など、目的に応じて財産の使い道をコントロールできます。
たとえば、
「将来、認知症になったときのために、生活費として預貯金を使ってもらう」
「不動産は亡くなったあとに特定の人に相続させたい」
といった希望を、家族信託で事前にルール化できます。
家族信託は自由度が高く、後見制度と併用することでより強固な財産保護が可能です。
ただし、契約内容が複雑になるため、司法書士や信託に詳しい弁護士など専門家への相談が推奨されます。
死後事務委任契約とは?実務での効力
死後の手続きを信頼できる第三者に任せるための制度が「死後事務委任契約」です。これは民法上の委任契約であり、公正証書で結んでおくことで法的な効力が発生します。
委任できる内容の例は、以下のとおりです。
- 葬儀・火葬の手配
- 納骨・供養の方法の実行
- 賃貸物件の退去手続きや原状回復
- 各種契約(電気・ガス・通信など)の解約
- 医療費や葬儀費用の支払い
おひとりさまにとっては、自分の死後の事務を信頼できる人に託しておくことで、孤独死のあとに何も処理されないといった事態を防ぐことができます。
契約相手は弁護士・司法書士・NPO法人・身元保証会社などが一般的です。
財産管理等委任契約との違い
「財産管理等委任契約」は、判断能力があるうちから、特定の人に財産管理や日常生活に関する手続きを代行してもらう契約です。
これは「生前における事務の委任」であり、死後の事務には対応していません。
対して「死後事務委任契約」は、亡くなった後の事務を対象としており、両者の役割とタイミングが異なります。
| 項目 | 財産管理等委任契約 | 死後事務委任契約 |
| 契約のタイミング | 生前 | 生前(死後に効力発生) |
| 効力が及ぶ期間 | 生存中のみ | 死後の一定期間 |
| 主な内容 | 銀行・支払・手続き代行など | 葬儀・納骨・契約解約など |
これらはセットで利用されることも多く、将来のあらゆるリスクに備えたいおひとりさまにはとくにおすすめの制度です。
終活を支援してくれる存在
おひとりさまと言えど、終活を一人で抱え込む必要はありません。
最近では、行政・専門家・民間サービスなど、終活を総合的にサポートしてくれる仕組みや人のネットワークが充実してきています。
ここでは、信頼できる終活のパートナーとして頼れる存在を紹介します。
司法書士や弁護士によるサポート
終活には、契約・相続・財産管理など法的な知識が必要になる場面が多くあります。
その際に頼れるのが司法書士や弁護士といった法律の専門家です。
たとえば
- 任意後見契約、公正証書遺言の作成支援
- 相続や遺贈のアドバイス
- 財産管理契約、死後事務委任契約の締結と実行
- トラブル防止のための事前確認や書類チェック
といった形で、実務と法的リスクを両面からサポートしてくれます。
とくにおひとりさまは家族の助けが得にくいため、信頼できる専門家と早期に関係を築いておくと安心です。
また、「円満相続ラボ」では、相続に関する基本知識やトラブル回避の方法をわかりやすくお伝えし、専門家によるサポートを提供しています。円満な相続を実現するための最適なご提案をいたします。
相続に関する疑問がある方には、相続診断士による無料相談窓口もご利用いただけます。どうぞお気軽にご相談ください。
自治体による見守り・終活支援事業
多くの市区町村では、高齢者の孤立防止や終活支援を目的とした公的事業を実施しています。
たとえば、
- 市区町村が主催する無料セミナー
- 社会福祉協議会・NPOによる高齢者向け講座
- 終活カウンセラーや専門士業による有料講演
- オンライン開催による参加のしやすさも拡大中
など、身近な場所で利用できるサービスが数多くあります。
経済的な支援や、民間サービスと比べて低価格で利用できるものもあるため、まずは役所や地域包括支援センターに相談してみましょう。
おひとりさま向け終活セミナーの活用
最近では「おひとりさまの終活」をテーマにしたセミナーや講座も増えています。
これらは、終活の基本知識や制度、費用の考え方、書類の書き方などを体系的に学べる機会です。
- 市区町村が主催する無料セミナー
- 社会福祉協議会・NPOによる高齢者向け講座
- 終活カウンセラーや専門士業による有料講演
- オンライン開催による参加のしやすさも拡大中
こうした場で他の参加者と交流できることも、おひとりさまにとっては社会とのつながりを保つ良いきっかけになります。
「何から始めたらよいかわからない」と感じている方は、セミナーから情報を得るのもおすすめです。
終活に役立つ書籍・ガイドブックの活用
自宅でゆっくりと自分のペースで学びたい方には、終活に関する書籍やガイドブックの活用が適しています。書店や図書館、自治体のパンフレットなど、さまざまな情報源があります。
おすすめの活用方法は、以下のとおりです。
- 市販のエンディングノートに沿って自分の希望を整理
- 制度や手続きの解説本で用語や流れを学習
- 終活体験談の本で、自分のケースに近い例を参考にする
- 地域情報誌や行政資料で地元の制度やサービスをチェック
ガイドブックを活用することで、必要な準備を「見える化」しやすくなり、終活への心理的なハードルも下がります。
よくある質問とその答え
ここでは、終活を始める際に多くの方が抱える疑問について、わかりやすく回答します。
とくにおひとりさまに特有の不安や迷いに寄り添いながら、実践的なアドバイスをお伝えします。
女性の一人暮らしでも終活は必要?
はい、女性の一人暮らしだからこそ終活は必要です。
「もし病気になったら?」「身元保証人がいないと入院できないのでは?」「亡くなったあと誰が手続きを?」
こうした不安は、一人暮らしをしている多くの女性が抱えています。
終活では、医療・介護・死後の事務を自分で整えておくことで、安心して今後の生活を続けることができます。
誰にも頼らず自立して暮らしてきたからこそ、人生の締めくくりも自分らしく選ぶ準備が大切です。
終活は何から始めればよい?
「エンディングノートを1冊用意すること」から始めるのがおすすめです。
最初から遺言書を書いたり、制度を調べたりするのはハードルが高いと感じる方も多いでしょう。
エンディングノートなら、自分の人生を振り返る感覚で、思いついたことから書き込むことができます。
名前・連絡先・通帳のありか・希望する治療や葬儀の形式など、少しずつ項目を埋めていけばOKです。
書いてみることで、自分に必要な制度や準備が自然と見えてきます。
終活を始める適切なタイミングは?
「思い立ったときが最適なタイミング」です。病気になってから、判断能力が衰えてからでは、できることが限られてしまいます。
50代、60代の元気なうちから少しずつ準備を始めておくと、精神的にも経済的にも余裕を持てます。
とくにおひとりさまの場合、「まだ早い」と先送りにせず、今日できることを一歩ずつ進めておくことが安心につながります。
終活にどのくらいお金がかかる?
内容によって差はありますが、最低限の準備でも10〜30万円程度、しっかりしたサポートを受ける場合は50〜150万円ほどかかるのが一般的です。
<費用の例>
- エンディングノート:1,000〜2,000円程度
- 公正証書遺言作成:15万円前後
- 任意後見契約・死後事務委任契約:30〜60万円前後
- 葬儀・納骨:15〜200万円(形式により幅あり)
ただし、自分でできることは自分で行い、必要な部分だけプロに任せるなど工夫すれば、費用は抑えられます。また、公的支援制度を活用することで、経済的な負担を軽減できる場合もあります。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を書いたのは…

笑顔相続サロン®静岡代表、FP事務所 LP想暖や代表、保険代理店 有限会社シー・フィールド代表取締役
栗原 久人(くりはら ひさと)
上級相続診断士・終活カウンセラー・ファイナンシャルプランナー(AFP)生前整理カウンセラー・住宅ローンアドバイザー
ファイナンシャルプランナー歴・保険代理店経営歴共に20年、ライフプランや家計の見直し等の相談件数は2000件以上。
2019年笑顔相続サロン®静岡を開設 特に相続診断士×ファイナンシャルプランナー×終活カウンセラーの要素を活かした、終活+生前+相続のトータル対策を得意としている。
サイトURL:https://lpsoudanya.com/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC95ZnN5--uvM3GLQ9LwMtbA








