相続した土地売却時の税金を最小限に抑える方法|取得費加算の特例と確定申告のポイント

相続した土地を売却する際には譲渡所得税や住民税、復興特別所得税がかかりますが、適切な知識と対策により税負担を大幅に軽減できます。本記事では取得費加算の特例や3000万円控除などの節税対策から、確定申告の具体的な手続き方法まで詳しく解説します。税金計算の仕組みを理解し、最適な売却タイミングを見極めることで、手取り額を最大化する方法が分かります。
Contents
1. 相続した土地を売却する際にかかる税金の基本知識
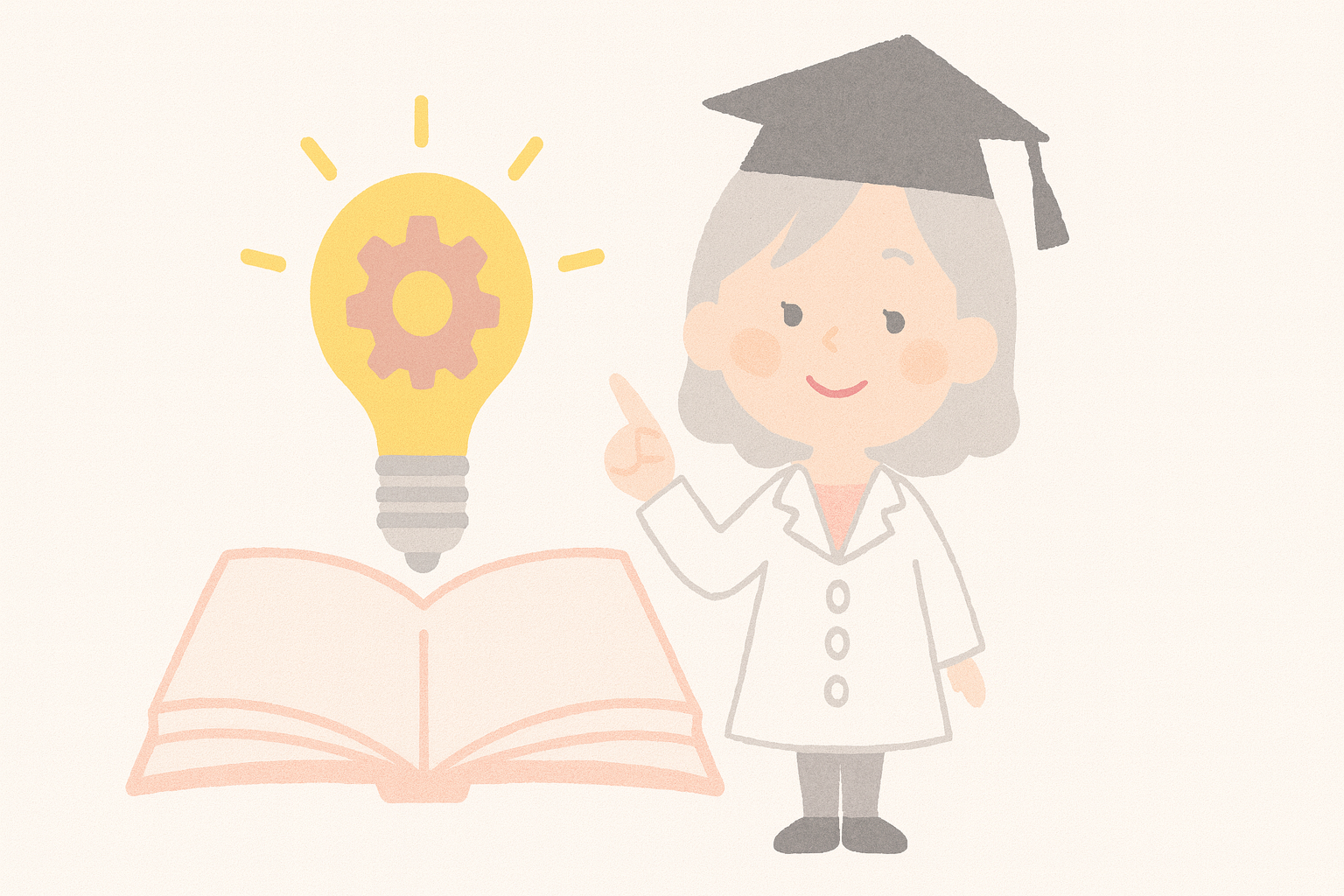
相続によって取得した土地を売却する際には、譲渡所得に対して複数の税金が課税されることを理解しておく必要があります。主に課税されるのは所得税、住民税、復興特別所得税の3つで、これらの税金は譲渡所得金額に応じて計算されます。
相続した土地の売却では、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額が譲渡所得となり、この譲渡所得に対して税金が課税されます。ただし、相続した土地の場合は通常の不動産売却とは異なる特殊な計算方法や特例が適用される場合があるため、事前に正しい知識を身につけることが重要です。
1.1 譲渡所得税の仕組みと計算方法
譲渡所得税は、土地や建物などの不動産を売却した際に生じる利益に対して課税される税金です。相続した土地を売却する場合の譲渡所得は、以下の計算式で求められます。
譲渡所得 = 譲渡価額 – (取得費 + 譲渡費用)
| 項目 | 内容 |
| 譲渡価額 | 土地の売却価格 |
| 取得費 | 被相続人や贈与者がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算 |
| 譲渡費用 | 売却時にかかった仲介手数料、測量費、印紙税など |
譲渡所得税の税率は、土地の所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられ、それぞれ異なる税率が適用されます。
| 所有期間 | 区分 | 所得税率 |
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 30.63% |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 15.315% |
相続した土地の場合、所有期間は被相続人が取得した日から計算されるため、相続開始時点で既に長期譲渡所得の要件を満たしている場合が多くなります。
1.2 住民税との関係性
土地売却時の譲渡所得に対しては、所得税とあわせて住民税も課税されることになります。住民税の税率も所有期間によって異なり、以下のように定められています。
| 所有期間 | 区分 | 住民税率 |
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 9% |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 5% |
住民税は所得税と異なり、売却した翌年の6月から翌々年の5月にかけて4回に分けて納付する必要があります。所得税は確定申告により一括で納付するのに対し、住民税は分割納付となる点に注意が必要です。
また、住民税の計算においても所得税と同様の譲渡所得金額を基準とするため、取得費加算の特例などの適用がある場合は、住民税額も同様に軽減されます。
1.3 復興特別所得税について
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興を図ることを目的として平成25年から令和19年まで課税される特別な税金です。譲渡所得に対しても復興特別所得税が課税されます。
復興特別所得税の税率は、基準所得税額の2.1%となっており、先ほど示した所得税率には既にこの復興特別所得税が含まれた税率となっています。
| 所有期間 | 所得税率(本則) | 復興特別所得税 | 合計税率 |
| 5年以下 | 30% | 0.63% | 30.63% |
| 5年超 | 15% | 0.315% | 15.315% |
復興特別所得税は所得税と一体として徴収されるため、納税者が個別に手続きを行う必要はありません。確定申告により所得税額が確定すると、自動的に復興特別所得税額も計算され、合計額を納付することになります。
なお、復興特別所得税の課税期間は令和19年12月31日までとなっているため、令和20年以降の譲渡所得については復興特別所得税は課税されません。
2. 相続した土地売却時の税金計算で重要な取得費の考え方

相続した土地を売却する際の税金計算において、取得費の正確な把握と計算が節税の鍵となります。取得費は譲渡所得の計算式「譲渡価額-取得費-譲渡費用」において重要な要素であり、取得費が大きければ大きいほど譲渡所得が小さくなり、結果として税負担を軽減できます。
2.1 相続時の取得費の基準
相続によって取得した土地の取得費は、被相続人(亡くなった方)が実際にその土地を取得した時の価額が基準となります。これは相続時の時価ではなく、被相続人が過去に購入した際の価額を引き継ぐという考え方です。
具体的な取得費の基準となる価額は以下の通りです:
| 取得方法 | 取得費の基準 | 備考 |
| 購入による取得 | 購入代金+購入時の諸費用 | 契約書等で金額が確認できる場合 |
| 相続による取得 | 被相続人の取得費を引き継ぎ | 相続時の時価ではない点に注意 |
| 贈与による取得 | 贈与者の取得費を引き継ぎ | 贈与時の時価ではない |
| 交換による取得 | 交換時の時価 | 等価交換の場合 |
相続税の申告において土地の評価額が高く算定されていても、譲渡所得税の計算では被相続人の取得費を引き継ぐため、相続税評価額とは別の金額となる点に注意が必要です。
2.2 概算取得費と実額取得費の選択
相続した土地の売却において、被相続人が取得した時期が古く、取得時の資料が残っていない場合や、実際の取得費が不明な場合には、概算取得費と実額取得費のいずれか有利な方を選択することができます。
2.2.1 概算取得費の計算方法
概算取得費は譲渡価額の5%で計算されます。例えば、土地を3,000万円で売却した場合、概算取得費は150万円(3,000万円×5%)となります。
2.2.2 実額取得費との比較検討
実額取得費が譲渡価額の5%を下回る場合、または取得費が不明な場合には、概算取得費を適用することで節税効果が期待できます。一方、実額取得費が5%を上回る場合は、実額取得費を選択する方が有利です。
| ケース | 有利な選択 | 節税効果 |
| 実額取得費<譲渡価額×5% | 概算取得費 | 取得費が増額され、譲渡所得が減少 |
| 実額取得費>譲渡価額×5% | 実額取得費 | より多くの取得費を計上可能 |
| 取得費不明 | 概算取得費 | 確実に5%の取得費を計上可能 |
2.3 取得費に含められる費用の種類
相続した土地の取得費を計算する際には、被相続人が土地取得時に支払った購入代金以外の関連費用も含めることが可能です。これらの費用を適切に計上することで、取得費を増加させ、譲渡所得税の負担を軽減できます。
2.3.1 土地取得時に取得費に含められる費用
| 費用の種類 | 具体例 | 注意点 |
| 仲介手数料 | 不動産会社への仲介手数料 | 領収書等の証明書類が必要 |
| 登記費用 | 登録免許税、司法書士報酬 | 所有権移転登記に関する費用 |
| 不動産取得税 | 都道府県税として納付した税額 | 取得時に課税された分のみ |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付した印紙代 | 契約書1通分の印紙税 |
| 測量費 | 土地境界確定測量費用 | 取得に直接要した費用のみ |
2.3.2 土地改良費等の資本的支出
被相続人が土地取得後に行った改良工事や設備投資のうち、資本的支出に該当する費用も取得費に加算することができます。
資本的支出として取得費に含められる主な費用は以下の通りです:
- 土地の造成費用(整地、盛土、切土等)
- 土地の地盤改良工事費
- 擁壁工事費用
- 排水設備工事費
- 道路整備費用(私道部分)
ただし、これらの費用は単なる修繕費ではなく、土地の価値を高める資本的性質を有する支出であることが必要です。また、支出時期についても、相続開始前に被相続人が負担した費用であることが要件となります。
2.3.3 取得費に含められない費用
一方で、以下のような費用は取得費に含めることができません:
- 相続手続きにかかった費用
- 相続税の申告費用
- 土地の維持管理費用
- 固定資産税・都市計画税
- 借入金の利息(土地取得のための借入金を除く)
これらの費用と取得費に含められる費用を明確に区分し、適切な証拠書類を整備しておくことが税務調査対応においても重要です。
3. 取得費加算の特例で税金を大幅に軽減する方法
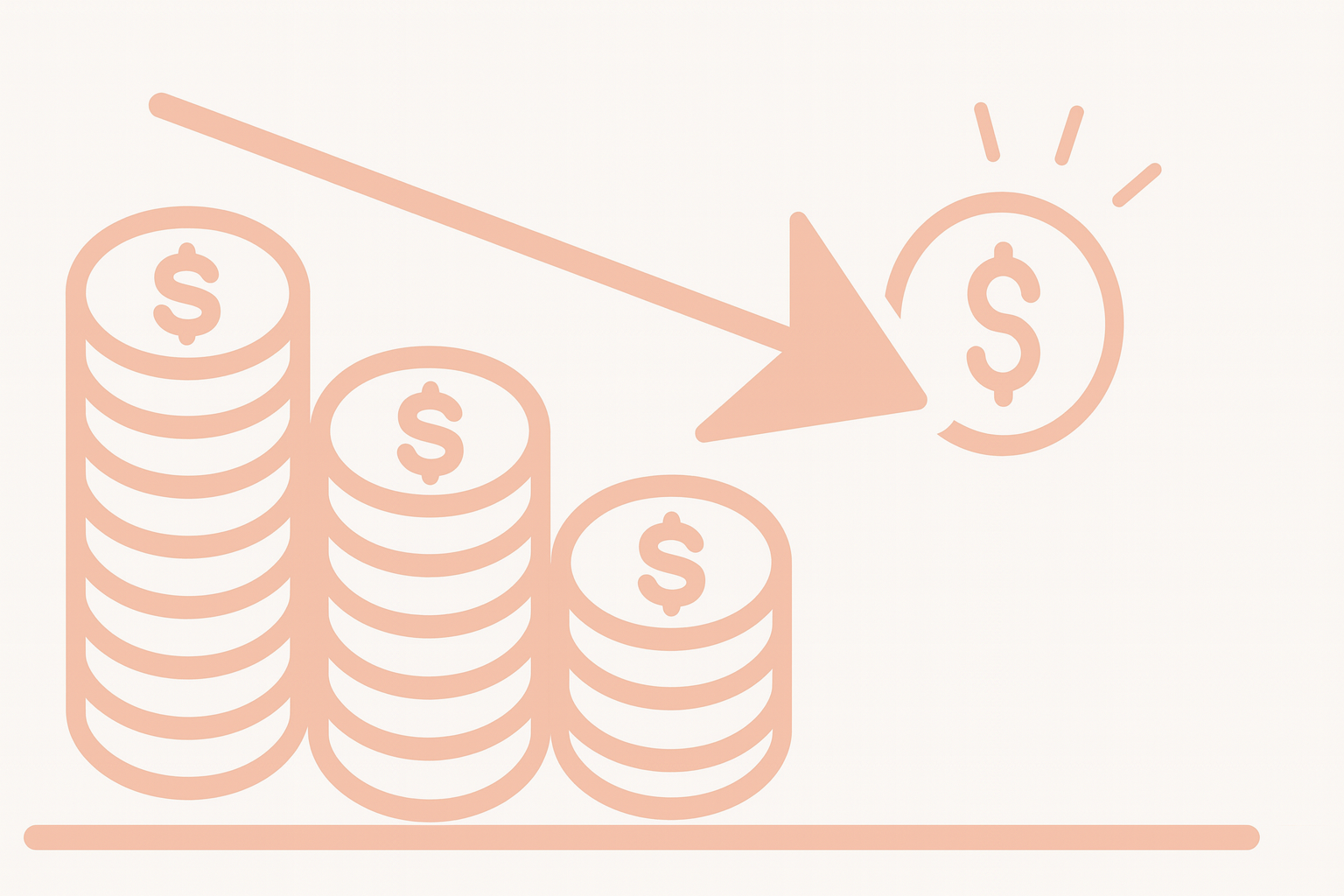
相続した土地を売却する際の税負担を大幅に軽減できる制度が取得費加算の特例です。この特例を活用することで、相続税として支払った金額の一部を土地の取得費に加算でき、譲渡所得税を大幅に減額することが可能になります。
3.1 取得費加算の特例の適用要件
取得費加算の特例を適用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
| 要件項目 | 詳細内容 |
| 相続または遺贈による取得 | 相続または遺贈により土地を取得していること |
| 相続税の納税 | その土地を取得した人が相続税を納めていること |
| 売却期限 | 相続開始日の翌日から3年10か月以内に売却すること |
相続開始日の翌日から3年10か月以内という期限は特に重要で、この期間を過ぎてしまうと特例の適用を受けることができません。相続税の申告期限が相続開始から10か月以内であることを考慮すると、相続税の申告期限(=相続開始日から10か月)の翌日から3年以内に譲渡を行う必要があります。
また、相続税を実際に納めていない場合、例えば基礎控除内で相続税がかからなかった場合や、配偶者の税額軽減等により相続税額が0円になった場合は、この特例を適用することができません。
3.2 加算できる相続税額の計算方法
取得費に加算できる相続税額は、以下の計算式で算出されます。
取得費加算額=相続税額×売却した土地の相続税評価額÷(相続税の課税価格+債務控除額)
| 計算要素 | 説明 |
| 相続税額 | 実際に納付した相続税の総額 |
| 売却した土地の相続税評価額 | 相続税申告書に記載された売却土地の評価額 |
| 相続税の課税価格 | 相続財産全体の課税価格の合計額 |
| 債務控除額 | 相続債務として控除された金額 |
この計算により、売却した土地に対応する相続税額の按分計算が行われ、その金額を取得費に加算することができます。計算が複雑になるため、税理士等の専門家に相談することを強く推奨します。
3.3 特例適用時の具体的な節税効果
取得費加算の特例による節税効果は非常に大きく、場合によっては数百万円の税負担軽減につながることもあります。
具体例として、以下のケースで節税効果を確認してみましょう。
| 項目 | 金額 |
| 土地の売却価格 | 5,000万円 |
| 通常の取得費(概算取得費) | 250万円(売却価格の5%) |
| 取得費加算の特例適用額 | 1,500万円 |
| 譲渡費用 | 200万円 |
特例適用前の譲渡所得:5,000万円-250万円-200万円=4,550万円
特例適用後の譲渡所得:5,000万円-(250万円+1,500万円)-200万円=3,050万円
譲渡所得の差額は1,500万円となり、長期譲渡所得税率20.315%を適用すると、約304万円の税負担軽減効果が生まれます。
さらに、取得費加算の特例は他の特例との併用も可能です。例えば、居住用財産の3,000万円特別控除との併用により、さらなる節税効果を期待できる場合があります。
ただし、この特例の適用を受けるためには、相続税申告書の写しや売却時の契約書等、多くの書類を確定申告時に提出する必要があります。書類の準備漏れがないよう、事前に税務署や税理士に相談し、必要書類を整理しておくことが重要です。
4. 相続した土地売却で活用できるその他の節税対策
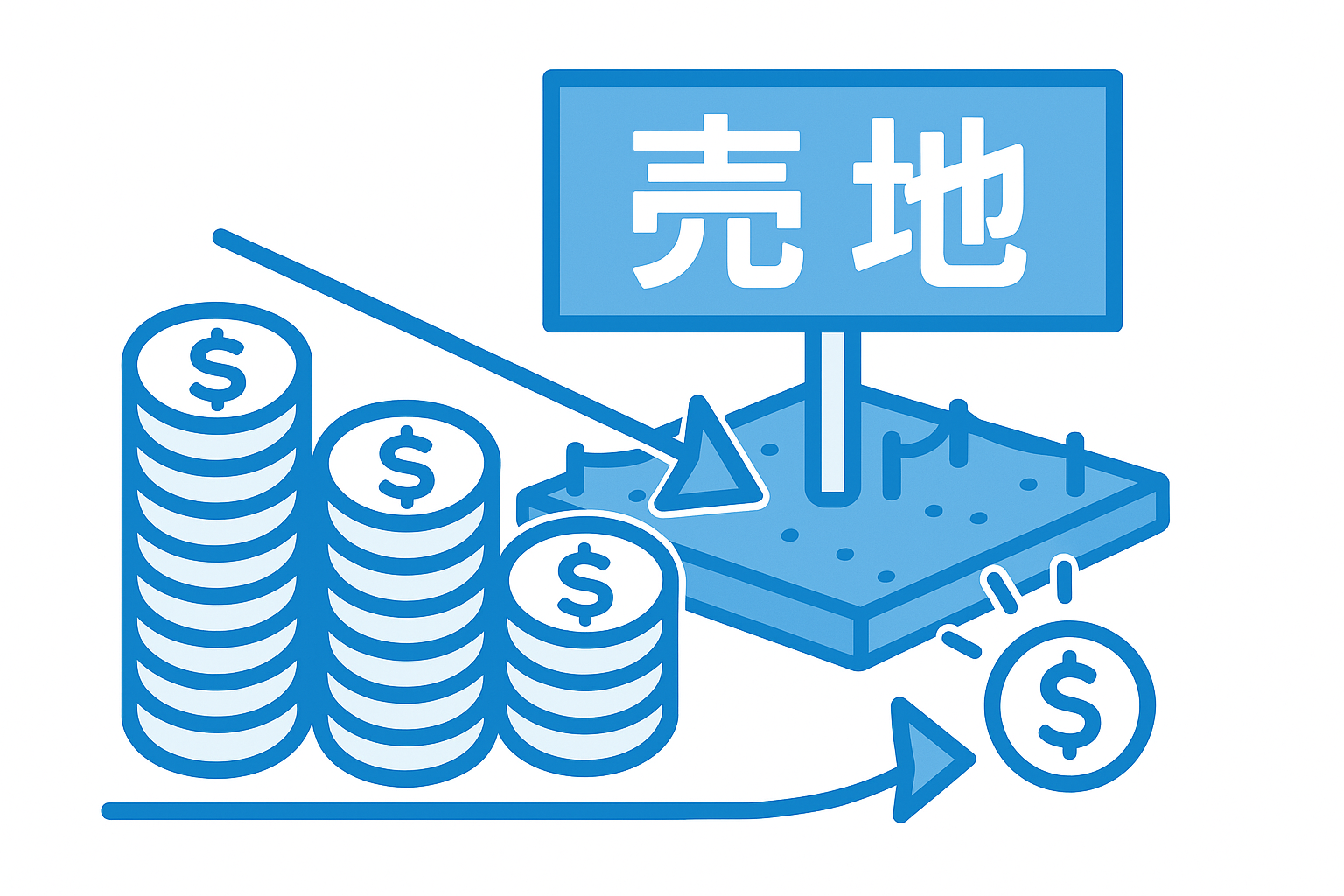
相続した土地を売却する際、取得費加算の特例以外にも活用できる節税制度があります。これらの制度を適切に組み合わせることで、譲渡所得税の負担を大幅に軽減することが可能です。
4.1 居住用財産の3000万円特別控除
相続した土地に被相続人が居住していた家屋がある場合、居住用財産の3000万円特別控除の適用を受けられる可能性があります。この制度により、譲渡所得から最大3000万円を控除できるため、大幅な節税効果が期待できます。
4.1.1 適用要件と条件
居住用財産の3000万円特別控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
| 要件項目 | 詳細条件 |
| 居住期間 | 被相続人が相続開始直前まで居住していた家屋であること |
| 売却期限 | 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
| 家屋の状況 | 昭和56年5月31日以前建築の場合は耐震基準を満たすか家屋を取り壊すこと |
| 売却価格 | 売却価格が1億円以下であること |
4.1.2 空き家の特別控除との併用
被相続人が一人暮らしで亡くなった場合、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の適用も可能です。この制度では、一定の要件を満たす空き家を売却した場合に最大3,000万円の特別控除を受けることができます。
ただし、この特別控除は、取得した相続人が3人以上の場合には最大2,000万円に制限されることがあります。 また、同一年中にマイホームの譲渡特例(最大3,000万円)と併用することはできず、控除額は合計3,000万円までが上限となります。
4.2 軽減税率の特例適用条件
相続した土地の所有期間が5年を超える長期譲渡所得に該当する場合、軽減税率の特例を適用できる可能性があります。
4.2.1 長期譲渡所得の軽減税率
相続により取得した土地は、被相続人の所有期間を引き継ぐため、被相続人が5年以上所有していれば長期譲渡所得として扱われます。
| 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税 | 合計税率 |
| 短期(5年以下) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期(5年超) | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
4.2.2 10年超所有軽減税率の特例
居住用財産で所有期間が10年を超える場合、さらなる軽減税率が適用されます。譲渡所得6000万円以下の部分については、所得税10%、住民税4%の軽減税率が適用されます。
4.3 損益通算による税負担軽減
相続した土地の売却で譲渡損失が生じた場合、損益通算や繰越控除の制度を活用することで税負担を軽減できます。
4.3.1 他の譲渡所得との損益通算
同一年分に他の土地や建物の譲渡による所得がある場合、譲渡損失と譲渡所得を相殺することができます。これにより、全体の譲渡所得税額を減少させることが可能です。
4.3.2 居住用財産の買換え特例
相続した居住用財産を売却して新たに居住用財産を取得する場合、一定の要件を満たせば譲渡所得の課税を将来に繰り延べることができます。
| 特例の種類 | 適用要件 | 節税効果 |
| 買換え特例 | 売却価格1億円以下、床面積50㎡以上の住宅取得 | 譲渡所得の課税繰延べ |
| 交換特例 | 同種の固定資産との交換 | 譲渡所得の非課税 |
| 買換え損失の繰越控除 | 住宅ローン残高超の買換え損失 | 4年間の繰越控除 |
4.3.3 複数年にわたる繰越控除
居住用財産の譲渡によって生じた損失は、その年の給与所得や事業所得などと損益通算することができます。また、当年で控除しきれなかった譲渡損失については、譲渡の年の翌年以後最大3年間にわたって繰り越して控除(繰越控除)することも可能です。これにより、給与所得や事業所得から譲渡損失を差し引くことができ、所得税および住民税の還付を受けることができます。
これらの節税制度を適切に組み合わせることで、相続した土地の売却に伴う税負担を最小限に抑えることができます。ただし、各制度には細かな適用要件があるため、事前に税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
5. 相続した土地売却後の確定申告手続きのポイント

相続した土地を売却して譲渡所得が発生した場合、確定申告が必要となります。手続きには期限があり、必要書類の準備や正確な計算書の作成が求められるため、事前に全体の流れを把握しておくことが重要です。
5.1 確定申告の期限と提出書類
5.1.1 確定申告の期限
相続した土地を売却した場合の確定申申告は、売却した年の翌年2月16日から3月15日までに行う必要があります。この期限を過ぎると延滞税などのペナルティが課される可能性があるため、余裕を持った準備が必要です。
ただし、譲渡所得が損失となった場合でも、他の所得との損益通算や翌年以降への繰越控除を受けるために確定申告を行うことで、税務上のメリットを得られる場合があります。
5.1.2 基本的な提出書類
相続した土地売却に関する確定申告で必要となる基本的な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 用途 | 入手先 |
| 確定申告書B | 所得税の申告 | 税務署・国税庁ウェブサイト |
| 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書) | 譲渡所得の詳細計算 | 税務署・国税庁ウェブサイト |
| 住民税の申告書 | 住民税の申告 | 市区町村役場 |
5.2 譲渡所得の計算書作成方法
5.2.1 譲渡所得の計算式
譲渡所得の計算は、以下の計算式に基づいて行います。
譲渡所得 = 譲渡価額 – (取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額
5.2.2 譲渡価額の記載方法
譲渡価額には、土地の売却代金だけでなく、固定資産税や都市計画税の精算金として受け取った金額も含まれます。売買契約書に記載された金額を正確に転記することが重要です。
5.2.3 取得費の算出と記載
相続した土地の取得費は、被相続人が当初その土地を取得した際の価額となります。ただし、取得時の資料が不明な場合は、譲渡価額の5%相当額を概算取得費として計算する方法も認められています。
取得費加算の特例を適用する場合は、相続税額のうち売却した土地に対応する部分の金額を加算して記載します。
5.2.4 譲渡費用の集計
譲渡費用として計上できる主な項目は以下の通りです。
- 仲介手数料
- 印紙税
- 測量費
- 建物解体費用
- 登記費用
- 広告宣伝費
5.3 添付書類の準備と注意点
5.3.1 売却関連の必要書類
土地売却に関する確定申告では、以下の書類の添付が必要です。
| 書類名 | 記載内容・用途 | 注意点 |
| 売買契約書のコピー | 売却価額の証明 | 印紙が貼付されているか確認 |
| 登記事項証明書 | 所有権の証明・面積確認 | 売却後3か月以内の取得分 |
| 仲介手数料等の領収書 | 譲渡費用の証明 | 原本またはコピーを保管 |
5.3.2 相続関連の必要書類
相続した土地であることを証明し、取得費加算の特例を適用する場合には、追加で以下の書類が必要となります。
- 相続税の申告書のコピー(第1表、第11表、第11の2表、第14表、第15表)
- 相続税の納税通知書のコピー
- 被相続人の取得時の売買契約書等(取得費を証明する書類)
- 戸籍謄本等(相続関係を証明する書類)
5.3.3 書類作成時の注意事項
書類作成の際は、以下の点に特に注意が必要です。
計算ミスや記載漏れは税務調査の対象となる可能性があるため、複数回の確認作業を行うことが重要です。特に、取得費加算の特例を適用する場合の相続税額の計算は複雑になるため、税理士への相談も検討すべきです。
また、売却から確定申告までの期間が短いため、売却が決まった段階で必要書類の収集を開始し、計画的に準備を進めることが重要です。書類の不備により申告が遅れると、特例の適用を受けられない可能性もあるため注意が必要です。
6. 相続した土地売却のタイミングと税務上の注意事項

相続した土地を売却する際は、売却のタイミングや相続状況によって税務上の取り扱いが大きく変わります。適切な知識を持って対応することで、税負担を最小限に抑え、トラブルを回避することができます。
6.1 売却時期による税率の違い
相続した土地の売却では、所有期間によって適用される税率が大幅に変わるため、売却時期の判断が重要になります。
6.1.1 短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分
相続した土地の所有期間は、被相続人が取得した時点から通算して計算します。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうかで、以下のように税率が決まります。
| 所有期間 | 区分 | 所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税率 | 合計税率 |
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
6.1.2 売却タイミングの最適化
短期譲渡所得の場合は税率が約2倍となるため、可能であれば長期譲渡所得の適用を受けられる時期まで売却を待つことが節税の基本戦略となります。ただし、土地の市場価値の変動や維持コストも考慮して総合的に判断する必要があります。
特に相続税の申告期限(相続開始から10か月)との関係で、取得費加算の特例(3年10か月以内の売却が条件)を活用する場合は、売却時期の調整が重要になります。
6.2 複数の相続人がいる場合の対応
相続人が複数いる場合の土地売却では、法律上および税務上の複雑な問題が生じるため、事前の準備と適切な手続きが不可欠です。
6.2.1 共有名義での売却手続き
相続した土地が複数の相続人の共有名義になっている場合、売却には全相続人の同意が必要となります。一人でも反対する相続人がいれば売却はできません。
売却手続きでは以下の点に注意が必要です:
- 売買契約書への全相続人の署名・押印
- 印鑑証明書の取得(発行から3か月以内)
- 売却代金の分配方法の事前協議
- 各相続人の持分割合の確認
6.2.2 遺産分割協議による単独名義での売却
共有状態を解消して単独名義にしてから売却する方法もあります。この場合は遺産分割協議書の作成が必要となり、協議が成立した日から4か月以内に相続税の修正申告が必要になる場合があります。
6.2.3 税務上の取り扱いと注意点
複数相続人による共有土地の売却では、各相続人がそれぞれ譲渡所得の申告を行う必要があります。持分に応じて譲渡所得を計算し、それぞれが確定申告を行います。
| 項目 | 注意点 |
| 譲渡所得の計算 | 各相続人の持分に応じて按分計算 |
| 取得費加算の特例 | 各相続人が負担した相続税額を基に計算 |
| 特別控除の適用 | 居住用財産の特例は居住していた相続人のみ適用 |
6.3 税務調査への備えと対策
相続した土地の売却は、税務署にとって注目度の高い取引であり、税務調査の対象となりやすい分野です。適切な準備と対策を行うことで、調査時のトラブルを回避できます。
6.3.1 必要書類の整備と保管
売却から5年間は関連書類を適切に保管することが重要です。税務調査で求められる可能性の高い書類は以下の通りです:
- 売買契約書(原本・写し)
- 登記事項証明書(売却前後)
- 相続税申告書の控え
- 取得費を証明する書類(被相続人の購入時契約書等)
- 仲介手数料等の領収書
- 測量費用や解体費用の明細書
- 固定資産税評価証明書
6.3.2 申告内容の根拠資料の準備
概算取得費を適用した場合や、取得費加算の特例を適用した場合は、その計算根拠を明確に示せる資料の準備が必要です。特に相続税額の計算については、税理士による計算書を保管しておくことが望ましいです。
6.3.3 税務調査時の対応ポイント
実際に税務調査が行われた場合の対応では、以下の点に注意が必要です:
| 調査項目 | 対応のポイント |
| 売却価格の妥当性 | 不動産鑑定書や複数業者の査定書で客観性を示す |
| 取得費の根拠 | 被相続人の購入時書類や概算取得費の計算過程を明示 |
| 特例適用の要件 | 適用要件を満たすことを証明する書類の提示 |
| 相続税額の計算 | 相続税申告書と税理士による計算書の確認 |
6.3.4 プロフェッショナルとの連携
相続した土地の売却では、税理士や不動産専門家との連携が税務リスクの軽減に有効です。特に高額な土地の売却や複雑な相続関係がある場合は、事前に専門家に相談することで、適切な申告と税務調査への備えができます。
また、売却前の段階から税理士に相談することで、最適な売却時期の選択や節税対策の検討が可能となり、結果として税負担の大幅な軽減につながる場合があります。
7. まとめ
相続した土地を売却する際の税金は、取得費加算の特例を活用することで大幅に軽減できます。譲渡所得税・住民税・復興特別所得税の負担を最小限に抑えるためには、相続時の取得費を正しく算定し、居住用財産の3000万円特別控除などの特例も併せて検討することが重要です。確定申告では必要書類を漏れなく準備し、売却のタイミングも税率に影響するため慎重に判断しましょう。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を監修したのは…

一般社団法人日本相続研究所理事兼税理士
扇山 博司(おおぎやま ひろし)
「揉めない」相続のためにそばに寄り添える専門家です。実は「遺産相続争いは、親の人生を冒涜する最も悲しい社会問題」です。相続なんて関係ないと思っている人も今現在相続について悩んでいる人も「争続」ではなく将来の「笑顔相続」のために一緒に考えていきましょう。








