包括遺贈とは?遺産を包括的に託すメリット・デメリットと注意点
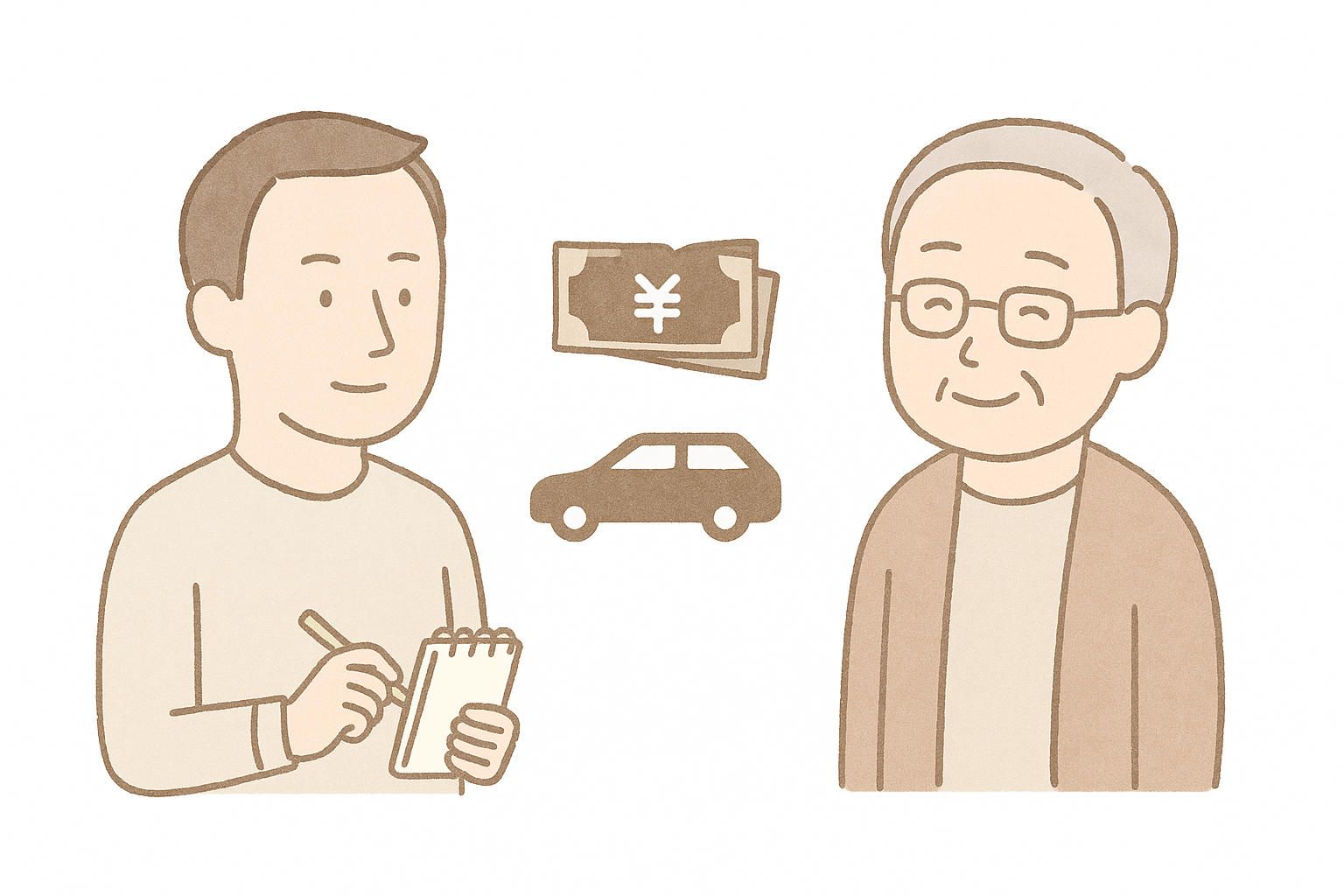
包括遺贈は、遺産を包括的に託すための強力な遺言方法です。この記事では、包括遺贈の定義や特定遺贈・相続との違いを分かりやすく解説します。そのメリット・デメリットを深く理解し、遺言書の作成方法、税金、遺留分、遺言執行者の選任など、注意すべき点を網羅的に解説。これにより、あなたの意思を確実に実現し、遺族間のトラブルを未然に防ぐための知識が手に入ります。
1. 包括遺贈とは何か

1.1 包括遺贈の定義と意味
包括遺贈(ほうかついぞう)とは、遺言によって、遺産の全部またはその割合を示して、特定の人物(受遺者)に財産を遺贈することを指します。民法第964条に定められている遺贈の一種であり、遺言者の最終的な意思を反映させるための重要な手段となります。
「包括」という言葉が示す通り、特定の個別の財産を指定するのではなく、「私の全財産」や「私の財産の2分の1」といった形で、遺産全体を包括的に、あるいはその割合で承継させるのが大きな特徴です。受遺者は、遺言者の財産だけでなく、負債などの義務もその割合に応じて承継する可能性があるため、相続人と同様の権利義務を持つとみなされます。
包括遺贈は、法定相続人ではない人物や団体に財産を渡したい場合、あるいは遺産分割協議を簡素化したい場合などに有効な手段として用いられます。受遺者は、包括遺贈を受けるか放棄するかを選択する権利を有します。
1.2 包括遺贈と特定遺贈の違い
遺贈には包括遺贈の他に特定遺贈があり、両者には明確な違いが存在します。特定遺贈は、特定の財産を指定して遺贈する形式です。例えば、「自宅の土地建物を〇〇に遺贈する」や「預貯金のうち1000万円を△△に遺贈する」といった形で、個別の財産を特定して遺贈します。
包括遺贈と特定遺贈の主な違いを以下の表にまとめました。
| 比較項目 | 包括遺贈 | 特定遺贈 |
| 対象となる財産 | 遺産の全部またはその割合(例:「全財産」「遺産の2分の1」) | 特定の個別の財産(例:「自宅」「預貯金1000万円」) |
| 権利義務の承継 | 遺言者の権利義務(負債を含む)を、その割合に応じて承継する | 原則として、特定の財産のみを承継し、負債は承継しない |
| 登記・登録の要否 | 遺言執行者がいれば、遺言執行者単独で登記・登録が可能(受遺者と共同申請の場合もある) | 原則として、相続人全員または遺言執行者と受遺者の共同申請が必要 |
| 遺産分割協議 | 遺産分割協議が不要になる場合がある(受遺者が単独で承継する場合など) | 遺贈されない残りの財産については、遺産分割協議が必要 |
| 放棄の方法 | 相続放棄と同様に、家庭裁判所に申述して放棄する | 遺贈義務者(相続人など)に対して意思表示することで放棄できる |
| 遺留分侵害額請求 | 遺留分を侵害した場合、請求の対象となる | 遺留分を侵害した場合、請求の対象となる |
このように、包括遺贈は相続に近い性質を持つ一方、特定遺贈は個別の贈与に近い性質を持つと言えます。どちらの遺贈方法を選択するかは、遺言者の意思や遺したい財産の種類、受遺者の状況によって慎重に検討する必要があります。
1.3 包括遺贈と相続の違い
包括遺贈と相続は、いずれも遺言者の財産が次の世代へ引き継がれるという点では共通していますが、その法的根拠や承継の仕組みには大きな違いがあります。
相続は、民法の規定に基づき、被相続人(亡くなった人)の財産を法定相続人が承継する制度です。これに対し、包括遺贈は、遺言者の意思表示である「遺言」に基づいて、特定の人物(受遺者)が財産を承継する制度です。
主な違いは以下の通りです。
| 比較項目 | 包括遺贈 | 相続 |
| 発生原因 | 遺言(遺言者の意思表示) | 被相続人の死亡(民法の規定) |
| 財産を承継する人 | 受遺者(法定相続人以外も可) | 法定相続人(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹など) |
| 対象財産 | 遺産の全部またはその割合 | 被相続人のすべての財産(プラスの財産、マイナスの財産すべて) |
| 権利義務の承継 | 遺言者の権利義務をその割合に応じて承継する | 被相続人のすべての権利義務を承継する |
| 遺産分割協議 | 受遺者が単独で承継する場合など、不要になる場合がある | 相続人が複数いる場合、原則として遺産分割協議が必要 |
| 放棄の方法 | 家庭裁判所に申述して放棄する(相続放棄と同様) | 家庭裁判所に申述して放棄する |
| 税金 | 相続税が課される(相続税法上、相続とみなされるため) | 相続税が課される |
包括遺贈は、遺言者の意思をより強く反映させたい場合や、法定相続人以外に財産を承継させたい場合に特に有効な手段となります。しかし、受遺者が負債も引き継ぐ可能性がある点など、相続と同様に慎重な検討が求められます。
2. 包括遺贈のメリット

包括遺贈は、遺言者の意思を明確に反映し、残された財産を希望通りに承継させるための強力な手段です。ここでは、包括遺贈がもたらす主な利点について詳しく解説します。
2.1 遺産全体を包括的に承継させられる
包括遺贈の最大のメリットの一つは、遺言者が所有するすべての遺産、または遺産の一定割合を、特定の受遺者にまとめて承継させられる点にあります。特定遺贈のように個々の財産(「〇〇不動産をAに」「〇〇銀行の預貯金をBに」など)を指定する手間が不要なため、遺言書作成の負担を軽減できます。
例えば、「私の遺産の全てを妻に遺贈する」といったシンプルな記述で、不動産、預貯金、有価証券、動産など、遺言者のあらゆる財産を網羅的に指定することが可能です。これにより、遺言者の意思がより明確に伝わり、財産の種類や数が多い場合でも、漏れなく遺贈を実現できるという利便性があります。
2.2 遺産分割協議が不要になる場合がある
包括遺贈は、相続人同士の遺産分割協議を不要にする、または簡素化する効果が期待できます。特に、遺言者が遺産の全てを特定の単独の受遺者(例えば配偶者や特定の子供)に包括的に遺贈する旨を明確に定めた場合、受遺者が遺言内容に従って遺産を承継するため、原則として他の相続人との間で遺産分割協議を行う必要がなくなります。
これにより、相続人間での紛争のリスクを大幅に低減し、スムーズな遺産承継を実現できる可能性が高まります。ただし、受遺者が複数いる場合や、遺留分侵害額請求が行われる可能性のある場合は、遺産分割協議が必要になるケースもあります。この点は「包括遺贈のデメリット」の章で詳しく解説します。
2.3 相続人以外にも財産を渡せる
包括遺贈は、法定相続人ではない人物や団体にも、遺産を包括的に託すことを可能にするという重要なメリットを持っています。例えば、長年連れ添った内縁の配偶者、お世話になった友人、特定の慈善団体や学校法人など、法律上の相続権を持たない相手に財産を遺したいと考える場合、遺言による包括遺贈が有効な手段となります。
これにより、遺言者は自身の人生で築き上げた財産を、最も貢献したいと考える相手に自由に分配することができます。これは、法定相続分にとらわれず、遺言者の個人的な意思や社会貢献の意図を最大限に実現するための強力なツールとなります。
2.4 遺言者の意思を明確に反映できる
包括遺贈は、遺言者の最終的な意思を最も明確かつ包括的に反映させるための有効な手段です。遺言書を通じて、「誰に、どの財産を、どのような割合で承継させたいか」という遺言者の具体的な希望を、法的な効力をもって実現できます。
特に、相続人間での意見の相違や争いが予想される場合、包括遺贈によって遺言者の意思が明確に示されていれば、不必要なトラブルを未然に防ぎ、円満な遺産承継を促す効果が期待できます。遺言者が生前に抱いていた「この財産はあの人に」「この割合で分けたい」といった細やかな配慮も、包括遺贈によって具体的に形にすることが可能です。
3. 包括遺贈のデメリット

3.1 受遺者が負債も引き継ぐ可能性がある
包括遺贈は、遺産全体を包括的に承継させる性質を持つため、遺産に負債が含まれていた場合、受遺者もその負債を引き継ぐ義務を負うことになります。これは、相続人が負債を承継するのと同様の扱いです。例えば、被相続人に多額の借金や未払いの税金、連帯保証債務などがあった場合、包括受遺者はそれらの債務も引き受けなければなりません。
遺言者が亡くなるまで、遺産全体の内容、特に負債の有無や金額を正確に把握することは困難な場合があります。そのため、遺言書作成時には想定していなかった負債が後から発覚し、受遺者が思わぬ負担を強いられるリスクがあります。遺産が負債超過であった場合、受遺者は経済的に大きな不利益を被る可能性があります。
3.2 遺留分侵害額請求のリスクがある
包括遺贈によって、遺言者の財産が特定の受遺者に集中して渡される場合、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が持つ「遺留分」を侵害する可能性があります。遺留分とは、一定の法定相続人に法律で保障された最低限の遺産取得割合のことです。
包括遺贈によって、遺留分を持つ相続人の取り分が不足した場合、その相続人は受遺者に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。この請求が認められると、受遺者は遺留分を侵害した分の金銭を、請求した相続人に対して支払う義務が生じます。遺贈を受けた財産の中から金銭を支払う必要が生じるため、受遺者にとっては予期せぬ出費となり、大きな負担となる可能性があります。
3.3 相続放棄の検討が必要になる場合がある
包括受遺者は、相続人と同様に、遺贈された財産の中に多額の負債が含まれている場合や、遺贈を受けることで経済的に不利益が生じると判断した場合に、その包括遺贈を放棄することができます。これを「包括遺贈の放棄」と呼び、実質的には相続放棄と同じ手続きを踏みます。
包括遺贈の放棄は、自己のために包括遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を過ぎてしまうと、原則として放棄はできなくなり、負債を含めた包括遺贈を全て受け入れることになってしまいます。そのため、遺言者の死後、遺産の内容を速やかに調査し、負債の有無やその額を把握した上で、放棄の要否を慎重に検討する必要があります。
3.4 遺産分割協議が必要になるケースがある
包括遺贈は遺産全体を特定の受遺者に託すため、原則として遺産分割協議が不要になるというメリットがありますが、以下のような場合には遺産分割協議が必要になるケースがあります。
- 遺言書に記載されていない財産があった場合: 遺言書で包括遺贈の対象とされなかった財産(例えば、遺言書作成後に取得した財産など)が残っていた場合、その財産については法定相続人による遺産分割協議が必要になります。
- 受遺者が複数いて、各自の取得割合が不明確な場合: 複数の人物に包括遺贈を行う場合でも、遺言書でそれぞれの受遺者がどの割合で財産を受け取るかが明確に定められていないと、受遺者間で協議が必要になります。
- 遺留分侵害額請求が発生し、その解決のため: 前述の遺留分侵害額請求が行われた場合、受遺者と遺留分権利者との間で、金銭の支払い方法や金額について協議が必要となることがあります。
- 包括遺贈が一部の財産に限定されている場合: 「遺産の一部を包括的に遺贈する」といった内容の遺言の場合、残りの財産については相続人による遺産分割協議が必要となります。
このように、包括遺贈を行ったとしても、遺言書の内容や遺産、相続人の状況によっては、必ずしも遺産分割協議を完全に避けられるわけではない点に注意が必要です。
4. 包括遺贈を行う際の注意点

包括遺贈は、遺言者の意思を強く反映できる強力な手段ですが、その実施にあたっては様々な注意点を理解しておく必要があります。適切な手続きを踏まないと、遺言が無効になったり、受遺者や相続人との間で予期せぬトラブルが発生したりする可能性があります。ここでは、包括遺贈を円滑に進めるために特に留意すべき事項を詳しく解説します。
4.1 遺言書の作成方法と形式
包括遺贈を行うためには、必ず遺言書を作成する必要があります。遺言書には民法で定められた厳格な要件があり、これらを満たさない場合、遺言全体が無効となる恐れがあります。特に注意すべきは、公正証書遺言と自筆証書遺言のそれぞれの特徴と留意点です。
4.1.1 公正証書遺言の活用
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がそれを筆記して作成されます。この方式の最大のメリットは、法律の専門家である公証人が関与するため、形式不備による無効のリスクが極めて低い点です。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配もありません。遺言能力の確認も公証人が行うため、後々の争いを防ぐ上でも有効です。
4.1.2 自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印することで作成できる遺言書です。手軽に作成できる点がメリットですが、形式不備による無効のリスクが高いという大きなデメリットがあります。例えば、日付の記載漏れや押印忘れ、加筆修正方法の不備などが原因で無効と判断されるケースは少なくありません。また、保管場所によっては紛失や改ざんのリスクも伴います。これらのリスクを軽減するため、2020年7月10日からは法務局における自筆証書遺言の保管制度が始まりました。この制度を利用すれば、形式の確認と保管を法務局が行ってくれるため、安全性と確実性が向上します。
4.2 遺言執行者の選任
包括遺贈を含む遺言の内容を円滑に実現するためには、遺言執行者を選任しておくことが非常に重要です。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な一切の手続きを行う権限を持つ人のことです。
具体的には、遺言執行者は、遺言書の内容を相続人や受遺者に通知したり、遺産目録を作成したり、不動産の登記名義変更手続きを行ったり、預貯金の解約・名義変更手続きを行ったりするなど、多岐にわたる業務を遂行します。遺言執行者が選任されていない場合、これらの手続きを相続人全員で行う必要があり、意見の対立などから手続きが滞る原因となることがあります。
遺言執行者には、相続人の中から選任することも可能ですが、利害関係のない弁護士や司法書士、信託銀行などの専門家を選任することで、より公平かつスムーズな遺言の執行が期待できます。
4.3 受遺者の権利と義務
包括遺贈によって財産を受け取る受遺者は、特定の財産を受け取る特定遺贈の受遺者とは異なり、相続人とほぼ同様の権利と義務を負うことになります。これは、包括遺贈が遺産の全部または一定割合を承継させるものであるためです。
具体的には、受遺者は、遺贈された財産だけでなく、遺言者が残した負債(借金や未払金など)も承継する可能性があります。そのため、遺贈を受ける前に、遺言者の財産状況(プラスの財産とマイナスの財産)を十分に確認することが重要です。もし負債が多額であると判明した場合や、遺贈を望まない場合には、後述する「包括遺贈の放棄」を検討する必要があります。
4.4 包括遺贈の放棄について
包括遺贈を受けた受遺者は、その遺贈を放棄する権利を持っています。これは、遺贈によって負債を承継するリスクがあるため、受遺者を保護するための制度です。
包括遺贈の放棄は、自己のために遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述することで行います。この期間を過ぎると、原則として放棄はできなくなり、包括遺贈を承認したものとみなされます。一度放棄すると、原則として撤回はできません。
包括遺贈を放棄した場合、その受遺者は最初から遺贈がなかったものとみなされます。その結果、放棄された財産は、遺言書に別の定めがなければ、他の相続人や受遺者に帰属することになります。
4.5 税金に関する注意点
包括遺贈によって財産を取得した場合、税金に関する様々な注意点があります。特に、相続税、贈与税、不動産取得税、登録免許税について理解しておくことが重要です。
4.5.1 相続税と贈与税の違い
包括遺贈によって財産を取得した場合、その財産は相続税の課税対象となります。これは、遺言者の死亡によって財産が移転するためです。一方、贈与税は生前に財産を無償で受け取った場合に課される税金であり、遺贈とは課税のタイミングや税率、基礎控除額などが異なります。相続税には基礎控除額が設けられており、一定額以下の財産であれば税金がかからない場合があります。しかし、受遺者が遺言者の法定相続人以外の場合、相続税額が2割加算される点に注意が必要です。
4.5.2 不動産取得税と登録免許税
包括遺贈によって不動産を取得した場合、不動産取得税と登録免許税がかかります。不動産取得税は、不動産を取得したことに対して課される地方税です。登録免許税は、不動産の所有権移転登記を行う際に課される国税です。
特に登録免許税については、相続による移転登記の場合と遺贈による移転登記の場合で税率が異なります。一般的に、遺贈による不動産の所有権移転登記の登録免許税率は、相続による場合よりも高くなる傾向があります。具体的な税率は、不動産の評価額や取得原因によって変動するため、事前に税理士や司法書士などの専門家に相談し、正確な税額を把握しておくことが重要です。
以下の表で、相続と包括遺贈における不動産取得時の税金の違いをまとめました。
| 税金の種類 | 相続による取得 | 包括遺贈による取得 |
| 相続税 | 課税対象 | 課税対象(受遺者が法定相続人以外の場合2割加算) |
| 贈与税 | 課税対象外 | 課税対象外 |
| 不動産取得税 | 原則として非課税 | 課税対象 |
| 登録免許税 | 不動産評価額の0.4% | 不動産評価額の2.0% |
※上記税率は一般的な目安であり、特例や個別の状況により異なる場合があります。詳細は専門家にご確認ください。
4.6 遺留分に関する対策
包括遺贈は遺言者の意思を最大限に尊重するものですが、遺留分を侵害する可能性があり、これがトラブルの原因となることがあります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に法律上保障された、遺産のうち最低限取得できる割合のことです。
包括遺贈によって、特定の受遺者に財産を集中させすぎると、他の法定相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使して、受遺者に対して金銭の支払いを求めることができます。この請求は、遺贈の効力発生後、原則として1年以内に行使される可能性があり、受遺者にとっては予期せぬ金銭負担となることがあります。
遺留分に関するトラブルを避けるためには、遺言作成時に以下の対策を検討することが重要です。
- 遺留分を考慮した遺贈内容にする。
- 生前贈与や生命保険の活用など、遺留分を侵害しない形での財産移転を検討する。
- 遺留分を放棄してもらう(ただし、家庭裁判所の許可が必要)。
遺留分に関する問題は複雑なため、遺言作成前に必ず弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。例えば、日本弁護士連合会のウェブサイトなどで相談窓口を探すことができます。日本弁護士連合会
4.7 トラブルを避けるためのポイント
包括遺贈は、遺言者の意思を明確に反映できる強力な手段である一方で、その性質上、トラブルに発展しやすい側面も持ち合わせています。円滑な遺産承継を実現し、紛争を未然に防ぐためには、以下のポイントを意識することが重要です。
- 遺言書の内容を明確にする:あいまいな表現や解釈の余地がある記述は、後々の争いの原因となります。具体的にどの財産を誰に、どのような割合で遺贈するのかを明確に記載しましょう。
- 専門家への相談:弁護士、司法書士、税理士などの専門家は、遺言書の作成支援、税務アドバイス、遺言執行者の引き受けなど、包括遺贈に関するあらゆる面でサポートを提供できます。特に複雑な財産構成の場合や、相続人以外への遺贈を検討している場合は、必ず専門家の助言を得ましょう。
- 相続人への配慮と事前説明:包括遺贈によって法定相続人の取り分が大きく減少する場合、感情的な対立が生じやすくなります。可能であれば、生前に遺言の意図や内容について相続人に対し説明し、理解を得る努力をすることが、トラブル回避につながります。
- 遺言執行者の選任:前述の通り、遺言執行者の選任は遺言の確実な実現のために不可欠です。中立的な立場の専門家を選任することで、相続人間の紛争を避け、スムーズな手続きが期待できます。
これらの注意点を踏まえ、慎重に準備を進めることで、包括遺贈が遺言者の意思を尊重しつつ、円満な遺産承継を実現する有効な手段となるでしょう。
5. 包括遺贈の活用事例

包括遺贈は、遺言者の多様な意思を実現するための強力な手段となります。ここでは、具体的な活用事例を3つご紹介し、それぞれのケースで包括遺贈がどのように役立つのかを解説します。
5.1 法定相続人以外に財産を渡したい場合
包括遺贈は、法律上の相続権を持たない方に財産を遺したい場合に特に有効な手段です。例えば、長年連れ添った内縁の配偶者や事実婚のパートナー、献身的に介護をしてくれた親族(甥、姪など)、あるいは親しい友人など、法定相続人ではないけれども、自分の財産を託したいと考えるケースは少なくありません。
特定遺贈では個々の財産を具体的に指定する必要がありますが、包括遺贈であれば「私の全財産の半分を〇〇に遺贈する」といった形で、包括的に財産を承継させることが可能です。これにより、遺言書作成の手間を省きつつ、遺言者の意思を明確に反映させることができます。
| 対象者 | 包括遺贈が適する理由 | 注意点 |
| 内縁の配偶者・事実婚のパートナー | 法律上の相続権がないため、包括遺贈によって生活保障や感謝の意を示すことができる。 | 他の法定相続人との間で遺留分侵害額請求のリスクがある。 |
| 献身的に介護してくれた親族(甥・姪など) | 相続権がない場合でも、労をねぎらい、今後の生活を支援できる。 | 受遺者が負債も引き継ぐ可能性があるため、遺産内容の確認が重要。 |
| 親しい友人・知人 | 個人的な関係性に基づいて、特定の財産ではなく包括的に遺産を託したい場合に有効。 | 相続税の負担が重くなる場合がある(受遺者と遺言者の関係性による)。 |
5.2 特定の団体や法人に寄付したい場合
社会貢献や特定の活動支援を目的として、ご自身の財産を特定の団体や法人に遺贈したいと考える方もいらっしゃいます。これを「遺贈寄付」と呼びます。包括遺贈は、このような遺贈寄付においても有効な選択肢となります。
例えば、長年支援してきたNPO法人、研究を支援したい公益財団法人、出身校の学校法人、信仰する宗教法人などに対し、ご自身の遺産の一部または全部を寄付することが可能です。包括遺贈であれば、「私の全財産の〇分の〇を〇〇法人に遺贈する」といった形で、遺産の構成が複雑であっても包括的に指定できるため、手続きが簡素化されます。
遺贈寄付を受けた団体側は、原則として相続税が非課税となるメリットがあります(ただし、公益目的事業に利用されることなどの要件を満たす必要があります)。遺言者は、自身の死後も社会に貢献できるという形で、その意思を実現することができます。
| 目的 | 包括遺贈の利点 | 考慮すべき点 |
| 社会貢献・特定の活動支援 | 遺言者の意思に基づき、特定の団体を通じて社会に貢献できる。 | 受遺者となる団体が遺贈を受け入れる能力(受遺能力)があるか確認が必要。 |
| 事業の継続的な支援 | 遺産の一部または全部を包括的に寄付することで、団体の安定的な運営に貢献できる。 | 遺言執行者の選任を検討し、遺贈が確実に実行されるようにする。 |
| 遺産整理の簡素化 | 複数の財産を個別に指定する手間なく、包括的に遺贈できる。 | 遺贈寄付に関する税制上の優遇措置について、専門家への相談が推奨される。 |
5.3 遺産全体を特定の人物に託したい場合
包括遺贈は、特定の人物に自身の遺産の大部分または全部を承継させたい場合に非常に有効です。例えば、事業を承継する後継者に事業用資産を含めた全ての財産を集中させたい場合や、特定の相続人(例:長男)に多くの財産を遺し、遺産分割協議の手間を省きたい場合などが挙げられます。
「私の全財産を〇〇に遺贈する」と指定することで、遺産の内容が多岐にわたる場合でも、個々の財産を特定する煩雑な作業が不要となります。これにより、遺言者の意思が明確に反映され、遺産分割を巡る将来的なトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。
ただし、この場合も、他の法定相続人の遺留分を侵害しないよう十分な配慮が必要です。遺留分侵害額請求のリスクを考慮し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。
| 目的・状況 | 包括遺贈のメリット | 留意点 |
| 事業承継を円滑に進めたい | 事業用資産を含む全財産を後継者に包括的に引き継がせ、事業の継続性を確保できる。 | 負債も引き継がれる可能性があるため、事業の財務状況を考慮する必要がある。 |
| 特定の相続人に多くを遺したい | 遺言者の強い意思を反映し、特定の相続人に遺産を集中させることができる。 | 他の法定相続人の遺留分を侵害しないよう、遺留分対策を検討する。 |
| 遺産分割協議を避けたい・簡素化したい | 包括的な指定により、遺産分割協議が不要になる場合があり、手続きがスムーズに進む。 | 受遺者が遺贈を放棄する可能性や、遺留分侵害額請求により協議が必要になるケースがある。 |
6. まとめ
包括遺贈は、遺産全体を特定の受遺者に託し、遺言者の意思を明確に反映できる強力な遺言方法です。遺産分割の負担軽減といったメリットがある一方で、受遺者が負債を引き継ぐ可能性や遺留分侵害額請求のリスク、税金に関する注意点も存在します。これらのメリット・デメリットを理解し、遺言書の作成方法から税務対策、遺留分への配慮まで、多岐にわたる注意点を踏まえることが不可欠です。円滑な遺産承継と将来のトラブル回避のためには、弁護士や税理士といった専門家へ事前に相談し、慎重に計画を進めることが最も賢明な選択と言えるでしょう。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を監修したのは…
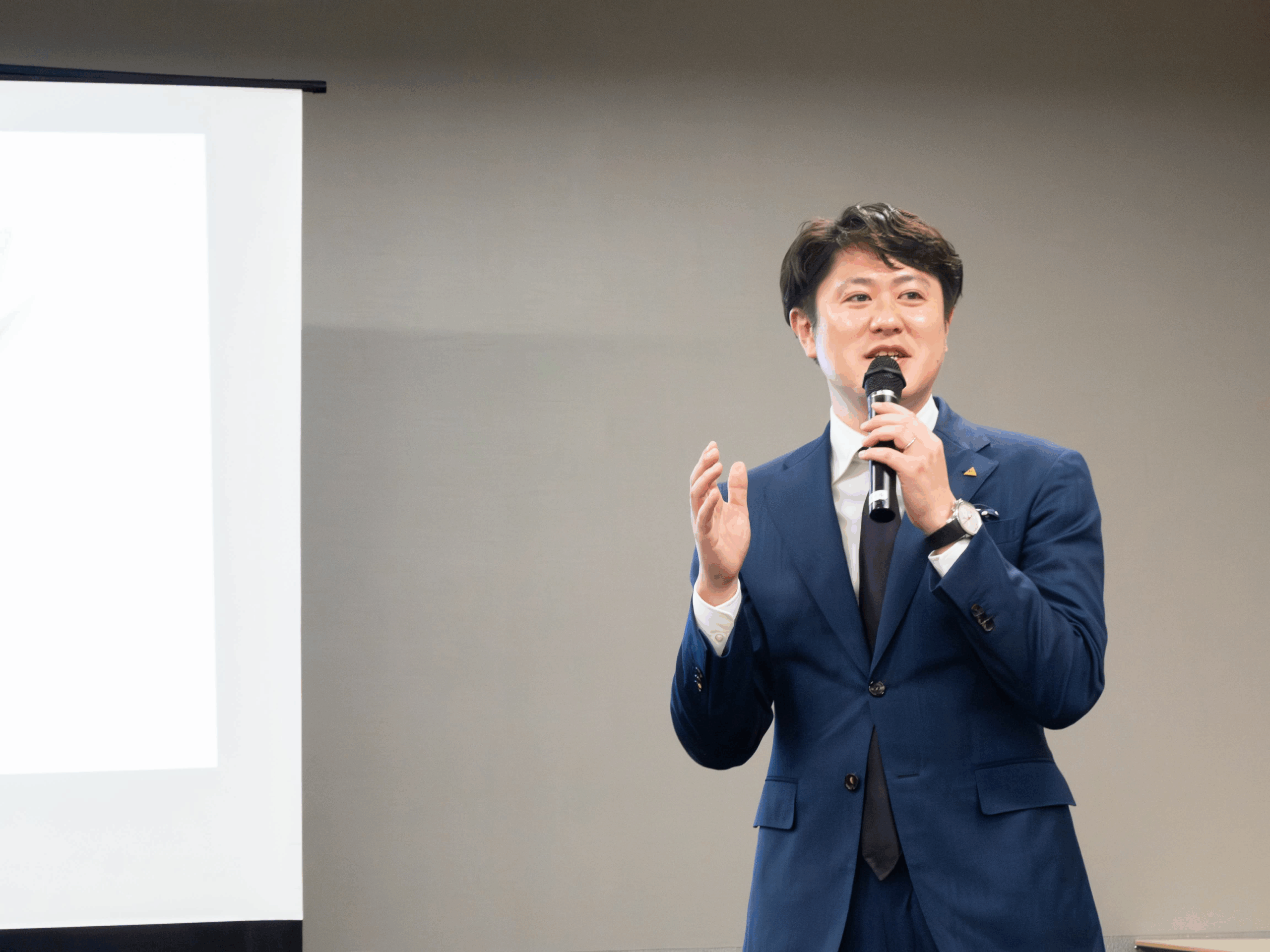
司法書士法人・行政書士あかりテラス代表、株式会社あかりテラス代表、 一般社団法人債務整理相談センター
宮村 和哉(みやむら かずや)
司法書士・行政書士宮村和哉は、相続手続きに精通した司法書士として、地域密着型のサービスを展開。相続トラブルにしないためには「事前準備」が大切であるとの想いで、情報発信を積極的に行っている。年間相談件数700件、終活セミナー年間80会場。熊本を拠点に、福岡などにも支店を構え、多くの相続相談に対応してきた実績を持つ。親しみやすい人柄と的確なアドバイスで信頼を集めている。
サイトURL:https://office-akariterrace.com/ https://www.instagram.com/akariterrace.hohoemi/








