小規模宅地の特例の要件とは?適用条件や計算方法、手続きや必要書類を解説

Contents
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、相続または遺贈により取得した宅地について、一定の要件を満たすことで、その土地の相続税評価額を最大80%まで減額できる制度です。これにより、相続税の大幅な軽減が可能となり、相続人の生活維持や事業の継続がしやすくなります。特に、不動産などの分割・換金が難しい資産を相続する際の納税負担を軽くするために設けられた制度であり、相続税対策の柱ともいえる存在です。
この特例の対象となるのは、故人(被相続人)が生前に居住していた土地や、事業あるいは貸付に供していた土地であり、相続人がそれを引き継ぐ場合に限られます。
特例の概要と適用の背景
相続税は、現金や預貯金だけでなく、不動産や有価証券などすべての財産を対象として課税されます。とりわけ、被相続人が長年住み続けていた自宅や、家族で営んできた事業用の土地が高額な評価額になると、相続人が納税資金を捻出できずに売却を余儀なくされるリスクがあります。こうした不合理を回避し、故人の生活や事業の基盤を守るために、小規模宅地等の特例が制度化されました。
この制度は、居住や事業の継続を前提として、相続税の課税価格を大幅に減額することにより、相続人の生活や事業の安定を図るものです。税負担の軽減という観点だけでなく、土地の有効活用や円満な遺産分割の促進にもつながっています。
小規模宅地等の特例のメリットと節税効果
本特例を利用する最大のメリットは、相続税の節税効果が非常に高い点です。特例が利用できるならば、例えば土地の相続税評価額が2億円であった場合、最大4,000万円まで評価額を下げられ、その分かかる相続税は少なくなります。
また、土地を売却せずに済むため、相続人がそのまま居住を続けたり、事業を継続できるという点でも大きな利点があります。
適用対象となる土地の種類と減額割合
特例の対象となる宅地の種類は次の4種類です。
- 特定居住用宅地等:被相続人やその親族が住んでいた土地。330㎡まで80%減額。
- 特定事業用宅地等:貸付事業以外で被相続人やその親族が事業をしていた土地。400㎡まで80%減額。
- 特定同族会社事業用宅地等:貸付事業以外での法人の事業のために利用していた土地。400㎡まで80%減額。
- 貸付事業用宅地等:被相続人やその親族が貸付業務をしていた土地。200㎡まで50%減額。
つまり、特例が適用される土地に相続開始の直前、被相続人が単独で住んでいたり、事業へ使っていたりしていた場合だけでなく、被相続人と「生計を一」にしていた親族が住んでいた場合等も含まれます。
なお、生計を一にするとは、被相続人と家族がいわば同じ財布で共に日常の生活を送っているという意味です。同居していなくても家族へ生活費等のため常に送金している場合は、生計を一にしていると言えます。
小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例は、相続税の申告時に税務署で手続きを行います。その他、宅地の種類ごとに細かい要件が設定されています。
特例の適用要件と対象宅地の種類
小規模宅地等の特例を適用するには、宅地の用途区分ごとに異なる要件を満たす必要があります。共通する条件としては、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに申告書の提出を行い、特例の適用を明記し、必要書類を添付することが求められます。土地の種類ごとに「居住」「事業」「貸付」の実態、所有者の続柄、生計一関係の有無などが判断基準となります。
特定居住用宅地等(居住用宅地)の適用要件
住んでいたのが被相続人か、生計を一にしていた親族かで要件が変わります。
(1)住んでいたのが被相続人の場合・住んでいたのが生計を一にしていた親族の場合
・被相続人の配偶者:申告期限まで宅地等へ居住の必要も、所有の必要も無し
(2)住んでいたのが被相続人の場合
次のケースが認められます。
| 被相続人と同居の親族 | 被相続人と同居していない親族 |
|---|---|
| 申告期限まで宅地等へ居住し、所有している | 次の要件に合致する(家なき子特例) ・被相続人に配偶者、同居の相続人がいない ・宅地を引き継いだ親族が相続の3年前までに自己または自己の配偶者、3親等以内の親族、特別の関係がある法人の持ち家に住んだことがない ・相続開始時、居住家屋を過去に所有していない ・相続開始時から申告期限まで宅地等を所有している |
(3)住んでいたのが生計を一にしていた親族の場合
こちらの条件は、生計を一にしていた親族が申告期限まで宅地等へ居住し、所有していることが条件です。
特定事業用宅地等(事業用宅地)の適用要件
貸付事業以外で被相続人やその親族が事業をしていた土地に関しては、2つの区分があり次の要件を満たしている必要があります。
(1)被相続人の事業の用に供されていた宅地等
| 事業承継要件 | 保有継続要件 |
|---|---|
| ・宅地上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継いでいる ・相続税の申告期限までその事業を営んでいる | ・宅地等を相続税の申告期限まで有している |
(2)被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等
| 事業承継要件 | 保有継続要件 |
|---|---|
| ・相続開始の直前~申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいる | ・宅地等を相続税の申告期限まで有している |
特定同族会社事業用宅地等の適用要件
特定同族会社事業用宅地等の場合は、次の4点が要件です。
- 相続開始の直前に被相続人・その親族等が発行済株式の総数か出資の総額の50%超を有している
- 法人に対し相当な対価で対象不動産を賃貸
- 宅地等を引き継いだ親族が申告期限に法人の役員である
- 宅地等を申告期限まで保有
前提として被相続人・その親族等は、法人に対し強い支配権を有している必要があります。
貸付事業用宅地等(貸していた土地)の適用要件
被相続人やその親族が貸付業務をしていた土地に関しては、2つの区分があり次の要件があります。
(1)被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等
| 事業承継要件 | 保有継続要件 |
|---|---|
| ・宅地上に関する被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継いでいる ・相続税の申告期限までその貸付事業を継続している | ・宅地等を相続税の申告期限まで有している |
(2)被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業に供されていた宅地等
| 事業承継要件 | 保有継続要件 |
|---|---|
| ・相続開始前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っている | ・宅地等を相続税の申告期限まで有している |
異なる用途の宅地を併用する場合の適用条件
たとえば、自宅用地と貸付用地の両方を相続した場合、それぞれの区分ごとに特例を併用することができます。ただし、全体としての限度面積(730㎡)を超えることはできません。用途ごとの要件を満たしていれば、合算しての特例適用が可能です。
小規模宅地等の特例の適用範囲と計算方法
ここでは、特例を利用した場合の相続税評価額の減額率や、その計算方法をみていきましょう。
宅地の種類ごとの減額率と適用面積の制限
本特例が適用される面積・減額率は、宅地の種類ごとに違ってきます。下表をご覧ください。
| 宅地の種類 | 適用面積 | 減額率 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330㎡以下 | 80% |
| 特定事業用宅地等特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡以下 | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡以下 | 50% |
減額率は50%〜80%になっています。
適用面積を超えた場合の減額計算方法
特例の上限面積を超えた部分については、通常通りの相続税評価額が課税対象になります。たとえば、貸付事業用宅地が300㎡ある場合、適用されるのは200㎡分までであり、残りの100㎡は減額の対象外です。
計算式の例:
評価額2,100万円、面積300㎡→
2,100万円×(200㎡/300㎡)×50%=700万円(減額)
相続税課税対象評価額は残りの1,400万円となります。
特例適用後の相続税計算例
具体的な事例をあげて、相続税評価額の減額率を計算してみましょう。
居住用宅地の計算例
被相続人が住んでいた土地(特定居住用宅地等)を相続人が引き継いだケース。
- 宅地の面積:250㎡(上限330㎡以内)
- 評価額:3,000万円
→減額率80%が全面適用
3,000万円×80%=2,400万円の減額
課税対象評価額:600万円
事業用宅地の計算例
被相続人が事業に使用していた土地を相続したケース。
- 面積:350㎡(上限400㎡以内)
- 評価額:5,000万円
→5,000万円×80%=4,000万円の減額
課税対象評価額:1,000万円
貸付事業用宅地の計算例
被相続人が賃貸用に保有していた土地を相続したケース。
- 面積:300㎡(うち200㎡までが対象)
- 評価額:2,100万円
→2,100万円×(200/300)×50%=700万円の減額
課税対象評価額:1,400万円
複数の土地を併用する場合の計算例
特定居住用宅地330㎡と貸付事業用宅地200㎡を同時に相続した場合の試算:
- 居住用宅地評価額:4,000万円
→4,000万円×80%=3,200万円減額 - 貸付用宅地評価額:1,500万円
→1,500万円×50%=750万円減額
合計減額:3,950万円
課税対象:550万円(5,500万円-3,950万円)
小規模宅地等の特例の申請手続きと必要書類
申告手続きは、相続税の申告書に本特例の適用希望を明記後、必要書類を添付し、納税地を管轄する税務署へ提出します。
特例適用の申請の流れと期限
相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告書を提出しなければなりません。この期限を過ぎると、小規模宅地等の特例は原則として適用されません。
相続発生から申請までのステップ
相続発生から申請までのステップは、以下のとおりです。
- 被相続人の死亡により相続が発生
- 相続人の確定と遺産分割協議の実施
- 相続財産(宅地等)の調査と評価
- 小規模宅地等の特例が適用できるかを確認
- 必要書類の収集と申告書の作成
- 相続開始から10か月以内に税務署へ提出
この一連の流れを適切に進めることで、特例の適用を受けることができます。相続人の事情や土地の状況により手続きが複雑になるため、早めの準備と専門家への相談が重要です。
相続税申告と特例の適用期限
相続税の申告期限は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。この期間内に、相続税の申告書と共に、小規模宅地等の特例に必要な書類を提出する必要があります。
ただし、遺産分割協議が申告期限内にまとまらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、特例の適用を保留することが可能です。この場合、3年以内に分割協議を終え、正式な遺産分割協議書を提出すれば、特例を遡って適用できます。
特例申請の提出手順と注意点
小規模宅地等の特例を受けるためには、通常の相続税申告とは異なり、以下のような追加の手続きや書類の添付が必要になります。土地の種類や利用状況によって要件が異なるため、事前に正確な確認と準備を行いましょう。
1.相続税申告書に「特例適用希望」の旨を明記する
特例を適用する場合、相続税申告書の中にある「明細書(第11表)」に該当土地の情報を記載し、減額の対象とすることを明示します。これを記載しない限り、特例の適用はされません。
- 特定居住用宅地等、特定事業用宅地等など、該当する区分を正しく記入
- 各宅地ごとに面積・所在地・利用状況などの詳細な情報を記載
2.土地の区分を正確に分類し、必要な情報を記載
小規模宅地等の特例は、宅地の用途(居住・事業・貸付)によって要件が大きく異なります。誤った区分で申請すると却下される可能性があるため、以下の点を明確にしましょう。
- 被相続人または相続人の居住実態の有無(居住用)
- 被相続人または相続人の事業の内容・継続性(事業用)
- 不動産貸付業の内容と継続性(貸付用)
また、複数用途の宅地を併用している場合には、それぞれの面積や利用形態を明確に分けて記載しなければなりません。
3.各種要件を満たしていることを証明する資料を添付
土地の利用状況や相続人の資格を証明するために、状況に応じた書類を添付する必要があります。主な添付資料は以下のとおりです:
- 戸籍謄本や住民票:生計一関係、同居関係の証明
- 登記事項証明書:土地の所有関係の証明
- 固定資産税の課税明細書:土地の用途と利用状況の証明
- 開業届、確定申告書:事業の有無や継続性の証明(事業用)
これらの証明書が不十分な場合、税務署から追加の資料提出を求められたり、特例の適用が認められないこともあります。
4.遺産分割協議書を添付(未分割の場合は見込書を添付)
原則として、遺産分割協議が成立しており、分割協議書が添付されていることが特例適用の条件です。宅地をどの相続人が取得するか確定していないと、特例の対象とはなりません。
ただし、やむを得ず10か月の申告期限内に分割協議がまとまらない場合は、以下の2点を提出することで特例の「保留申請」が可能です。
- 「申告書」:宅地等の評価減希望を明記
- 「申告期限後3年以内の分割見込書」:分割が成立する見込みである旨を記載
この猶予を使えば、最大3年間は分割協議の成立を待つことができます。期限内に協議がまとまった場合、特例をさかのぼって適用することが可能です。
5.被相続人と相続人の「居住・生計一関係」を正確に証明
特定居住用宅地等では、「同居していた」「生計を一にしていた」といった関係が要件となります。そのため、下記のような点を証明することが必要です。
- 同居を証明する住民票(同一世帯であることが明記されている)
- 生計一関係を示す資料(生活費の送金記録、扶養控除申告など)
- 過去の住民票履歴(転居歴がある場合)
これらの関係性が確認できないと、たとえ形式上は相続していても特例の適用を受けられません。
6.相続税が発生しない場合でも、申告書の提出が必要
「相続税がかからないから申告しない」という判断は大きな誤りです。特例を適用するには、税額がゼロであっても申告書の提出と、必要書類の添付が絶対条件です。
申告がなければ、税務署はその土地に対して評価減の適用を判断することができません。よって、相続税の課税対象外であっても、申告書は必ず提出しましょう。
特例申請に必要な書類
ここでは、特例の申請に必要な書類について解説します。それぞれのケースに合わせて説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。
全てのケースで共通する必要書類
特例を適用する際にすべてのケースで必要となる書類は次の通りです。
- 相続税の申告書:最寄りの税務署の窓口等で取得
- 住民票(相続人の世帯全員):住所地の市区町村役場で取得
- 住民票除票(被相続人):住所地の市区町村役場で取得
- 戸籍謄本:本籍地の市区町村役場から取得、なお相続開始の日から10日経過後に作成されたものが必要
- 遺言書の写し:遺言書があったとき
- 遺産分割協議書の写し:遺産分割協議をしたとき
- 印鑑証明書(相続人全員分):各住所地の市区町村役場で取得、なお遺産分割協議書と同じ印鑑であることが必要
相続人の状況別に必要な書類
相続人が被相続人と同居していたか、別居していたか、または老人ホームに入所していたかによって、必要書類が異なります。
同居していた相続人の申請に必要な書類
同居していた相続人の申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 同一世帯であることを証明する住民票
- 宅地を所有していることを示す登記事項証明書
- 宅地が居住用として使用されていたことを示す固定資産税の課税明細書など
別居していた相続人(家なき子特例)の場合
別居していた相続人(家なき子特例)の場合に必要な書類は、以下のとおりです。
- 過去3年間の居住履歴を示す住民票の除票または履歴付き住民票
- 相続人自身・配偶者・3親等内の親族または特定法人の所有不動産に居住していなかったことを証明する資料(不動産登記簿など)
- 被相続人に配偶者または同居相続人がいなかったことを確認する戸籍謄本
- 宅地の登記事項証明書
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合に必要な書類は、以下のとおりです。
- 要介護認定証または要支援認定証
- 老人ホーム等との施設入所契約書の写し
- 被相続人の自宅が賃貸されていなかったことを証明する書類(空き家証明、電気水道の使用履歴など)
- 被相続人の戸籍の附票(生活の本拠が変わっていないことを証明)
事業用宅地・貸付事業用宅地を申請する場合
事業用宅地・貸付事業用宅地を申請する場合に必要な書類は、以下のとおりです。
- 事業の開業届、確定申告書、青色申告決算書など(事業の継続性を示す資料)
- 賃貸契約書(貸付事業の場合)
- 宅地の登記事項証明書
- 固定資産税課税明細書など、宅地の利用用途がわかる資料
介護施設入所時の特例適用と証明書類
介護施設入所時の特例を適用するためには、要件に該当することと、必要書類を集めることが必要です。
適用要件と確認ポイント
被相続人が亡くなる前に老人ホームや介護施設に入所していた場合、形式的には「自宅に居住していなかった」とも取れるため、特例の対象外となる恐れがあります。
しかし、以下の3つの条件をすべて満たせば、居住用宅地として小規模宅地等の特例が適用される可能性があります。
- 被相続人が要介護認定または要支援認定を受けていたこと
- 施設に入所後も、元の自宅が第三者に貸し出されることなく保有されていたこと
- 施設が生活の本拠とはいえない状況にあったこと(例:入退所を繰り返していた、家族が管理し定期的に帰宅していた、など)
これらの条件が揃っていれば、形式的には居住していなかった宅地でも、「特定居住用宅地等」として特例の適用が可能です。
証明に必要な書類と提出方法
上記の条件を満たしているかを税務署に説明するには、次のような書類を提出する必要があります:
- 要介護認定証または要支援認定証の写し
⇒介護保険証などで要介護・要支援の区分を確認します。 - 介護施設の入所契約書または入退所履歴が分かる書類
⇒入所日や利用形態が明記された契約書の写しなど。短期入所や試用期間の有無なども記録されていると有利です。 - 宅地を第三者へ貸していなかったことを示す資料
⇒空き家であったことを証明できる電気・ガスの使用状況、近隣住民の陳述書、不動産会社に「未賃貸」として登録されていた事実など。 - 戸籍の附票の写し
⇒被相続人の最終的な居住地が施設ではなく、形式上も「自宅」となっていたことを確認します。
これらの書類を相続税の申告書に添付して提出します。内容が不十分な場合は、税務署から照会や追加資料の提出を求められることがあります。
小規模宅地等の特例が受けられないケースと注意点
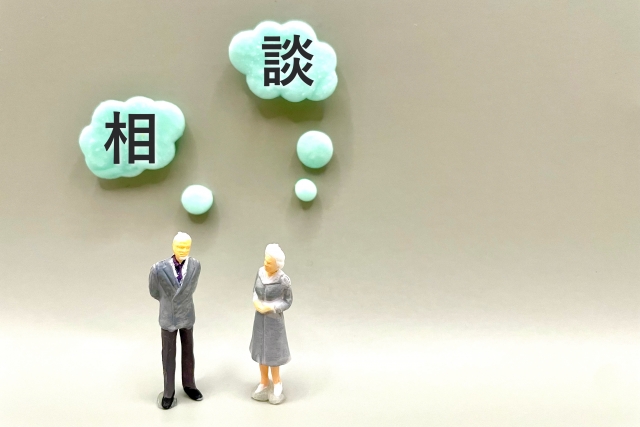
小規模宅地等の特例は節税効果が非常に大きいため、税務署も厳格に審査を行っています。以下のようなケースでは、特例の要件を満たしていないとして適用が否認されることがあります。
特例の適用要件を満たさないケース
ここでは、小規模宅地等の特例の適用外となるケースをいくつか取り上げて説明します。自分の状況と見比べて、参考にしてみてください。
相続人が住民票のみを移していた場合の適用可否
被相続人と仲が良い親族でも、生活の本拠が別にあり、住民票だけを被相続人の住所地へ移しているだけでは特例の適用外です。
子Aは申告期限まで宅地等へ居住し、所有している必要があります。また、被相続人と別居していて、被相続人の様子を見に定期的に何回か被相続人宅へ泊まっていた、という場合も適用外です。
なお、子Aではなく被相続人の配偶者が引き継ぐ場合に限っては、無条件で本特例が適用されます。
相続人が過去に対象宅地上の建物を被相続人へ譲渡していた場合
宅地を引き継ぐ子Bがずっと前から賃貸住宅に住んでおり、被相続人に配偶者・同居の相続人がいなかった場合、一見「家なき子特例」を利用し、相続税評価額の減額ができそうに思えます。
しかし、何らかの理由で以前、対象宅地上にある子Bの所有家屋を被相続人へ譲り、相続で譲渡した家屋が再び戻ってきたという経緯なので、家なき子特例は適用できません。
相続時精算課税制度で贈与を受けた場合の影響
相続開始前に、相続時精算課税制度を利用して宅地を贈与された場合、その宅地は相続によって取得したものとはみなされない可能性があります。
- 特例は「相続または遺贈により取得した宅地」が対象です。
- 精算課税制度の利用履歴は申告書等で確認されるため、過去の贈与と相続財産の関係性をしっかり整理しておく必要があります。
特例適用における注意点とリスク
小規模宅地等の特例の申告を望んでいるのに、いろいろな事情によりなかなか準備が整わないという事態も想定されます。ここでは申告の際の注意点を取り上げます。
特例適用には相続税の申告が必要
小規模宅地等の特例は、相続税の申告を行った人しか適用を受けられません。たとえ税額がゼロになる見込みであっても、申告書の提出そのものが特例の前提条件です。
「課税されないから申告は不要」と判断してしまうと、せっかくの特例が利用できなくなってしまいます。
また、申告書には特例を適用する土地の区分・面積・評価額など、詳細な情報を記載する必要があります。
相続税の申告期限前に売却した場合の影響
小規模宅地等の特例は、「相続税の申告期限まで宅地を保有していること」が適用の必須条件です。
そのため、申告期限前に宅地を売却してしまうと、減額の対象外となり、通常の評価額で課税されます。
特に相続税の納税資金を確保するために宅地の売却を検討する場合には、以下の点に注意しましょう。
- 売却は必ず申告後に行う
- 売買契約書の日付や引渡日にも注意(申告期限を過ぎてからであること)
遺産分割協議がまとまらない場合のリスク
原則として、宅地がどの相続人に帰属するかが確定していない限り、小規模宅地等の特例は使えません。
しかし、申告期限までに分割が終わらないケースでは、次の対応をとることで特例適用の可能性を残すことができます。
- 申告書に「分割見込書」を添付して仮申告する
- 申告期限後3年以内に遺産分割協議書を提出する
この「3年ルール」は、納税者にとって大きな救済措置です。ただし、最終的に3年以内に分割が成立しないと特例は適用されません。
また、その間に宅地を売却してしまうと、当然特例の適用はできなくなります。
被相続人の居住状況による適用可否
被相続人が亡くなる直前まで実際にどこに居住していたかは、特例の適用に大きく関わります。たとえ自宅を所有していたとしても、老人ホームに入所していたり、住民票の住所と実際の生活の拠点が異なる場合などには、特例の対象とならない可能性があります。ここでは、被相続人の居住実態に応じた特例の可否を詳しく解説します。
老人ホーム入所中の被相続人の宅地の適用要件
前述の通り、被相続人が施設に入所していた場合でも、以下の条件をすべて満たす場合には、特定居住用宅地等として特例が適用されます。
- 要介護または要支援認定を受けていた
- 元の自宅を誰にも貸していなかった(賃貸していない)
- 施設が生活の本拠とされていなかった(自宅に戻る意思や管理体制があった)
加えて、戸籍の附票や施設契約書、介護認定証などの証拠書類の添付が必須です。税務署はこのようなケースにおいて、書類の整合性や実態の整合性を慎重に確認します。
二世帯住宅の特例適用条件
二世帯住宅でも、特例が適用されるかどうかは、建物の構造や生活実態に応じて判断されます。
「内部で行き来できる」「水回りを共有している」などの一体性がある構造であれば、同居扱いとなり、居住用宅地として特例の適用が可能です。
逆に、完全分離型の二世帯住宅で、被相続人と相続人が別世帯扱いになっていた場合には、同居していたとは認められないことがあります。
建築図面や住民票、生活実態の記録などにより、同居の実態を税務署に説明できる準備が必要です。
マンションの宅地は適用対象となるか
被相続人がマンションの一室に住んでいた場合でも、建物全体の敷地に対する「敷地利用権」(所有権や借地権)を持っていた場合は、小規模宅地等の特例の対象となります。
- 敷地全体のうち、自己所有していた持分に相当する部分に対して評価減を適用可能
- 専有部分の居住実態があれば、居住用宅地として判断される
ただし、共有部分の持分がごくわずかであったり、借地権が複雑に絡んでいるようなケースでは、評価方法や要件判定が難しくなるため、事前に税理士に相談するのが安心です。
小規模宅地等の特例に関するよくある質問
小規模宅地等の特例は、条件を満たすことで大幅に相続税が軽減される有利な制度ですが、その分、適用条件が細かく、誤解や疑問も多く生じます。ここでは、実際に多く寄せられる代表的な質問とその回答を取り上げます。
被相続人が老人ホームに入所していた場合の取り扱い
被相続人が相続開始時点で老人ホーム等に入所していたとしても、次の3条件をすべて満たす場合には、特定居住用宅地等として特例の適用が可能です。
- 要介護認定または要支援認定を受けていたこと
- 自宅が他人に貸し出されていなかったこと
- 老人ホームが「生活の本拠」ではなかったと判断されること(例:自宅への帰宅意思があった、家具等が残されていたなど)
この場合、施設の契約書や介護保険証、自宅の光熱費の使用状況などを資料として提出することが求められます。
二世帯住宅は同居とみなされるのか
二世帯住宅が「同居」として扱われるかは、その構造と生活実態により判断されます。
内部で行き来ができる、台所・風呂・トイレなどの設備を共有している構造の場合は、同居とみなされる可能性が高く、居住用宅地として特例の適用が可能です。
逆に、完全分離型で外からの出入りしかできない二世帯住宅の場合は、たとえ同じ建物でも「別居」と判断されるケースがあります。
建物の構造図、住民票、光熱費の支払状況、家族の証言などを総合的に見て判断されます。
遺産分割が確定しないと特例は適用できない?
原則として、遺産分割協議が成立し、相続人が取得した宅地が確定していなければ、特例の適用はできません。
しかし、申告期限内に協議がまとまらない場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、特例適用の意思を残すことができます。
その後、分割が成立した時点で改めて分割協議書を提出することで、遡って特例を適用することが可能です。
ただし、3年以内に分割が完了しない場合や、宅地が申告期限内に売却されてしまった場合は、特例の適用が認められませんので注意が必要です。
マンションの敷地にも適用されるか?
被相続人がマンションに居住していた場合でも、そのマンションの敷地に対する「敷地権」(所有権や借地権)がある場合には、その持分に応じた面積について特例の適用が可能です。
たとえば、1棟のマンション全体で1,000㎡の土地があり、そのうち5%の持分を有していた場合は、持分に相当する50㎡が居住用宅地として評価減の対象になります。
区分所有建物であっても、敷地権がある限り、特例は適用可能です。ただし、借地権などの形態によっては計算や判断が複雑になるため、税理士等への確認をおすすめします。
小規模宅地等の特例の活用は専門家に相談を
小規模宅地等の特例は適用条件が複雑で、手続きを進める際に困惑する場合も多いです。そんなときは税理士に不明点や悩み事を相談してみましょう。
小規模宅地等の特例の利用は、判断が難しい特例だと言えますので、税理士に必ず確認する必要があります。
税理士の中には相続に精通した「相続診断士」という専門資格を有した方もいます。相続診断士は、相続全般の専門資格を有する人なので、的確なアドバイスが期待できます。
「円満相続ラボ」では、相続に関する基本知識やトラブル回避の方法をわかりやすくお伝えし、専門家によるサポートを提供しています。円満な相続を実現するための最適なご提案をいたします。
相続に関する疑問がある方には、相続診断士による無料相談窓口もご利用いただけます。どうぞお気軽にご相談ください。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を書いたのは…

弁護士・ライター
中澤 泉(なかざわ いずみ)
弁護士事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続といった幅広い分野の案件を担当した後、メーカーの法務部で企業法務の経験を積んでまいりました。
事務所勤務時にはウェブサイトの立ち上げにも従事し、現在は法律分野を中心にフリーランスのライター・編集者として活動しています。
法律をはじめ、記事執筆やコンテンツ制作のご依頼がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。
この記事を監修したのは…

不動産と終活のお悩み解決パートナー
松本 直之(まつもと なおゆき)
私が宅建士とFP、妻が税理士という組合せで不動産×終活サポート×税務の3本柱で相続や終活の困りごとをワンストップで解決しております。
一般的な不動産会社は「地域密着型」なのに対して、私は「悩み密着型」で、例えば、全国にある実家の空き家の相談に乗っています。
お客様を利益優先の業者から守り、安心して充実した人生を送って貰える社会の実現を志としております。
サイトURL:https://satei3-ways.com/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC13ZCULhVarL0Z5fS25zTwg/featured








