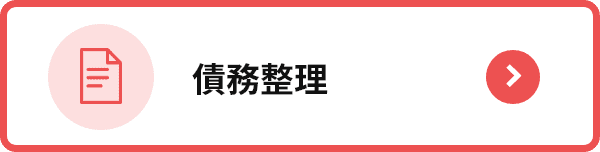NISAの相続完全ガイド!手続きの流れや税金、積立NISAや生前贈与について解説

Contents
NISAとは
NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益に税金がかからない制度です。少額からの資産形成を支援するために導入されました。
ここでは、NISAの基本的な仕組みやメリット・デメリット、新しく始まる「新NISA」について詳しく解説します。
NISAの基本概要
NISA(ニーサ)は、投資で得た利益に税金がかからない「少額投資非課税制度」です。通常、株や投資信託の利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を使えばこれが免除されます。
NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つがあり、2024年から新しい制度に変更されました。これにより、非課税の投資枠が増え、非課税で保有できる期間も無期限になりました。
NISAのメリット
NISAのメリットは、主に以下の4つです。
- 投資利益が非課税
株の売却益や配当に税金がかからず、資産を効率的に増やせます。 - 非課税保有期間が無期限
長期間の資産運用が可能になり、自由に売却や再投資ができます。 - 資産形成の自由度が高い
iDeCo(個人型確定拠出年金)は60歳まで引き出せませんが、NISAはいつでも売却して現金化できます。
NISAのデメリット
NISAのデメリットは、主に以下の4つです。
- 利益が出ないと非課税の恩恵がない
元本割れすると節税効果はなくなります。 - 損益通算ができない
NISA口座での損失は、課税口座の利益と相殺できません。 - 年間投資枠の繰り越し不可
使わなかった投資枠を翌年に持ち越せません。 - 課税口座の資産を移せない
既に持っている株や投資信託をNISA口座に移動できません。
積立NISAとは?どんな種類がある?
積立NISAとは、2018年から開始された少額からの長期・積立・分散投資を支援する非課税制度です。
積立NISAと一般のNISAの違い
初心者が気軽に投資信託を利用できるよう配慮されており、積立NISAの対象になる金融商品は金融庁に届け出があった「株式投資信託」と「ETF(上場投資信託)」のみに限定されます。
一般のNISAと特徴を比較してみましょう。
| 比較 | 積立NISA | 一般のNISA |
|---|---|---|
| 非課税保有期間 | 20年間 | 5年間 |
| 年間投資枠 | 40万円 | 120万円 |
| 投資可能商品 | 金融庁に届け出があった株式投資信託・ETF | 上場株式・ETF・公募株式投信・REIT等 |
| 買付方法 | 積立投資 | 通常買付・積立投資 |
なお、現時点では積立NISAと一般のNISAが併用できないので注意しましょう。
2023年税制改正での変更点
積立NISAと一般のNISAは2023年(令和5年)税制改正で大幅な変更が行われ、2024年から次のような内容に変わります。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 非課税保有期間 | ・積立NISA:最長20年間 ・一般NISA:最長5年間 | 無期限 |
| 口座開設期間 | ・積立NISA:2042年まで ・一般NISA:2028年まで | 恒久化 |
| 年間投資枠 | ・積立NISA:40万円まで ・一般NISA:120万円まで | 年間360万円まで投資可能 ・積立投資枠:年間120万円まで ・成長投資枠:年間240万円まで |
| 非課税保有限度額 | ・積立NISA:800万円まで ・一般NISA:600万円まで | 全体で1,800万円まで 成長投資枠は1,200万円まで売却後の投資枠再利用が可能 |
| 積立NISA・一般のNISA併用 | 不可 | 併用可能 |
新しいNISAの変更点と活用ポイント
新NISAは、従来のNISA制度を大幅に改良し、より柔軟で長期的な資産形成が可能になった投資制度です。非課税の恩恵を最大限に活用するために、改正点を理解し、賢く運用しましょう。
新NISAとは?
新NISAは、2024年からスタートした新しい少額投資非課税制度です。これまでのNISA制度が改正され、投資の自由度が大幅に向上しました。特に、非課税保有期間の無期限化や年間投資枠の拡大が大きな特徴です。
投資枠は次の2種類に分かれます。
- つみたて投資枠(年間120万円)
長期・積立・分散投資向けの投資信託が対象。 - 成長投資枠(年間240万円)
株式やETFなど、より幅広い投資が可能。
生涯の非課税投資枠は1,800万円(うち成長投資枠は最大1,200万円)までとなっており、売却した分は翌年以降に再投資が可能です。
新NISAのメリット・デメリット
ここでは、新しくなったNISAのメリットとデメリットについて説明します。それぞれを比べて、自分に合った投資方法を見つけてみてください。
新NISAのメリット
新NISAのメリットは、主に以下の4つです。
- 非課税枠の拡大で大きな資産形成が可能
旧NISAよりも投資上限額が増え、運用の幅が広がります。 - 売却後も再投資できる仕組み
売却した分の投資枠を翌年以降に再利用できます。 - ライフプランに合わせた柔軟な運用
つみたて投資枠と成長投資枠を組み合わせ、目的に応じた投資が可能です。 - いつでもスタートできる制度の恒久化
口座開設の期限がなくなり、将来の資産形成計画を立てやすくなりました。
新NISAのデメリット
次に、新NISAのデメリットを見てみましょう。
- 価格変動リスクがある
株式市場の影響を受けるため、投資元本が減少する可能性があります。 - 節税効果が限定的
NISA口座では所得控除が適用されず、節税の恩恵は利益が出た場合に限られます。 - 非課税投資枠の年間上限が決まっている
その年に使い切らなかった投資枠を翌年に繰り越すことはできません。 - 一度NISA口座で買った商品は他の口座へ移せない
NISA枠内で投資した商品は、他の証券口座に移動できないため、運用の選択肢が限られます。
新NISAの活用ポイント:「早く・長く・賢く」
新NISAを最大限に活用するには、次の3つのポイントが重要です。
- 早く始める
投資期間が長いほど資産形成の効果が高まります。 - 長く続ける
短期間での値動きに左右されず、コツコツ積み立てることが重要です。 - 賢く運用する
つみたて投資枠と成長投資枠をバランスよく活用しましょう。
投資は計画的に行うことで、長期的な資産形成の成功につながります。
新NISAを活用した資産承継の考え方
NISAは相続対策にも有効です。相続財産の一部をNISAで運用することで、税負担を抑えながら資産を増やせます。
【ケース】相続財産3億円の場合
2024年から導入された新NISAにより、資産運用の幅が広がりました。同時に、相続税や贈与税の制度も改正され、資産の引き継ぎ方法に新たな選択肢が加わっています。
特に、「相続時精算課税制度」に新しく「年間110万円までの非課税枠」が設けられたことで、これまでの暦年課税制度と比較し、より柔軟な資産承継が可能になりました。
これらの制度を活用することで、贈与税を抑えつつ、子ども世代の資産形成もサポートできます。具体的なシミュレーションを見ていきましょう。
【前提条件】
- 相続財産:3億円(現金・預貯金)
- 相続人:配偶者1人、子ども2人
- 基礎控除額:4,800万円(3,000万円+600万円×3人)
- 課税遺産総額:2億5,200万円(3億円-4,800万円)
【相続税の計算】
| 相続人 | 法定相続分 | 相続財産 | 相続税額 |
| 配偶者 | 1/2 | 1億5,000万円 | 0円(配偶者控除適用) |
| 子どもA | 1/4 | 7,500万円 | 1,430万円 |
| 子どもB | 1/4 | 7,500万円 | 1,430万円 |
| 合計 | – | 3億円 | 2,860万円 |
このまま相続を迎えると、子ども2人の相続税額は合計2,860万円となります
仮に、生前に子ども2人へ毎年110万円ずつ贈与し、5年間続けた場合どうなるか見てみましょう。
- 贈与総額:1,100万円(110万円×2人×5年)
- 相続財産の減少額:3億円 → 2億8,900万円
- 相続税の軽減額:192万円(2,860万円 → 2,668万円)
| ケース | 相続財産 | 贈与財産 | 相続税額 |
| 贈与なし | 3億円 | 0円 | 2,860万円 |
| 5年間贈与 | 2億8,900万円 | 1,100万円 | 2,668万円 |
| 税額差 | – | – | ▲192万円 |
少額でも計画的に生前贈与を進めることで、相続税を削減できます。
さらに長期間にわたって贈与を続けると、相続税はより大きく軽減されます。
| ケース | 相続財産 | 贈与財産 | 相続税額 |
| 贈与なし | 3億円 | 0円 | 2,860万円 |
| 10年間贈与 | 2億7,800万円 | 2,200万円 | 2,475万円 |
| 20年間贈与 | 2億5,600万円 | 4,400万円 | 2,090万円 |
| 税額軽減額(20年) | – | – | ▲770万円 |
- 10年間の贈与で相続税が385万円減少
- 20年間の贈与で相続税が770万円減少
長期的に計画すれば、より大きな節税効果が得られることがわかります。
贈与を受けた資金を新NISAのつみたて投資枠(年120万円まで)に活用すると、さらにメリットが生まれます。
例えば、贈与を受けた110万円をそのまま新NISAで運用した場合、非課税のまま資産が増やせます。
親世代は相続税を軽減しながら資産を移転でき、子世代は非課税運用によって資産形成をスタートできます。
新NISAと生前贈与を上手に活用することで、親子双方にとって有利な資産承継が可能になります。今から計画的に進めていきましょう!
新NISAの活用は専門家への相談が重要
新NISAは非課税で資産を増やせる魅力的な制度ですが、適切に活用しなければ十分なメリットを得られません。特に、相続対策として新NISAを利用する場合、税制や贈与のルールを正しく理解し、最適な方法を選択することが重要です。
相続税や贈与税の計算は複雑で、適用される控除や特例も多岐にわたります。さらに、税制は毎年のように改正されるため、最新の情報をもとに計画を立てなければなりません。専門家のアドバイスを受けることで、現在の法律に適した形で相続対策を進めることができます。
また、新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を活用できますが、それぞれの投資商品の特徴を理解し、資産形成の目的に合った選択をすることが大切です。例えば、長期安定運用を目指す場合はつみたて投資枠を中心に、短期間でリターンを狙う場合は成長投資枠を活用するなど、目的に応じた使い分けが求められます。
専門家に相談することで、税務面のリスクを抑えつつ、新NISAの非課税メリットを最大限に活かした資産形成や相続対策が可能になります。相続財産の管理や運用に不安がある場合は、税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談しながら、最適なプランを立てることが重要です。
また、「円満相続ラボ」では、相続に関する基本知識やトラブル回避の方法をわかりやすくお伝えし、専門家によるサポートを提供しています。
相続に関する疑問がある方には、相続診断士による無料相談窓口もご利用いただけます。どうぞお気軽にご相談ください。
NISA口座の相続手続きと税務

NISA口座を持っていた方が亡くなると、その口座内の資産はどうなるのでしょうか?ここでは、NISAの相続手続きや税務上の注意点についてわかりやすく解説します。
相続発生時のNISA口座の取扱い
人が亡くなった時、NISA口座はどのように取り扱われるのでしょうか。相続財産になり、課税対象となるのでしょうか。詳しく解説します。
NISA口座の金融商品は相続税の課税対象
NISA口座で運用していた方が亡くなった場合、その口座内の金融商品は相続財産として扱われます。つまり、NISAの非課税制度は終了し、相続税の対象となります。
相続時の含み益は非課税となる
NISA口座にある金融商品を相続する際、相続が発生するまでに生じた含み益は課税されません。これはNISAの大きな非課税メリットの一つです。
含み益とは、購入時の価格よりも値上がりした分の利益を指します。例えば、NISA口座で100万円分の株を購入し、相続時点での評価額が150万円になっていた場合、その50万円の利益が含み益です。
通常の課税口座では、売却時に約20%の税金がかかりますが、NISAでは相続時点までの含み益については課税されません。
ただし、相続後に発生する配当金や売却益は課税対象となります。そのため、相続後の運用や売却のタイミングをしっかり考えることが重要です。
被相続人死亡時のNISA口座の手続き
NISA口座を開設している被相続人が亡くなった場合、そのまま株式等を売却したり、配当金・分配金を受け取ったりはできません。次の手続きを進める必要があります。
- 金融機関に連絡をし、相続に関する手続き書類を送ってもらう
- 必要書類を収集する
- 未受領配当金明細書の請求をして、相続対象となる株式等の保有銘柄・数量確認する
- 被相続人の遺言書があれば引き継ぐ相続人を確認、遺言書が無い場合は遺産分割協議で引き継ぐ相続人を決める
- 株式等を引き継ぐ相続人に証券口座がないとき、前もって被相続人と同じ金融機関に口座を開設する
- 金融機関の所定の用紙に相続人全員で署名・押印、必要書類を添付し提出する
- 2~3週間程度で株式等を引き継いだ相続人の口座に移管、手続き完了
相続手続きの際にはいろいろな書類を準備し、金融機関へ提出する必要があります。相続手続きの手数料は基本的に無料です。
- 相続手続依頼書(株式等移管依頼書):金融機関から郵送される
- 非課税口座開設者死亡届出書:金融機関から郵送される
- 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本(除籍謄本):本籍地の市区町村役場、1通450円~750円
- 相続人全員の戸籍謄本:本籍地の市区町村役場、1通450円
- 相続人全員の印鑑登録証明書:住所地の市区町村役場、1通300円
- 遺言書または遺産分割協議書:あれば提出する
なお、残高証明書(投資信託等がいくらあるのかを証明する書類)が必要ならば、次の書類を金融機関へ提出します。
- 残高証明書等発行依頼書:金融機関から取得
- 被相続人の戸籍謄本(死亡記載あり):本籍地の市区町村役場、1通450円
- 請求者の戸籍謄本等
- 請求者の実印・印鑑登録証明書
「非課税口座開設者死亡届出書」などの提出
NISA口座を持っていた方が亡くなった場合、相続人は速やかに金融機関へ連絡し、相続手続きを進める必要があります。その際、「非課税口座開設者死亡届出書」などの必要書類を提出しなければなりません。
【提出に必要な書類】
金融機関から届いた書類に記入し、以下の添付書類とともに提出します。
- 故人の死亡を証明する戸籍謄本
- 相続人の代表者が法定相続人であることを証明する戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書(原本)
- 相続人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
金融機関ごとに必要な書類が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
【相続人が複数いる場合の追加書類】
相続人が複数いる場合、遺産分割の合意を証明する書類が求められることがあります。
- 遺産分割協議書
- 遺言書
- 相続人全員の署名・捺印をした金融機関の指定書類
これらの書類をそろえて提出することで、スムーズにNISA口座の相続手続きを進めることができます。
「相続上場株式等移管依頼書」の提出
故人が所有していた株式や投資信託を相続人の口座に移すためには、「相続上場株式等移管依頼書」を金融機関に提出する必要があります。この手続きを進めるためには、相続人名義の取引口座を開設済みであることが条件となります。
相続した株式を移管する際は、特定口座か一般口座のどちらか一方にまとめる必要があります。同一銘柄の株式を特定口座と一般口座に分けて移すことはできません。
- 特定口座(源泉徴収あり)に移管すると、売却時に税金が自動で差し引かれるため確定申告の手間を減らせる。
- 一般口座に移管する場合、売却時の税計算や確定申告が必要になるため手続きが複雑になる可能性がある。
手続きをスムーズに進めるため、金融機関の担当者に相談しながら、どの口座に移すか慎重に決めましょう。
NISAの相続手続き3ステップ
NISA口座を持つ人が亡くなった場合、相続手続きを進める必要があります。ここでは、スムーズに相続を進めるための3つのステップを紹介します。
【STEP1】金融機関へ連絡し、残高証明書を取得
まずは、故人が取引していた証券会社や銀行に連絡し、相続の手続きを開始します。金融機関によって必要な書類が異なるため、手続き方法を確認しましょう。
① 金融機関に連絡する
- 取引先の証券会社や銀行にNISA口座を持っていたことを伝える。
- 「非課税口座開設者死亡届出書」など、提出が必要な書類を確認する。
- 残高証明書の発行を依頼する。
② 残高証明書の確認
- NISA口座内の金融資産(株式・投資信託など)の保有状況を確認する。
- 相続財産の評価額を把握し、相続税の計算に備える。
【STEP2】遺言書や遺産分割協議で相続人を確定
NISA口座の資産を誰が相続するか決めることが重要です。相続人が複数いる場合、遺産分割協議が必要になります。
① 遺言書の確認
故人が遺言書を残している場合は、内容を確認し、記載通りに手続きを進める。
② 遺産分割協議を行う
- 遺言書がない場合、法定相続人全員で話し合い、誰がNISA口座の金融資産を取得するか決める。
- 遺産分割協議書を作成し、合意内容を明文化する。
- 金融機関に提出するため、相続人全員の署名・押印を忘れずに。
【STEP3】NISA口座内の金融商品を相続人の口座へ移管
被相続人が運用していた積立NISA口座内の投資信託を引き継ぐ場合、相続人名義の口座が必要です。
ただし、移管のためにはどんな証券会社の口座でも良いわけでなく、原則として被相続人の口座と同じ証券会社の口座に限定されます。
同じ証券会社の口座を持っていないならば、事前または相続手続きと同時に、被相続人がNISA口座を持っていた同じ証券会社で、相続人本人名義の口座を開設しておく必要があります。
また、申込時に口座の種類を選ばなくてはいけません。口座には「特定口座」と「一般口座」の2種類があります。
選ぶ際におすすめなのが「特定口座・源泉徴収あり」です。こちらの口座にすれば、確定申告等の一連の手続きが面倒でも、税金の処理を証券会社に任せられるので安心です。
NISA口座の相続税評価額の計算方法
NISA口座にある株式を相続するとき、相続税評価額は「相続発生日の終値×株式数」で算出されます。しかし、株価の変動によって相続税の負担が大きくならないよう、以下の4つの評価方法のうち、最も低い価格を基準に計算できます。
- 相続発生日の終値
相続が発生した日の株価の終値を基準とします。 - 相続発生日の当月の終値の月平均額
その月の株価の終値を平均した金額で評価します。 - 相続発生日の前月の終値の月平均額
1か月前の終値の平均額を基準とします。 - 相続発生日の前々月の終値の月平均額
2か月前の終値の平均額を採用します。
積立NISA口座の相続税評価額の計算方法
一般的な投資信託の評価額を算出する際には、まず投資信託の1口あたりの価格と保有口数を掛け合わせて全体の評価額を求めます。通常、投資信託の1万口あたりの基準価格が公表されているので、これを基に1口あたりの価格を計算します。
次に、相続が発生した日を基準として、もしその日に投資信託を換金した場合に発生する配当所得や利子所得から源泉徴収される所得税を考慮し、解約時にかかる手数料や信託財産留保額を差し引いた後の金額を評価額とします。
計算式は以下のようになります:
1口あたりの基準価格×保有口数−配当所得・利子所得に対する源泉徴収額−信託財産留保額および解約手数料
相続税の基礎控除とその影響
相続税には、一定額までは課税されない基礎控除が設けられています。この基礎控除額を超えた遺産についてのみ、相続税が発生します。現在の基礎控除額は2015年(平成27年)に改正され、以前よりも大幅に引き下げられました。そのため、課税対象となる人の割合も増加しました。
相続税の基礎控除額の変更(2015年~)
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】
例えば、法定相続人が2人の場合は、
3,000万円+(600万円×2)=4,200万円
この額を超える遺産に対して、相続税が課されます。つまり、遺産総額が3,600万円以下であれば、相続税はかからない仕組みです。
以前の基礎控除額は、【5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)】でした。
例えば、法定相続人が1人の場合、基礎控除額は6,000万円だったため、現在の控除額(3,600万円)と比べると、2,400万円も引き下げられたことになります。
この改正により、相続税の負担が増え、課税対象者も増加しました。以前は相続税がかからなかった家庭でも、現在は課税される可能性が高くなっています。
NISAの相続に関する注意点
NISA口座を持つ人が亡くなった場合、その資産は相続人に引き継がれますが、いくつかの制約があります。相続時のポイントをしっかり理解し、スムーズな手続きを進めましょう。
相続人のNISA口座へ直接移管することはできない
NISA口座内の株式や投資信託は、相続人のNISA口座に直接移すことはできません。相続が発生すると、NISA口座は自動的に閉鎖され、保有していた金融商品は特定口座または一般口座へ移管されます。
また、これらの資産は亡くなった方が利用していた金融機関でしか移管できません。相続人が他の金融機関の口座を持っていたとしても、別の金融機関には移せないため、同じ金融機関で口座を開設する必要があります。
相続後はNISAの非課税枠が適用されない
NISAの大きなメリットは、投資による利益が非課税になることです。しかし、相続が発生した時点でNISAの非課税枠は消滅し、課税対象となります。
たとえば、NISA口座で100万円の株を購入し、相続時点での評価額が150万円だった場合、その50万円の含み益には相続税はかかりません。しかし、相続人がその後に売却して利益が出た場合には、通常の課税口座と同じく約20%の税金が発生します。
さらに、相続後に発生した配当金や分配金も課税対象となり、税金の支払いが必要です。これらの点を把握し、相続後の運用方法を慎重に検討しましょう。
相続人は同じ金融機関で口座を開設する必要がある
故人のNISA口座内の金融商品を相続する場合、相続人の口座も同じ金融機関で開設していることが必須です。他の証券会社や銀行の口座には移せないため、相続前に口座を開設しておくとスムーズです。
移管手続きには、金融機関指定の申請書を提出する必要があり、手続き完了までに2~3週間程度かかることが一般的です。相続発生日の時価を基準に資産が相続人の口座へ移されるため、その後の売却時には通常の課税ルールが適用されます。
相続財産としての取得価額は相続発生日の時価となる
通常、相続した株式や投資信託の取得価額(購入時の価格)は、故人が取得した際の価格を引き継ぎます。しかし、NISA口座内の金融商品の場合、相続発生日の時価が取得価額として設定されます。
これは、NISAが相続開始時点で終了する仕組みであるためです。例えば、NISA口座で取得した株が相続時に値上がりしていた場合でも、相続人はその時点の価格を取得価額として扱います。
つまり、相続人が将来的にその株を売却する際には、相続発生日の時価を基準に利益を計算し、税金を支払う必要があります。この仕組みを理解し、相続後の資産管理を適切に行いましょう。
含み益・分配金の取り扱い
相続発生時には、被相続人の積立NISA口座内の投資信託はすべて払い出された扱いになります。
その際、積立NISA口座内の投資信託に含み益(購入してから値上がりした利益)があれば非課税です。その他、相続開始日までに権利が確定した分配金も非課税となります。
ただし、相続人の口座へ移管後、投資信託を売却したならば課税口座内での取引になるため、相続時点の時価と比較し値上がりしていると、その利益分は課税されてしまいます。
また、相続開始日の翌日以降、権利が確定した分配金も課税の対象なので注意が必要です。
換価分割のケースについて
相続した投資信託を売却し、複数の相続人で代金を分ける(換価分割)と、確定申告が必要になる場合もあります。その場合とは売却した際に利益(譲渡益)が出たときです。
売却代金を受け取った相続人全員が確定申告をしなければいけません。
この換価分割のケースでは、NISA口座内の投資信託を移管した口座がたとえ「特定口座・源泉徴収あり」であっても、譲渡益が出れば確定申告を行う点に注意しましょう。
積立NISA口座と通常の口座で相続時の扱いの違い
被相続人が積立NISA口座内で投資信託を保有し、相続人も積立NISA口座を保有していても、相続開始時、被相続人の積立NISA口座の投資信託は、相続人の積立NISA口座に移せません。
被相続人が積立NISA口座で投資信託を保有していた場合、非課税措置がとられるのは相続発生日までです。
相続発生後は相続人の積立NISA口座ではなく、通常口座(特定口座か一般口座)に移管しなければいけません。
積立NISA口座での非課税措置は、あくまでも被相続人が生きている間です。相続開始時点ではもはや非課税として扱われず、その効果は相続人に継続されないのです。
生前贈与とNISAの活用
生前贈与を活用すると、相続税を抑えながら資産をスムーズに次世代へ引き継ぐことができます。さらに、贈与された資金をNISAで運用すれば、非課税のメリットを活かしながら効率的な資産形成が可能になります。本記事では、生前贈与とNISAを組み合わせた活用法について詳しく解説します。
相続税と生前贈与の関係
相続税は、遺産の総額が一定の基準を超えると課税されます。そのため、生前贈与を活用し、相続財産を減らすことで、相続税の負担を軽減できます。特に、年間110万円までの贈与は非課税となるため、長期間にわたって計画的に贈与すると、大幅な節税効果が期待できます。
また、2024年の相続税改正により、相続開始前7年間の贈与が相続財産に加算されることになりました。これを踏まえ、早めに対策を取ることが重要です。
【例】相続財産8,000万円、法定相続人が子供3人の場合
ここでは、親の財産が8,000万円あり、子供3人が法定相続人となるケースを見てみましょう。
生前贈与なしの場合の比較
生前贈与なしの相続税の計算は以下のようになります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 相続財産 | 8,000万円 |
| 基礎控除額(3,000万円+600万円×3人) | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 3,200万円 |
| 相続税額(合計) | 約520万円 |
生前贈与を行わないと、基礎控除額を超えた3,200万円に相続税が課税されるため、約520万円の相続税が発生します。
生前贈与ありの場合の節税効果
生前に年間110万円ずつ10年間、子供3人へ贈与した場合を考えます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 相続財産(贈与後) | 4,700万円(8,000万円-110万円×3人×10年) |
| 基礎控除額 | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 0円 |
| 相続税額 | 0円 |
このように、計画的に生前贈与を行うことで、相続財産が基礎控除内に収まり、相続税をゼロにすることも可能です。
NISAを活用した生前贈与の事例
贈与された資金をNISA口座で運用することで、さらに大きなメリットが得られます。たとえば、子供が受け取った110万円をNISAの「つみたて投資枠」(年間120万円まで)で運用した場合、次のような効果が期待できます。
【シミュレーション】NISAで運用した場合
- 毎年110万円を贈与し、NISA口座で年利5%で運用
- 10年間続けた場合、元本1,100万円が約1,430万円に増加(税金なし)
- 20年間続けた場合、元本2,200万円が約3,780万円に増加(税金なし)
通常の課税口座で運用すると、約20%の税金がかかりますが、NISAならすべて非課税です。
生前贈与の資金をNISA口座で運用するメリット
生前贈与を活用することで、相続税の負担を軽減しながら、家族の資産形成をサポートできます。さらに、その資金をNISAで運用すれば、非課税の恩恵を受けながら資産を効率的に増やすことが可能です。
相続対策を考える際には、長期的な視点を持ち、NISAを活用した資産運用も選択肢の一つとして検討しましょう。
【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ
相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。
本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。
本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください
この記事を書いたのは…

弁護士・ライター
中澤 泉(なかざわ いずみ)
弁護士事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続といった幅広い分野の案件を担当した後、メーカーの法務部で企業法務の経験を積んでまいりました。
事務所勤務時にはウェブサイトの立ち上げにも従事し、現在は法律分野を中心にフリーランスのライター・編集者として活動しています。
法律をはじめ、記事執筆やコンテンツ制作のご依頼がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。
この記事を監修したのは…

ジェニユイン・パートナーズ株式会社 取締役 / 一般社団法人証券相続普及協会 代表理事
小林 裕(こばやし ゆたか)
保有資格:証券外務員一種、終活カウンセラー、上級相続診断士
大学卒業後、準大手証券会社に入社。
新人賞、社長優秀賞などの数多くのタイトルを受賞。
その後、金融商品仲介業(IFA)に転身。
2020年12月、一般社団法人証券相続普及協会を設立。
2024年9月、『誰にでもやさしく教えてくれる 会社を退職する前に知っておくべき「退職金運用の基礎知識」』を出版し、Amazonランキング4部門1位を獲得。